ALBUMS 50 - 41
| 順位 | アルバム名 | アーティスト | YEAR |
| 50 | SYNCHRONICITY | The Police | 1983 |
| 49 | BADUIZM | Erykah Bady | 1997 |
| 48 | TALL BLONDE HELICOPTER | Francis Dunnery | 1995 |
| 47 | CORE | Stone Temple Pilots | 1992 |
| 46 | THE SEEDS OF LOVE | Tears For Fears | 1989 |
| 45 | PROMISE | Sade | 1985 |
| 44 | COUNTDOWN TO EXTINCTION | Megadeth | 1992 |
| 43 | SPORTS | Huey Lewis & The News | 1983 |
| 42 | LEVERT, SWEAT, GILL | LSG | 1997 |
| 41 | THRILLER | Michael Jackson | 1982 |
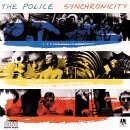 50. SYNCHRONICITY - The Police 洋楽を本格的に聴き始めた1983年、自分のお金を出して買った2枚目のアルバム。そりゃもう嬉しくて、繰り返し聴きまくったものです。もっとも、本当の凄さが分かってきたのはずっと後のことでしたけれど。 アナログでいうA面とB面とで若干性格が異なります。A面は "Synchronicity I" と "Synchronicity II" に挟まれた合計6曲のロック小品集、B面はお馴染み "Every Breath You Take" などミディアム/スロウを並べたポップ曲集といった趣きで。心理学者ユングの用いた「共時性」とでも言うべき概念がアルバム全体を貫くテーマ。知的で深みのある歌詞とシンプルなトリオ編成でのアレンジを、制作/エンジニアのヒュー・パジャムが素晴らしくクリアなサウンドで仕上げています。弦のきしみやハイハットの残響音のひとつひとつまで目に見えるような録音。 このアルバムを議論する時に必ず問題になるのが、アンディ・サマーズが書いた素っ頓狂な "Mother" の存在でしょう。多くのリスナーはこの曲さえなければパーフェクトだと言います。だが、ヒット曲だけ聴きたいのならベスト盤を買えばよろしい。僕に言わせれば "Mother" あってこそのシンクロニシティ。これほどイライラさせ、場違いで、聴いてるだけでおかしくなりそうな曲なんてそうそうありません。遠回しに言うと、一度聴けば絶対に忘れないよ。間違いなく本アルバムの要、偏愛してます。  49. BADUIZM - Erykah Badu "On & On" が突然チャートインした時にはビックリしたものです。他のヒット曲とは全く異なるその質感。一聴しただけではさっぱり理解できませんでしたが、じわじわと身体に浸透してきてクセになり、アルバムを買ってみたら完全に中毒に。ホント、麻薬みたいな歌唄いです。 流れとしては New Classic Soul のムーヴメントに乗っかるものですが、全体のコンセプトはもっとジャズ寄り。D'Angelo の1stでいい仕事をした Bob Power や、The Roots といった生音志向の制作陣が腕によりをかけて生み出す激渋&ファットなトラックの上で、軽やかに舞うエリカのヴォーカル。暑苦しさとか力強さとは対極にある彼女の声が妖しく浮遊するのです。 アルバムの構成も素晴らしい。イントロの "Rimshot" からして異様。低音域をうねるベースラインで始まり、エレピが揺れる中で高音のリムショットがリズムを刻む。これがアルバムの基調を成すトラックで、多少の振幅はあるものの、ほとんど同じペースでラストまで一気に聴かせてしまいます。全曲がこの "Rimshot" と "On & On" のバリエーションといってもよいくらい、自然な流れでつないであります。コンセプトの勝利。音数的にはスカスカですが、だからこそ音の良いステレオで聴きたいアルバム。特にベースが肝。夜中に、酒飲みながら聴くとゾクゾクするよ。  48. TALL BLONDE HELICOPTER - Francis Dunnery フランシス・ダナリーは元 It Bites のギタリスト/ヴォーカリストです。といっても、このソロアルバムに往年のプログレ趣味のサウンドは一切録音されていません。とてもシンプルでアコースティックな、暖かい作品。 たまたま95年に仕事でロンドンに住んでいて、フランシスのライヴを見る機会がありました。ギター1本を抱えての弾き語りです。小さなクラブに集まったたくさんの熱心なファン。あれほど歌い手と聴き手の距離が(物理的にも精神的にも)近かったコンサートはありません。後にこのアルバムに収録されることになる曲をいくつも歌ってくれましたが、中でも "Too Much Saturn" と "Thankful And Grateful" のメロディの良さと真摯な歌いっぷりには本当に感動。今振り返ってもちょっと涙が出てくる、大切な想い出の夜です。 It Bites の解散やロバート・プラントのバンドでのツアーなどを経て、ようやく「独り」であることを大切にするようになった90年代半ばのフランシス。当時の心境がよく表れた楽曲/アレンジでしょう。彼はその後別の方向へ歩き出し、この作品のような音は残念ながら聴くことができません。でも一度吹き込んだレコードは永遠に鳴り続ける。ストレートで、素朴で、暖かくて。全曲大好きなアルバム。  47. CORE - Stone Temple Pilots 似非グランジ。便乗オルタナティブ。安物イミテーション。 痛い。サンディエゴ出身のストーン・テンプル・パイロッツ(STP)に投げつけられたレビュウは散々なものでした。しかしビジネスの世界では誰が何と言おうと売れた者勝ち。じわじわと火が付いて93年の年間アルバムチャート10位(最高位3位)、2002年現在800万枚以上のセールスを上げてまだまだ売れ続けるモンスターアルバム。批評家が何とほざこうと、キッズはいつだって "Plush" のコーラスが大好きなのです。 何といっても曲が良い。スコット・ウェイランドが歌うヴォーカルメロディのキャッチーなこと。すぐに一緒に歌いたくなります。バックの楽器隊にも技巧的なソロなど皆無。エリック・クレッツのタメの利いたドラムスに絡むディーンとロバートのディレオ兄弟のギター/ベースが生み出す、三位一体の独特のグルーヴ。ヘヴィな曲でもぐじゃぐじゃにならない分離の良い乾いたサウンドは、この後グランジ界を席巻するプロデューサーのブレンダン・オブライエンと、子飼いのエンジニア、ニック・ディディアの手によるもの。特にブレンダンはSTP5人めのメンバーと言っても良いほどの絶妙の相性の良さ。ある意味、グランジ史上最も重要な1枚(にして最も攻撃された1枚)。 本作で業界の期待どおりにオルタナティブの虚像を演じきったSTPは、次第に殻を脱ぎ捨てて、より「普通」のバンドになっていきます。突如訪れたスターダムに戸惑ったウェイランドのドラッグ依存問題もあり、この後のアルバムには「実は僕たちこんな感じです」的な剥き出しの痛々しさを感じなくもありません。でも同じ痛さなら、僕はグランジの虚勢を張って粋がっていたこのデビュー作のSTPを支持したい。死ぬなよ、ウェイランド。  46. THE SEEDS OF LOVE - Tears For Fears 思い入れという点では思春期に聴き込んだ "SONGS FROM THE BIG CHAIR" の方が遥かに大きいのですが、完成度というかヤリ過ぎ感では圧倒的にこちらの方が上。細部に至るまで偏執狂的に作り込まれた信じられない作品。 そうなってしまった理由を考えると、決して手放しで楽しめるわけではありません。"BIG CHAIR" がマルチ・プラチナムのメガヒットになり、それを上回る作品を期待されるプレッシャーは想像を絶するものがあったことでしょう。思いきりファンを突き放した作品を作ることもできたのでしょうが(例:スマパンの「アドア」とかレディオヘッドの「キッドA」とか)、TFFは逆に守りに入って必死にガチガチに作り込んでいきました。丸4年もかけて。結果として一分の隙もない息苦しいほどのパーフェクトなアルバムに仕上がったわけです。 果たしてそれが良かったのかどうか? 振り返って是非を考えてみても答は出ませんが、いずれにせよ本作品を最後にカート・スミスはグループを離れ、以後TFFはローランド・オーザバルのソロプロジェクトとして存続していくことになります。ある意味プログレッシヴといっていい作品ですが、それでも後期ビートルズ風の "Sowing The Seeds of Love" や、軽やかな "Advice For The Young At Heart" をシングルヒットさせたセンスは流石。また "Woman In Chains" で Oleta Adams という逸材を掘り当てた功績も忘れられません。10年以上を経た今でも場違いに燦然と輝き続ける鬼アルバム。  45. PROMISE - Sade シャーデー・アデュが発声した瞬間に場の空気が変わる。その意味では、どのアルバムでも大差はありません。いやむしろ、差が無すぎる。この驚異的な安定感と一貫性こそが、シャーデーというバンドの恐ろしさ。 まさに大ヒットした前作の勢いに乗って作られた 2nd (US#1)。ジャズ趣味を更に押し進めたお洒落な楽曲群の一方で、シングルの "The Sweetest Taboo" ではこれまでにないシャープなリズムを聴かせたりもします。個人的な聴きどころはアデュが感情を露わにして歌う次の3曲。まずはオープニングの大曲 "Is It A Crime"。捨てられた相手に対する未練を切々と歌い上げる情熱的なナンバーで、ドラマティックなイントロのサックスから完全に持っていかれます。続いてA面最後(だったかな)に置かれた "Jezebel"。貧しい家に生まれた美しい娘が逞しく生き抜いていく様を歌う曲で、ライヴでも非常に人気があるようです。そして最後に、ラストを飾る "Maureen"。親友であるモーリーンに歌いかける軽快なアップテンポナンバーなのですが、実はそのモーリーンは既に死んでいるという設定。これから寂しくなるわ、とさらりと歌う別れの曲で、ちょっと不思議な感覚。 この他の曲もアデュのクールなヴォーカルと、ホーンを中心としたジャジーなトラックが絶妙に絡み合うものが多く、アルバム単位で聴かれるべき作品でしょう。シャーデーはこの後次第に装飾を削ぎ落としたシンプルな作風に枯れていきますが、個人的にはやはり初期のスムースでお洒落な作品を引っ張り出して聴くことの方が多いです。  44. COUNTDOWN TO EXTINCTION - Megadeth 大きなターニングポイント。複雑系インテレクチュアル・スラッシュメタルを究めた前作 "RUST IN PEACE" も大好きですが、立ち止まることなく次の次元に踏み込んだ点を高く評価してこのアルバムを。 とにかく、プロダクションが恐ろしくタイトなのです。無駄が一切存在しない。メタリカのブラック・アルバム以降、かつてのスラッシュ勢はこぞってダーク&ヘヴィな路線を目指し、結局自分のものにできずに倒れていきましたが、メガデスだけは違いました。確かにこのアルバムもミディアムテンポの楽曲が多くて、一聴するといわゆる悪しき「ブラック・アルバム症候群」に冒されたのかと思うかもしれません。しかしその実、切れ味はむしろ "RUST IN PEACE" 以上に増している。バンド・アンサンブルという点では過去最高なのではないか。 特に惹かれるのはニック・メンツァのソリッドなドラミング。ドラムだけ聴いててもアルバム1枚聴けちゃうよってくらいに良い音で録音されています。この辺は制作と録音・ミックスに関わったマックス・ノーマンの手腕なのかな。自分はどうやら各楽器の音がきちんと整理されたミックスが好みのようで、このアルバムも音響的に非常にお気に入り。恐らくマーティ・フリードマンが持ち込んだと思われるメロディ志向の楽曲群に捨て曲は見当たらず、オープニングのスピーディな "Skin O' My Teeth" から本編ラストの "Ashes In Your Mouth" まで息もつかせず突っ走ります。"Symphony of Destruction" のザクザクしたリフや "Sweating Bullets" のシャッフル・ブギーにびっくりしたのも、今となっては懐かしい想い出。  43. SPORTS - Huey Lewis & The News 「80年代」を象徴する西海岸ロックバンド。録音はシスコでもミックスはニューヨーク。クレジットにパワー・ステーションというスタジオとボブ・クリアマウンテンというエンジニアを見つけたら、それはほぼ間違いなく古き良きビッグな80年代サウンド。ついでに言うと、ヒューイ自身もNY生まれ。ちょっと意外? ヒューイ・ルイスは実に親しみやすく明るいキャラの人。とても人なつっこい笑顔+パワフルな声で僕らを魅了します。このアルバムも聴くだけでイヤなことを全部忘れられる最高のロック。心臓の鼓動音でフェードインしてくる1曲目の "The Heart of Rock & Roll" は大好きなロック讃歌。歌詞には全米の都市名を織り込んで。ツアー時にはご当地の地名に変えるファンサービスも忘れない気配りの人たち。メンバー間の信頼関係が強く感じられるところも気に入ってました。力強いサックスとリードギターの掛け合いに、ヒューイのハーモニカが絡むスタイルにも味がある。R&Bやカントリーの影響をふんだんに感じさせる、シンプルな正統派ロケンロー。 「キミと2人でいるような気持ちにさせてくれるクスリが欲しい!」と歌う超ストレートな "I Want A New Drug" も好きだし、切ない系では "If This Is It" も良いね〜。ちなみに第5弾シングルとしてカットされ全米12位まで上がった "Walking On A Thin Line" は、80年代いろいろな形で問題になったベトナム戦争帰還兵テーマ。やや内省的な異色曲ですが、例えば "Born In The U.S.A." なんかよりずっと心に響きました。死ぬまでに一度はライヴを観ておきたいバンドっす。  42. LEVERT, SWEAT, GILL - LSG Gerald Levert、Keith Sweat、Johnny Gill。正直言ってこの3人のいずれにも過剰な思い入れはありません。強いて言えばジョニー・ギルかなあ。"Rub You The Right Way" や "Fairweather Friend" のようなアップも、"My, My, My" のような必殺スロウも自在にこなす巧さ。でも(だから?)器用貧乏。キース・スウェットの気だるさに好感を持てるようになるまでには割と時間がかかったし。ジェラルド・リヴァートに至っては迫力ある人って印象だけで、覚えている曲メロはほぼ皆無。いかんいかん。 それぞれ十分なキャリアのあるR&B界の3ヴォーカリストを半ば強引にくっつけた企画ながら、とても一過性のものとは思えない出来の良さ。三者三様の異なる個性を殺すことなく、かといってバラバラにもならず、まるで何年も一緒に歌ってきたユニットであるかの如く自然に流れていきます。圧倒的なユルさ。これ本作のキーワード。ゲスト陣も豪華ですが、むしろ3人だけでリラックスして淡々と歌うナンバーの方が落ち着くなあ。パフ・ダディやジャーメイン・デュプリらに混じって制作面で名を上げたのは 2000 Watts。この後シルクの "If You (Lovin' Me)" などで大注目されることに。 キースとジェラルドの自作曲も良いものが多く、決して手抜き仕事ではありません。エッチ系ソウルの極致 "My Body" も好きですが、3人がそれぞれ自分のヒット曲のタイトルを織り込みつつ順番にリードを回す1曲目の "Door #1" にヤラれます。そうかこの手があったのかと。もし再び集まることがあるのなら、次回もぜひこのユルさで。  41. THRILLER - Michael Jackson 「生まれて初めて」は全ての人に平等に、たった1度だけ訪れる。だから人は、生まれて初めてキスした日のことや、生まれて初めてエッチした夜のことや、生まれて初めてフラれた体験などを、ずーっと忘れない。だから音楽好きの人なら、生まれて初めて自分で買ったレコードのことを一生忘れないでしょう。僕にとってはこのアルバム。 今ではマイケル・ジャクソンを真面目にとりあげるのはカッコ悪いことになってしまったのかもしれませんが、やはり一時期のマイケルが神がかり的だったのは間違いない。"Billie Jean" のビデオなんて20年経つ今見ても凄まじいオーラ放ってるしね。そんなマイケルのスター性を演出したのがプロデュースのクインシー・ジョーンズだったことは今さら説明するまでもないでしょう。ポール・マッカートニー、エディ・ヴァン・ヘイレンなどの飛び道具に加えて、Toto のメンバーや名だたる豪華スタジオミュージシャンを贅沢に配置したバックトラックは、クインシーの考える理想の「クロスオーバー」サウンドだったはず。ブラックミュージックの伝統をギリギリ残しつつ、ホワイトとの壁を軽々と超えた究極のポップ。でもクインシーがそれを実現できたのは、やっぱりマイケルという非凡な素材/キャラクターがあったからこそなんだよね。 奥の深いリズムトラック、ホーンセクション、コーラスアレンジ。無駄なくらい注ぎ込まれたエネルギーの凄さに、聴けば聴くほどのめり込む。ただ売れているから買ってみたという人が何千万人いても構わないけれど、もしこれほど素晴らしいレコードに一番最初に出会えたのなら感謝すべき。少なくとも僕は、その偶然に心底感謝しています。きっといついつまでも。 正直に言うと、20代後半以降は "OFF THE WALL" の方が遥かにしっくりくるけれど、それでも "THRILLER" は僕の中で永遠のクラシック。今日も久しぶりに取り出して聴いてみることにしようか。 |
|