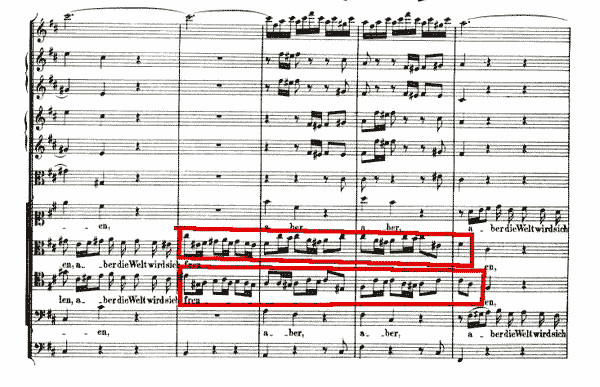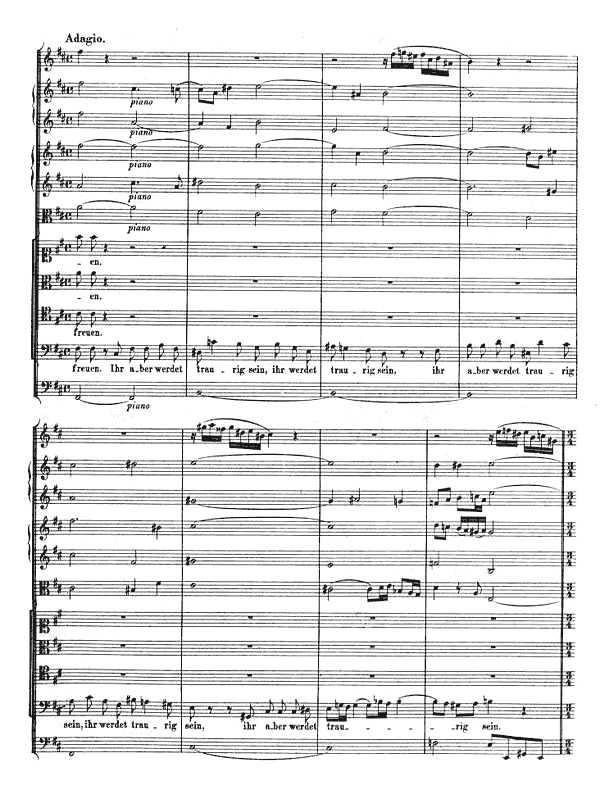もっと ...
●BWV167のGoogle動画検索
●Suzuki 1998 (1:04:28-)
●Rilling
●Gardiner yyyy live London uk
●Harnoncourt
●Montréal Baroque | Eric Milnes ca
●Rilling 1974 Stuttgart de
■ヘルムート リリング
■フンツィカー
●Yo-Yo Ma (終曲コラール)
【楽章構成】
05 (Choral) Sei Lob und Preis mit Ehren
(2:27)
Choralchorsatz-S *
"Nun lob, mein Seel, den Herren"/5.
[ Clarino, Oboe, Violino I/II, Viola, Continuo ]
リトルネッロ形式(オブリガート間奏つき)コラール
●
原コラール歌詞(Johann Gramann 1530)・旋律(?Johann Kugelmann 1540)
●
このコラール解説(wikipediaへリンク)
●全歌詞(ChatGPT回答)
Q: コラール”Nun lob, mein Seel, den Herren"の全歌詞を教えて下さい。
A: (ChatGPT)
「Nun lob, mein Seel, den Herren」は、ヨハン・グラーマン(Johann Gramann)によって1530年に作詞されたドイツ語の賛美歌で、詩篇103篇に基づいています。全5節から成り、各節は12行で構成されています。以下に各節の歌詞を示します。
第1節:
Nun lob, mein Seel, den Herren, Was in mir ist, den Namen sein! Sein Wohltat tut er mehren, Vergiss es nicht, o Herze mein. Hat dir dein Sünd vergeben Und heilt dein Schwachheit groß, Errett' dein armes Leben, Nimmt dich in seinen Schoß, Mit reichem Trost beschüttet, Verjüngt, dem Adler gleich; Der Herr schafft Recht, behütet, Die leiden in seinem Reich.
第2節:
Er hat uns wissen lassen Sein herrlich Recht und sein Gericht, Dazu sein Güt' ohn' Maßen, Es mangelt an Erbarmung nicht; Sein' Zorn lässt er wohl fahren, Straft nicht nach unsrer Schuld, Die Gnad' tut er nicht sparen, Den Schwachen ist er hold; Sein' Güt' ist hoch erhaben Über die, die fürchten ihn; So fern der Ost vom Abend, Ist unsre Sünd' dahin.
第3節:
Wie sich ein Vater erbarmet Über seine junge Kindlein klein, So tut der Herr uns Armen, Wenn wir ihn kindlich fürchten rein. Er kennt das arme Gemächte Und weiß, wir sind nur Staub; Gleich wie das Gras vom Mähen, Ein Blum' und fallend Laub: Der Wind nur drüber wehet, So ist es nimmer da; Also der Mensch vergehet, Sein End', das ist ihm nah.
第4節:
Die Gottesgnad' alleine Steht fest und bleibt in Ewigkeit Bei seiner lieben Gemeine, Die steht in seiner Furcht bereit, Die seinen Bund behalten. Er herrscht im Himmelreich; Ihr starken Engel, waltet Seins Lobs und dient zugleich Dem großen Herrn zu Ehren Und treibt sein heiligs Wort! Mein Seel' soll auch vermehren Sein Lob an allem Ort.
第5節:
Sei Lob und Preis mit Ehren Gott Vater, Sohn und Heil'gem Geist! Der wolle in uns mehren, Was er aus Gnaden uns verheißt, Dass wir ihm fest vertrauen, Uns gründen ganz auf ihn, Von Herzen auf ihn bauen, Dass unser Mut und Sinn Ihm allezeit anhangen. Drauf singen wir zur Stund': Amen, wir werden's erlangen, Glaub'n wir von Herzensgrund.
この賛美歌は、ドイツの宗教改革時代に広く歌われ、現在でも多くの教会で親しまれています。特に第5節は、ヨハン・ゼバスティアン・バッハのカンタータやモテットに引用されるなど、音楽史においても重要な位置を占めています。
●
オルガン編曲演奏
... こちらの方が、同形式の有名な「主よ人の望みの喜びよ」より有名になっていたかも知れないと思わされる。
【解説】(英語原文からGoogle翻訳)
- Simon Crouch: 2 番目のレチタティーヴォは、このカンタータの真の逸品である、見事に喜びにあふれた伴奏付きのコラールへと続きます。BWV 147の「主よ、人の望みの喜びよ」 やBWV 22の「汝の善良さによってわれらを謙虚にならせ給え」がお好きなら 、この曲を手に入れるために全力で走るべきです。この作品がなぜもっと知られていないのか全く理解できません。
- Julian Mincham: ついに、私たちが集まって三位一体を讃える時が来ました。そこでバッハは、単純にハーモニーをつけた四部コラールではなく、忙しく執拗な楽器のサポートによる、より華やかに編曲されたバージョンを私たちに与えました。さらにもう 1 つの楽器、トランペットが活躍します。しかし、それは神の偉大さや神への感謝を誇示するためではなく、コラールのメロディーを倍増し、強めるためだけのものです。
これはバッハのコラール曲の中でも最も楽しい曲の一つでしょう。第一バイオリンとオーボエが加わり、爽快な16分音符がほぼ絶え間なく響き渡ります。3つの下声部は、16分音符、時には16分音符の動きで活発に演奏されます。三位一体は祝福され、神の言葉への私たちの継続的な信頼が宣言され、私たちは心と魂を込めて「アーメン」と歌います。対位法は複雑ですが、この動きには単純で率直な雰囲気があります。私たちは神と比べれば確かに単純な魂であり、この祈りと嘆願の慣習的な行為には、まったくの欺瞞や二面性がありません。
一見無造作で素朴でありながら、明らかに奥深く満足のいく音楽を作曲するには、名人が必要です。この楽章の成功が、これから完成するであろう一連のコラール合唱曲のアイデアの種をまいたのかどうかは、推測するしかありません。
他の候補:
- BWV023-3,4.html
- BWV072-1,6+BWV027-1,6.html
- BWV072-1,6+BWV107-1,7.html
- BWV102-1,7+BWV008-6.html
- BWV103-1,6+BWV167-5.html
- BWV109-1,6.html
- BWV144-1+BWV107-1,7.html
- BWV187-1,7+BWV022-5.html
| 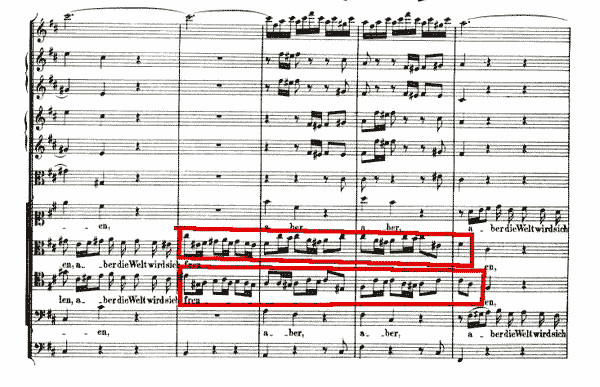
 喜びの動機
喜びの動機

 泣き喚く動機
泣き喚く動機