 |
|
|
|
|
|
|
|
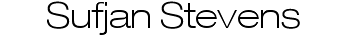  Tokyo, 2008. 1. 24 text by Yoshiyuki Suzuki interpretation by Yuriko Banno translation by Ikuko Ohno photo by Denny Renshaw ← Prev | 1 | 2 | Next → |
2008年の初頭に実現した待望の初来日時に、『アメリカン・オルタナティヴ・ロック特選ガイド』用にとったインタビューの完全版を公開。
マルチプレイヤーとしての資質とクラシックをはじめ多様な音楽的素養を持ったスフィアン・スティーヴンスが、真の意味で新しい存在感を持ったシンガーソングライターであるということは、彼が創り出した数々の独創的なアルバムのみならず、そこに盛り込まれたコンセプトのユニークさや、他の芸術表現への意欲的な姿勢、さらには家族経営のようにしてレーベルを成立させていることに至るまで、あらゆる活動内容が証明している。前述の本で「この人が後世において『21世紀の音楽家の中でも最も重要な人物のひとり』になる可能性は、かなり高い」と書いた気持ちは今も変わりない。
なお、この時の取材は諸事情により、インタビュアーである自分が途中で退席しなければならなくなるという異常なシチュエーションで行なわれた。なので、特に後半のやりとりは(質問そのものは自分が考えたものとはいえ)現場に私がいない状態で進められたものだ。この仕事も長くやってきたけれど、こういうのは後にも先にもこれっきりである。なので、ちょっと質問事項がとっちらかった感じになってしまっているが、それでもスフィアンの回答はいずれもが非常に面白く、さらに興味を沸き立たせるものになっていると思う。彼には改めて非礼を詫びつつ、またいつかじっくり対面で話をチャンスを持ちたい。
「僕の音楽には野外劇風なところがあるから、カラフルな衣装はそれを反映しているんだ。オーディエンスの感覚を直接的に刺激するような音の振動を使ったりもしてるし、視覚や聴覚に訴えかけて鼓舞するのが目的の音楽だからね。基本的には、人間の日常のこと、試練と苦難と……そして想像力について歌ってる」
一昨日の東京公演を見せていただきましたが、とても素晴らしいショーでした。
Sufjan:ありがとう。
ちなみに東京公演には特別にホーン・セクションを3人ほど増員していましたが、彼らは、たまたま同時期に来日していたルーファス・ウェインライトのバック・バンドから借りたんだそうですね。どのようにしてそういうことが実現したのか経緯を教えてもらえますか?
Sufjan:僕のショウは普段、5人のホーン・セクションでやってるんだ。今回はそのうちの2人が、The Nationalというバンドとプレイするためにオーストラリアに残ったんで、補充人員として、たまたま東京に来ていたルーファス達に頼んだんだよ。彼らとは以前から友達で、みんな素晴らしいミュージシャンだって分かってたから、快く引き受けてくれたのは光栄なことだった。まったく初めてプレイする曲もあったのに、本当にうまく代役を務めてくれたよね。
あなたの作り出す楽曲は、そういった管楽器だけでなく、他にも様々な楽器をフィーチャーしていて、すごく凝ったアレンジ、曲構成になっているものが多いですけれども、そういった作品はどういうふうに生まれてくるのか、あなたの作曲/アレンジの基本的なやり方のようなものを教えてください。
Sufjan:んー……どの曲にも凝ったアレンジが常に必要なわけじゃないけど、必要だと思った場合が…………ごめん、やり直していい?(笑) ええと……知りたいのはプロセスのことかな?
ええ、どういう作業を経て完成するのかと思いまして。
Sufjan:ふむ。曲のアレンジというのは、その曲ごとに最初から存在してるように感じるんだ……曲の中に備わってるとでもいうか。アレンジって作業の醍醐味は、それを見分けることなんだよね。抽象画を見ているうちに、だんだん形が浮かんできて、抽象の中から意味を組み立てることができるようになるのと似ているかもしれない。アレンジは時に、曲の意味を増補する役目を果たしたり、緊張感を高めたりする。で、僕はソングライターとしてはバロック派というか(笑)、多くの声を重ねたり、多くの楽器、ポリリズム、対旋律を使ったりするのが好きだから、自然とそうなるんだよね。自分の頭の中で聴こえる通りにアレンジしていくのが、僕のやり方なんだ。
一昨日のライヴでは、かなり頻繁にMCで曲の背景とかを説明して、しかも通訳してもらって観客に伝えようとしてくれていましたが、やっぱり各曲にはあの時に説明されたようなテーマやストーリーみたいなものが先にあって、そこから曲が出来上がってくるという順番になることが多いのでしょうか?
Sufjan:音楽の方が先だよ。ストーリーは後。僕の曲は、まず最初に音楽という形で出てきて、それにストーリーが適用されるんだ。ストーリーは大抵、僕自身、僕の人生、僕の世界、僕の経験を音楽に投影したもので、時とともに変わっていく。MCで話すストーリーだって毎回変わるんだよ。経験に基づいた基本的な青写真は同じで、後は色んなエピソードをその日によってアレンジしてる。ちなみに、2人の人物の対話形式が多いのは、僕の家族にそういう伝統があったからなんだ。お互いの注目を浴びようと、いろんなストーリーの違うヴァージョンを競って披露し合ってたんだよね。物語を語ることは、自分たちの暮らしに意味を与える方法だった。そういった伝統がある文化は世界中に存在するんじゃないかな。
では、何か実際に体験した物事を歌にしよう、っていう感じで書くのではなくて、まず曲があって、そこにどういう歌詞を当てはめようかなってことになった時、初めてそこでストーリーが出てくる、そういう形なんですね。
Sufjan:そんなにシンプルなものでもなくて。ソングライティングというものを簡単に要約することはできないよ。曲ごとに違うしね。曲作りのプロセスについて質問されることはよくあるんだけど、説明する度に違うことを言ってる自分に気づくんだよね。(通訳に)そう思わない? 僕の外交官である彼女が証言してくれるよ。
(笑)。
Sufjan:出産みたいなものだね。生まれてくる様子は1人1人が違うじゃない? 逆子だったり、双子だったり、大泣きする子もいれば、笑顔で生まれてくる子もいる(笑)。そんな感じだよ。……うーん、今の分かりにくかったかな?
大丈夫です。じゃあ、もう少し具体的な訊き方をしてみますね。まず『ミシガン』というアルバムは、あなたが生まれ育った故郷がテーマなわけですから、あなた自身の体験が、より直接的に歌詞へ反映されているような気がするんです。で、次の『イリノイ』はと言うと、あなたがイリノイ州についていろいろ調べて……例えばスーパーマンとか、UFOの事件とか、殺人鬼とかについて……つまり一般的な事実をより多く盛り込んで書いた曲が多いのではないでしょうか。で、そのことを踏まえつつ、この2枚のアルバムにおけるソングライティングのプロセスには、何か違いがありましたか?
Sufjan:そうだね。その推論はなかなか正確だと思う。片方はエモーションに基づいていて、もう片方はリサーチに基づいてる。表面的に要約すれば、確かにその通りだよ。でも、どちらのアルバムにも共通していることがあって、それは、地理とか実際のストリートよりも、みんな僕のイマジネーションの産物であるってことなんだ。だから、ミシガン州で生まれ育ったのに、『イリノイ』に登場する史実なんかが『ミシガン』のよりずっと正確じゃないかって言われれば、その通りなんだよね。自分の故郷に関しては主観的になるわけで。『イリノイ』のマテリアルの方が、実体験による感情的な重荷がない分、客観的に取り組めたんだ。
それから『イリノイ』の場合は、この1枚だけに収まりきらず、アウトテイクだけでもう1枚『ジ・アヴァランチ』というアルバムが出来てしまったぐらい、たくさんの曲が書けたわけですけれども、そういう客観的なテーマがあると、音楽だけでなく、歌詞についても、どんどん思い浮かんできてしまうものなんでしょうか?
Sufjan:そうなんだよ。本当に、このテーマには想像力がかき立てられて、曲が出来すぎてしまってね。必ずしもいいことじゃないんだけど(笑)、曲に対する責任を取らなきゃならなくて、どうしようもなかったんだ。
じゃあ、このあと48州も残ってますけど、まだまだ各州ごとに想像力がかき立てられ続けてそうな感じですね。
Sufjan:うん、そうなんだけど、ただ僕がインスパイアされるのは、実はアメリカでも、州ごとというコンセプトでもないんだ。曲自体は日常的なことを歌ってるし、50州のことを歌ってない曲も作ってるしね。どんなものでも魂を込めて、活き活きとするように書いてるつもりだよ。
それでは少し話題を変えて、あなたが子供の頃、どういう音楽環境で育ち、どうして自分でも楽器を習おうと思ったのか、それから、当時とりわけ影響を受けた音楽やアーティストを教えてください。
Sufjan:家で誰かが楽器を弾いてたってことはなかったな。両親は音楽家じゃないし。でも僕は中学の頃にオーボエを習い始めて、高校でも大学でも、オーケストラに入って演奏してたんだ。で、やっぱりオーボエをやってたせいで、クラシック音楽に親しむようになったんだよね。そんなに真剣に聴き込むことはなかったんだけど、オーケストラのレパートリーがクラシックだったから自然と接する機会が多かった。それから中高生の頃は基本的に、ヒット・チャートに入るようなポップ・ミュージックを聴いてたよ。もともと音楽に関してそれほど凝った趣味を持つタイプじゃないんだ。バングルズとかゴーゴーズとかキュアー、マイケル・ジャクソン……学校のみんなと同じものを聴いていた。でもある時、義父が自分の集めてたレコードをテープに録音してくれて、それで60年代〜70年代の良質な音楽を知ることができたってわけ。ビートルズとか、ストーンズとか、イエスとかね(笑)。それとビーチ・ボーイズ、ニール・ヤング……。大学で曲を書き始めたのは、その辺の音楽にインスピレーションを受けたからだよ。USトップ40ものだけ聴いてたら、自分で曲を書こうという気持ちにはならなかっただろうな。そういうのはエンターテインメントとして楽しめるけど、インスパイアされたのはニール・ヤングとかなんだ。
なるほど。ところで、2001年の作品『Enjoy Your Rabbit』は、十二支をコンセプトにしたアルバムでしたが、そこではエレクトロニックなサウンドを聴かせていましたよね。その種の音楽にも親しんできたのでしょうか。また、ああいったエレクトロニック・ミュージックをいつか再び試してみたいと考えていたりしますか?
Sufjan:えーと、その可能性はあるかもしれない。家では今でもそういう手法で作曲することはあるよ。ドラムのプログラミングもライヴでは時々トラックに重ねて使ってる。ただ、エレクトロニック・ミュージックって、今はちょっと新機軸が必要な時っていうか……ニッチ的になってるよね。10年ぐらい前はすごく盛り上がってて、既存の音楽に挑戦するような、ポスト・モダンでアンチ・ヒューマンな感じがして刺激的だった。僕もそこに惹かれてたんだ。ハイパーに未来的で、『ブレードランナー』的で(笑)。でも、その後の動向では商品化によって革新性が鈍ったような状態になってるね。もっと、エレクトロニック・ミュージックの外部の人間が実験していくべきなんじゃないかな。多分、そういう流れになってるんだろうと思うけど……まあ、質問に端的に答えるとすれば、僕もいつかまた試してみたい、ってことになるね。エレクトロニック・ミュージックは大好きなんだ。マウス・オン・マーズとか、オヴァル、オウテカ……すごく面白いと思うよ。
|
← Prev | 1 | 2 | Next → Special Issue | Interviews | Articles | Disc Reviews Core BBS | Easy Blog | Links © 2009 HARDLISTENING. all rights reserved. |