 『大野俊三』 『大野俊三』
1980年代の初頭、ニューヨークに移り住むことを考えていた僕は友人の紹介で一人のトランペッターを紹介された。初対面から気さくなその人物は紳士的に僕を受け入れてくれた。
さかのぼること数年、東京の武蔵小金井に住み着きジャズ・トランペッターとしてのスタートを切るべく村田浩(敬称略)に師事しながら日々練習に励んでいた僕は、その駅前にあった古本屋の2階の一件のジャズ喫茶に入り浸った。あまりお金がなかったため、そこで毎日のようにコーヒー一杯で長時間粘り、たくさんのレコードを耳にする。それまで日本人のトランペッターは日野皓正と師匠しか聴いたことがなかった僕はそこで初めて大野俊三というトランペッターの存在を知ることになる。
それは確か、ジョージ大塚のアルバムで1970代初頭のものだったと思えるが、「Invitation」や「Autumn
Leaves」における彼のソロのインパクトは今でも忘れない。直感的に「天才肌」だと悟った。マスターに彼のことを聞くと渡米して消息はきかないと答えた。
目の前に座ってライス・アンド・ビーンズを食べながら談笑する人物に目を向けながら、数年前のあのサウンドを思い浮かべていた。それから数ヵ月後、僕はニューヨークに移り住み幾度となく彼と行動を共にすることになる。
ある日彼に、「TAKAYAくん、一緒に練習しようよ」と自宅に誘われ生まれてはじめて他人と練習することになった。しかし、その力の差は歴然としていて、ほとんど個人レッスン状態になったのは言うまでもない。教則本やウウォーム・アップ等の重要性を彼から思い知らされることとなった。彼と僕は9歳しか離れていなかったが、ジャズに命をかけていた若輩にとっては認めたくはなかったが、その実力に脱帽するしかなかった。セッション等にも同行させてもらったが涙が出るくらい悔しかった。日野皓正が僕の背中を押してくれた存在なら彼は僕に火を点けてくれた存在だった。とにかく吹き続けた、彼の背中を見ながら死に物狂いに吹き続けた。それまでの日本人には見られなかった黒人のようなレイド・バック感、そのリー・モーガンやウディ・ショウに影響を受けたと思われるヒップなフレーズは僕が目標とする方向にはっきりと重なって見えた。しかし理由あって、その後彼とは、ぷっつり交流を断ってしまった。
彼がその当時使用していた教本は「Max Schlossberg」だった。それまでウォーム・アップも適当、ただ闇雲にラッパを吹き続ける、という僕本来の練習方法を根底屈がえさせられるきっかけとなった。タンギングはすべてシングル、リップ・スラーは強引、おまけにハード・プレスと、とにかく奏法で考えられるすべての悪癖を積み重ねていたのだ。ジャズを演奏するのに教本など必要ないと確信していた。
この教本のすばらしいところは、まず薄いというところ。これは教本嫌いには重要なポイントだろう。それに加えて内容が豊富で、クラシックの匂いがあまりせず、機能的にそれぞれの項目が学習できる。レンジも広く、本当の意味での実用音域を網羅している。教本など一冊で十分と思う人にはお勧めだ。Max Schlossberg 〜 William Vacchianoというニューヨーク・フィルの師弟関係の傘下には多くの優秀な弟子たちが存在する。まさしくニューヨークで生まれ育った「METHOD」だ。
何年か後に三上クニ(P)を介して大御所ビリー・テーラー(P)に呼ばれてリンカーン・センターで彼と横並びにステージに立てたとき、その充実感はそこに居ることより大きかった。人づてにそのときの僕の演奏を彼が褒めてくれたことを聞き、それまでの努力が報われたような気がした。そして、つくづく人との出会いの大切さを思い知らされることになった。実はそのときジミー・オーエンスやタイガー大越との4人でバトルをやったんだけど、お世辞にも僕の演奏は目立っていたとは言 えず氏の気使いを感じた。 えず氏の気使いを感じた。
そのときのリハ。左から
ベニー・パウエル、大野俊三(以下敬称略)、Akira Tana、Curtis Boyd、僕、クニ三上、ビリー・テーラー、増尾好秋、手前が秋吉敏子。
ここに、彼が初めて僕に聴かせてくれたアルバムを紹介する。
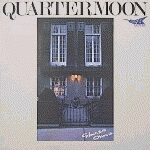 ジャケットは当時のLPとは違うが、16ビート主体の当時でいうところのフュージョンだ。4ビート信者だった僕は、彼をロッカーよばわりして少し反感をかったが、そのジャズ・スピリッツは十分伝わってくるアルバムである。ただ、僕が最も気に入った彼のアルバムは今は亡きカーター・ジェファーソン(TS)のリーダー・アルバム(MUSEレーベル)だ。その中の彼のプレイはすごくナチュラルで派手さも自己顕示もなく「PURE」なサウンドだった。そのレコーディング時のエピソードなど色々聞かせてくれた記憶がある。ちなみにその片面のトランペッターは、日野皓正だった。 ジャケットは当時のLPとは違うが、16ビート主体の当時でいうところのフュージョンだ。4ビート信者だった僕は、彼をロッカーよばわりして少し反感をかったが、そのジャズ・スピリッツは十分伝わってくるアルバムである。ただ、僕が最も気に入った彼のアルバムは今は亡きカーター・ジェファーソン(TS)のリーダー・アルバム(MUSEレーベル)だ。その中の彼のプレイはすごくナチュラルで派手さも自己顕示もなく「PURE」なサウンドだった。そのレコーディング時のエピソードなど色々聞かせてくれた記憶がある。ちなみにその片面のトランペッターは、日野皓正だった。
これらのアルバムでは聴くことが出来ないが、特筆すべきは彼のミュート・プレイだ。その美しさはマイルスに匹敵するかそれ以上だと僕には感じる。近年、たびたび日本を訪れそのプレイは健在らしい。僕のあるお弟子さんですらそのことを僕の前で絶賛するぐらいだ。
僕がある時期、無気力になって活動を停止していた頃、人づてにそのことを耳にした彼がこう言ったらしい「TAKAYAくんニューヨークに戻って来ればいいのに」と。
脱帽。

|