『我が永遠のアイドル日野皓正万歳』
それは、1970年代後半、僕がまだ高校生の頃だった。ジャズ・トランペッターとしての自我に目覚め始めた僕は音楽好きの友人達と連れ立ってあるレコード・ショップに赴いた。そこでレコードを物色していた僕は一枚のレコードを手にして友人に言葉を吐きかけた。「何やこれ、日本人やないか。カッコつけてんな」。その当時の僕はジャズは黒人のものだと確信していたし、日本人トランペッターが存在することすら知らなかった。友人の一人が「お前、日野皓正(敬称略)も知らんのか!世界的ジャズ・トランペッターやぞ」と一蹴された。返す言葉もない僕は、そのジャケットをしげしげと眺めた。頭にはパーマをあて、レイバンのサングラスをつけたその面立ちは、その頃流行っていたフォーク・シンガーと変わりないように自身には思えた。
あるとき、FMラジオから流れてくるその旋律に僕はある共感と快感を憶えた。そのとき初めて日本人ジャズ・トランペッターのサウンドを意識的に耳にすることになる。日野皓正そのひとだった。高校生ながらも僕の耳には衝撃的だった。日本人でもここまでやれるんだなというのが率直な感想だった。言い換えれば、それまで不可能だと思っていた領域への自分自身に希望を与えてくれた。遥かかなたではあったが、僅かな光を見出させてくれたのである。マイルスが僕の人生の方向を見せてくれたなら、この日本人トランペッターは僕の背中を押したようなものだった。
 19歳で上京した僕は東京で浪人生活を送ることになるのだが、その頃から頻繁にマスコミから彼の情報を知ることになる。いわゆるブレイクというやつだ。かつてもそういう状況はあったらしいがその当時小学生だったと思われる僕の知る由もない。そんなこともあって当然、僕は彼にのめり込んでいった。もちろんブラウニーやフレディー、モーガン、マイルスといった人たちは別格だが僕が聞く唯一の日本人トランペッターだった。レコードを聞きあさり、ライブに出かけまさしくアイドルだった。何もかもがかっこよかった。ただストレイトなジャズを好んだ僕にとって4ビートジャズを当時の彼から聞けないのは唯一の不満だった。楽器も不満とまではいかないが、コルネットよりトランペットの方が彼に適していたのではなかったかということも一ファンとして思ってもいた。しかし、アルバム「City Connection」における、ブルー・ミッチェルに捧げた彼自身の手によるバラードは、僕自身の感性を揺さぶった。感動的だった。しかし前述のこともあって、その後何年かの彼のアルバムには食指がいかず、その存在が僕の中から遠ざかっていった。 19歳で上京した僕は東京で浪人生活を送ることになるのだが、その頃から頻繁にマスコミから彼の情報を知ることになる。いわゆるブレイクというやつだ。かつてもそういう状況はあったらしいがその当時小学生だったと思われる僕の知る由もない。そんなこともあって当然、僕は彼にのめり込んでいった。もちろんブラウニーやフレディー、モーガン、マイルスといった人たちは別格だが僕が聞く唯一の日本人トランペッターだった。レコードを聞きあさり、ライブに出かけまさしくアイドルだった。何もかもがかっこよかった。ただストレイトなジャズを好んだ僕にとって4ビートジャズを当時の彼から聞けないのは唯一の不満だった。楽器も不満とまではいかないが、コルネットよりトランペットの方が彼に適していたのではなかったかということも一ファンとして思ってもいた。しかし、アルバム「City Connection」における、ブルー・ミッチェルに捧げた彼自身の手によるバラードは、僕自身の感性を揺さぶった。感動的だった。しかし前述のこともあって、その後何年かの彼のアルバムには食指がいかず、その存在が僕の中から遠ざかっていった。
それから数年後、すでにニューヨークで活動を始めていた僕は何度か「Lash Life」や「Sweet Basil」で彼の演奏に接する機会があったのだが、そのいずれもサイドで彼本来の姿を目にしたというものではなかった。それでもアルバム「Bluestrack」で彼が王道(僕の思う)に戻ってきたときは、何かほっとした気分になり久々にそれを購入した。僕自身の好みから言えばHal Galper(P)やSam Jones(B)のリーダーアルバムにおける彼のプレイが最も好きだ。それは彼のそれまでの奇跡の中で、最もハングリーなサウンドをかもし出すように僕には思え、音のひとつひとつから悲壮感が伝わってきたからだ。
今から10年ほど前に、あるテレビ局の企画で、彼とたまたま同じステージに立つ機会があった。別のバンドでステージを終え、フィナーレでそれぞれのバンドからピックアップ・メンバーでオール・スターセッションとなった。演奏が終了したあと彼と話がしたかったのであるが、僕自身があまり社交的ではない上に、彼に取り巻きが多く、それに嫌気がさしてそのままステージを降りることとなった。僕の悪い癖だ。
僕は評論家ではないので、何がどういいのかここでは論じたくもないし、多くのファンが賞賛を浴びせているのであろうことに対して今更付け足すこともあるまい。ただ演奏者の立場からひとつだけ確実に言えるのは、リズムの取り方が大きいということ。僕が昔、大変に世話になった在ニューヨークのトランペッター大野俊三(敬称略)も同様の感性をもっていた。他にも日本人のトランペッターには素晴らしい奏者はいるであろうが、僕にとってこの二人は最初から別格であった。楽器本来の奏法のあり方や理論的なアプローチとはかけ離れたところで、他の演奏家、特に若い人たちにとって十分参考になると思う。
「ヒノテル、万歳」。
追伸:その他、僕がはまったアルバム。
 写真『タローズ・ムード』1973(Enja) 写真『タローズ・ムード』1973(Enja)
とにかくエネルギッシュだ。上昇気流が巻き起こっている。
『ピース・アンド・ラブ』1970(テイチク)
『JOURNEY INTO MY MIND 』1973(CBSソニー)
情緒的なプレイは日本人のDNAを強く感じる。
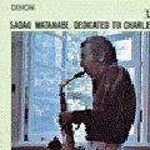 『DEDICATED
TO CHRLIE PARKER』1969 『DEDICATED
TO CHRLIE PARKER』1969
(NIPPON
COLUMBIA )
ナベサダのリーダー作での1曲だけの参加。
大きな壁を前にもがき苦しんでいる、そんな印象をうける。
結果より、そのプロセスが大切だということを強く感じた。
 |