
日本音楽会の頭脳、佐藤允彦が現在進めている数々のプロジェクトの中のひとつに「ランドゥーガ」がある。これからの音楽の鍵を握る、ランドゥーガの秘密に迫る。
取材・構成=山城國彦
 |
●神南備の岩(ホントは富士山の6合目近くのただの危ない岩場)に、なんとなく音楽の神様気分でたたずむ、佐藤允彦 |

佐藤允彦が「ランドゥーガ」の第2段アルバム『KAM−NABI』を発表する。 KAM−NABI(神南備)とは民族学の用語で“神が降りてきて、宿る場所”という意味だ。
ランドゥーガという場に、いろんな国の音楽の神様に降りてきてもらって遊んでもらおう、そういう感じです。神様っていうのは、どこの国でも、喜怒哀楽が激しくて、嫉妬深かったりして、案外人間的なんだよね。尊いとか偉いというイメージではなくて、すごく人間的になった神様って、魅力的じゃない?
90年の「セレクト・ライブ・アンダーザスカイ」で、日本初の新しい音楽として、佐藤允彦が提示した衝撃の「ランドゥーガ」。そのサウンドは、ファースト・アルバム『ランドゥーガ』(Epic Sony)に記録されている。それは、佐藤、ウェイン・ショーター(ss)、峰厚介(ts)、梅津和時(as)、レイ・アンダーソン(tb)、ナナ・ヴァスコンセロス(perc)、高田みどり(perc)、アレックス・アクーニャ(ds)、土方隆行(g)、岡沢章(b)という、世界各国混合メンバーによって、日本の民謡をモチーフにして、インプロヴィゼイションによって―――しかしこれまでのジャズとは違った方法で、音楽を作っていくものだった。
「ライブ・アンダー」で、サン・ラのアーケストラを見て、僕らがあれくらいインパクトのあることができることといったら「民謡」しかないかなって思った。それをつかってインプロヴァイズするわけだけれど、コードとかアドリブとか既成のインプロヴァイズの方法は使わないでやってみた。
…と、ランドゥーガ・デビュー・ステージの準備期間中に、佐藤はこう語っていた。 ランドゥーガは、特定のバンドの名前ではなく、音楽の種類といってもいいだろう。佐藤は91年の1年間六本木ピットインで、月一回の「ランドゥーガ・マンスリー・ライヴ」をおこない、さらに各地のジャズ・フェスに出演し、さまざまなメンバーで、新曲を増やしつつ、ランドゥーガ方式の音楽を発展させてきた。その成果が、この度のランドゥーガ作品2枚目『KAM・NABI』に集結したのだった。
「ランドゥーガ」で提示されたインプロヴィゼイションの新しい方法は、「遊び」が第一の目的となっている。気合いや楽器の演奏そのものを聴かせる音楽でも、自己表現のための音楽でもなく、純粋に子供のように遊ぶ音楽、それがランドゥーガだ。
こういうオモチャがあるんだけど、これで遊ばない?っていうのが、ランドゥーガの方法。オモチャ持ってない人でも、「何か貸してよ」ってやって来る人は歓迎。だけど、オモチャたくさん持ってるけど、見せびらかすだけで貸してくれない人はダメですね。 ランドゥーガの「寄り集まり」は、みんな肩肘張った「これが自分だ」みたいなものを捨てて、誰に似てもいいし、違うものになってしまってもいいし、なんでもいいから、そこにルーズなルールをこしらえて遊んでみようというものなんです。だから、聴く人もジャズとかいうのは捨てちゃって、コオロギの声とか風の音を聴くような感じでさらっと聴いてくれたらいい。時々何か耳にひっかかるものがあったら、何だこれ?って思って、入り込んで行ってもらって、またどこかへ抜け出ちゃうとか、そういうのがいいなぁと思ってます。
ランドゥーガは既成のインプロヴィゼイションの概念に捉われないで、自由に演奏者が「音で遊んでいる」音楽だ。当然、メンパーは固定されているものではなく、出入り自由だ。
90年の「ライプ・アンダー〜」の時は、日本の民謡の節を、いろんな国の人が演奏したらどうなるかなぁ?という発想で、ああいうメンバーになった。 マンスリー・ライヴ以降は逆に、今度は日本の人たちがいろんな国の節をやったらどうなるか?という発想を基盤にして、日本のミュージシャンに入れ替わり立ち代わりランドゥーガで遊んでもらっだわけです
これまでランドゥーガを体験したミュージシャンは以下のように実に十人十色のインプロヴァイザーたちだ。 梅津和時★、峰厚介★、土岐英史★、林栄一、山口真文、ウェイン・ショーター、姜泰煥(以上サックス)/ナナ・ヴァスコンセロス、アレックス・アクー二ヤ、高田みどり★、ヤヒロトモヒロ、YAS−KAZ★(以上パーカッション)/岡沢章★、グレッグ・リー、坂井紅介、吉野弘志(以上ベース)/レイ・アンダーソン(tb)/フェビアン・レザ・パネ(kb)/土方隆行(g)/内藤洋子★(箏)木津茂理★(民謡vo、perc)/松原勝也、桑野聖、後藤龍伸(以上violin)、宮田浩久(cello)<★は『KAM‐NAMI』にも参加している人>
ジャズをジャズ的なイディオムで表現して昔楽を演るのも、それはそれでいいんだけど、いろんなバックグラウンドをもったミュージシャンとインプロヴィゼイションする場合、ジャズ・イディオム…たとえばドミナントがどうとかスケールがどうのこうのということを持ち込んできちゃうと、ジャズを知らない人が入ってきた場合に、会話が成立しなくなる。だから、ランドゥーガは、そこに集まった人の中で、全員で会話カ成立するような約束ごと、ルールが出来るというのが理想なんです。 だから、参加者は、自分が今まで獲得してきて表現の方法を、一回全部を捨てちゃった状態で、つまりオープン・マインドの状態でやればいいわけです。インプロヴァィザーでなくても、とにかくオープン・マインドであれば、ランドゥーガは誰でもできるものなんです。
「オープン・マインド」という姿勢は、ジャズ・インプロヴィゼイションの範疇でも、多くのジャズ・ミユージシャンが口にする言葉だが、佐藤はそれをどう捕えているのか?
オープン・マインドでインプロヴィゼイションするというのは、どんな音楽でも、すごく難しい。どうしても自分が獲等した音楽表現によりかかってしまうからね。こういうふうにすれば、こうなるという効果が見えてるから、それに固執してしまう。それをいかに忘れて、何人かが集まって、パっと音を出した時に、その音の行く末を…そこに芽生えた音楽の芽みたいなものを、どれだけ素直に見守れるか?ということじゃないかな? できつつある音楽に対して自分が全部のものをそぎ落としたピュアな状態で対峙できた時、それがはじめてオープン・マインドの状態だと言えると思うんです。そういう状態になった時って、おもしろくて、気がつくと30分や1時間が経っている。
具体的にランドゥーガは、どのような方法で演奏される(遊ばれる)のか? たとえば【図1】は、佐藤が書いたランドゥーガの譜面のアイディアだ。この譜面に書かれているモチーフが、演奏者の自由な解釈で演奏される 1曲の中でいくつかのモチーフが使われる場合は、佐藤が瞬間的にキューを出して、場面を転換させていく。構成そのものもインプロヴァイズしていくわけだ。 以上のようなシンプルな約束が、「遊びのルール」あるいは「オモチャ」となって、後は演奏者の素直な音楽的反応に任される。このように、最低限の決まりの中で、無我の境地で音楽に対峙することを理想としたランドゥーガは、「究極のインプロヴィゼイション」の側面をも持っていると言えよう。このままつき進むと、ランドゥーガ式集団即興はどこへ辿りつくのだろうか?
ランドゥーガの行く末としてふたつの道が考えられる。 ひとつは、みんながほんとうにオープン・マインドになって、遊びの道具というのは何もいらないから、集まって何かやるべえって言って、完全にインプロヴァイズで、すごくいいものができるという道。 もうひとつは、モチーフがどんどんシンプルになっていって、しまいにはたったの2音だけになって、それをみんなで「プー・プー」って延々やり続けて、「ああ楽しい」ってことになるか、(笑)ですね。
ランドウーガは初め日本民謡をモチーフとして出発したが、その後、佐藤はさまざまな国(というか民族・部族)の音楽をネタにして、ランドゥーガの遊び道具としての曲を作ってきた。
『KAM・NABI』に収められている曲だけでも、その元ネタの分布は図2のようになる。言ってみれば、ランドゥーガはいわゆる「ワールド・ミュージック」でもあるわけだ。
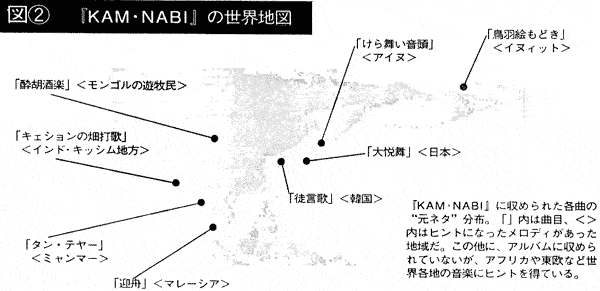
──元ネタとなるメロディを選ぶ基準は?
佐藤:もちろんメロディが気に入ったというのが第一です。それから、どうやってインプロヴァイズの中に溶け込ませられるか?という方法論・手掛かりが自分の中でみつかったら、曲にできる。 みんなで楽しく遊べる遊び方が見つかるか?という感じです。 ──ランドゥーガは、寄せ集めでできていると批判される種類のワールド・ミュージックとは、一線を画しているように思うのですが。 佐藤:全然消化していない音楽の断片を集めて、そこに装飾的にポツポツと置いていく手法は、体質的にぼくにはできない。きっかけはどうであれ、一回自分の中に取り込んで、自分なりに納得したものでないと曲に書けない。 けれども、その国の、その民族のメロディがどうやってできてきたとか、そのメロディの背後にどういう歴史的なものがあったかというのはぼくにはわからないし、逆にそれを知ったら、曲にできなくなるんじゃないかと思う。 ぼくの場合は「ああおもしろい、これやろうって」思って、曲にするだけだから、ものすごく表面的だと思います。もしかすると、その国の人たちにすごく失礼なことかもしれない。だから、敢えてたとえば韓国のシナウイを元にしているものでも『シナウイなんとか』っていうタイトルは付けていない。聴く人も、シナウイだと思って聴いてくれても、シナウイに似てるなと思って聴いてくれてもいいしね。 たとえば安藤広重の浮世絵をフランスの印象派の人たちが見てインスピレイションを受けて、新しい絵の手法を生み出しだけれど、別に印象派の面家たちは浮世絵を徹底的に研究してエキスパートになる必要はなかっだわけ。 そのへんにある花や鳥と同じように、モチーフとして浮世絵があったわけです。それと同じかなとぼくは思うわけです。 だから、盗んできたとか、表面的な理解で引っ張ってきたと言われれば、それはそうかもしれないけれど、その先はぼく自身の作業だから、誰も何も言えないはずだな、と。 これが「遊ぶ音楽」でなかったら、もっと徹底的に研究して咀嚼して構築し直してと思う。でも、ランドゥーガはそういう性質の集まりじゃなくて、やっぱり、こういうのありましたよ、ぼくはこういうふうに思ったんだけど、これを元にして遊ばない?という感じなんです。
──これからランドゥーガの方向性としては、このモチーフのネタになっている曲のオリジナルの演奏家と一緒にやるというのは考えられますね?
佐藤:それはおもしろいですね。レコードには入ってないけど、ガーナに演奏旅行に行った時に、現地の人がぼくたちを歓迎するためにずっとギターの原型みたいな楽器を弾いてくれたことがあって、それを録音してきたからモチーフにしていくつかの曲を作ってマンスリー・ライヴでやってみた。 それを、そのギターの原型を弾いてるガーナのミュージシャンに入ってもらってやったら、すごく変わってくるだろうね。そのガーナの人自身も変わってきちゃうかもしれないし。だから一回やってみたい。 ただ、彼が、オープン・マインドなインプロヴァイザーであればの話だけどね。そうではなくて、ただ伝続音楽をやるだけの人だったら、遊びにはならない。向こうの主張を聴くだけの集まりになっちゃ、しょうがないから(笑)。
ランドゥーガは、西洋音楽の外にはみ出した音楽だ。たとえば図1の譜面にも現われているように、テンポを自由に変化させたり、同じフレイズを好き勝手に繰り返したり、コブシを効かせてみたりと、西洋音楽のような、かっちりと決まったリズムとハーモ二ーは必要としていない。「音が同時に鳴ったら、それがハーモニーになる」というノリ。リズムについてはどうだろうか?
ランドゥーガのリズムは、うねるとか回転するという感じがする。それはランドゥーガに参加するパーカッションの個性なんだろうけどね。 これまでランドゥーガをやってきて、ある種の克服の仕方をしたと思うけど、実はまだまだインプロヴァイズをする上での、リズムの問題、リズムの組立て方は、後回しになってしまうんです。 だから今度は、リズムの側面にこだわったインプロヴァイズをしていく方法論を追求してみたい。西洋音楽系の直進性のリズムではないリズムの問題は、ほとんど考えられていないんですね。特にこれまでのワールド・ミュージックなどは、回転するリズムをもった各種民族音楽を、どのように直進性のリズムの上にのっけてしまうかということで、興業的な正否が決まってくる…そういう世界じゃないですか? だから、そういう糸トンポを新幹線に載せてどこかへ連れてってしまうような音楽ではなくて(笑)、糸トンボの中のものすごく小さなリズムの輪廻みたいなリズムを見て、糸トンボの棲んでる小さな池以外のところで、ぼくが糸トンポにどんな回転するリズムを与えられるか?それをこれから考えていくつもりなんです。
ランドゥーガは「徹底した遊びの音楽」だからこそ、究極のインプロヴィゼイションを追求し、新しい世界音楽への道をも歩み、常に自由に、無限の可能性を秘めている。 佐藤允彦を中心としたミュージシャンたちの、新しい「世界の遊び」を、これからも時々、覗いてみようではないか。
 |
佐藤允彦(さとうまさひこ)…ピアニスト、作/編曲家。日木を代表するピアニストであり、ジャスならもちろん何でもこい。作・編曲の分野でも常に斬新なアイディアを提示し続ける、日本音楽界の頭脳。1941年東京生まれ。 |
 |
『ランドゥーガ』 ■<曲目>1.磯浦網引き唄 2.陵王伝 3.捨丸囃子 4.井戸替え唄 5.田の畦節 6.鬱散うっぽぽ 7.稲が種あよー ■エピック・ソニー ESCA5171 |
 |
『KAM‐NABI』 ■<曲目>1.迎舟 2.大悦舞い 3.キェションの畑打歌 4.徒言歌 5.酔胡酒楽 6.鳥羽絵もどき 7.塔婆楽 8.けら舞音頭 9.タン・テヤー ■日本クラウン 11月21日発売 |
 |
●『KAM・NABI』レコーディンク参加者の面々。 前列左から、木津茂理.佐藤允彦、高田みどり、後列左から、峰厚介、土岐英史、内藤洋子、岡択章、梅津和時、ヤス・カズ。 レコーディングとは言え、遊びの音楽だけに.笑い声か絶えず、みな童心に帰り、リラックスしていた。突然、思わすジャズのフレイズか出たりすると、大ウケするというような状態。 |