|
第8章 マイ ディレクター
「頭の中が爆発した‥‥今度爆発したらもうあかん」 弱々しく笑って点滴の針が突き刺さった手で握手を求めはった。
「大丈夫ですよ」「弱気になったらあきませんよ」「早.よようなって下さい」‥‥月並みな言葉ばかり並べたてた。狭い病室で独り、白髪混じりで無精髭の彼を見ていると僕の方が心細くなる。追い討ちをかけるように「今度こそ捕まった。もう逃げられへん。」を繰り返す彼はもう観念しているようであり、そう云われると「ほんまにあかんのかなあ」と思えてくる。僕は自分の不安を振り払った。「ようなったら俺の2作目作って下さい。」そう、彼に今死んでもらう訳にはいかない。彼は9年前に出したレコードのディレクターだった。「俺も上手くなりましたよ」「見届けてくれなあかんわ」彼が僕の音楽史の唯一の理解者であるように思え、知らず知らず彼の必要性を自分の中に見つけ出していた。(この人を今失ってはならない)そう思うと、願いは具体化して熱を帯びた。
若き日は多少の非凡を信じて突っ走る。僕の場合、その集大成が半ば意地も手伝って作った一枚のLPである。出来上がった音をプレイバックした時点で、ちっぽけな野心は吹っ飛んだ。無惨な抜け殻は二・三度ターンテーブルの上を回ったきり、専ら見るレコードとして(ジャケットのイラストがよかった)部屋に飾られ、いつしか棚の奥に追いやられた。ーーーその一部始終を彼は見ていた。
「このレコードを作る事によってフィードバックされる時間は彼も僕も同様である。」 とは、彼がこのLPの為に書いてくれたライナーノーツである。あれからの年月をとにかく唄い続けてきたんだという足跡が今の僕にはある。というよりそれしかない。長い間傍観者だった彼がまた身近に感じられた。
くも膜下出血で倒れた彼は、己の生と死をじっと見つめていた。「感性と理性がずれるんだ」それは、音を創る者として致命傷である。たとえ生き延びれても仕事上生ける屍になるかも知れない。彼の見つめる死もまたその辺りを意味していた。「廃人になるとしても生きていたいよ」ぼんやりした意識の中でポツリと呟いた。
スポットライトを浴びている者ばかりが主役ではない。唄う者と一緒になって音を創り出してきた者達、創り出された音をずっと見守ってきた彼‥‥。
人の生死を己とのかかわりだけで捉えようとするところに自分の冷酷さを見た。と同時に、そんな狭い視野からの彼への願いが達成される事が、彼にとっても最良である事を‥‥立場が逆なら「音楽だけが人生やないよ」なんて言葉は、断じて聞きたくない。
「祈り‥なんて‥ケチ臭いもんはやめてしまえ‥‥マリア‥マリア賛歌や」クリスマスまでに仕上げる予定だった仕事の事が、彼の頭にこびりついていた。
(その調子や)僕はちっぽけな祈りを抱いて病室を出た。
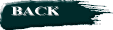
|