|
第6章 会えない友
見知らぬ町にきて ひとつの仕事分け合って
ひとつの部屋で ひとつ茶碗で食べあった
今祈る一人旅 この旅に幸あれと
今祈る流れ者 あいつに幸あれと
(ランブリングボーイ)
テレビのない暮らしもいいナと思え始めたが、3月から取り始めた新聞の最初に目がいくところがテレビ欄である事に苦笑する。「これ観たいなあー」というのが毎朝お決まりの台詞になった。かといって実際に実家にまで観に行くというところまでいかず、その台詞は、折込み広告を見て「これ欲しいなー」というのと変わらない。それから、おもむろに求人欄に目を走らせる。そこに求める業種を見つけたためしはないが、この2日間一つの会社の求人広告に目がとまる。以前バイトでいった事のある会社だ。そしてその社名と共にそこで働く一人の友の面影が浮かぶ。かつて友と呼ぶにこれほどふさわしい奴はいないと確信していた男だ。
僕らは古惚けた茶店のカウンターで知り合い、名乗り合った記憶もないまま、いつしか互いの姓を呼び合い、国鉄のストの最中歩いて旅に出た。ひもじいと座り込む僕に博学の彼は食べられる草を教えてくれた。一つの器でラーメンをすすり、最後の一本を両端からすすって思わず顔を見合わせた時は、互いの間抜けた、しかも真剣な面の一旦停止に心底笑い転げた。酔っ払って雑巾を投げ合った挙げ句に店を追い出されたり、千鳥足のスクラムがよろけて葬儀屋のガラスを割ったり、凡そ乱暴で寸劇風な絵に描いたような青春のエピソードばかりが思い浮かぶ。
ある日のこと明石城の芝生に座り込んで、行き交うアベックに下駄を投げながら、僕らはもの書きになろうと誓い合う。それから原稿を持ち寄って批判し合う日々が続き、事務所を作り、同人誌を発行し売り回った。その後互いの連絡が途切れてからも彼は企業PR誌を、僕は詩を書き続ける事で若き日の誓いは心細いながらも保たれていた。書き続けていればいつかまた会う日も来るし、疎遠感を持つ事もない。そんな風に考えて無理に会おうとはしなかった。
彼がPR誌の編集を投げ出したと聞かされた時、僕はすぐに彼が以前書きたいと構想を話してくれた小説のことを思った。ずっと何かを書き続けてきた男だ。一つの企画をやめたとしても筆を置いていられる筈がない。これはきっと他に書きたいものが出来たからに違いないと僕の記憶の中でほくそ笑んでいる彼の肖像がちらついた。ところが、いくら待っても何の動きも伝わってこない。しびれをきらして今年初めて出した年賀状も宛先不明で返ってきた。ーーーそしてこの広告。
連絡をとってみる事は容易い。多分会う事もそれほど困難ではないだろう。しかし何の為にーーー。「一度会おや」という友は多い。近況を晒し合い思い出を振り回す。しかし彼の位置づけは僕の中で特別である。彼を誘い出すに充分な生き様が今俺にあるか、とそんな風に身構えてしまう。空間的に離れていたのなら、なつかしさだけで会えただろうが、いつでも会えるという設定が僕を力ませる。
「壁に爪をたてる」と言えば「壁の内側をぐるぐる回る」と切り返し、「夢を追う」と言えば「夢は食らうもんだ」と言い返す。そんな彼とのやりとりを忘れた事はない。彼の歩き回る壁は若しかしたらメビウスの輪のようにねじれていて、いつの間にか壁の外側に出てしまったのかも知れない。それならば、また一回りして壁を越える日も来るだろう。
もう少し待ってみるかーーー待ち応えのある奴なのだから。
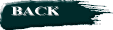
|