|
第5章 もの書き
五階建ての団地を昇りきった突き当たりに「団栗出版」の看板があった。引っ越しの度に表札代わりに運ばれた看板である。ある時彼は「"団栗出版"は一生の仕事やで」と言った。彼と知り合ったのも団栗出版の発行による「西部夜話」という小冊子を通してである。その頃の僕は友人と二人で事務所まで借りて「絵流夢」というミニコミ紙を出していたので、彼との出会いも自然書評から始まった。その後「書いてみいへんか」という話しがあり、彼との共著による小冊子を作る事になる。その間何度かもった会合で話題の中心になったのは「何故書くか」という事であった。僕にしてみれば今更何故そんな事にこだわらねばならないのかが分からず、その話題になると閉口せざるを得なかったのだが後にそれは、彼自信の作品に対する厳しさである事がぼんやりとではあるが分かったような気がした。何度も自問自答を繰り返しながらテーマを突き詰めていったに違いない。この一冊を発行して以来、彼はいつしか僕の"もの書きの師匠"となった。
「お前の文は理屈っぽい。歌詞の方がましや」と言ったのも彼なら、「姿勢が悪いとええ歌唄われへんぞ」と正座の本を手渡してくれたのも彼である。元来、他人の意見ー特に命令には耳を貸さない僕が彼の「出てこい」の一言で、夜中であろうと駆けつけた。そこにはいつも新たな出会いが待っていたからである。カメラマン、もの書き、イラストレーター、漫画家と彼の家にはいつも新奇な人種が集まった。体験や夢を語り合う夜に何杯もの酒を注いだ。決して夢ではない自由な行き様がある事を、感化され飛び立とうとしている自分を見つけた日々である。
ある時彼は陶芸家だった。茶器とどんぶりの合いの子みたいな器は今も僕のラーメンどんぶりとして重宝されている。
ある時彼は高校の美術教師だった。落ちこぼれの生徒達が美術室にたむろするようになり、彼はそのリーダーであった。
またある時彼は日雇い人夫だった。後に僕も同じ仕事をするようになるが、彼の名前は既に伝説となっていた。
そしてある時彼は仏教課の通信生でもあった。彼がより厳しく人間を見つめ始めたのはこの頃からである。
40歳の正月、子連れで彼の家に行くと、彼もまた赤ん坊を膝に抱えていた。「春になったら引っ越す」という言葉を聞いたのはこの時である。別に驚きはしなかった。引っ越しは毎度の事であるし、彼が何をしようと今までの仕事以上の重みはなかろうと思っていたからである。その根底には"もの書き"の彼がいた。その辺りで安心していた僕は彼が「農業をやるんだ」と言った時も、当然の帰結のように受けとめていた。
今年で2年目に入った農業は彼にしてみれば一大決心だったのかも知れない。このまま一生の仕事イヤ生活として定着してしまうのだろうか。どっちみち彼は日々の生活を書き留めていくのだ。そこに書く事の必要性を求められながら‥‥。いつか「農業って難しいナア」と自信に満ちた顔で言う彼を、「もの書きの師匠です」と紹介すると「恥じかきの師匠で‥」と茶化す彼を、そして表札代わりにまた何処かの家に「団栗出版」の看板をあげる彼を、僕は待っているのである。
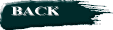
|