第3章 ラストカウボーイ
不要になったものが剥ぎ取られた赤裸々な骨格をまた透明な風がくっきり浮かび上がらせるものだから、秋の日は風の音を聞いただけで震え上がってしまう。削って削られてもうこれ以上切り捨てるものがないといった殺風景なカウンターに座り込んだ。
神社の参道から入り込んだ路地裏の空間に土建屋の倉庫がある。この倉庫以外の何ものでもない扉がこの店の入り口ーーーコカ・コーラの広告入りの蛍光看板や、或いは"COWBOY"という木製の看板など凡そ喫茶店らしい装飾が一切無いのは決してマスターの怠惰のせいではない。それらはある日突然無くなっていた。酔っ払いが夜中に持って行ったという。以来この倉庫が知る人ぞ知る茶店となってから既に久しい。
外見ばかりではない。「ごちゃごちゃして気にくわんのや」という同じ理由で店内から様々なものが姿を消していった。
先ずポーカー用の(僕にとっては占い用であったが)トランプが消えた。続いてコンクリの壁を飾っていたダートが消えた。酔っ払いがOLDの瓶片手に入ってきて悪態をついて帰ると、次の日には棚から酒瓶が消え代わりに"酒気を帯びての入店お断り"の貼紙がはられた。ゴキブリが徘徊するようになると、奥の棚隠しに使われていた星条旗が消えクレオゾートの原液が店内隈無く塗られ、トイレのタンクのパッキングの調子が悪いとなると、タンクが消え水道の元栓から直接ホースがひかれ、「ガス代が高い」とこぼしていたと思うと、コンロが消え豆炭の七厘が置かれた。しかしこれだけは倉庫という密室の中で客が酸欠状態に陥った事から後に灯油ストーブの改良コンロに変わる。
その他にもメニューが削られ、客の数も削られ12年という月日を経て残ったものは、客が寛げる唯一のカウンター、そのカウンターに客がいる時だけ点る天井から吊るされたむき出しの蛍光灯、そしてマスターのベッドとなるカウンターの足置きと膝当て板等、最低必要な生活の臭いがするものだけである。更にそれは現在進行形で、来る度に何かが消え「マスター あれは?」と聞くと今でも同じ答えが返ってくる。そして僕はその合理化の徹底にいつも成る程とうなづいてしまうのである。
合理化というと便利とか文化的とかいうイメージに直結してしまう事が多いが、決してそうでない事をこの店に来る度考えさせられる。そして客観的にはもうこれ以上削りようがないと思われるマスターの生活は、彼に言わせるとまだまだ無駄が多いのである。
そのマスターが先日「店 たたもうか思てね」と切り出した。無理もない。ここ数年僕がいる時に(僕は大抵2〜3時間ボケーッとしているのだが)他の客と居合わせた事がない。この店が存在する事自体奇跡だという者もいた。
それでも一応「なんで?」と聞かずにはいられない。「もう年やし 年金もろて翻訳の仕事しよう思てね」「‥‥!」「これからは文筆活動しよう思てね」
店の事を振り返って「昔は‥‥」調で話し出すのは決まって客の方である。マスターはその類いの会話には入ってこない。「今度××しよう思てね」‥‥そしてその××は決して客の相槌の中に消えてしまう事はなかった。
合理化というのは無駄をなくす方向性を持った自然の摂理であると同時に、ライフワークへのより近い道を見い出す事かも知れない。マスターからこの店をも削り取っても「はるかなる西部」は彼の中で膨らみ続けて行く。"COWBOY"というのはこの店の名前ではなく、彼自身の代名詞なのだ。
「音 出そうか」 うなづき返す間もなく、手は自家製のレキントギターに伸びている。カウボーイソングとブルーヨーデルのステージが始まる。何もかもが初めてこの店の扉をくぐった時そのままに‥‥あの時既にラストカウボーイだったんだ この人は。
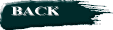 |