|
第17章 道具商
初夏の雲が浮かんでいた。光は白く乱反射して埃っぽい車道に溢れていた。国道沿いにあるその倉庫は、見過ごしてしまいそうな程ありふれている。が、一歩中に踏み入れた途端、そこに広がる異様な世界にキュッと萎縮する体を感じた。
倉庫のほぼ中央の高い天井から吊り下げられた一つの裸電球、電球の下には一脚の机、その机の上を流れる様に次々と現われては消えていく"物"達ーーー電化製品、人形、食器、電話、本、眼鏡、家具等々凡そこの机の上を流れない文化はない。"物"はある時は一つで、またある時は一箱にまとめられて流れていく。そして裸電球の真下で僅かに止められた。
机をはさんで向こう側に立つ一人の男が"物"にチラッと目配せしてこちら側を睨む。「ハイ100両!」その声にこちら側から声がかぶさる。「500」「1000」‥‥「はい2500!」その間僅か4秒、休む間もなく視線は次のモノに注がれる。ーーーここは道具商の市、ありふれた倉庫が一と六のつく日には市場になる。ギャラリーは近辺の道具商達である。道具商といっても古美術商から荒ゴミ専門の人迄種々雑多で、何を競り落とすかを見ているとその人の店の専門が分かる。とは言え店を構えている人はごく僅かで、多くはまた他の市に流してその差益で暮らしていると聞く。ここで500円で競り落としたオーディオが地方に持っていくと7000円にもなるという。それだけにこの僅か4秒は緊迫している。
この日、道具商のHに連れられて初めて市なるものを見た。彼が"ぐうたら堂"を構えてそろそろ一年が経とうかというのに「まだまだ市で欲しいものが買えない」という。競り負けるのでは仕方がないが、同じ値をつけてもモノは古参の手に落ちる。ひどい時など高い値をつけても無視されるといった調子だ。そのうえガラクタ同然の品で誰も値をつけないでいる時買わなければ、競り師に睨まれる。彼に睨まれるとその次いくら大声を張り上げても無駄で、あからさまに「お前には落としたらへん。なんでさっき落とさへんかってん」とくる。とかく新参者には排他的である。市にいい品を持っていくとその分信用が出来て、「◯◯の山」(○○が持ってきた品)というだけでギャラリーは高い値をつけるが、ここでも儲け過ぎてはいけないらしい。持っていってばかりで買わなければまた心証を悪くする。
こうしてガラクタばかりを買わされる羽目になるのだが 、このガラクタが結構面白い。一箱500円の"福袋"といったところだ。外に出て落とした品を仕分けし、要るものと要らないものに分ける。要らないものはその場に捨てていく。古時計を一つ落としたのだが、陽光の下では顔が違う。その時になってあの裸電球の効力に気付いた。
"物"はその時代に生きている。蛍光灯の下ではただの屑のような品々が、裸電球の下では確かに生きていた。時計の中に紛れ込んでいた"大日本帝国"の10銭切手を眺めながら、このガラクタの活きていた時代とかつての所有者達の面影を追っていた。
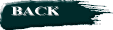
|