|
第14章 運動から個人へ
死体となった僕の上を警官がまたいでいく。見渡せば通りは死体の山ーー寄り添うように手を繋ぎ、車道を埋めつくしている。
「歩道に上がって下さい」しきりに怒鳴る拡声器ーー「死体に耳は無いぞ」応える人達。僕の傍らで幼子を背負い小さな男の子の手を引っ張った母親が哀願する。「悪いのはあの人達ですよ。間違わないで下さい‥‥」これがダイ・イン 2月12日午前9:00、高松の四国電力本社前での出来事である。
10年前、伊方原発運転反対の裁判費用をつくる為にカンパという形で買った準備書面から原発というものに関わり始めた。しかしそれは半ば好奇心から生まれたもので、運動といっても決して連続していた訳ではない。今日に至る迄の間に力を注いだ住民運動ーー三里塚、関西新空港等が悉く破れていく中で、いつしか僕はニヒリズムに陥っていった。"所詮他人事"という考え方が常に心の片隅にあった。
差別は悪い事だと人は云う。若い自分もそう思った。では何が出来るのかーー運動ーー連帯そしてそれが決して一体と成り得ない事にはがゆさを覚え、支援していた筈のグループから「他人事だろう」と突き放された時、応える言葉もなく運動というものに疑問を持ち始めた。それは在日韓国人或いは金芝河とのかかわりの中でニヒリズムに変わっていった。金芝河は言う「あなた方の運動は私を助けられない。でも私の言葉はあなた方の運動を助けるだろう。」
‥‥この言葉は今も心に刻まれ、運動の本質を問い続けている。‥‥それから僕は逃げ始めた。運動から、そして現実から‥‥唄からもメッセージ色が消えた。
スリーマイルで、チェルノブイリで事故が起きた時"そらみたことか"と心の隅でほくそ笑んでる自分がいた。情けない話だ。2月に入って、今は陶芸家として"原発無用"のロウソク立てを焼いている師匠から電話があった。「お前は本当の恐ろしさが分かっていない」「分かってます」「イヤ分かっていない」ーーそんな押し問答の末、高松行きを承知した。チェルノブイリが及ぼす食品汚染は知識として知っていたし、授業でも折に触れ取り上げてきた。その自分が今は動いていない。過去に反対したのだと言う自負からかろうじて語る事が出来たに過ぎない。
広瀬 隆は言う「数字やパーセントに誤魔化されるな」ーー何千何万の死者が出ようとそれが「何%の危険性」と聞かされてはピンと来ない。恐ろしいナで終わってしまう。これがニヒリズムだ。彼は本音を吐く「何万人の死者が出たという事より、私の娘一人の命が危ぶまれている。それだけで充分だ」「もう運動の段階ではない。多くの人が知る事が肝要なのだ」と。この言葉に僕は動かされた。運動となればそっぽを向いてしまうが、自分の子供の命を考えた時、個人としての関わりが始まる。私生活主義に陥った大衆一人一人が事実を知る事、そこから生まれるエネルギーは社会を動かす。
チェルノブイリは今も死者を出し続けている。日本にも放射能の雨が降り続けている。要素131を含んだ牛乳を僕は毎日がぶ飲みしている。誰一人もう逃げられない事は知っているのだ。
「皆で死ぬなら恐くない。せめて生きてる間は楽しく暮らそう」ーー恐るべき日本人の心中思想ーーセシウムが体内に入って病状が発現する迄30年‥‥僕らは知っている。広島を、長崎をそしてビキニ島を。しかしビキニ島の住民が島を離れたのがほんの2年前だという事実を知っているだろうか。みんな死ぬ。でも一緒にではなくジワジワと一人また一人と苦しみながらだ。
「あきらめたらあかん」師匠の言葉がようやく自分の言葉になった。
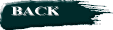
|