|
第12章 旅人
彼がそこにいるというだけで、その国や街が身近に感じられるのは不思議である。ボリビア共和国から手紙が来た時は政情不安を案じ、インドに住み着いたと聞くと「何食べてんのかなあ」と食生活のことを思い、「ナイロビに行く」とパリから連絡が入った時はただもう羨望だけで地図帳に広がるアフリカ大陸を見つめていた。
特に親しいという訳でもない彼が、僕の放浪に割り込むようになってからもう10年以上経つ。僕が広島でフラーリフラーリしていた頃彼は750ccを飛ばしてやってきた。ヘルメットを脱いでバサッと顔を覆った長髪を掻き揚げようともせず、黙り込んで部屋の片隅に座り込んだ。僕は持ち前の暗さで張り合っていたが結局彼の沈黙に負けて話しかけたのがきっかけである。
当時の会話といえば自分が旅してきた土地のエピソードを話し、相手からもいろんな街のことを聞き出すというようなやりとりが話のきっかけであり、それに第三者が口を挟んで会話が発展するという仲間意識に支えられたものだったが、彼とはこの最初のきっかけからいつも通りに行かなかった。
「何処行ってきたん?」「ドイツ」「‥‥」「‥‥(黙)‥‥」「‥‥」海外旅行は決して珍しい事ではなかったけれど隣町に行ってきたみたいにポツンと言ってのけ決して小集団に溶け込もうとしない彼には確かに仲間意識が欠けていた。勿論こんなやつは何処に行ってもいたが、彼の場合孤独を演じたり楽しんだりしているというのではなく、生まれながらの孤独を仲間意識というベールに覆って馬鹿騒ぎする僕らとは違って臆面もなくむき出しているように思えた。孤独なんだからこうして黙して座り込むしかないといったような‥‥。そんな負の絶対値のような強さから、彼の存在は通り過ぎる旅先の友達とは違って、深く重く僕の生活に割り込んできたのである。
言葉は行った先で覚えるとか片道分稼いだらとにかく出るとかいったやり方は行き当たりばったりで不安ではあるが、でもきっとそれが本当の放浪であり、旅なのだろう。ホテルの予約など計画的にとろうものなら修正された絵葉書の風景を探すばかりで、冒険といっても片手にしっかり日本から持ち出した家イデオロギーを握りしめているのだからその街に溶け込むって事は出来ないような気がする。とにかく僕が沖縄に行くにも北海道に行くにも片道の船賃くらいでなんとかやってこれたのは全く彼のおかげなのであり、その間彼の方もシベリア鉄道経由パリ〜北アフリカ〜インド、パリ〜アメリカ〜南米と貪欲に歩き回って忘れた頃に帰ってきた。いや帰った来たというより旅の途中に訪ねてくれた。何処の国にも染まらないのは素敵だ。まるで無国籍人のように「南アフリカに行きたいんだ」と言った。2年前その言葉を受け取った時僕にはもう嫁さんも子供もいた。そして独りで生きていける彼を強い人だと思った。男の浪漫・憧れを追い続ける彼に少なからず嫉妬していたのだろう。
ニューヨークから電話がかかってきたのは1月の終わりである。「ホテルの部屋に電話ひいたんだ」南アフリカからパリに帰った彼がアメリカに渡った事は前の手紙で知っていた。しかし詳細を聞くには電話代が気になるし「元気?」とか「どないしてる?」とか全く仕様のない事しか口に出なかった。そんなやりとりの後突然「手紙届いてないよ‥」と彼は言った。「‥ごめん居場所が分からなくて‥」と言ってから「淋しい?」と聞いてみた。「そりゃあ淋しいよ」「日本に帰りたい?」「そりゃあ帰りたいよ」友人みんなに電話してるから電話代が高くつくと言って笑った。電話番号を繰り返した後「留守番電話も入れてるから」と言った彼‥‥これだから彼とは離れられないのだと思った。彼の存在感はその強さにではなく、その弱さに根ざしている。「あと1・2年は帰らない」という言葉を受け取って受話器を置いた後ニューヨークの街並をまた身近に感じていた。
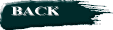
|