第1章 何度目かのプロローグ
神戸を離れる時この街にはもう何の未練もなかった。唄い続ける事にも行き詰まっていたし、何より失恋の痛手は僕を押しつぶす迄に膨らんでいて身の置き場もなかった。肌寒くなった秋風を纏いながら、もう何も信じるものかと小樽行きの長距離フェリーに乗り込んだ。北海道という地に夢見るほど若くはなかったし、ただ遠くへ逃げ出したかったのだ。
2等客席のだだっ広い床の端に陣取ってせめてラーメンでも買い込むべきだったと後悔し始めた頃、目の前に一本のきゅうり巻きが差し出された。
何のためらいもなく一気に食べてしまう。「よかったらこっちのも食べていいよ」−ーーその時になって初めて相手の顔を見た。髭面の中に涼しい目許が眩い微笑みの輪郭を生み出す。
「有難う」口に出したのはニ本目ののり巻きを頬張ってからだった。31時間のフェリーの中で彼と話したのはふた言三言「行くあてがないなら一緒に山小屋へ来ないか。友達が枕木で作った小屋なんだ。」もともと行くあてなど無い。早朝五時の小樽に着いてフェリーを降りる時にはきっちり彼の車に乗り込んでいた。
M(彼の名前は山小屋に着いてから知った)はそのまま知床にある彼の店に車を走らせて行った。それから三年、僕はニセコにある山小屋と知床の彼が働いている店を行き来し北海道に住み着く事になる。
山小屋の生活はのんびりしたもので一日中何もしない。ぼけーっと眼前の羊蹄山を見ながら一日を暮らす。仕事といえば犬のえさを作る事と貰い水に行く事くらいだ。その中で、僕はまた唄い始めていた。灯油代ぐらいは出るだろうと隣街まで唄いに行く事もあった。
冬の夜長に暖をとる猫達がいた。みんなが夢の中に生きていた。
長い氷点下の中で僕はフォークシンガーの僕を取り戻そうとしていた。
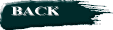
|