![]()
アートワークにまつわるエトセトラ
〜 Storm Thorgerson 展@渋谷パルコギャラリー
6月2日(土)、ストーム・トーガソン (Storm Thorgerson) の展覧会を観に渋谷パルコギャラリーに出かけてきました。 ソーガソンとかソージャーソンとかいろいろなカタカナ表記を見たことがあるような気がしますが、今回は「ストーム・トーガソン」ということになったようです。彼はヒプノシス(Hipgnosis) という芸術集団の中心人物で、70年代を中心に Pink Floyd の一連のアルバムカバーをはじめ、ポール・マッカートニーやレッド・ツェッペリン、フラッシュ、10cc、ウィッシュボーン・アッシュ、果ては松任谷由実まで、数多くのアーティストのジャケットデザインを手がけたことで知られています。「知らないよ」というお方もフロイドの『原子心母』のアートワークくらいはご覧になったことがあるのではないでしょうか?  自分はヒット曲/アルバムを聴くにあたって、割とアートワークが気になるタイプです。厳密に言えば、録音物として封じ込められている音や歌詞とは切り離して捉えられるべきものかもしれません。どんなによい録音であっても、ダサダサのジャケットの盤もありますし、逆に、ついジャケ買いしてしまったディスクのあまりにも酷い楽曲に涙を呑んだことも数知れず。 それでも多くの場合、音楽を聴くときに心に浮かぶ映像はレコードのアートワークであり、ジャケットを眺めるときに心に流れるサウンドは収録されている音楽であるわけです。例えば、アイアン・メイデンやメガデスを聴く場合、そのサウンドはジャケットのキャラクターと完全に一体化してるでしょう? あるいは、スティーリー・ダンの "AJA" を聴くとき、あの山口小夜子のジャケット写真はAORの粋を究めたサウンドと一心同体だと思うのです。 さて ストーム・トーガソンあるいはヒプノシスの場合、単なるレコードの付属物としてのジャケットアートを超えた何かを感じずにはいられません。それ単体としても十分に鑑賞に堪える芸術作品といってよいのではないでしょうか。しかしやはり、その拠って立つべき元のレコードのイメージを壊さない、むしろその良さを大いに引き立てる役割を果たしている理想的な例ではないかと思います。 会場にはこれまで彼が手がけてきた数多くのロックレコードのジャケットやポスターがびっしりディスプレイされています。やはり目を引くのはピンク・フロイドの一連の作品のお仕事。アナログ時代の大きなサイズでのアートワークはもちろん、CD時代に入ってからも趣向を凝らして特殊ジャケットの可能性を追求してきたひとつの究極が、95年のライヴ盤 "PULSE" における、電池入りでが点滅し続けるというパッケージでしょう。  もちろん、中には決して成功したとはいい難いアートも展示されています。例えば Dream Theater の "FALLING INTO INFINITY" のデザインなどは、あまりアーティスト側と深くコンセプトについて議論した結果とは思えません。むしろフロイドの "DIVISION BELL" のアウトテイクに近い印象。"DIVISION BELL" のアウトテイクでは他に Bruce Dickinson の "SKUNKWORKS" まで作っており(と勝手に決めつけるのもアレですけど)、ちょっとタチが悪い感じです。また、Thunder の2ndアルバム "LAUGHING ON JUDGEMENT DAY" なんかもちょっと首を傾げざるを得ません。大上段に構えすぎたアートの大仰さが、このバンドの最大の魅力であるロケンローの楽しさを殺してしまっているから。 してみると、フロイドとの仕事が抜きん出ているように感じられる理由は、バンド側とアルバムコンセプトについて十分に話し合った結果を踏まえて、ストーム・トーガソン(またはヒプノシス)側がじっくりアイディアを練り上げた印象を受けるからなのでしょう。アートワークをじっくり鑑賞してから音を聴くと、なるほどそういうことかと納得し、逆にアルバムを聴きこんでからジャケットを手に取ると、そうだったのねと合点する。そんな視覚と聴覚がお互いを刺激し合うある種理想的な関係が、ここにあります。 他の例を挙げてみましょう。私にとって極めて重要なバンドにカナダの Rush があります。そのサウンドは、私にとってトリオ編成で演奏し得るロックのひとつの究極。単に Geddy Lee, Alex Lifeson, Neil Peart の3人のテクニックだけを指して言うのではなくて、少ない音数でも曲を心に響かせる術を心得ている点をこそ評価したい。  そんな Rush のアートワークを手がけてきたのは Hugh Syme です。彼と Rush との付き合い方はストーム・トーガソンとフロイドのそれによく似ています。アルバム1枚1枚のコンセプトを、如何にヴィジュアルに表現するか。結果は当然、ジャケットごとに作風がどんどん変わります。 例えば "A FAREWELL TO KINGS" "MOVING PICTURES" "PERMANENT WAVES" "PRESTO" などでは、知的なジョークも感じさせるトリック・アート的な写真をデザインしていますが、"HEMISPHERES" では大脳生理学と神話世界が交錯する重厚なイラスト、かと思えば "A SHOW OF HANDS" のようなポップなイラストや "GRACE UNDER PRESSURE" での淡い水彩画の如き世界も描きつつ、"HOLD YOUR FIRE" "COUNTERPARTS" では超シンプルなロゴ風デザインも。"EXIT... STAGE LEFT" での過去キャラ大集合も楽しい。 このように、Rush のジャケットにおいてはアーティスト側と綿密に打ち合わせた結果が窺い知れますが、当然 Hugh Syme 自身の得意な形式というのはあるようで、それは次のようなジャケットに典型的に表れているのではないでしょうか。いずれもこの手のロックのファンならニヤリとするものばかりではないかと思います。ああ、コレね、と。      左から、"NEW JERSEY" - Bon Jovi, "KINGDOM COME" - (same), "IN YOUR FACE" - Kingdom Come, "1987" - Whitesnake, "SLIP OF THE TONGUE" - Whitesnake      左から、 "PROMISED LAND" - Queensryche, "PARALLELS" - Fates Warning, "RETRO ACTIVE" - Def Leppard, "YOUTHANASIA" - Megadeth, "COVERDALE PAGE" - (same) 一番好きなロックアート画家であるロジャー・ディーンと、Yes の諸作品における彼のアートワークなどについても語りたいのですが、ちょっと脱線しすぎたのでそれは別の機会に。 本題に戻ってストーム・トーガソン。 残念ながら近年の作品は、個人的には絶賛というわけにはいきません。上でも触れた Dream Theater の作品や、The Cranberries の "BURY THE HATCHET"、The Alan Parsons Project の "TRY ANYTHING ONCE" "ON THE AIR" など、明るい色調のシャープな写真を用いたものが増えつつあるようですが、本当にアーティストのイメージしたヴィジュアルを体現できているのか、疑問なしとしません。 その意味ではフロイドにおいてもそうで、"THE DIVISION BELL" のアートはやや理解に苦しみました。さらに、"A MOMENTARY LAPSE OF REASON" については、そもそも音自体ピンク・フロイドと呼んでよいのかどうかという深刻な問題もありますが、アルバムジャケットについてだけ言うと、空っぽのベッドを水際に無限に並べるという気が遠くなるようなアイディア、アルバム中の曲名や歌詞を引用したモチーフがあちこちに配置されたデザインなど、よくできているのは確かです。ですが、どうも上っ面を撫でただけのアートという印象を免れません。フロイドのジャケット、という期待に形式上応え得るような体裁だけを整えただけ、というか… 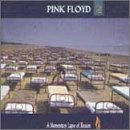 同作のサウンドに耳を傾けてみてもまったく同じこと。確かによくできた仕掛けや聴かせどころが散りばめられてはいますが、やはり精巧な贋物という印象を拭えないのです。尊敬するトニー・レヴィン先生がロジャー・ウォータースをイメージして淡々と刻む、決して派手なプレイが存在しないベースラインが虚しく響きます。 …してみれば、ひょっとしてこれはアルバムのサウンドをもっとも的確に反映したアートワークということになるのではないか? 上っ面を撫でただけのアルバムには上っ面を撫でただけのジャケを着せるのが相応しい。すなわちこのジャケで正解、恐るべしストーム・トーガソン。もっとも重要なコンセプトを、ここでもやはり確実に掴まえていたのです。 …そんなことを考えながら会場を後にしてみたり。 6月25日(月)まで、入場料500円。まだ間に合うようなら、ぜひ足を運んでみて、多いにイマジネーションを刺激されてみるのもいいかもしれませんよ。 (June, 2001) |