ALBUMS 30 - 21
| 順位 | アルバム名 | アーティスト | YEAR |
| 30 | INVASION OF YOUR PRIVACY | Ratt | 1985 |
| 29 | RHYTHM NATION 1814 | Janet Jackson | 1989 |
| 28 | TIDAL | Fiona Apple | 1996 |
| 27 | KICK | Inxs | 1987 |
| 26 | TOTAL | Total | 1996 |
| 25 | INNERVISIONS | Stevie Wonder | 1973 |
| 24 | VALGAR DISPLAY OF POWER | Pantera | 1992 |
| 23 | NUYORICAN SOUL | Nuyorican Soul | 1997 |
| 22 | MAXWELL'S URBAN HANG SUITE | Maxwell | 1996 |
| 21 | FUNKY DIVAS | En Vogue | 1992 |
 30. INVASION OF YOUR PRIVACY - Ratt ラットについては思い入れが深いだけにくどくど書きたくもなりますが、オリジナルアルバムを1枚選べと言われれば文句なくコレ。メタル聴き始めの頃に友人に借りて、ズブズブにハマりました。1曲目の "You're In Love" からラストの "Dangerous But Worth The Risk" まで、前作 "OUT OF THE CELLAR" の大成功と長期に及んだツアーの勢いをそのまま封じ込めています。 ウォーレン・デ・マルティーニとロビン・クロスビーのツインギターは信じられないほど息の合った絡みを聴かせます。全曲活きのいいリフの宝庫、加えてウォーレンが切れ味のいいソロを弾き始めました。ライヴでは不安のあるスティーヴン・パーシーの声も金属的なエコーをガンガンかけながら、時に傲慢さすら感じさせつつ堂々と歌いきっています。ボビー・ブロッツァーのドラムスも、この作品が一番安定してるんじゃないかな。要所を締めるフォアン・クルーシェのベースとコーラスワークについては言わずもがな。プロデューサーのボー・ヒルも絶好調で、曲間の無音部分を詰めて一気に聴かせる独特の手法も冴えてます。例えば "Never Use Love" から "Lay It Down" につながる部分などほとんどシームレス。アルバムタイトルと連動した巨乳モデルの脱衣アートワークも含め、パッケージとして究極の完成品。 "OUT OF..." をベスト作品に推す声もありますが、曲にややバラつきが見られますし、いわゆる RATT 'N' ROLL の究極の姿はむしろ次作の "DANCING UNDERCOVER" で完成されます。その中間に位置するこのアルバムが好きなのは、思い入れによる偏愛だろと言われても致し方ない。しかしすべての好き嫌いは思い入れによる偏愛なのであって、そんな自分(の嗜好)を肯定的に受け入れることが必要な場合だってあると思うのです。誰にも知られたくない自分の嗜好を皆さんに晒す。これぞ INVASION OF MY PRIVACY。  29. RHYTHM NATION 1814 - Janet Jackson モノクロームのフレームに、黒の衣装で固めたジャネット。きっと結んだ口元に、現実を見据えるクールな視線。アートワークがすべてを物語っています。ここには前作 "CONTROL" までの彼女はいない。あるのはジャネットという逸材を用いてジャム&ルイスが仕掛けた壮大な実験と、その結果。 アルバム全編を貫く偏執狂的なまでの打ち込みとサンプリング。"Black Cat" における Jesse Johnson のハードロック風ギターのような極端な例を除けば、ほとんどすべての音をジミー・ジャムとテリー・ルイスがアレンジし、演奏し、プログラミングしています。ジャネットのヴォーカルすらもひとつの楽器に過ぎない。膨大な時間をかけて録音されたであろう彼女のさまざまな声を、自由自在に重ね、織り込み、変調させながら作り上げたトラックは、ところが思いのほか開放的だったりするのです。ライヴ性を捨ててコツコツと積み上げた密室作業が、逆に極めて肉体的でダンサブルに仕上がるという罠。アルバム前半に顕著な、国境や肌の色を超えて、より素晴らしい世界(リズム・ネイション)を目指そうとする政治的メッセージもまったく浮いていません。その政治性は、"Rhythm Nation" でリズムを引用した全米#1ヒット "Thank You" を歌った Sly & The Family Stone の精神を受け継ぐもの。つまり脈々と流れるアメリカ黒人音楽の系譜に則った、黒人であることの自覚と誇りにあふれる由緒正しきアルバム。 もっとも、後半はラヴソングのオンパレード。"Alright"、"Escapade" といったダンス曲の出来の良さが光る一方で、個人的にはラストを締めるセクシーなバラッド "Someday Is Tonight" に惹かれます。長く付き合っているがまだパートナーに身体を許していない女の子。「でも今夜でおあずけはおしまいよ」 と、彼との初めてのセックスを前にした気持ちを歌うジャネット。「約束したわね / 私には待つだけの価値があるって」 というフレーズが出てきますが、これは前作からヒットした "Let's Wait Awhile"の最終行 "I promise, I'll be worth the wait" を踏まえたもの。2作がかりでついに結ばれたこのカップルを祝福するようにハーブ・アルパートが吹くトランペット・ソロに、ちょっとだけ心が温かくなるのです。  28. TIDAL - Fiona Apple 95年のアラニス・モリセットのブレイクが生んだ女性シンガーブームの中で、ひときわ強烈な個性を放っていたのが彼女。自らレイプ体験を語る様子や、ピアノと一体化したその音楽は、アラニスよりはむしろトーリ・エイモスに近い。しかもトーリと違ってジャズ/ブルーズ寄りの和音やフレーズを聴かせる点が新鮮だった。ヴォーカルも同年代の女の子たちに比べずっと醒めていて、言葉を投げつけるように低音で淡々と歌う。半ば引きこもり状態の孤独なティーンエイジャー時代に書き溜められた曲がずらりと並んでいる。 デモテープが渡った先がアンドリュー・スレイターだったのは、彼女にとって(僕にとって?)幸運だった。彼が揃えたミュージシャンは Jon Brion、Patrick Warren、Matt Chamberlain ら。僕が大好きなエイミー・マンやマイケル・ペン、トーリ・エイモスらにつながる人脈だ。いずれも手堅い演奏をするプレイヤーばかり。結果としてフィオナのぎこちないヴォーカルが引き立つ。思春期特有の漠然とした不安や、陰鬱な感情を見事に表現しつくしたアレンジメントが素晴らしい。夜中にリピートでかけていると、本当に何周も何周も回したまま朝が来てしまう。身を切られるように痛い音楽だが、その痛みに生命を感じられるディスクでもある。 全米最高21位を記録したシングルの "Criminal" での下着姿も話題になった。次作 "WHEN THE PAWN..." は大きな期待を持って迎えられたが、残念ながら小ヒットに終わる。2枚を聴き比べればその差は歴然。要するに自分の「傷」をさらけ出して売り物にできる時間は短い。その点、さっさと妊娠していったん表舞台から姿を消すことにした椎名林檎は賢明だった。売れまくり、洗練されることと引き換えに失ってしまった何かに、フィオナ林檎は気付いているだろうか。  27. KICK - Inxs みずみずしい。この文章を書くにあたり、もう通算何回目か数えきれませんが、改めて聴き直しながらやっぱりそう思った。実にみずみずしい。1987年に初めて聴いたときとまったく同じ新鮮な感動。これぞニュー・センセーション。マジで奇跡的。 オーストラリアから世界を制覇したイン・エクセス最大のヒットアルバム。芯のぶっといロック魂に、ヒップホップの香りもブレンドした絶頂期のクリス・トーマス制作盤。アルバム冒頭の "Guns In The Sky" に打ちのめされた日のことは今も忘れません。乱暴極まりないざっくりしたギターリフ+大胆この上ないマイケル・ハッチェンスの挑発的なヴォーカル。前作までの頼りなさげな姿からは想像もできないほど自信に満ちた男の魅力を振りまく彼、その雄叫び一発で勝負あり。ヒット曲もいいけれど、非シングル曲が実に良い。文字通りワイルド過ぎる "Wild Life"も、シャープでダンサブルな "Calling All Nations" も、どうにも前のめりな "Kick" も、爽やかにラストを締める "Tiny Daggers" も。どこにも捨て曲が見当たらないのです。それくらいエネルギーが充満している。ついでに言えば "Need You Tonight" は常に "Mediate" になだれ込まねばなりません。Liberate, liberate, liberate... しかしこの成功が、彼らに大きなプレッシャーとなってのしかかりました。次作 "X" ではU2あたりを意識したのか、妙にスケールの大きなロックにこだわってフットワークが重くなり、もがけばもがくほどヒットから遠ざかる。そして、ようやく吹っ切れたかと思わせた97年の "ELEGANTLY WASTED"発売から程なくして、僕らはロック界最高のヴォーカリストの一人の死を知らされるのです。だからこそ今でも、痛いくらいにみずみずしく響くのかもしれません。このアルバムは。  26. TOTAL - Total どうしてこんな位置にこんなディスクが?と思われるかもしれません。正直、自分でもどうして?と激しく悩みまくっています。徹底的に分かりやすいサンプリングソースと、集中的なマーケティング戦略によって、90年代半ばを支配したパフ・ダディことショーン・パフィ・コムズ。彼の仕掛けた代表的アーティストと言えば一般的にザ・ノトーリアスBIGであり、メアリー・J・ブライジであり、フェイス・エヴァンスでしょう。いずれも華があります。存在感があります。飛び抜けた素材を活かしたまま調理する、音料理の鉄人パフ・ダディ。 ところがトータルはどうか。これはもう圧倒的にキャラが弱い。それ以前に歌が下手すぎる。これで女性ヴォーカルトリオを名乗ろうだなんて、冗談なんじゃないかとすら思える。2ndアルバムで無理やりメンバー名をタイトルにして("KIMA, KEISHA & PAM")、少しでも印象付けようと思ったようだが逆効果。予想を遥かに下回る小ヒットに終わりました。"Trippin'" の無駄に嘘っぽいフューチャリスティック感覚とか個人的にはかなり好きでしたけど。 じゃあパフ・ダディはいったい何故彼女らを手がけたのか。既に答えは出ています。それはこの3人が如何ともしがたい弱キャラ集団だったから。誰一人として満足にリードが取れず、ラップもできない。要するにSWVにもTLCにもなれない3人だからこそ、パフ・ダディのマジックが炸裂し得たという逆説。つまりこの子達で成功したならすべては自分の手柄。恐るべき独り占め根性が開花したこの作品は、しかし実際聴きどころ満載です。重量感あふれる "Do You Know" でまずKO。KRS-1の "South Bronx" 使いで唖然とさせた "No One Else" は言うに及ばず、ベタな "The Payback" ネタに The Notorious B.I.G. を無駄にフィーチャーした "Can't You See" も忘れがたい。Raphael Saadiq が手がけた "Kissin' You"と "Do You Think About Us" が残す清涼感もまた格別。徹底的に「時代と寝てる」感覚を共有できたアルバムでした。  25. INNERVISIONS - Stevie Wonder 「奇跡的」なんていう修飾語は使えば使うほど価値を失ってしまう。安っぽく、嘘っぽく、どこまでも陳腐に響くばかり。でもスティーヴィー・ワンダーの音楽を語るときには遠慮はいらない。「的」すら不要。奇跡そのもの。特にこの時期の彼は、本当に音楽の神様が乗り移っているとしか思えない。 内省的で、メッセージ性の強い作品です。オープニングの "Too High" の異様なテンション。くぐもったシンセ音の上でスティーヴィー自身が叩くドラムの危なっかしいビートが、不安を一層かき立てます。理想郷を歌う静謐な "Visions" で内省モードは頂点に達し、3曲目の "Living For The City" では怒れるスティーヴィー節が爆発。激しい貧富の差、人種差別、力を持てる者と持たざる者。今すぐ問題を解決しなければ…という切実さが劇的なまでに「音」に昇華されています。極めてロック的なファンク "Higher Ground" などもこの系譜の上にあると言えそう。"Golden Lady" や "All In Love Is Fair" のように美しい恋愛テーマの楽曲もあるし、"Don't You Worry 'Bout A Thing" のように、より普遍的な人間愛を感じさせるものもあります。くよくよするなよ。いつだって僕がついているからさ。ラテンのリズムに乗って元気付けてくれるスティーヴィーの歌声に、なぜか却って物悲しさを感じてしまうのは何故だろう。涙が出そうになっちゃうのは、僕だけですか? 作曲、アレンジ、プロデュース、ほとんどすべての楽器の演奏を一人でこなし、ほとんどすべての楽曲がマスターピース足りうるクオリティを誇っています。盲目の彼が見せてくれる広大な「心の中の映像」はまさに奇跡的。いや、奇跡そのもの。  24. VULGAR DISPLAY OF POWER - Pantera 「時代を変えたアルバム」というのがあります。非常に狭いジャンルではありますが、へヴィメタルという世界において、92年のこのパンテラ「俗悪」の前と後では明らかに時代が違う。それまでの流れを暴力的にねじ曲げた、まさしくエポックメイキングな1枚。 スラッシュメタルが袋小路に入りかけていた90年代前半、「俗悪なまでのパワーの顕示」なるタイトルを引っさげてこのアルバムが登場し、しかも全米チャート44位まで上昇して大ロングセラーになったのには驚きました。怒りを剥き出しにしたフィル・アンセルモの咆哮。流行とは別次元の凄まじい速さ&重さで突き進むダイムバッグ・バレルのギターリフ。その間を埋めて驚異的なリズムを叩き出すヴィニー・ポールのドラムス(特に完全に常軌を逸したバスドラのストンプ!)。破壊するだけではなく、重厚で、目が回るようなグルーヴすら感じさせてくれる。これぞスラッシュ/ハードコア/パワーメタルが渾然一体となった南部のトレンドキラー。戦車の如く迫り来るリフがキッズを狂わせる "Mouth For War" で幕を開けるアルバムは、速さと重さだけでなく、知性や時には神秘的な香りすら感じさせます。ライヴでもひときわ盛り上がる "Fuckin' Hostile" でのカタルシスといったらありません。さあさ皆さんご一緒に。「ファッキーン! ファッキンホスターイル!」。馬鹿にも程がある。 THE WiLDHEARTS の "Suckerpunch" シングルと並んで、人を殴っているデザインのジャケットとしてもポイント高いです。尋常でない顔の歪み具合がそのサウンドを物語る名アートワーク。知らないうちにこんなバンドがテキサスでキャリアを積み重ねていたなんて。アメリカの広大さと自分の無知さを思い知らされた1枚でもありました。まさしく「パンテラの前にパンテラなし、パンテラの後にパンテラなし」。 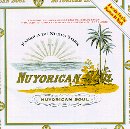 23. NUYORICAN SOUL - Nuyorican Soul クラブ音楽好きなら "Little" Louie Vega と Kenny "Dope" Gonzalez の名を知らない人はいないでしょう。Masters At Work(MAW)や Kenlou など様々な名義で創造的な仕事を続ける彼らが、Nuyorican=「ニューヨークに住むプエルトリカン」としてのルーツに立ち返って制作したアルバム。「クラブ meets ラテン」という明確なコンセプトが、徹底的に生音にこだわって具現化されています。 確かに以前から、MAWって気持ちいいなーとは思ってました。でも中古屋でたまたま拾ったこのディスクに、ほとんど人生観そのものを変えられてしまうほど影響を受けるなんて予想もしていなかった。アシッドジャズやフリーソウルっぽい音楽にはずっと本能的に惹かれていたわけですが、このアルバムを聴いてすべての疑問が氷解。要するに「探し求めていたのは、これだった」。ソウル、R&B、ジャズ、ファンク、ラテン。この作品の前にはこうした分類が一切意味を持ちません。まったく境界線を感じさせない絶妙のごちゃ混ぜグルーヴ。これぞ音楽のメルティング・ポット。 豪華すぎるゲストたちの客演もため息モノ。Jocelyn Brown がパワフルなリードを聴かせたかと思えば、Roy Ayers 先生が登場してヴァイブをプレイ。約9分に及ぶ George Benson のギター/スキャット熱演や大御所 Tito Puente の至宝のティンバレスに耳が釘付け。他にもラテン界から David Sanchez の活きのいいテナーサックスや Eddie Palmieri の美しいピアノもフィーチャーされています。個人的には Lisa Fischer、Cindy Mizelle、Paulette McWilliams といったプロ中のプロたちが聴かせるバックコーラスに大感動。リードも取れる人たちですが、敢えて一歩下がって鉄壁のハーモニーを聴かせてくれる。11曲目の "Runaway" なんて、ほとんどリードの India を食っちゃうくらいに無駄に贅沢なコーラスで。 そう、その "Runaway" ですよ。豪華なストリングス&ホーンのアレンジと、ローズとヴァイブの演奏者としてクレジットされているのはあの Vincent Montana Jr.。この曲のオリジナルである The Salsoul Orchestra (f/Loleatta Halloway) の中心人物本人を担ぎ出す大技に、90年代のサルソウルたらんとするMAWの野心が垣間見えてニヤリ。心から出会えて良かったと思える宝物アルバム。  22. MAXWELL'S URBAN HANG SUITE - Maxwell 「ニュー・クラシック・ソウル」についてはオールタイムアルバム83位のディアンジェロのところでもちょっと触れました。しかしマクスウェルの音楽は、ちょっと手触りが異なります。あまり「ソウル」っぽくない。むしろ、密室にこもって執筆された純文学のようなエロティシズムを感じるのです。感情のうねりと余韻の中に、崇高な精神性すら感じさせる何かがある。 彼のファルセットを引き立てる端正なバックトラックの立役者は、シャーデーの鍵を握るスチュアート・マシューマン。トレードマークの気だるく官能的なサックスに加え、ギター/ベース/ドラムス/キーボード/プロデュースに全面関与。彼のセンスが随所に感じられる「男性版 Sade」作品に仕上がっています。もっとも、近年のシャーデーの無国籍サウンドとの決定的な違いは、ブルックリン出身のマクスウェルが持ち込んだニューヨークの香り。ミドル〜アップでのクールなファンクも、スロウでのどうしようもない切なさも、NYの夜を彩るBGMとしての機能を忘れない。一緒に踊っていても、どこか冷たく孤独で、心を許さない相手が、静かに僕らの内側に入り込んできて、いつの間にか心を虜にしてしまう。そんな危うさに満ちているのです。 一人の美しい女性と出会って心惹かれた瞬間から、熱烈なセックスを交わして別れるも彼女を忘れられず、ついに再会して結婚を申し出るまで。一連の時間の流れに沿って楽曲が配置されたトータルコンセプト作品。彼女を神聖な女性として崇拝し、すべてを献身的に捧げて時代遅れの「純愛」を歌い上げる。読んでいて気恥ずかしくなるようなリリックも、マクスウェルの心の中の女性を賛美し尽くすにはまだまだ言葉不足に違いない。マーヴィン・ゲイとも比較される美しいヴォーカルだけでなく、随所で劇的な効果を上げる Wah Wah Watson のワウ・ギターの導入や、ブックレット全体に渡って統一されたフォントや写真のアート感覚も含めて、総合芸術として評価。ある女性との出会いとそれにまつわる感情をじっと温めて紡ぎ上げた現代の寓話に、僕は今夜もそっと身を任せるのです。 脱ぎ捨てられたミュールのアルバムカバーが、裸になるのももどかしく2人でベッドに倒れこんだあの頃を思い出させる1枚。  21. FUNKY DIVAS - En Vogue 突然ですが、「生きてる」って実感するのはどんな時ですか? 美味しいものを食べてる時だったり、好きな人とキスしてる時だったりするかもしれません。僕の場合、素晴らしい音楽を聴いてる時もそのひとつ。特にブラックの女の子の歌声には無条件でやられてしまうことが多いです。中でもこのアン・ヴォーグの恐ろしく活き活きとしたコーラスは、聴く度に震えるような喜びを全身に感じます。その瞬間、僕は確かに生きている。 90年代以降のガールグループの出発点にして最高峰。テリー、シンディ、マキシーン、ドーンの4人のいずれもがリードを取れるだけの実力を持ちつつ、コーラスでは一分の隙もなくピッタリとハモります。のみならずヴィジュアル面、ファッション面でも大いに魅せてくれました。最高の素材を前に究極の料理人 Denzil Foster & Thomas McElroy も腕を振るいました。一言でいえば「飽きない」アルバム。リリースから10年経った今でも、僕は何回も繰り返して聴けるし、何なら毎日聴き続けたっていい。カーティスのカヴァーをしっとり歌い込んでみたり、ヒップホップ的なトラックにも挑戦してみたり、人種差別を批判する "Free Your Mind" では思いきりハードロックしてみたりと実に多彩なアレンジが施されています。なのにちっとも散漫でないのはやはり彼女らの「声」が立っているから。スピーカー前にくっきりと浮かび上がる立体的なコーラスが、アルバム全体を貫くぶっとい芯なのです。 ヒット曲ではありませんが、オープニングの "This Is Your Life" にはいつも胸が熱くなります。世間がどう思うか、他の人に何と言われるかなんて気にせず、堂々と自分の夢を追いかけよう。貴方らしく生きなくちゃ。だって貴方自身の人生なんだから…と繰り返すポジティヴな楽曲。ブラックの女の子たちが丁寧に声を重ねると、そんなメッセージが僕の周りで突如前向きに響き始めます。理屈なんてない。その瞬間、僕は確かに生きている。 |
|