

������
�싞��s�E�̓E�\���I
http://www.history.gr.jp/~nanking/index.html
�싞��s�E�h�̃E�\�ʐ^�Ə،�
http://www.history.gr.jp/~nanking/lie.html
�싞�ח���ɎB�e���ꂽ���i
http://www.history.gr.jp/~nanking/fukei.html
�싞��s�E�Ƃ́H
 |
 |
| �싞����A���a12�i1937�j�N12��17�� | ������叫 |
�@1937(���a12)�N12��13���̓싞�ח��̗�������6�T�Ԃ̊ԂɁA
���E�q�����܂ޓ싞�s��������R�Ȓ����R���m�̕ߗ�
�i�����}�A����p���{�R�j���܂ޖ�30���l���E�Q���ꂽ�Ƃ���鎖���B
�@���̎�����ɂ͍��ۘA���E���O����������������ȏ��ȂǂɌf������Ă���B
�@�����ٔ��ɂ����ē��{�R�i�ߊ��A������i�܂�����ˁj�叫���s�E���߂��s�����Ƃ���A�i��Y�ƂȂ��Ă���B
�Q�l�����N
-------------------
�A�C���X�E�`�������w�U�E���C�v�E�I�u�E�싞�x�̃E�\
��s�E�h�̃E�\�ʐ^�Ə،�
���a13�i1937�j�N12��13���A
�싞�ח����̐l���́H
��ʎs���E�E�E��20���l�A�����R���m�E�E�E��3.5�`5��
 |
| �싞�h�q�R�i�ߊ� �����q�i��ʐ^�j |
�@1���b�g���̕r�l�߂̎����A�ǂ��������ƁA�ǂ����ڂ����ƁA1���b�g���̎���1���b�g���ł���B
�@20���l�������Ȃ��l�Ԃ��A30���l�E�����Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@����Ȃ��Ƃ́A3�˂̎q���ł��킩�肫�������Ƃł���B
�@���a12�i1937�j�N12���A���{�R���싞���U�������Ƃ��A�싞����ɂ����s���͈�̉��l�����̂��H
�@�s�E���ꂽ�l�Ԃ̐��́A�͂��߂����ɂ����l�Ԃ̐��ȏ�ɂ͐�Ȃ�Ȃ��B
�@�싞������_����ۂ́A���ꂪ�ł���{�I�Ȗ��ł���B
�@�n���r�E�싞�s����12��1���A�S�s���ɑ��āu�싞���S�捑�ۈψ����v���Ǘ�������S��i���j���ɔ���Ɩ��߂����B
�@����A���ۈ��S�ψ���ɑ��ẮA�āA���A���q�ƌx�@������ϑ�āA�������Ӊ�Α�����̌��ǂ��ē싞��E�o�����B
�@���łɁA��A�����K���̎s���⊯�����͗g�q�]�㗬�Ȃǂɔ��݂ŁA�c�����s���͂قƂ�lj��w�̎s���݂̂ł������B
�@�܂��A�싞�̍L���ɂ��Đ������Ă����K�v������B
�@�����̎�s�Ƃ����A�����ɂ��L��ȓs�s�̂��Ƃ��z�������ނ������낤���A���s��k���A��C�Ƃ͔�r�ɂȂ�ʏ����Ȓ��ł���B���������̋�������ɔ�s�������A�������R���A��������B
�@�����̎苖��1937�N�ɒ��������s�����싞�̒n�}������B
�@��������Ă��A����5�L���A�܂��ԕ��L�����R�傩�犿����܂ŕ�����1���Ԃقǂʼn��鎖���ł���B
�@��̒��ؖ傩��Ŗk�̂䂤�]��܂Ŗ�11�L���A�����Ă�2���Ԃ��炸�ł���B
�@���ʐς͏�O�̉��ւ܂ʼn����Ė�40�����L���B
�@�����s���c�J�悪58.81�����L���ł��邩��A����5����4��̍L���ł���B
�@�s�s�Ō����A���q�s��39.53�L���䂦����Ƃقړ����L���Ǝv���܂������Ȃ��B
�@���āA���̂悤�ȋ������̈�p�ɁA3.8�����L���������"���S��"��݂��A��O���l����Ȃ鍑�ۈ��S�ψ���������Ǘ����Ă����B
�@����"���S��"�i���j�ɓ싞�s����S�������e���ĕی�ɓ��������̂ł���B
�@���̍��ۈψ���́A���{�R�����邵��12��13�����痂�N��2��9���܂ł̊ԂɁA���{��g�ق���ѕāE�p�E�Ƒ�g�و��ɁA61�ʂ̕���������܂��͔������Ă���B
�@��Ƃ��ē��{�R�̔�s�⎡���E�H�Ƃ��̑����{�R�ɑ���v����i�������̂ŁA���ɋ��ׂɂ킽���Ė����̂��Ƃ��L�^���Ă���B
�@�܂�����Ȃ�����61�ʂ̌������́A���������ł���A��ꋉ�j���Ƃ����悤�B
�@�c�O�Ȃ�����{�O���Ȃ͏I�펞������ċp���Č������Ȃ����A����61�ʂ̕��͂͏��i�m�́u�싞���S�����āv�ƃ}���`�F�X�^�[�E�K�[�f�B�A���̓��h���e�B���p�[���[���u�푈�Ƃ͉����v�iWhat war means : the Japanese terror in China : a documentary
record /compiled and edited by H.J.Timperley�j�̒��ɑS���������߂��Ă���A�����ٔ��ɂ��؋����ނƂ��Ē�o���ꂽ�B
�@���̑S���̒��ɁA3��ɂ킽���āA�u���S�������̑��l����20���l�ł���B�v�ƋL�q����Ă���B
�@�ĕ��̎��̃G�X�s�[�̖{���ւ̕ɂ��A�܂����[�x�ψ����̃h�C�c��g�قւ̕ɂ��A�u�싞�̐l����20���l�v�ƕ���Ă���B
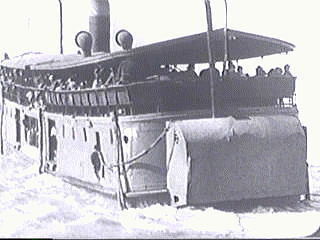 |
�@�������A�h�C�c�E�t�����N�t���^�[���̓��h���Ŋח����O�싞��E�o���������[�E�A�x�b�N���j���u���|�t�H�v�i���a13�i1938�j�N�E2�j�Ɂu�싞�E�o�L�v�������Ă���B
�@����ɂ��ƁA�����̒E�o���ɂ́A�u�Q�i�悤��j���A15���l�𐔂ӂ鏬�s�s�ɐ��艺�����Ă������v�Ƃ���B
�@�܂��A�ă��C�t���ɂ́u���{�R��15���l�̓싞�s�����������S���������҂���������v�Ə����Ă���B
�@����ɓ��{�R�̕ߗ��ƂȂ������Q�v�����́u�싞�q��R�̕��͐�5���A��퓬��10���v�Əq�ׂĂ���A�������ߗ��ƂȂ�A�̂����������{�̌R���w�Z���ɏA�C�������[�Y�����i�����J�ԑ�w�n��������������j�́A�s�����u�T�i�����ށj��20���v�ƌ����B
�@����叫�́u�w�������v��12��20���ɁA�u����j���e�Z�����A���x�ߐl�n�T�V�e�ז��w�j���X�����m�i�����A�����\�]�j�B�V�v�ƋL�q���Ă���B
�@�ȏ�̎����𑍍����Ă݂�ƁA�����̓싞�̐l���́A12�`13������ō�20���̊ԂƂ݂ĊԈႢ�Ȃ��B
�@�����q�����i�����j�̓싞�h�q�R��3.5������5���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��A�ڈ�t�������ς����āA���킹��25���A���Ȃ����ς�����16�`17���ł���B
�@�h�q�R�Ǝs���A��l�c�炸�E�Q���Ă�16���Ȃ���25���Ȃ̂ł���B
�@���ꂪ�ǂ�����30���Ȃ̂��H
�@�H��ł��E���Ȃ����30���s�E�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�@�����ŋs�E�h�́A���Ƃ��Z���̐l���𑝂₻���Ƃ���B
�@���x�Y���́u���{�R���싞�U�����J�n���ꂽ�Ƃ��A����Ɏc�����Ă����s���̐���25���Ȃ���30���ł������Ƃ����Ă����v
�@�u�s�c���̑|�����I�������̓싞�ɂ́A20���l�߂��s�������Z���Ă������̂��������v
�@�u�Ƃ�����̍�10���Ȃ���5������s�E�҂Ƃ������ƂɂȂ�v�i���x�Y�i�ق�Ƃ݂��j���u�싞�����v�i�V�l�������Ёj179�y�[�W�j�B
�@�u�����Ă���v�u������v�Ƃ��������ʼn��̍������Ȃ��B���i�ق�j���������z�����A�����i���������j���Ă��邾���̘b�ŁA�M�ߐ��͑S���Ȃ��B
�@�������l�A�싞��30���A40���̑�j�E�����������Ƃ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��싞�s���j����������ҁw�،��E�싞��j�E�x�́A��͂�싞�̐l���̐�������}���Ă���B
�@�u�����̌����ɂ��A���̐l���͍ł���������29���ɒB�����B�s�E�̖����A��������ɓ��𗣂��悤�ɋ����������i���{���́j25�����Ə̂��Ă����B2�������炸�̊Ԃ�4���l���������̂ł���B�����̌����͂�����������邪�A�d�v�Ȍ����́A����������ʂɋs�E�������Ƃɂ����̂ł��邱�Ƃ͊m���ł���B�v�i�u�،��E�싞��s�E�v�싞�s���j����������ҁ@���{���i�؏��X�j178�y�[�W�j
�@������������29���l�Ƃ����̂́A�ǂ����玝���Ă����̂������Ȃ̂��H
�@�����Ɠ��l�A���̍������Ȃ��B
�@�������狳���Ē��������B
�@�����ٔ��Ń����B���ٌ�m���u�싞�j���i�����j�e�E�Q�T���^���n30���g�i�b�e���i���j���}�X�K�A���m���m�V�e���i���j���͈̓j���L�}�V�e�n�싞�m�l���n20���f�A���}�X�v�ƃY�o�����̖��̖{����˂�����������B
�@����ƃE�G�b�u�ٔ����͂���ĂāA�u���n�\�������`�o�X���f�n�A���}�Z���v�Ƃ��̔������Ă��܂����B�i�u�ɓ����یR���ٔ����L�^�v58��21�E8�E29�j�B
�@�������āA���ɓ����ٔ��ɂ����Ă��A�싞�s���̐l�����ɂ͂ӂ�邱�ƂȂ��A����10���Ƃ��A20���Ƃ��A12��7000�Ƃ��A���̐��l�������肩�łȂ��E�Q��������ׂ������ނ̔��������������ꂽ�B
�@�Ȍ�A�s�E�_�҂́A�l�������h�����邩�A�܂��͓����̂悤�ɒP�Ȃ鐄����������ׂĐ��������͂��邩�̂����ꂩ�ł���B
 |
 |
| �}�M�[�q�t�B�e�̓싞�s���E�o�̗l�q | ���ɓ��� |
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
"�싞��s�E�i�싞�����j"�̒n��Ɗ���
�@"�싞��s�E�i�싞�����j"�����������Ƃ����n��Ɗ��ԁA�������̎咣�͈ȉ��̒ʂ�B
�@����͋ɓ����یR���ٔ��i�����ٔ��j����咣���̂ł���B
�@�i���������A�Ȃ�����C����s�E���n�܂�Ƃ��钿�������{�̈ꕔ�̋s�E�m��h�ɂ͂���B�j
[ �n�@�� ]
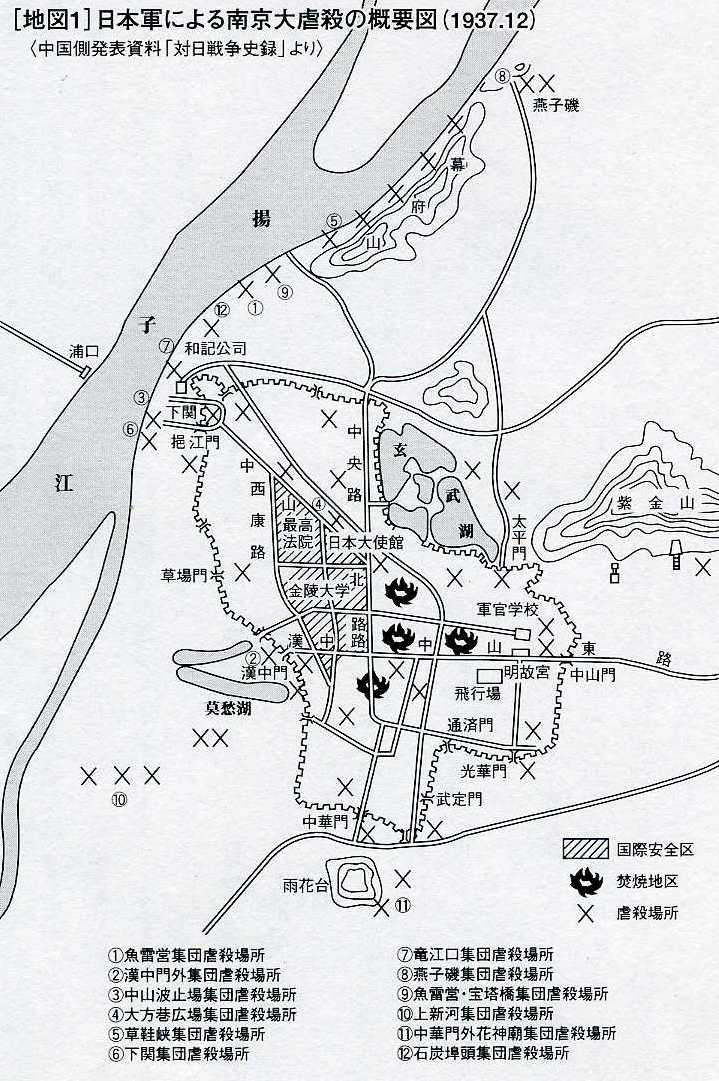
���i��}�j�w����ɂ����钆������@�ʐ^�E�L�^�W�@�����őΓ��푈�j�^�x�i�Ҏ[�F�����E���ې헪���������j������p����������Y���A���l�Њ��w�v���p�K���_��u�싞�����v�x����
[ ���@�� ]

�싞�ɂ���s�E�F�O��ɑ发�����ꂽ���ԁA�u1937.12.13�|1938.1�v�B
��1937�i���a12�j�N12��13���̓싞�ח������痂�N��1938�i���a13�j�N1���܂�
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
"�s�E�i���Ⴍ���j"�Ƃ͉����H
 |
 |
| �u�����̗��v�\���i��j | �u�싞�ւ̓��v�\���i��j |
�u�s�E�v�Ƃ͉����H
�@"�s�E"�i���Ⴍ���j�Ƃ����P��������Œ��ׂ�Ɓ@�E�E�E�@�ނ����炵�����@�ŎE�����A�Ƃ���B
�@"��s�E"�Ƃ����ƁA��ʂɂނ����炵�����@�ŎE�����ɂȂ�̂��낤���H
�@���{�̗��j�̒���"�s�E"�Ƃ����P�ꂪ�g��ꂽ�l�q���������A���������������B
�@������"�s�E"�Ƃ������t�ɂ́A����ӂ�ȓ_�������A���Ȃǂ̊�͖����B
�@�ނ����炵���Ƃ����\���́A�l���ꂼ��̎�ϓI�Ȕ��f�̉e�������邾�낤���A�ߋ��ɘ_����ꂽ�L���͂�����̂̌��ǂ́A��`�Ȃǂ͖����Ƃ������_�Ɏ����Ă���B
�@�������Ȃ��猻�݂ł́A"�싞��s�E"�Ƃ������t���������Ă���̂ł���B���X�s�v�c�Ɏv�킴��Ȃ��B
�@���͂���"��s�E"�Ƃ����P�ꂪ�n�߂Ďg���n�߂��̂́A�����ŋ߂̘b�ŏ��a46�i1971�j�N�W�����Ɂu�����V���v����Ń��|�[�g�L���Ƃ��Ė{������L�҂ɂ���Ď�ށA�f�ڂ��ꂽ�u�����̗��v�i��ʐ^�Q�Ɓj�ɂ���Ăł���B
�@���̋L���ɂ���Ďn�߂�"��s�E"�Ƃ����P�ꂪ�o�ꂷ��B
�@���̎��ɒ��������p�ӂ����،��ҒB����l��"��j�E"�i�����Ƃ��j�Əq�ׂ�B
�@��������"��j�E"�Ƃ͓��{�l�ɂ͑S���Ȃ��݂������A�����{������L�҂�"��s�E"�ƖL���Ƃ��Čf�ڂ����悤�ł���B
�@�ƁA����"�싞����"�ƌĂԂ��"�싞��s�E"�ƌĂ����������C���p�N�g������ƍl������ł̌v�Z�Â��̖�ł������̂��낤�Ǝv����B�F�܂�܂ƈ�������������ł���B
�@���̎��ɂ��A��ؖ����u�싞��s�E�̂܂ڂ낵�v�i���Y�t�H�j�A���x�Y�u�싞��s�E�v�i����j�o�ʼn�j�Ƃ����^�C�g���Ɏg���n�߁A����ɏ��a57�i1982�j�N�̋��ȏ�����ɂ���Ĉ��r���𗁂т鎖�ƂȂ����B
�@���݂͊F"�싞��s�E"�ƌĂ�ł��邪���ۂɂ́A�������30�N�O�A���25�N�߂��o���Ă���g���n�߂��̂ł���B
�����ٔ����璩���V�����|�[�g�L���u�����̗��v
�@���݁A"�싞��s�E"�ƌĂ�Ă��鎖���́A���a21�i1946�j�N5��3������n�܂����ɓ����یR���ٔ��i�ʏ́E�����ٔ��j�ɂ���ē��{�����ɒm���鎖�ƂȂ����B
�@GHQ�͐��E�֑�X�I��`�����{�R�ɂ��i�`�X���h�C�c�̃A�E�V�r�b�c�Ƌ��ɐl����̍߂Ƃ��Ēm���鎖�ƂȂ����B
�@���̎��A�����ٔ��ł́A�싞�ł̖\�s��"The Rape of Nanking"�i�싞�\�s�E�싞�����j�ƌĂ�ł����B
�@�����ٔ��ł́A�A�������i�A�����J�A�����j���珺�a12�i1937�j�N12��13���̓싞�ח�����A���̂悤�Ȏ��������{�R�ɂ���čs��ꂽ�ƍ������ꂽ�̂ł���B
�@���a23�N11��12�������ٔ����I�����A12��23���ɁA�싞�ł̎����̍߁i�i��55����3�ށu�ʗ�̐푈�ƍߋy�ѐl���Ɋւ���߁v���푈�@�K�y�ъ���@�K�ᔽ�����@�K����`���̖����j�ɂ���ď�����叫�������S�u���ŏ��Y����Ĉȍ~���A"�싞�ł̖\�s����"�ł���Ƃ�"�싞�ł̖\�s����"�Ȃǂƌ������Ă���������B
�@�Ƃ��낪�����͐��܂��Ȃ��̎��ł�����A�]�R�o���҂������A����ɓ싞�ɒ��݂����R�W�ҁA���Ԑl����������V���L�҂��������؍݂��Ă����B
�@�����l�X�͓싞�����Ɋւ��Ă͑S�ʓI�ɔے�I�ł������B
�@�����ٔ��������A�قƂ�ǎ����Ƃ��ĔF�߂��鎖�������A�_���鎖�������A���{�l�̒��ɂ��싞�ł̎����ɂ��Č����̂��S�����炸���A�����푈�Ɋւ��鏑�Ђ╶���ɂ��S�����p����鎖�������A�Y�ꂳ���悤�Ƃ��Ă����B
�@�Ƃ��낪�푈���I���A���ۂɓ싞�����Ă����l�B�����a40�N�㒆���납��V���Ђ��炢�Ȃ��Ȃ�Ƌ��ɁA�ˑR�������������Ƒ呛�������n�߂�B
�@���ꂪ���a46�i1971�j�N8��������12���܂ł̊ԂɁA�u�����V���v����ɂďՌ��I�ȃ��|�[�g�ł���u�����ւ̗��v�Ƃ����{������L�҂ɂ��L���ł���B�i��ʐ^�Q�Ɓj
�@���̃��|�[�g�́A�����̒����͕�����v���Ƃ������C�̎���ł��葽���̏��O���̃}�X�R�~�͒����̍s�����C���݂��l���i���キ�����j�̗��ɔᔻ�����_���s�����B
�@���ׁ̈A�������Y�}�������ł��C�ɐH��Ȃ��ƃ}�X�R�~�e�Ђ͍��O�Ǖ����鎖�ƂȂ����B
�@���a42�i1967�j�N�̃T���P�C�A�����̍��O�Ǖ����R�́A�ё̎���G��V���Ɍf�ڂ����Ƃ������̂������B
�@�܂��A�ǔ��V���̒Ǖ����R�͓����œǔ��V������Â���`�x�b�g���W���J�Â����Ƃ������������B
�@���̂悤�ȍ��ׁi�������j�ȗ��R�Œ����ȊO�̊e�Ђ͎��X�ƒ������獑�O�Ǖ��Ƃ��ꂽ�B
�@���������V��1�Ђ����́A���O�Ǖ���Ƃ��ׂɁA�������Y�}�֓z��i�ǂꂢ�j�Ƃ�������悤�ȒǏ]�L���R�ƌf�ڂ��A����ɂ͋��C�̕�����v�����^���A���⒆�����Y�}�̍L�Ƃ��Ă̖�����S�����ƂȂ�B
�@����ɂ��̍��A�A�����J�̓x�g�i���푈���ŁA�푈�I���ׂ̈ɖk�x�g�i���ƃJ���{�W�A�̃N���[���E���[�W���i�J���{�W�A�Ő��S���l���E�Q�����|���E�|�g�����j���x�����Ă��������Ƌ}���ɐڋ߂����B
�@���̍ۂɂ��A�����V���͐��S���l�����s�E�����A�|���|�g�����ɑ��āh�|���E�|�g�̓A�W�A�I�D�����ɂ��ӂ�Ă���h���ƌ������A�s�E�m����s���L���R�Ƃ����Ď��X�ƌf�ڂ��Ă������B
�@�����ɒ������������s�ׂɋy��ł������z���ł��悤�A���_���̂悤�Ȏ����肵�Ă����̂ŁA���̌㔭�s������1�ʂ���2�ʂւƓ]������̂����B
�@�Ē��ڋ߂ɂ���ē��{���A�c���p�h�̎���ɒ������Y�}�����Ƃ̍����������ʂ������ƂȂ����B
�@���{�͔s�풼��A�Ӊ�ΐ����ł��钆�ؖ����𐳎��Ȓ�����\�ƔF�߂Ă���A1949�i���a24�j�N�̏Ӊ�Η����鍑���}�����i����p���{�j�Ɩё����钆�����Y�}�i���������{�j�̓���ȍ~�����̏�Ԃ͑����Ă����B
�@���̓������������𐄐i���悤�Ƃ���A�����̒����V���̌́E�L���m�j�В��������ɒ����ׂ̈Ɏ��������ł��낤���L���ɂ��A�E�\�̋L���R�ƌf�ڂ��Ă��������ʍ����Q�Ƃ��Ē��������B�i�u���a�S��싞�v�ʐ^���W�j
�@���̒����^�L���̈�тƂ��āA�����V���̖{������L�҂ɂ��u�����ւ̗��v��u�����W���[�i���v�u�T�������v�ł̘A�ڋL���ł���B
"��s�E"�͐����I�Ӑ}�����P��ł���
�@�O�q�������A���̖{�����꒩���V���L�҂ɂ�郌�|�[�g�L���u�����̗��v�L���ɂ���ď��߂āu��s�E�v�Ƃ����P�ꂪ�g���鎖�ƂȂ����B
�@���́u�����̗��v���f�ڂ����悤�ɂȂ������R��1�Ƃ��āA���a40�N�㒆����ɂ͊e�V���Ђɂ����ē싞��Ɏ�ނ��싞�ɒ��݂��Ă����W�҂����X�ɑގЂ��n�߂Ă����̂ł���B
�@���̂悤�ȐV���Ђɂ�����w�i���������̂ł���B
�@����ɖ{�����꒩���V���L�҂͌��_�̎��R�ǂ��낪�������Y�}�������ł��ᔻ���悤���̂Ȃ璆���̈�ʎs���ł��瑦�A���Y����镶����v������ɒ������Y�}���p�ӂ����i���́j��Q�҂��畷����蒲�����s���B
�@���̍ۂɏ،��ҒB�͈�l��"��j�E�i�����Ƃ��j"�Ƃ����P����g���Ă���̂ł���B
�@����"��j�E"�Ƃ����Ӗ��͒����l�̗��j���╶�������Ɏg����P��ł���A���{�ɂ͑S�����̖����P��ł���B
�@�ߋ��ɒ����̗��j�ł́A�����A���\�����ɂ͕S���Ƃ�������E�C�̗��j���������B
�@"�g�B�\���L"��"�Ò�j��L"�����]��ɂ��L���ȕ��ꂪ�����ɂ͑��݂���B
�@���{�l�Ɍ��킹��ΔN���ƌ�����"���b��"�Ɠ������o�ł���B
�@����"�g�B�\���L"��"�Ò�j��L"�̕���͐�����������łڂ����܂�ɍ~�����������A��i�����̊X�j�ɗ����Ă����V��j�����݂ȎE���ɂ��āA�̂����ɐؒf���āA���̓����ςĐH�����Ƃ��Ӗ�����B
�@�Ⴆ���A�L�ł��낤����������̂͑���1�l�A1�C�c�炸�E�C���܂��鎖���Ӗ�����̂ł���B
�@���̓j�E�̐��S����L�̓��L�ł͋L�q����Ă���A����ɒ����̗��j�ł͊��x���s���Ă��銵��ł�����B
�@�]���āA�x�ߐl�̗��j���o�������Ă���ƍ~�����������₵�Đ킢�s�k�����싞�́A�ΓG���R�ɂ��u�j��v���ꂽ�ƖӐM���邱�Ƃ͂������Ȃ��B
�@�����l���K���z���o����l�Ԃ����߂ɂ��A������X�ƁA�͂˂鎖�͓��풃�ю��A����ɂ͐l�Ԃ̎葫���ƒ{�Ƃ��Ĉ�Ă�l�Ȃǂƌ������c�E�Ŏc�s�ȓ��{�l�̑z�����y�Ȃ���I�s�ׂ����R�ƒ����̗��j�ɂ͑��݂��邵�A�����͉\�̕����ł���A�}�X�R�~�����\��l�ÂĂ̘b��M����y�낪����̂ł���B
�@���̓_���[���ɗ�������K�v������B
�@���a12�i1937�j�N7��29���ɋN���������푈�̌�����1�ɂ��Ȃ����ʏB�����ł͓��{�l260�]����223�������c�ɎE�Q���ꂽ�����̖͗l�Ȃǂ́A�����l�̐��ݓI�ȗ���Ⴆ�ł���B
�@���{�l�̑z���̋y�Ԃ��̂ł͖����B
�@����"��j�E"�Ƃ����P����V���L�҂ł������{������L�҂��u�����̗��v�ɂ���āA�����ɂ����Ă͔ے�o���Ȃ������l�̗�ł���c�s�s�ׂ̂��������肻�̂܂ܓ��{�l�ɓ��Ă͂߂悤�Ƃ��Đ��������̂�"��s�E"�Ƃ����P��Ȃ̂ł��邱�̎��͏d�v�Ȏ��ł�����B
�@��ɓ����ٔ��ɂ����ẮA"�싞�\�s�E��������"�Ƃ����Ăі��ł����������q�ׂ��B
�@�Ƃ��낪�A���a40�N�㒆���듖���͍����^���^������A���ł͏��b�ƂȂ邪���{�����Y��`���Ƃɕς��鎖��^���ɍl�������Ńe�����N�����Ă�������ł������B
�@���̂悤�Ȏ���ɁA��������"��s�E"�Ƃ��������̐����p��ł���P����A�{������L�҂͗A�������������Ă��܂����̂ł���B
�@�����V���Ƃ��������A���s�������ʂ��ւ��V�����g���Ăł���B
�@���̂��߁A���́u�����̗��v�f�ڈȍ~�u�싞��s�E�v�Ƃ����P�ꂪ���R�Ǝg����悤�ɂȂ��Ă��܂����B
�@����Ɍ���I�������̂͏��a57�i1982�j�N�ɁA���ȏ�������N����B
�@NHK�ł���Ӑ}�I�ɋ��ȏ�������X�I�ɕ��A�����ăZ���Z�[�V���i���Ƀ}�X�R�~���L�����y�[�����s�������߂Ɂu�싞��s�E�v�̔F�m�x�͋}���ɍ��܂����̂ł���B�i�������Y�o�V��1�Ђ����͂���܂���F�߂��j
�@�u��s�E�v�Ɓu�����v�ł́A�ǂސl�ɗ^����C���p�N�g���S���Ⴄ���ƂȂ�B
�@�����V���L�ҁA�{�����ꂵ�Ă������ł������B
�{���̌Ăі��́u�싞�ŋN�����Ƃ���鎖���v�܂��́u�싞�ł̖\�s�������N�����Ƃ���鎖���v��������
�@���a57�i1982�j�N11���A���{���̃}�X�R�~���u�N���v����u�i�o�v�ւƏ����������Ƃ������ȏ�����̐�������ɏo�ł��ꂽ�A������20���l�ȏオ�E�Q���ꂽ�Ƃ����咣�ł������s�E�h�̌�����c��w�����A�́E���x�Y���̒���u�싞��s�E�v�i����j�o�ʼn�j�̊����ɂ͂���������Ă���B
�@�{�����u����ŁE�싞��s�E�v�Ƒ肵�Ă���̂́A���Ȃ炸�����A�M�҂̈ӂɂ����̂łȂ����Ƃ��A���f�肵�Ă����B�Ȃ��A���͒蒅���Ă���u�싞��s�E�v�Ƃ����ď̂��A���͏�ɂ́u�싞��c�s�����i�A�g���V�e�B�[�Y�j�v�ƌĂԂ��Ƃɂ��Ă���B
�@���̈Ӗ��͈�̉��Ȃ̂��낤���H
�@���x�Y���͂��̒�������10�N�O�̏��a47�i1972�j�N4���ɂ́u�싞�����v�Ƃ����������o�ł��Ă���B
�@���̔N�ɂ́u�����̗��v�������V���ɘA�ڂ���Ă���B
�@�Ƃ��낪����́u����ŁE�싞��s�E�v�͂��傤�Nj��ȏ�������琔������ɏo�ł���Ă���B
�@����́A"��s�E"�Ƃ����P�ꂪ�C���p�N�g�������Ă��鎖�ɏo�ŎЂ����ڂ������߂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@"��j�E"�̂������̗��j�����܂ޒP�����{�֗A�����A���̊����̎��C���p�N�g���o�ŎЂ����p���悤�Ƃ����̂ł͂Ȃ��낤���H
�@�����炱����҂ł���́E���x�Y������c��w�����́A�����ɂ�����"��s�E"�Ƃ����^�C�g���ɍ�Ҏ��g�̈ӂɂ����̂Ŗ������Ƃ�f���Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B
�@������"��j�E"�Ƃ�1937�i���a12�j�N�̎������ł͖����A�ߋ��ɋN���������ł̍~���������ۂɂ���ĊF�E���E�C�ɂ�����ɗ�I�������܂�ł���̂ł���B
�@�܂��ɈΓG�i���؎v�z�ɂ������Ȗ����j�ł�����{�R���~���������s�����ۂ��������R��l�����F�E���ɂ����͓̂��R�̎��ł���ƁA�z������͖̂������������ł���B
�@�����l�͓��{�l�Ƃ͗��j�w�i������A�������������������S���Ⴄ�̂ł���A���̓_���[���ɍl�����ׂ��ł���B
�@�푈��嗤�̒����l��m��Ȃ����m�Ȑ�㐢��ɂƂ��āA�����l�̐S���𗝉��ł��Ȃ��̂͒v�����Ȃ����A�����V��������ɕt�����̂͐�ɋ����Ȃ��s�ׂł���B
�@��ʂ�"��s�E"�ƌĂ�A�܂��Ă⒆���l���_�o���ɑi���鎖�����܂������������ł���Ƃ͓��{�l�̊��o�Ƃ��Ă͎����͓̂��R�ł���B
�@�����A�^����1�Ȃ̂ł���B
�@"�싞��s�E"�͒����V���ɂ���č��ꂽ�P��Ȃ̂ł���B���m�Ɍ����A�������V���L�҂ł���{������L�҂ɂ���Ăł���B
�@"�싞��s�E"�Ƃ����P����g���̂͒����̎咣���̂��̂𐭎��I�E�����I�Ӗ��������ᔻ�Ɏ���鎖���Ӗ����Ă���B
�@���̖ړI�͖����ł���B
�@"�싞��s�E"�Ƃ����P�����{�l���g�����œ싞�ł̖\�s�E���������ᔻ�ɔF�߂����A�������Γ��O���J�[�h��1�Ƃ��Ďg���A�O���ɂ����ėL���ɐi�߂鎖���o����Ƃ������ł���B
�@����1��Ƃ��Ĉȉ����f�����Ă����B
���a63�i1988�j�N�ɋN���������̗�Ԏ���
�@���a63�i1988�j�N3��24���A��C�ŋN�������m�w�|���Z�̏C�w���s���̏�������̂��������B
�@���̎��A�⏞���̂��߂ɗ��������������́A�ȏ�A�싞��s�E�����ɏo���Ă���B
�@�����͐�㔅���ӔC����ؕ������Ă���̂�������{������������Ƃ������������B
�@���������{���ٌ̕�m���A��肪�S���Ⴄ�Ɣ��_�͂��Ă���B
�@�����Ŏ��͈ꌾ���������̂́A���{�������ŎE�C�s�ׂ��s�����Ƃ����̂͂��Ȃ肠��ӂ�ŁA����������̂قƂ�ǂ͐�㋤�Y�}���˔@�����o�������ł���A����ɓ��{���������������B�⒆�����Y�͔����ǂ��납����ȏ�̊z�ɏ��B���̓_��Y��ė~�����Ȃ��B
�@����ɋߔN�A���{�R�����������ŃK�X�e����������Ƃ������A���{�R����ڎ������̂͒����R�ł͂Ȃ��������A����ɂ����̒��ɂ͋��\�A�R�̂��̂�A�����R�̂��̂��啔������Ƃ����B
�@"�싞��s�E"�Ƃ����J�[�h���g�����ŁA�����͉��ł��o����ƍl���Ă���̂Ȃ�A����͊ԈႢ�ł��낤�B
�@����ɒ����V�����s�����s�ׂ͖��炩�ɏ��O���ł͍��ƕ��J�߂┽�t�߂ɓ�����͂��ł���B
�@�����V�����Ȃ����̓��{�ɑ��ݏo����̂��A���ɂ͕�����Ȃ��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
3�ɕ������咣
�u�܂ڂ낵�h�v�u���Ԕh�v�u��s�E�h�v
�Ƃ͈�̉����H
�@�u�싞��s�E�v�ɂ����ċs�E���ꂽ�l���ɂ��āA��܂��Ɍ�����3�̘_�h�����݂���B
�@���ꂪ�u�܂ڂ낵�h�v�u���Ԕh�v�u��s�E�h�v�ł���B
�@���̓���͈ȉ��̒ʂ�
| �܂ڂ낵�h | �E�E�E | �@�s�E���́A�قڃ[���ƍl���Ă���B�s�E�����̂�ے�B |
| ���Ԕh | �E�E�E | �@����l���琔���l�O�オ�E�Q���ꂽ�Ǝ咣�B |
| ��s�E�h | �E�E�E | �@10���l�ȏ�̓싞�s���A�ߗ����E�Q���ꂽ�Ǝ咣 |
�@�Ȃ��A�����Œ��ڂ��Ă����������́A�������͎E�Q���ꂽ�l����30���l�ȏ�Ǝ咣���Ă��邪�A���{�����́u��s�E�h�v�ƌĂ��l�B�ł��猻�݂ł�30���l�����q�ׂĂ���l���͗B��1�l�����Ȃ����ł���B
�@�Ƃ��낪���݂̒������Y�}��30���l�ȏ���咣���Ă���B30���l�ł��班�Ȃ��Ǝ咣���Ă���B
�@�����A���{�R�̓G�ł͂Ȃ������������Y�}�͉��n�ł��鉄���ɂ���A���̋L�^�͌��݂ł͐����Ƃ�����Ȃ��̂ł���A���{�����̑�s�E�h�̈�c����w�A�g�c�T�����ł���u�������̂���Ă��鎖�̒��ɁA�����������������܂��B�v�Əq�ׁA���m��w�A�]���\�ꋳ���u�������{�̂����u30���l�s�E�v�͖��炩�Ɍ֑�B20���ɓ͂����ǂ������^�₾�B�v�A20���l�s�E�x���̈�c����w�A���������_�������u�����ł��A�����Ƃ��������҂͕������Ă���̂ł͂Ȃ����v�Əq�ׂĂ���B�i���Y�t�H�Ёu���N�I�v2001�N1�������j
�@�Ȃ��u�܂ڂ낵�h�v�́u�܂ڂ낵�v�Ƃ́A���a48�i1973�j�N3���ɕ��Y�t�H�Њ��u�u�싞��s�E�v�̂܂ڂ낵�v��ؖ�������Ƃ����Ăѕ��ŁA�����싞��s�E���L�����Ƒ�X�I�ɐ�`���s���Ă������[�_�[�I���݂ł����������V���Ȃǂ̃}�X�R�~�ɑ���^��𓊂����������Ђ̖��O���Ƃ��āA�s�E�ɑ��Ĕے�I�ȗ���̐l�X�ɖ������ꂽ�����ł���B
�@�������A���̒��ҁA��ؖ����͋s�E���ɂ��Ă͕s���ł���Ƃ���咣���Ƃ��Ă���B
���a12(1937)�N12��13����
�싞�ח����̏�
| �ځ@�� | |
| 1. | �����̓싞�̐l�� |
| 2. | �싞�̒n�� |
| 3. | �싞���S�捑�ۈψ��� |
| 4. | �����{��ԂɊׂ����싞 |
| 5. | �~������ |
| 6. | �����R�ɂ��Ă������̋��� |
| 7. | �������ɂ�闩�D |
| 8. | �ֈߕ��͐펞���ۖ@�̈ᔽ |
| 9. | �ֈߕ����炪���ɓٓ� |
| 10. | �㑗���ꂽ���a���Ɩ����� |
| 11. | ���{�R����ђ����R�̓싞��ɂ�����Ґ� |
| ���@�� |
| (1) | ���p�p�x�̍������̕����͗����ŕ\���A���̉��ɐ����Ńy�[�W�����������B |
| �m�`�T�E�E�E�E�n�w�����푈�j�����x��8���E�싞�����T�@���x�Y�ҁi�͏o���[�V�Ёj | |
| �m�`�U�E�E�E�E�n�����9���E�싞�����U | |
| �m�j�E�E�E�E�n�w����ŁE�싞��s�E�x���x�Y���i����j�o�ʼn�j | |
| �m�m�E�E�E�E�n���x�Y���w�싞�����x�i�V�l�������Ёj | |
| �m�r�E�E�E�E�n�w�،��E�싞��s�E�x�싞�s���j����������ҁ@���{���i�؏��X�j | |
| �m���L�^�E�E���n�@�ɓ����یR���ٔ����L�^�E�E�E������A�Ȃ����̍ٔ����u�����ٔ��v�Ɨ��L�����B | |
| �m�w�싞��j�x�E�E�E�i�@�j�n�@���{�������u�،��ɂ��w�싞��j�x�v�G���u��s�v�A�ځ����a59�N4�����60�N2�����A�i�@�j�������͂��̉� | |
| (2) | ���t�͓��ɒf��Ȃ�������A�N���͏��a12�i1937�j�N�A�N���͏��a13�i1938�j�N�B |
| (3) | �����{�R�l����і�l�̊K���E��E�͓����̂��́B |
| (4) | ����叫�̐w�����L���̑��R�l�̎�L���u�J�^�J�i�v���u�Ђ炩�ȁv�ɉ��߂��B |
| (5) | ���ˑ�w�͋ɓ��R���ٔ������u�싞��w�v�Ɖ��̂��ꂽ�B |
 |
| �����q |
�@1���b�g���̕r�l�߂̎����A�ǂ��������ƁA�ǂ����ڂ����ƁA1���b�g���̎���1���b�g���ł���B
�@20���l�������Ȃ��l�Ԃ��A30���l�E�����Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@����Ȃ��Ƃ́A3�˂̎q���ł��킩�肫�������Ƃł���B
�@���a12�i1937�j�N12���A���{�R���싞���U�������Ƃ��A�싞����ɂ����s���͈�̉��l���H
�@�s�E���ꂽ�l�Ԃ̐��́A�͂��߂����ɂ����l�Ԃ̐��ȏ�ɂ͐�Ȃ�Ȃ��B
�@�싞������_����ۂ́A���ꂪ�ł���{�I�Ȗ��ł���B
�@�n���r�싞�s����12��1���A�S�s���ɑ��āA�u�싞���S�捑�ۈψ���v���Ǘ�������S��i���j���ɔ���Ɩ��߂����B
�@������ۈ��S�ψ���ɑ��ẮA�āA���A���q�ƌx�@������ϑ�āA�������Ӊ�Α�����̌��ǂ��ē싞��E�o�����B
�@���łɁA��A�����K���̎s���⊯�����͗g�q�]�㗬�Ȃǂɔ��݂ŁA�c�����s���͖w�lj��w�̎s���݂̂ł������B
�@�܂��A�싞�̍L���ɂ��Đ������Ă����K�v������B�����̎�s�Ƃ����A�����ɂ��L��ȓs�s�̂��Ƃ��z�������ނ������낤���A���s��k���A��C�Ƃ͔�r�ɂȂ�ʏ����Ȓ��ł���B
�@���������̋�������ɔ�s�������A�������R���A��������B
�@�����̎苖��1937�N�ɒ��������s�����싞�̒n�}������B
�@��������Ă��A����5�L���A�܂��ԕ��L�����R�傩�犿����܂ŕ�����1���Ԃقǂʼn��鎖���ł���B
�@��̒��ؖ傩��Ŗk�̜��]��܂Ŗ�11�L���A�����Ă�2���Ԃ��炸�ł���B
�@���ʐς͏�O�̉��ւ܂ʼn����Ė�40�����L���B
�@�����s���c�J�悪58.81�����L���ł��邩��A����5����4��̍L���ł���B
�@�s�s�Ō����A���q�s��39.53�L���䂦����Ƃقړ����L���Ǝv���܂������Ȃ��B
�@���āA���̂悤�ȋ������̈�p�ɁA3.8�����L��������āg���S��h��݂��A��O���l����Ȃ鍑�ۈ��S�ψ���������Ǘ����Ă����B
�@���́g���S��h�i���j�ɓ싞�s����S�������e���ĕی�ɓ��������̂ł���B
�@���̍��ۈψ���́A���{�R�����邵��12��13�����痂�N��2��9���܂ł̊ԂɁA���{��g�ق���ѕāE�p�E�Ƒ�g�و��ɁA61�ʂ̕���������܂��͔������Ă���B
�@��Ƃ��ē��{�R�̔�s�⎡���E�H�Ƃ��̑����{�R�ɑ���v����i�������̂ŁA���ɋ��ׂɂ킽���Ė����̂��Ƃ��L�^���Ă���B
�@�܂�����Ȃ�����61�ʂ̌������́A���������ł���A��ꋉ�j���Ƃ����悤�B
�@�c�O�Ȃ�����{�O���Ȃ͏I�펞������ċp���Č������Ȃ����A����61�ʂ̕��͂͏��i�m�́w�싞���S�����āx�ƃ}���`�F�X�^�[�K�[�f�B�A���̓��h���e�B���p�[���[�́w�푈�Ƃ͉����x�̒��ɑS���������߂��Ă���A�����ٔ��ɂ��؋����ނƂ��Ē�o���ꂽ�B
�@���̑S���̒��ɁA3��ɂ킽���āA�u���S�������̑��l����20���l�ł���B�v�ƋL�q����Ă���B
�@�ĕ��̎��̃G�X�s�[�̖{���ւ̕ɂ��A�܂����[�x�ψ����̃h�C�c��g�قւ̕ɂ��A�u�싞�̐l����20���l�v�ƕ���Ă���B
�@�������A�h�C�c�E�t�����N�t���^�[���̓��h���Ŋח����O�싞��E�o���������[�E�A�x�b�N���j���u���|�t�H�v�i���a13�N�E2�j�Ɂw�싞�E�o�L�x�������Ă���B
�@����ɂ��ƁA�����̒E�o���ɂ́A�u�Q���A15���l�𐔂ӂ鏬�s�s�ɐ��艺�����Ă������v�Ƃ���B
�@�܂��A�ă��C�t���ɂ́u���{�R��15���l�̓싞�s�����������S���������҂���������v�Ə����Ă��� �B
�@����ɓ��{�R�̕ߗ��ƂȂ������Q�v�����́u�싞�q��R�̕��͐�5���A��퓬��10���v�Əq�ׂĂ���A�������ߗ��ƂȂ�A�̂����������{�̌R���w�Z���ɏA�C�������[�Y�����i�����J�ԑ�w�n��������������j�́A�s�����u�T��20���v�ƌ����B
�@����叫�́w�w�������x��12��20���Ɂu����j���e�Z�����A���x�ߐl�n�T�V�e�ז��w�j���X�����m�i�����A�����\�]�j�B�V�v�ƋL�q���Ă���B
�@�ȏ�̎����𑍍����Ă݂�ƁA�����̓싞�̐l���́A12�`13������ō�20���̊ԂƂ݂ĊԈႢ�Ȃ��B
�@�����q�����̓싞�h�q�R��3.5������5���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��i�ʍ��ڎQ���j�A�ڈ�t�������ς����āA���킹��25���A���Ȃ����ς�����16�`17���ł���B
�@�h�q�R�Ǝs���A��l�c�炸�E�Q���Ă�16���Ȃ���25���Ȃ̂ł���B
�@���ꂪ�ǂ�����30���Ȃ̂��H
�@�H��ł��E���Ȃ����30���s�E�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�@�����ŋs�E�h�́A���Ƃ��Z���̐l���𑝂₻���Ƃ���B
�@���x�Y���́u���{�R���싞�U�����J�n���ꂽ�Ƃ��A����Ɏc�����Ă����s���̐���25���Ȃ���30���ł������Ƃ����Ă����v�u�s�c���̑|�����I�������̓싞�ɂ́A20���l�߂��s�������Z���Ă������̂��������v�u�Ƃ�����̍�10���Ȃ���5������s�E�҂Ƃ������ƂɂȂ�v�i�m-179�j�B
�@�u�����Ă���v�u������v�Ƃ��������ʼn��̍������Ȃ��B
�@�����������z�����A�������Ă��邾���̘b�ŁA�M�ߐ��͑S���Ȃ��B
�@�������l�A�싞��30���A40���̑�j�E�����������Ƃ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��싞�s���j����������ҁw�،��E�싞��j�E�x�́A��͂�싞�̐l���̐�������}���Ă���B
�@�u�����̌����ɂ��A���̐l���͍ł���������29���ɒB�����B
�@�s�E�̖����A��������ɓ��𗣂��悤�ɋ����������i���{���́j25�����Ə̂��Ă����B
�@2�������炸�̊Ԃ�4���l���������̂ł���B
�@�����̌����͂�����������邪�A�d�v�Ȍ����́A����������ʂɋs�E�������Ƃɂ����̂ł��邱�Ƃ͊m���ł���B�v�iS-178�y�[�W�j
�@������������29���l�Ƃ����̂́A�ǂ����玝���Ă����̂������Ȃ̂��H
�@�����Ɠ��l�A���̍������Ȃ��B
�@�������狳���Ē��������B
�@�����ٔ��Ń����B���ٌ�m���u�싞�j���e�E�Q�T���^���n30���g�i�b�e�����}�X�K�A���m���m�V�e�����͈̓j���L�}�V�e�n�싞�m�l���n20���f�A���}�X�v�ƃY�o�����̖��̖{����˂�����������B
�@����ƃE�G�b�u�ٔ����͂���ĂāA�u���n�\�������`�o�X���f�n�A���}�Z���v�Ƃ��̔������Ă��܂����B�i�u���L�^�v58��21�E8�E29�j�B
�@�������āA���ɓ����ٔ��ɂ����Ă��A�싞�s���̐l�����ɂ͂ӂ�邱�ƂȂ��A����10���Ƃ��A20���Ƃ��A12��7000�Ƃ��A���̐��l�������肩�łȂ��E�Q��������ׂ������ނ̔��������������ꂽ�B
�@�Ȍ�A�s�E�_�҂́A�l�������h�����邩�A�܂��͓����̂悤�ɒP�Ȃ鐄����������ׂĐ��������͂��邩�̂����ꂩ�ł���B
 |
�@���}���A�싞�Ɠ��{�̈ʒu�B �g�q�]�i���]�j�̗���ɉ����Ĉʒu���Ă���A���̉����ɂ͏�C������B��C���炷���̋����B |
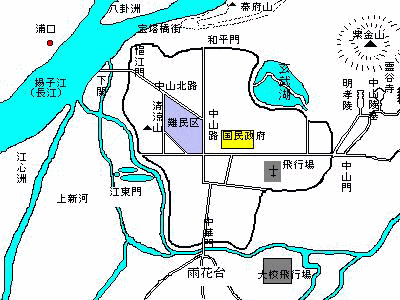 |
�@ ���ꂪ�A�����̓싞�s�y�ѓ싞��A��O�̒n�}�B �싞��͖�20���[�g�����̍����̏�ǂɈ͂܂�Ă����O����̐N���҂�h�����߂ɂ��̗l�ȏ�ǂ�����Ă����B �g�q�]�̂������Ɉʒu���A���������̎���ɂ͌��������B �@���́A���ۈ��S�ψ���̂P�T�l�̑�O���l�B�ɂ���ĊǗ��A�������ꂽ���n�т̔��n��ŁA�����̓싞��ɊW�̂Ȃ��A��ʐl�͂P�Q���P���ɂ����֏W�܂�悤�ɔn�싞�s���ɂ���ĕz�����ꂽ�B �@���̒��ɂ͑�g�فA��w�A���q�w�@�A�Ȃǂ̏d�v�Ȍ��z��������B97�N�H�ɍu�k�Ђ��甭�����ꂽ�u�싞�̐^���v�̒��҃W�����E���[�x�͍��ۈψ���ψ����ŗL�����B |
�@�싞�s���̔n���r�́A���a12�i1937�j�N12��1���A�s���ɕz�����āA�s���͐H�Ƃ���ѐg�̉��i�����Q���āu���S��v�i���̂��Ɓj�ɈڏZ����悤�����A�����ݗ������u�싞���S�捑�ۈψ���v�i�ȉ��u���ۈψ���v�Ɨ��́j�ɁA��3���S�i3000�g���j�A��1���S�i1000�g���j�A��10�������ϑ����A�x�@��450�����c���āA�s���̕ی���˗������B
�@���ۈψ���́A���ď�C��̂Ƃ��A���l�鋳�t�W���L�[�m�_�����A���{�R�̏��F����u��n��v����C��s�ɐݗ����ėǖ��̕ی�ɓ����������ɂȂ炢�A�싞�s�̐��k���ɂ�����n��\�\��͊����H�A���k�͒��R�k�H�����Ƃ��A�k�͎R���H�A���͐��N�H�ɋ��ꂽ��3.8�����L���i�싞���ʐς̖�8����1�j�̒n�������āu�싞���S��v��ݒ�i��̓싞���}�Q�Ɓj���A�����Ɏs���S�������e���Ă��̕ی�ɂ��������B
�@�u�싞���S�捑�ۈψ���v�Ƃ͉����A�싞�����������d�v�ȃJ�M�������Ă��邱�̈ψ���ɂ��Đ����������B
�@��O����싞�ɍݏZ���Ă�����O���l�͑��������������A�Ō�܂œ��݂Ƃǂ܂����̂�40���O���i���ۈψ���̈ψ�15���A�V���L��5����̌��و��Ȃ�20�������c���ق��́A12��7���̏Ӊ�ΒE�o�ƑO�サ�ē싞��ދ����Ă���j�ŁA���̂�����15�����ψ����Ґ����A�O�q�̒n�������āA�������u���S��v�Ə̂��A�n�싞�s���̐\��������āA�싞�s���̈��S�����A������ۏႷ��V�X�e�����������̂����̈ψ���ł���B�ψ���̎����ǂ͔J�C�H�T���ɂ���A�������J�݂�12��1���ƋL�^����Ă���B
�@�ψ����̓h�C�c�̃V�[�����X��Ўx�X���W�����E�g�E�c�E���[�x�ŁA���L���͕Đl�̋��ˑ�w�Љ�w�������C�Y�E�r�E�b�E�X�~�X���m�B
�����o�[�́A�Đl7���A�p�l4���A�h�C�c�l3���A�f���}�[�N�l1���̌v15���ł���B�i���M�ҁq���r���ˑ�w�͖���44�N�싞��w�Ɖ��̂����j
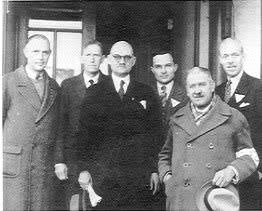 |
| �싞���S�捑�ۈψ���̃����o�[ |
| �@�������A�[�l�X�g�E�t�H�X�^�[�iErnest H.Forster�j�A�E�C���\���E�v���}�[�E�~���Y�iW.P.Mills�j�A�W�����E���[�x�iJohn.H.D.Rabe�j�A�X�}�C�X���m�iLewis Strong Casey Smythe�j�A�G�h���[�h�E�X�p�[�����O�iEdouard Sperling�j�A�W���[�W�E�A�V�����A�E�t�B�b�`�iGeorge Ashmore Fitch�j���Ȃ��t�B�b�`��YMCA�E���ňψ���̃}�l�[�W���[����S�� |
| �@���� | ���� | �E�� | ||
| �W�����E�g�E�c�E���[�x�i�ψ����j | John H D Rabe | �h�C�c | �V�[�����X��� | |
| ���C�X�E�X�g�����O�E�J�Z�C�E�X�~�X���m�i���L���j | Lewis Strong Casey Smythe | �A�����J | �싞�i���ˁj�勳�� | |
| �o�E�g�E�}�����t�H�[�� | P.H.Munro-Faure | �C�M���X | �A�W�A����� | |
| �W�����E�K���X�s�[�E�}�M�[�q�t | John Gillespie Magee | �A�����J | �ċ���`���c | |
| * | �o�E�q�E�V�[���Y | P.R.Shields | �C�M���X | ���ۗA�o��� |
| * | �i�E�l�E�n���Z�� | J.M.Hansen | �f���}�[�N | �e�L�T�X�E�I�C����� |
| * | �f�E�V�����t�F�E�p���e�B�� | G.Schultze-Pantin | �h�C�c | �V���f�Չ�� |
| * | �A�C���@�[�E�}�b�P�C | Ivor Mackay | �C�M���X | �o�^�t�B�[���h�E�A���h�E�X�E�B�A��� |
| * | �i�E�u�E�s�b�J�����O | J.V.Pickering | �A�����J | �X�^���_�[�h�E�o�L���E���E�I�C����� |
| �G�O�@�[�h�E�X�p�[�����O | Eduard Sperling | �h�C�c | ��C�ی���� | |
| �}�C�i�[�E�T�[���E�x�C�c���m | Miner Searle Bates | �A�����J | �싞�勳�� | |
| �E�C���\���E�v���}�[�E�~���Y�q�t | Wilson Plumer Mills | �A�����J | �k�����V�`���c | |
| * | D�E�i�E���[�� | D.J.Lean | �C�M���X | �A�W�A����� |
| �b�E�r�E�g���}�[���m | C.S.Trimmer | �A�����J | ��w�a�@��t | |
| �`���[���X�EH�E���O�X | Charles.H.Riggs | �A�����J | �싞�勳�� |
�@����\�Ɂu*�v�t���Ă���҂́A��͂����O�ɓ싞�������Ă���B
�@�����Œ��ӂ������̂́A����15���̑�O���l�͂�����������̓��{�̌��t�Ō����g�G�����l�h�ł���B
�@�܂�A���{�R��N���R�ƋK�肵�Ă���݁A�Ӊ�ΐ��{�������}���{�ɖ������A������x�����Ă��鍑�̐l�X�ł���Ƃ������Ƃł���B
�@�h�C�c�����Ɠ����Őe�����������悤�ɂȂ����̂́A���a13�i1938�j�N3�����b�y���g���b�v���O���ɏA�C���Ĉȍ~�̂��Ƃł���܂ł͕ĉp�Ɠ��l�A���{��G�����A�Ӊ�ΌR�ɕ��퉇���ƁA�R���ږ�c�𑗂��Ă����B�i���̏؋��ɐ�̌�̕ߊl����ɃV�[�����X���������A�`�F�R���̃}�V���K���A���̑����퓙�X���f���A���̑��������ɋL�^����Ă���j
�@����Ɉψ���́AYMCA�����g������𑽐��������āA��̉��̓��{�R�̔�s�����ɂ������Ă���i�ʍv�A�u���ۈψ���̓��R�ƍߓ��v�v�Q���j�B
�@���ۈψ���͈��S�����n�тɂ���悤���{���ɐ\�����ꂽ�B�ŏ����{���͂��̈��S��̐ݒu�ɓ��ӂ������A�h�q�i�ߊ������q���~�������ۂ������߁A�R�͏�C�s�ɂ�����W���L�[�m�E�]�[���i��s���n�сj�̂悤�ɁA�����ɂ͂������n�тƂ������n�тƂ��F�߂Ȃ������B���̉�12��5���A�đ�g�ق�ʂ��čs��ꂽ�B
�@���̗��R�͈ȉ��̒ʂ�B
| 1�A | �싞���̂���̗v�ǂƉ����Ă���A���������̒n��͂��̒��S�n�ɓ����邪�A�����ɂ͉��玩�R�̏�Q�����Ȃ��A���E�����R�Ƃ��Ă��Ȃ��B |
| 2�A | ���{�v�l�⍂���R�l�̊��@�������A�����Ȃ镺���ʐM�@�킪�B������Ă������͂����B�i���������R�������Z�̒��ɂ́A�ח����O�܂ň��S����ɋ��Z�����҂������i���[�x�̃h�C�c���̎����ď��ȁj�B |
| 3� | �ψ���̂�������͂�L�����A��������ֈߕ������₷�邾���̌����Ȓ����ԓx��]�ނ��Ƃ͍���ł���i�ȏ�͓����Q�����̓����ٔ��ɂ�����������̗v��j�B |
�@�Ƃ������̂ł���B
�@�����A�\�z�ʂ�A���ۈψ���́A�ֈߑ���s�c����S�R�`�F�b�N���邱�ƂȂ����������߂Ă���i���ꂪ���Ƃ�����ɂȂ�j�B
�@�������A������Ƃ����āA���{�R�͂��̓���ی삵�Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B
�@��̂Ɠ����ɕ����𗧂āA�e�����ɂ͐i���֎~���Ɩ������A���p�̎҂̏o������֎~���A�܂�����R�i�ߊ��̖��߂ɂ��A�C�E���������ɂ��܂��߁A��Ђ̔g�y��h�~�����B
�@���̂����A�~���i���x������Ȃǎ�����ی삵�Ă���B�]���Ă��̒n��ɂ́A�������C�����Ȃ��A�Ђ������N���Ă��炸�A���ۈψ���͓��{�R�̂��̂悤�ȕی�Ɏӈӂ�\���Ă���قǂł���B�i�ڍׂ́u�s�E�ے��17�̘_���v�́g��5�̘_���u���͈��ׁA���ӂ̏����v�h���Q�Ƃ��ė~�����j
�@�Ӊ�Α����A�v����v�l�A�����ԌR�������A�����U�Q�d�����琭�{����ьR��]�́A������12��7���Ɏs���Ɩh�q�R����������ɂ��ē싞��E�o���A�����ɓّ����Ă���B
�@���Ȃ킿�A12��7���̎��_�ŏӐ����͓싞����������̂ł���B
�@�������̋L�^�ɂ��ƁA�u�싞�̎���́A���̒n���Ŏ炵�ĉ��R��҂��̂ł͂Ȃ��A�G�̏��Ղ傷�邱�Ƃɂ������B
�@���̓_����݂�A���łȗv�ǂł͂Ȃ��A�܂��w��ɉ͐�i�g�q�]�j���T���ĕ�����K�łȂ������v�i�w�R����j�x�j�Ƃ���B
�@���ꂩ��݂�ƁA�싞�����炷�邽�߂̓O��R��ł͂Ȃ��A���{�R�ɂł��邾�����Ղ�^���āA���R�{���̑ދp��L���ɓ������߂̍��ł������悤�ł���B
�@����ɂ́A�G�̐i�R��j�~���A����R���P�ޗe�ՂȒn�`�łȂ���Ȃ�ʁB
�@�P�ގ����̑I���A�G�Ƃ̗��E�v�̂��Ȃ��Ȃ��ނÂ������A�������܂�Η��E������ɂȂ�A�ߑ��ɓP�ނ���ΓG�ɗ^������Ղ������Ȃ��Ȃ�B
�@��j�́A���̂悤�ȍ��́A�n�̗��A���s�R�𗦂�����قǂ̖����łȂ���ΐ������Ȃ����Ƃ������Ă���B
�@�싞�͔w��ɗg�q�]���T���āA�P�ނ͗e�Ղł͂Ȃ��A�J�ԑ�A�����R�̎���͌R���w�Z�̋��������̐��s�������������A����R�̑啔���͒n�̗��ɂ��Ƃ��L���A�L���A�Γ�o�g�̌R���ł������B�Q�d�����̔����U��h�C�c�̌R���ږ�c�́A�싞�h�q��ɔ������Ƃ�����B
�@�h�q�i�ߒ��������q�́A���{�R�ɂ�銮�S�ȕ�͉��ɂ����āA�Ȃ�������R�i�ߊ��̍~�����������ۂ����B
�@12��7���A�Ӊ�Α����琭�{�A�R�̍������싞��E�o�������_����A�싞�̓p�j�b�N��ԂɊׂ����B
�@�x�T�K���⍂�������͎��Ă邾���̉ו��ƌ����������āA�싞��E�o���A�����āA�i�@�@���s���{�����@�{�̊������A���悻��l�Ƃ�����l�͐��{�v�l�̂��Ƃ�ǂ��ē싞��E�o�����B�n�������������l�ł���B���t�A�x�@���A�X�Lj��A�d�b�A�d�M�A�����ǂ̍H���Ɏ���܂ŁA����ɂƓ싞�E�o���͂���A�싞�͕����ʂ�A�����{��Ԃɂ����ꂽ�B
�@�O�L�����悤�Ɍx�@��450�������ۈψ���̊NJ����Ɏc�����݂̂ŁA�������S���싞����p�������Ă��܂����̂ł���B
�@10���`12���ɂ͓d�b�͕s�ʂɂȂ�A�����͂Ƃ܂�A�d�C�����Ȃ��Ȃ����A�������x�@���ٔ������Ȃ��Ȃ����̂ł��邩��A���S�Ȗ����{��Ԃł���B���D�A�������肵�����ƌ������A�Í��̓s�s�ɂȂ����B
�@���{�R�����邵���Ƃ��A�������̑��ɂ��Č����悤�ɂ����̑�����Ȃ��A�ӔC�҂����炸�A���ނ����Ȃ��A����̂͂������A���D�̂��Ƃ̕����ʂ�̔p�Ђ̓s�s�ł������B�����������̓O�ꂵ�����D�Ԃ�́A�퍑���ケ�̕��A�𐢒������̏�K�ł���B
�@����R�i�ߊ��́A12��9���A�瓂���q�R�ɑ��č~�����������U�z�����B
�@���j�ɂ͂h�e�͋�����Ȃ��Ƃ����邪�A���������q���R���V���K�|�[���̃p�[�V�o�������̂悤�ɁA���邢�͍]�ˊJ���n���̏��C�M�̂悤�ɁA�싞���I�[�v���V�e�B�ɂ����Ȃ�A���̂悤�ȍ����ƔߎS�͋N����Ȃ������͂��ł���B
�@�~���������͈ȉ��̒ʂ�i���{����j�B
| �@���R�S�����ɍ]���Ȋ�����B �@�싞��͏��ɕ�͂̒��ɂ���B �@��Ǒ吨�������̌��͑��S�Q�����Ĉꗘ�Ȃ��B �@�҂ӂɍ]�J�̒n�͒����̋��s�ɂ��Ė����̎�s�Ȃ�B���̍F�ˁA���R�˓��ÐՖ���喏W�i�����Ӂj���A���R�i���Ȃ���j���������̐����̊�����B �@���{�R�͒�R�҂ɑ��Ă͋ɂ߂ďs��ɂ��Ċ�����������A�����̖��O����ѓG�ӂȂ������R���ɑ��Ă͊���������Ă����`�����A���������Ɏ���Ă͂����ی�ۑ�����̔M�ӂ���B �@�������M�R�ɂ��Č����p������Ȃ�A�싞�͐��ЕK�����Ђ�Ƃ��B �@�������Đ�ڂ̕������D���ɋA���A�\�N�̌o�c�͑S���A���ƂȂ��B �@�˂��Ė{�i�ߊ��͓��{�R���\���ċM�R�Ɋ������B�����싞��a���ɊJ�����A�������č��L�̏��u�ɏo�ł�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����{���R���i�ߊ��@�@����� �@�{�����ɑ���͏\�\�����ߒ��R�H��e����̕������ɂ����Ď�̂��ׂ��B �@�������M�R���i�ߊ����\����ӔC�҂�h������Ƃ��́A�Y���ɂ����Ė{�i�ߊ���\�҂Ƃ̊Ԃɓ싞��ڎ��Ɋւ���K�v�̋���𐋂���̏�������B �@�Ⴕ���Y�w�莞�ԓ��ɉ����̉ɐڂ�������A���{�R�͂�ނ��싞��U�����J�n����B |
�@�����Q�d�����i�����ٔ��ōi��Y�j���������Q�d�A���R���Q�d�A���c�ʖ̎l�l�́A�h�B�̌R�i�ߕ����ߑO3���ɏo�����A�[��̋�e�X���𒆎R��O�Ɍ����A�ߑO11��40������ړI�n�ɓ����A���������̂�œG�R�g�̗���̂�҂����B
�@12����5���߂��Ă��A10���߂��Ă��A���ɒ������R�g�͎p�������Ȃ������B
�@���ʓI�ɂ́A�O��R������тȂ���A�����q�͐��R����P�ލ��̎w�����ł����A�s�c��������Ɏc�����܂܁A12���[���A�u�e���e�ɕ�͂�˔j���āA�ړI�n�ɏW������v�Ɩ����āA�����ЂƂ�A�Ђ����ɗg�q�]�k�݂ɓّ������̂ł���B
�@���̖��ӔC�Ɨȓ����\�͂����e����A�����q��12��18���R�@��c�ɂ������A19���e�E�Y�ɏ�����ꂽ�Ɠ`������i�u�����V���v12��20���j�B
�@����ɑ��āA�~�������������A�������R��O�őҋ@�������c�ʖ́A���̎��̒������̑ԓx�ɂ��Ď��̂悤�ɊS�Q����B
�@
�@�u�����ˁA���́A�~�������������A�����R�͂��������Ȃ������̂ł����B���������͂͂����肵�Ă��܂��B���Ƃ͍~�����邾���ł��B���ƑS�̂̍~���ł͂���܂��A�싞�����~�����Ă�����ł��B���I�푈�̎������U���ŃX�e�b�Z�����T�ؑ叫�ɍ~�����Ă܂��ˁA����Ɠ����ł��B�����ח��œ��I�푈�͏I�������ł͂Ȃ��A���̌�������܂��B�싞�̏ꍇ���A�싞�̈�ǖʂ����~�����Ă������킯�ł���B
�@���͐��������āA�����т����ł��B���B�����������̂��^������Ȃ��B���x���ς����{�����߂����Ƃ��낪����Ǝv���Ă��܂��B�������A�싞�̍~�����ۂ͒����������B�������A���ǁA�ō��i�ߊ��̓����q�͓����܂�����ˁB����͒����̈����Ƃ���ŁA�`�a�c�̎��������ŁA���̐ӔC�҂͍Ō�ɂȂ�Ɠ����Ă��܂��B��Ђ��Ԃ�鎞�Ɠ����ŁA�ӔC�҂����Ȃ���Ή�Ђ͍������āA�Ј��͕��������ē����܂���B
�@�~�����ۂ��Ȃ���Εߗ��̖����Ȃ������Ǝv���܂��B���ۖ@��A�Ƃ悭�����܂����A���ۖ@�ォ�炢���Β����̂����͂܂����Ǝv���܂��v�i�u���_�v61�E6�����E�������꒘�w���{�l�̌����싞�ח��x���j�B
�@
�@�܂��������c���̂����Ƃ���ł���B
�@20���������s������������ɂ��āA���a�I���ɉ����邱�ƂȂ��A�Ӊ�Α����琭�{���R��]�����S�����S���A�n�s�������������A�Ō�Ɏc���������R���~�������ۂ��ēّ����Ă��܂����̂ł���B�s�X�͗��D���莟��̑卬���ɂ����������͓̂��R�ł���B
�@�����҂������A�n�̗��ɂ��Ƃ��s�c�̏����������p�j�b�N�Ɋׂ�A���Ă������B
�@�m�x�^�C���Y�̃_�[�f�B���L�҂̌����ʂ�A�싞�����̐ӔC�̑唼�́A���̂悤�Ȗ��ӔC�ɂ܂�ӁE���E�n�璆�����w���҂ɂ���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B����͂��̃��|�[�g�̒��ł����S�Q���Ă���B
�@�u�m���ɁA�ӏ��R�����̂悤�ȑ卬���̋N����̂������ׂ��ł͂Ȃ������B
�@�m���������R���������Ō�܂ł��ʂ����Ƃ��ł����A�Ƃǂ̂܂�͕s����ɏI������B�]���̓��ɂӂݏo�������Ƃ͋�������ׂ��ł����B
�@���́A���̓��������̏������̉���ŁA���{�R���s���[���N������̂��x���Ȃ���A���ދp�̔z�u�����邱�Ƃɂ���āA���~�����炩�̓w�͂����Ă��悩�����̂��B����Ȃ��Ƃ��s��ꂽ�l�q���Ȃ��A������ɂ���͉��P����Ȃ������B���͎����̖����̑����̃����o�[�ɂ������m�点���A�w�����Ȃ��ɌR��u������ɂ������Ƃ́A�S�ʓI�j��̍��}�ƂȂ����v�i�`�U295�y�[�W�j�B
�@�������{�́A�̂��ɂ��̂悤�ȍ��{�v�l��̓싞�s���S�t���u��Â��������A�����������A�l�S�h�����A�O���l�̚}�����т鎸�Ԃ��������v�ƍ��]���Ă���B���R�̕]���Ƃ����ׂ��ł��낤�B
�@�j���[���[�N�E�^�C���Y�̃_�[�f�B���L�҂́A�f�����̓싞�Ƃ��̎��ӂɂ�����g�Ă������̋����h�����̂悤�Ƀ��|�[�g���Ă���B
�@
�@�u���{�R����e�������āi�P�Q���V���j�A�i�����͂��߂����Ƃ������R�ɂ��Ă������̋����̍��}�ƂȂ������A����͖��炩�ɏ�ǎ��ӂŒ�R���邽�߂ɓy�d��̏������s���Ă�����̂ł������B
�@�����́u�E�G�X�g�|�C���g�v�ł��铒�R�ɂ́A�C���w�Z�ƕ����w�Z�A����ɏӏ��R�̉Ċ��Վ��i�ߕ����u����Ă��邪�A��������싞������15�}�C���ɂ킽��_���n��ł́A�قƂ�ǂ��ׂĂ̌����ɉ�����ꂽ�B
�@������ݏĂ�����ꂽ�̂ł���B
�@���R�ˉ����̕��ɁE�@���A�ߑ㉻�w��w�Z�A�_�ƌ����������A�x�@�w�Z�A���̑������̎{�݂��D�o�ɋA�����B�̎�͓����Ӓn��Ɖ��ցi�V���[�J���j�ɂ�������ꂽ���A�����̒n��͂��ꎩ�̏����Ȏs���Ȃ��Ă���̂ł���B
�@�����R�ɂ��Ă������ɂ�镨���I���Q���v�Z����A�D��2000���h������3000���h���ɂ̂ڂ����B
�@����́A�싞�U���ɐ旧�����������Ԃ��s��ꂽ���{�R�̋�P�ɂ�鑹�Q�����傫�����A�����炭���ۂ̕�͊��Ԓ��ɂ�������{�R�̔����ɂ���āA�܂���̌�̓��{�R�����ɂ���Đ��������Q�ɓ������ł��낤�B
�@�����R���́A�싞�s���ӑS��̏Ă��������R����̕K�v���炾�A�Ƃ����������Ă����B
�@��ǎ��ӂł̌���œ��{�R�����p�ł������Ȃ������Q���A������B��ƁA������{�݂�j�邱�Ƃ��K�v���Ƃ����̂��B
�@���̖ړI�̂��߂ɁA��������łȂ��A���E�|��ԁE�݂Ȃǂ���������Ă�����ꂽ�B
�@�u�������̊ώ@�҂̐M����Ƃ���ł́A���̏Ă��������܂��A���Ȃ�̒��x�͒����l�́g���������Ԃ����W�F�X�`���A�h�ł����āA�{��Ɨ~���s���̂͂����ł������B
�@����́A�����R�������Γ��{�R���g�p���邩������Ȃ����̂͂��ׂĔj�����Ƃ����~�]�̕\��ł���A�ɒ[�ȁs�œy���t����̕\��ł����āA���{�R����̂��钆���̊e�n�����A�����҂ɂ͉��̖��ɗ����Ȃ��œy�ɂ��Ă������Ƃ����̂ł������E�E�E�E�v�i�`�h�h287�y�[�W�j�B
�@
�@���ˑ�w�̃x�C�c�����͂����q�ׂĂ���B
�@�u�싞�̏�ǂɒ��ڂɐڂ���s�X�n�Ɠ싞�̓��싞�x�O�����̒����̏Ă������́A�����R���R����̑[�u�Ƃ��Ă����Ȃ������̂ł���B���ꂪ�K�ł��������Ȃ������������̌��肵���邱�Ƃł͂Ȃ��v�i�`�h�h212�y�[�W�j�B
�@�싞�ח���O�ɂ��āA�����R����p�Ƃ��ėp�����u������v�A���Ȃ킿�������z������@�A���@�Ȃǂ̏Ă������̋����������ɂ��̂��������̂ł��������A���̈ꕶ�ł������ł��悤�B
�@�u�싞�U���ɐ悾���ĉ������Ԃ��s��ꂽ���{�R�̋�P�ɂ�鑹�Q�v��������ɐr��Ȕj��ƁA���Ɨ��D���s��ꂽ�Ƃ����̂ł���B�������A�����ٔ��ł͂����̏Ă������Ɨ��D�̋����́A���ׂē��{�R�̎d�Ƃɒu���������A�s�싞�ɂ�������{�R�̖\�s�����t�Ƃ��č�������Ă���̂ł���B
�@���̒������Y�}�R�Ƃ͂������āA�̂̃V�i�i�����j�ɂ́u�ǓS�͓B�ɂȂ炸�A�ǖ��͕��ɂȂ炸�v�Ƃ������Ƃ킴������B
�@�܂�Ԉ���Ă����m�ɂ͂Ȃ�ȁA���m�ɂȂ�悤�Ȃ��̂��낭�łȂ����A�^�ʖڂȐl�Ԃ͌����ĕ��m�ɂ͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����Ӗ��ł���B
�@�×������ł͕��m�͗ǖ��̊ԂɎ�噁i�����j�̂��Ƃ�����ꂽ�̂ł���B
�@�Ȃ����Ƃ����ƁA�푈�ɏ��ĂΏ������ŁA������Ε������ŁA�u���D�v���邩��ł���B
�@�×������ɂ����ẮA�푈�Ɨ��D�͂����̂ł���A���D�����������̕�V�ł���A�ł������B
�@�܂��A����ɂ���Ē����������Ƃ��j���ɏo�Ă���B
�@�i�n�ɑ��Y���́u���H�Ɨ��M�v�ɂ���Șb������B
�@
�@���M�R�́A�m���̎m�C�̓_�ō��H�R�ɗ���Ă����B
�@�i�����j����͗��M����R���ʂ���C����Ă���l��������߂Č��i�ŁA��̒n�ŗ��D���邱�Ƃ��ւ��Ă�������ł���B
�@�𐢁A���̑嗤�ɂ����ẮA���m�Ɠ����Ƃ̋�ʂ����������A����ď��ĂΗ��D���A���D�����҂��邱�ƂŎm�C���オ��Ƃ����K�������������A�l���͂������������B�i��f���i��j273�y�[�W�j
�@
�@�܂�A���m�Ɨ��D�̊W�́u�O���u�v���ォ��A�𐢁A���̍��̏K���Ȃ̂ł���B
�@�����`��Y���i��16�t�c�ʐM�ǒ��E���R���сj�́A�싞�Ɍ������nj���ŁA�����͏�ɑ����ɂ����āA10��25���̖����A29���̏�B�Ɉ�ԏ����ʂ��������A��������B���������ɂ�闪�D�̐�R������̂����̖ڂŌ����B
�@�����ɂ��ꂪ���̐������̂��A�S���z���O�ł������A�ƌ���Ă���i�M�҂ւ̏��ȁj�B
�@�܂��A��19���c������C�������́A�k�x���̎��A��������̏�ǂ̏ォ��A10��13�������A�͂��炸���s�c���ɂ�闪�D�̏�ʂ������ƌ����Ă���B
�@���Ȃ킿�u��������ɂȂ��ꂱ�s�c���́A�܂��Z������ߗނ�D���ĕֈ߂ƂȂ�A���ɐH�Ƃ�D���A�����D���A��������҂��ē����o���Z�i�ŁA��ǂ����łɓ��{�R�ɂ���Đ�̂���Ă���̂��m�炸�A����͔s�c���ɂ�闪�D�A�\�s�E�����ň��@�����̂��܂��Ɖ����A���{���͂����������C�ɂƂ��āA���̒n���}����ǂ��璭�߂Ă����v�Ƃ����̂ł���B
�@�O�q�̃_�[�f�B���L�҂��A�싞�ɂ����钆���R�̗��D�ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�u�y�j���i11���j�ɂ́A�����R�ɂ��s���̏��X�ɑ��闪�D���g�����Ă����B
�@�Z��ɂ͎��G��Ă��Ȃ��������A�����ɓ��邽�߂ɕK�v�Ȍ���̔j��ɂƂǂ܂��Ă����B
�@���D�̖ړI���H�Ƃƕ⋋�����̊l���ɂ��邱�Ƃ͖��炩�ł������B
�@�싞�̏��X�͈��S��ȊO�ł͌o�c�҂������Ă��܂��Ă������A�H�Ƃ͑����ɒ������Ă������v
�@�u�i12���j�[���ɂ͑ދp���������R�͖\�k�Ɖ����Ă����B
�@�����R�͊��S�ɒזł����B
�@�����R�����͎w�������Ȃ��A�����N���������m��Ȃ��������A�����킩���Ă���̂́A�킢���I���A���Ƃ������̂т˂Ȃ�ʂƂ������Ƃ������v�i�`�h�h290�y�[�W�j
�@�싞�Ɏc�����Ă����^��O���l�̓��L���u�������X�V���v�i�������V���j���f�ڂ��Ă��邪�A����ɂ͂��������Ă���B
�@�u12��12���A�s�c���̕��A���D�Ȃ�����͂Ȃ����|�ɂ�������v�i���a12�E12�E20�j�B
�@���c�ʖ́A���D�ɂ��Ď��̂悤�ɏ،����Ă���B
�@�u����̓X�͋ƂɂȂ��Ă��܂��āA��������������Ƃ����D�����̂��A���{���������Ă��痪�D�����̂��A���D�̐Ղ�����܂����B���{���͐H�ו��͗��D�����Ǝv���܂����A���̑��͒�������������悤�ł��B
�@���a13�i1938�j�N3���ɈېV���{���o����ƁA�����싞�ɍs���܂������A�D�_�s�ɂ͂�������̍��ȃW���E�^���⍜���i������A�����́A���̎����D�������̂��Ǝv���܂��B
�@���̎����������\���邽�߃W���E�^�����܂����v�i�u���_�v�q���a61�E6�r�������꒘�w���{�l�̌����싞�ח��x�j�B
�@�M�҂����a13�i1938�j�N8���싞�ɍs���A�����D�_�s�̐����H�����Ă���B
�@�j���̈ߗނ���C�A�H��ށA�ʋl��C���ނ͂��Ƃ�荋�ȃV�����f���A��s�A�m�܂ŁA���X�ƁA�ۘO����k����тɓD�_�s���Ђ낪��A�����݈̂ٗl�ȕ��͋C�ł��������Ƃ��o���Ă���B
�@�ǎ҂ɖ��L���Ă��������������Ƃ́g�Ă������̋����h�ɂ��Ă��A���̂悤�Ȓ����l�⒆���R�ɂ��g���D�h�ɂ��Ă��A���͂��ׂē��{�R�̂��킴�ɂ����������Ă��邱�Ƃł���B
�@���҂��s�҂������������ٔ����A�����t��Ɉ����������������{�R�̎d�ƂƂ��A����߂킳�ꂽ�̂͂�ނȂ����������m��Ȃ��B�����c�O�Ȃ��Ƃ́A�S�Ȃ����{�̊w�҂�}�X���f�B�A���A���܂��ɓ����ٔ��j�ς̎����ɂƂ���āA�����R�͑P�ł����A���{�R�݂̂����ł�����
�@�x�ߎ��ςœ��{�R�������Ƃ��Y�܂����̂́A�O�L�́g������h�Ɓg�ֈߑ����h�ł���B
�@�ֈߑ����Ƃ����̂́A���K�̌R���𒅗p�������������Əꍇ�ɂ���ĕS������햯���ɒ��ւ��āA�G�̖��f���݂͂��炢�A�B������������œG����P�����p�̂��Ƃł���B
�@�Ȃ��ɂ͍ŏ�����햯���ŁA������Q����������҂�����B
�@���������̔r���A�R������͓O�ꂵ�Ă���A�w�l��q���܂ł��A��ԐM�����������ē��{�R�̏��݂�m�点����A�V�k�������������̒��Ɏ�֒e��铽���ĉ^��������A�S���p�̕ֈߕ��ɖ�P���ꂽ��E�E�E�E�A���̂��ߓ��{�R�͑����̎v��ʋ]����������ꂽ�B
�@�킪�R�������ɕֈߕ��ɔY�܂��ꂽ���ɂ��āA����R�i�ߊ��́u�x�ߎ��ϓ��������v�̒��Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B�i�{���J�^�J�i�j�B
�@�u�s������x�ߕ������̕�������ď����u�ֈߕ��v�ƂȂ�A���X�Ȃ��R�����ނ���̛����炴�肵�ׂ߁A��R�̔V�ɑ���R���̕ʂ𖾂炩�ɂ��邱�Ɠ�A���R��ʗǖ��ɗ݂��y�ڂ����̛����炴�肵��F�ށB�v�i�c���������u������叫�̐w�������v71�y�[�W�j�B
�@�Ȃ��A����叫�͐鐾���q���̒��ł����̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�u�x�ߌR�͑ދp�ɍۂ��Ă͏����u�����p�v���̂�A���݂̏d�v��ʋ@�y�ь��z���̔j��ċp���s�킵�߂���݂̂Ȃ炸�A�ꕔ���Z�͏����u�ֈߕ��v�ƂȂ�A�R����E���A���߂�Z�ӂĎc�����A�䂪������_�����A��R�̔w������������̏��Ȃ��炩���A�t�߂̐l���������邢�͓d����ؒf���A���邢�������ギ�铙�A���ڊԐڂɎx�ߌR�̐퓬�ɋ��͂��A��R�Ɋ����̊���^�ւ���B�v�i�O�f��207�y�[�W�j�B
�@�����܂łȂ����̂悤�ȕֈߕ��́A����@�K�̈ᔽ�ł���B
�@���{�R�͂������̈ᔽ�s�ׂɂ������x���������A�n�������ŁA�����R�͈���ɉ��߂悤�Ƃ��Ȃ��B
�@���̂悤�ȕֈߑ���p�́A�햯�ƕ����Ƃ̋�ʂ����Ȃ����߁A���R�߂��Ȃ��햯�ɐ�Ђ��y�Ԃ��Ƃ͖ڂɌ����Ă���A���̂��ߗ���@�K�͂�������ւ��Ă���̂ł���B
�@���w�E���Z�̗��j���ȏ��ɂ́u��������Ă������E�Q�����v�Ƃ����āA�����ɂ��l���ɂ����Ƃ�s�ׂ̂��Ƃ��L�q���Ă��邪�A������̂āA�햯�p�ɂȂ�������Ƃ����āA����Ŗ��ߕ��Ƃ��Ƃ����ƁA�푈�Ƃ͂���ȊÂ����̂ł͂Ȃ��B���̍��܂Ő���Ă����ֈߕ����A������̂Ă�����Ƃ����āA�ߗ��̂��������A���͏����邩�Ƃ����ƁA�����͂����Ȃ��B
�@�펞���ۖ@�ɂ��ƁA�ֈߕ��͌�펑�i��L���Ȃ����̂Ƃ���Ă���B
�@��펑�i��L������̂́A�����Ƃ��āA���K�̌R�l�Ȃ�тɐ��K�̌R�l�̎w������R�͖��͌R�p�@�ƂȂ��Ă���B
�@1907�N�̗���@�K�ɂ��ƁA�i�����܂��͋`�E���ł��j���̏��������Ȃ���ꍇ�̂݁A��펑�i��L������̂Ƃ��Ă���B
�@
�@(1)�����̂��߂ɐӔC�������ҁi�w�����j�����邱�ƁB
�@(2)��������F�����邱�Ƃ̂ł���ŗL�̓���W�͂�L���邱�ƁB
�@(3)���R�ƕ�����g�s���Ă��邱�ƁB
�@(4)�푈�̖@�K����ъ���ɏ]���čs�����Ă��邱�ƁB
�@�\�\�\���������������炢���Ă��A�ֈߕ��܂��͕ֈߑ��́u��펑�i�v��L������̂ł͂Ȃ��B
�@
�@�u��펑�i��L���Ȃ����̂��R���s���ɏ]������ꍇ�ɂ́A�G�ɕ߂炦��ꂽ�ہA�ߗ��Ƃ��Ă̑ҋ��͗^����ꂸ�A�펞�d�ƍߐl�Ƃ��Ă̏������Ȃ�������Ȃ��v�i�ȏ�͓c���Γ�Y���u�V�����ۖ@�v�i���j203�y�[�W���j�B
�@
�@����ɁA�䂪���̍��ۖ@�̌��Ђł���M�v�~�����m�͎��̂��Ƃ��q�ׂĂ���B
�@�u����҂̍s�ׂƂ��ẮA���̎��i�Ȃ��ɂȂ����G�s�ׂ����Ă��邪�@���A���Â���펞�d�ߔƂ̉��ɁA���Y�A�������͎��Y�ɋ߂��d�߂ɏ�������̂��펞���@�̔F�ނ��ʂ̊���ł���v�i�M�v�~�����u��C��ƍ��ۖ@�v125�y�[�W�j�B
�@�u�ֈߑ��v��_����ꍇ�A��X�͂܂����̂悤�Ȑ펞���ۖ@�̊T�O�ɓ���Ă����K�v������B
�@�����̓t�����X�̃��W�X�^���X�^���҂��h�C�c�̃Q�V���^�|�ɔ������ꎟ��A�ٔ��������Ȃ��ł��̏�ŏ��Y������ʂ������ǂ��j���[�X�f��Ō��Ă���B
�@�싞�s�E�̃f�}�S�M�[�̈�ɓ�悩��̕ֈߑ��̓E�o��肪����B
�@�����������̂悤�Ȗ�肪���N�����̂́A�ֈߐ�p���Ƃ��������̍����}�R�ƁA�����Ǘ��������ۈψ���̐ӔC�ł����āA��C�̓�s�ɂ�������i�W���L�[�m�E�]�[���j�̂悤�ɁA�Ǘ��҂����R�ƁA��������グ�A�햯�Ƌ�ʂ��Ė�����쐬����Ȃ�A���邢�͈ꏊ�ɍS�u���Ă����Ζ��͂Ȃ������̂ł���B
�@�싞�ח����O�A�����R���ֈ߂ɒ��ւ��āA���ɐ������邳�܂��_�[�f�B���L�҂͎��̂悤�ɕ��Ă���B
�@
�@�u���j���i12��12���j�̐��߁i�����j�A�N���R�i���{�R�j������i������j�t�߂����ǂ��悶�̂ڂ�Ɓi�M�ҁq���r��6�t�c�O�������̈�ԏ��j�A�����R�̕��n�܂����B�攪���t�̐V�����܂��������A�����܂����̎҂�����ɑ������B�[���܂łɂ͑�R�����ցi�V���[�J���j�̕��ւ��ӂ�o�����A���֖�i�c�]��j�͂܂������R�̎蒆�ɂ������i�M�ҁq���r���̂Ƃ��c�]��Ńp�j�b�N��Ԃ��N���A�l�Ȃ���ƂȂ��đ����̒����l���������Ă���j�B
�@���Z�����́i���́j�ɑΏ����邱�Ƃ����Ȃ������B�ꕔ���͏e���̂āA�R����E���A�ֈ߂�g�ɂ����B�L�҂��P�Q���̗[���A�s�����Ԃʼn�����Ƃ���A�ꕔ���S�����R����E���̂�ڌ��������A����͊��m�ƌ����Ă��悢�قǂ̌��i�ł������B�����̕��m�͉��ցi�V���[�J���j�������Đi�ޓr���ŌR����E�����B���H�ɓ��荞��ŕֈ߂ɒ��ւ��Ă���҂��������B���ɂ͑f�����ƂȂ��Ĉ�ʎs���̈ߕ����͂��Ƃ��Ă��镺�m�������E�E�E�E�v�i�`�h�h282�y�[�W�j
�@
�@�u���j���̗[���ɂ͒����R�͈��S��S�̂ɂЂ낪��A�����̎҂��A��ʎs������ֈ߂𓐂�A����ł䂸���Ă�������肵���B
�@�g��ʐl�h����l�����Ȃ����́A����ł����m�B�͌R����E���ʼn����ꖇ�ɂȂ��Ă����B
�@�R���ƂƂ��ɕ�����������āA�X�͏��e�E��֒e�E���E�w�̂��E�R���E�R�C�E�w�����b�g�ł����܂�قǂł������B
�@���֕t�߂ň�����ꂽ�R���i�̗ʂ͂��т����������̂������B
�@��ʕ��̑O����2�u���b�N��܂ł́A�g���b�N�E�C�E�o�X�E�w������p�ԁE�הn�ԁE�@�֏e�E���Ί킪�S�~�̂ď�̂悤�ɐςݏd�˂Ă������B�v
�@�u���j���i13���j�����ς��A�����R�����̈ꕔ�͎s���̓�������ѐ��k�n��œ��{�R�Ɛ퓬�𑱂����B�������܂̃l�Y�~�ƂȂ��������R�̑啔���͂��������C�͂��Ȃ������B����Ƃ������m���O���l�̈��S��ψ���ɏo�����A������̂Ă��B�ψ���͂��̎��͓��{�R���ߗ�������Ɉ������낤�Ǝv�����̂ŁA�~�����Ă�����̂������ق��Ȃ������B�����R�̑����̏W�c���X�̊O���l�ɐg���܂����A�q���̂悤�ɔ�����Ƃ߂��B�v�i�`�h�h290�`1�y�[�W�j�B
�@
�@�ē싞���̎��كG�X�s�[���͖{�����{�Ɏ��̂悤�ɕ��Ă���B
�@
�@�u�E�E�E�E�s���̑啔���͓싞���ۈψ���̌v��ݒ肷�邢����w���S�n�сx�ɔ�����A�������̎x�ߕ����I�݂ɕߑ�����͂��Ȃ肵����r�I�����Ȃ肵�Ȃ��A���ۂɎc������x�ߕ��̐��͕s���Ȃ�ǂ��A����̎҂͂��̌R����E���̂ď햯�̕��𒅂āA�햯�ɍ���s���̂ǂ����s���ǂ����ɉB�ꂽ��ɑ���Ȃ��Ȃ�v�B
�@�܂����̓����ٔ��ւ̒�o���ނ͎��̒ʂ�ł���B
�@�u�E�E�E�E�����Ɉꌾ���ӂ���������ׂ��炴��́A�x�ߕ����g�A���{�R����O�ɗ��D���s����������ƂȂ�B�Ō�̐����Ԃ͋^�Ȃ��ނ�ɂ��l����э��Y�ɑ���\�s�E���D���s��ꂽ��Ȃ�B�x�ߕ����ނ�̌R����E���햯���ɒ��ւ����}���̏��u�̒��ɂ́A��X�̎������A���̒��ɂ���������邽�߂̎E�l�����s�����Ȃ�ׂ��B
�@�܂��ދp����R�l�y�я햯�ɂĂ��A�v��I�Ȃ炴�闩�D���Ȃ������Ɩ��炩�Ȃ�B
�@���ׂĂ̌��̎{�݂̋@�\��~�ɂ��s�����̊��S�Ȃ�N�ǁi�Ђ������j�Ǝx�ߐl�Ƒ啔���̎x�ߏZ���̑ދp�Ƃɂ��s�ɔ��������銮�S�Ȃ鍬���Ɩ������Ƃ́A�s�������Ȃ�s�@�s�ׂ����s��������ꏊ�ƂȂ��I����Ȃ�B
�@���ꂪ���ߎc������Z���ɂ́A���{�l������ΑҖ]�̒����Ɠ����Ƃ̉���ׂ��Ƃ̈Ӗ��ɂāA���{�l�����}����C�����������肽�邱�Ƃ͑z��������Ƃ���Ȃ�B�v�i�@��ؑ�328�������@�ԍ�1906�����̈ꕔ��ٌ�l���N�ǂ������́����L�^210���j
�@
�@�����O�ɏq�ׂ��邲�Ƃ��A�܂��ĕ��̎��̕��Ƃ��A����̔s�c�������S����ɓٓ����A�g���B�������A���{�R�������14����16����2��ɂ킽���ēE�o�����f���Ă���B
�@�{�i�I�ɕֈߕ��̓E�o���͂��߂��̂́A12��24���ȍ~�̂��Ƃł���B
�@���̎��͌������A�����ێ���̒����l������̂��Ƃɍs���A��2��l���E�o���ꂽ�B
�@���A���̖�2��l�͂��ׂĊO�ɑ����ߗ��Ƃ��Ă̑ҋ��������Ă���i���X�ؓ��ꏭ����ژ^�j�B
�@���̕ֈߕ��E�o�������A���S��ɂ�����ő�̃g���u���ł������Ƃ����Ă悩�낤�B
�@�u�������X�V���v�́A12��20���̗[���ɁA�k18���u�����h�����l�Ƃ��āA��O����싞�ɂƂǂ܂��Ă����^�O���l�i���ɓ����j�̓��������āA�O�l�̌�����ɂ̓싞�Ō�̖͗l����Ă���B
�@����ɂ��ƁA7�������A�ӈψ�������s�@�œ싞��E�o�������A�u���̏ӈψ����̓s�������`����A�S�s���͉ƍ�������ē��ւȂ��ꍞ�v�Ƃ���B�܂�s���͈�l�c�炸���֓��������Ƃ݂Ă悩�낤�B
�@�܂�8���ɂ́u�n�싞�s������܂��s����u������ɂ��ē��������A�x�O�̎x�ߌR�͖��Ƃɉ�����A�싞�t�߂͎l���ɉ��X����Ή��N����A�s���܂��Ђ���A�������ӎs���̎p�͂��̐��̂��̂Ƃ͎v���ʁv�ƋL�q���Ă���B�x�ߕ����L�̔s�����̗��D�͂��̂���Ɍ��ɒB�������Ƃ͗e�Ղɑz���ł���B
�@���������ɏq�ׂ��悤�ɁA�d�M�A�d�b�͂��Ƃ��A�d�C���������r�₦�A�s�������D�E���̖����{��ԂɊׂ����̂͂��̍�����ł���B
�@�����ɂ͂�������B
�@
�@�u12���A��O�̎x�ߌR������ƂȂ�A87�t�A88�t�A���������́A�w���R���R���c���Ďs���ɐ���ꍞ�݁A�����q�͌��{���Ĕނ��w������36�t�ɖ����A�����s�c����Ђ��[����e�E������A�吨�@���Ƃ�����\�͂��A�����q���܂������Ƌ��ɖ�8�����뉽���Ƃ��Ȃ������̂ԁB�s�c���̕��A���D�Ȃ�����͂Ȃ��A���|�Ɋׂ��B�d���͏����A�����W���A���̐��̖����Ƌ^�͂�B�d�b�S���s�ʂƂȂ�E�E�E�E�v�i�u�������X�V���v12�E20�j
�@
�@����𗠕t����悤�ɁA�싞�ɓ��邵�����{���͐��K�����ֈ߂ɒ��ւ��邽�ߒE���̂Ă��R�ߌт�R�C�A�R�X�A����ޓ��̂��т��������U�������Ă���B
�@16���ߌ�A���R�傩��X�֎Ԃœ��邵�����X�،������́A����Ō�����i�����̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@
�@�u�{�ʂ�A�R��������C�R���ɂ��������̊Ԃ́A�^�ɋ����ׂ����@�����̐ՂƎv����B���̂͂��łɕЂ�����ꂽ�̂����Ȃ����A���e��S����ߕ����T�S���ɂ߁A�����ň�A�̎x�ߕ����|�˂��ꂽ���Ǝv�������ł���B����͎x�ߕ����R����E���̂āA�ֈ߂ɒ��ւ������̂炵���������v�i���X�،������u���X�֊��v216�y�[�W�j�B
�@�R�i�ߕ��t���c���ʖ́A13���A���鎞�̓싞����̗l�q�����̂��Ƃ����B
�@�@�u�s�����イ�R���A�Q�[�g���A�X�q���U�����Ă��܂����B����͂��������ň�Ԗڂɕt���܂����B���������R����E���Ŏs���ɕ��ꍞ�̂ł��B�������ɂ��Ă݂�A�R���𒅂Ă���Ɠ��{�R�ɂ���܂����瓖�R�Ƃ������܂��v
�@����叫�́w�w�������x�̒��Łu���ɓٓ������ֈߕ������E�E�E�E�E�E�v�Əq�ׂĂ���B
�@�Ƃɂ������̐���Ƃ݂���ֈߕ����A���ۈψ���͉���̃`�F�b�N��i����炸�A�������Ő��������߂��̂ł���B
�@��C��ł̐퓬�́A�����o���Ƃ������Ɏ��������ŁA�����̐펀���҂��o�������A�����̏ꍇ���̕����҂́A��Ƃ��ē싞����ѕ��Ε��ʂɌ㑗���ꂽ�B
�@���̓싞�Ɍ㑗���ꂽ���a�҂̐��͂��������ǂ̈ʂɂȂ邩�ɂ��āA���{�������́u�،��ɂ��u�싞��j�v�v�̒��Ŏ��̂悤�ɂ��킵���q�ׂĂ���B
�@�q11��25���̒��x�ߕ��ʌR���������̒����ɑ���ɂ��ƁA
�@
�@�u��C�̎x�ߌR83�t�c�̂����A���̔����͑��Ղ��Ă���A���̎���͖͂�40�����O�v�Ƃ�����B
�@��C�̌���n�ɒ�����������83�t�c�̑啺�͂ƂȂ��������R�́A��4�����Ԃɗv10���l�̎����҂��o�������ƂɂȂ�B
�@�����̎��҂͌��n�ɂ����ď��u����A�����҂͒����㑗���ꂽ�̂ł��낤���A�㑗���ꂽ�������̐��͂ǂ̂��炢�ɂȂ�ł��낤���B
�@�u�����ɂ�������{�R�̐펀�҂ƕ����҂̔䗦����݂āA���Ȃ��Ƃ�15���ȏ�̕����҂��싞�Ɍ㑗���ꂽ�v�Z�ɂȂ�A3�����ɋy��ł���̂ŁA1����5���l�A1������1700�l���A���싞�Ɍ㑗���ꂽ���ƂɂȂ�r�@
�@�����̕����҂́A�ꎞ�싞�ɂƂǂ܂�A�����d���҂͑D�Ŋ����ցA���邢�͗��H�]�k�Ɉڑ����ꂽ���̂Ǝv����B
�@�������싞�̕a�@�Őw�v���ď���̕�n�ɖ������ꂽ���̂�����������͂��Ɛ������Ă���B
�@�Ȃ��A��16�t�c�Q�d������O�v�卲�͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@
�@�u�싞��11�����{���A�����������̐펀���҂̎��e���ƂȂ�A�ړ]���鐭�{�@�ցA�l�̎��@�܂ŋ����I�ɕa���ɏ[�Ă��A�S�s���̍����A�т܂����ԂȂ�B����ɐ��������҂��܂������Ȃ��炸�v
�@�S�s�Ɉ��̍��肪�т܂��Ƃ����\���́A�O�q�́u�������X�V���i�������V���j�v���X�N�[�v�����^�O�l�̓��L�̒��ɂ��u25���i11���j�펀���҂̓싞�㑗�ŁA�ړ]��̐��{�@�ւ͂������A���l�̓@��܂ŋ����I�ɕa���ɂ��Ă��A�S�s���̍��肪�т܂A�R�l�̒��ƈ�ς����E�E�E�E�v�A�Ƃ���A���ł�11��25�����납��싞�S�s����⋕a�@�̊ς�悵���l�q������������̂ł���B
�@����Q�d�͂���ɂ��������Ă���B
�@
�@�u���鎞�A�O�̌����́A�啺⋁i�ւ�����j�a�@�J�݂���ꂠ��A��ƂƂ��ɊO�l�̎w�����ɂ���āA������Z���鑽���̊��҂�i�i�悤�j���A�d���ґ����B���X�A3�A40�����������肽��B
�����̏������A�^����R���������@���ɂ�����^��ɂ��āA�t�߂ɖ�������ꂽ�邱�Ɗm���Ȃ�v�i�����ٔ��ɒ�o���ꂽ�g����̖������̂̒��ɂ́A���R�����̎��̂��������������͂��j�B
�@����1������3�A40�����S�����Ƃ���A���̑��A�S�����A�R������̏�����@�A������@�Ȃǂ̕�⋕a�@�����v����A����1��100�����O�̎��S�҂������̂ƍl������B
�@��C�̌����8�����{�ȗ���3�����ԑ���������A��L�̌v�Z�����p����ƁA��9000�l���싞�ɂ����Đw�v�������̂Ɛ��������B
�@�Ȃ��싞��ɂ����钆���R�̐펀�҂̐����_�[�f�B���L�҂�3��3000�Ɛ������Ă���\�\�\�������g����ɂ���Ė������ꂽ�킯�����A�����̏����n�̖������̐����A���ׂē��{�R�ɂ��s�s�E���̐��t�ł���Ɠ����ٔ��ł͔������Ă���A���������A���{�̋s�E�h�̐l�X�����̂悤�Ɏ咣���Ă���B����������͂Ƃ�ł��Ȃ�����ł���A�s�E���𑝂����߂̍�דI�ȋ��\�ł���Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�ȏオ�ח����O�܂ł̓싞�̎���ł���B����Βf�����̓싞�̎p�ł����āA�싞�����͂��̂悤�ȏ̒��ɓ��{�R���˓��������Ƃ��܂��O���ɂ����K�v�����낤�B
�@���肩�������悤�ł��邪�A�싞�̗��D�ƕ�����ю�̎E�Q�́A���łɓ��{�R��̈ȑO�̎����A���S�A�i�[�L�[�̏�Ԃ̒��ŁA���݂��Ă����̂ł���B�������������ꂽ���̐��C�R�[�����{�R�ɂ��s�E���Ƃ��Čv�Z���邪���Ƃ��A���ӂɖ������A��דI���|�[�g���A�����͉L�ۂ݂ɂ����ɂ͂����Ȃ����ƂL���Ă��������B
�@�܂��A�싞�U����ɎQ���������{�R�̕Ґ����猩�Ă݂悤�B
�@�싞�U�����s�������{�R�́A�����(�܂�����ˁj���R�叫���R�i�ߊ��Ƃ��钆�x�ߕ��ʌR�ł��邪�A���̟����i�����j�ɏ�C�h���R�Ƒ�10�R���������B���̒ʂ�ł���B
�@��C�h���R�i�R�i�ߊ��@�����{�����j
�@�@��16�t�c�i���s�j�A��9�t�c�i����j�A��11�t�c�@�V�J�x���i�P�ʎ��j�A��13�t�c�i���c�j�R�c�x���A��3�t�c�i���É��j�̈ꕔ�A�@�@��101�t�c�i�����j�̈ꕔ
�@��P�O�R�i�R�i�ߊ��@���쒆���j
�@�@��6�t�c�i�F�{�j�A��114�t�c�i�F�s�{�j�A��18�t�c�̈ꕔ�i����x���j
�@�i�ȏ�ʕ\�E�Ґ��\�Q�Ɓj
�@�����͖͂�10���ƍ����Ă������A��C��ł̏��Ղ͂������A���ۂɓ싞��ɎQ���������͂�7�`8�����x�Ƃ݂��Ă���B
�@�싞���U�������i�ߕ�����ѕҐ��͎��̒ʂ�ł���B
�i�ߕ��̕Ґ��i���a12�N12���j
| ���x�ߕ��ʌR | ��C�h���R | ��10�R | |||
| �i�ߊ� | ��@���@������@�i9�j | �R�i�ߊ� | �����@�@�����{���F���@�i20�j | �����@�@���약���@�i12�j | |
| �Q�d�� | ���@���@�˓c�U�@�i19�j | �Q�d�� | �����@�@�я��@��@�i21�j | �����@�@�c�Ӑ����@�i22�j | |
| �Q�d���� | ���卲�@�����́@�i25�j | �Q�d���� | �����卲�@�㑺�@���ʁ@�i22�j | ||
| �Q�@�d | �R�卲�@�������@�i25�j�� �������@�F�����`�@�i28�j�� �������@���@�E�@�i28�j�� �������@���_�@���Y�@�i28�j�� �C�����@�����@�����@�i31�j �q�����@�����@�ȎO�@�i31�j �R�����@�{���@���v�@�i32�j�� �q�����@���R�@�J�l�@�i33�j �H�����@��{�@�`���@�i34�j �H�����@�͑��@�َ��@�i34�j �C�����@�g��@�@�ҁ@�i35�j ���ۖ@�ږ� �@�w���m�@�ē��@�ljq |
��1�� | �R�卲�@�����@���@�i25�j �������@�F���@���`�@�i28�j �q�����@�k���@�F�Y�@�i29�j �q�����@���@���u�@�i30�j �C�����@��@��n�@�i30�j �������@��_�@�@�́@�i34�j �C�卲�@���c�@��H�@ �C�����@�@�@���@�@ |
�q�卲�@���{�@�S�F�@�i26�j �������@���c�@��Y�@�i29�j �C�����@�g�i�@�@�p�@�i31�j �H�����@�r�J�@����Y�i33�j �������@�R��@���j�@�i33�j �q�����@���@�����@�i35�j ����с@�哪�@�r�O�@�i36�j |
|
| ��2�� | �������@���@�@�E�@�@�i28�j �R�����@�{���@���v�@�i32�j �������@��~�@���K�@�i33�j ����с@�吼�@��@�@�i36�j �C�����@���@���� |
���卲�@���@�@���@�i26�j �������@���c�@�d��@�i31�j �������@���e�@���Y�@�i34�j �C��с@�����@���j�@�i36�j �C�����@���{�@���� |
|||
| ��3�� | �������@���_�@���Y�@�i28�j �������@���c�@���v�@�i35�j �������@�匴�@��v�@�i35�j �������@�k��@�����@�i35�j �C��с@���X�@�����i38�j �C�����@�����@���g |
�H�卲�@�J�c�@�@�E�@�i27�j �n�����@�����@�M�ǁ@�i30�j ����с@���q�@�ω�@�i39�j �C�����@�����@���g |
|||
| �Ǘ����� | �������@�쏟�@��Y�@�i24�j | ||||
| ���핔�� | ���@���@�����@�L�O�@�i20�j | ||||
| �R�㕔�� | �㏭���@����@�G�� | ||||
| �o������ | �叭���@���݁@�Ύ� | ||||
| �b�㕔�� | �b�����@���{�@�����Y | ||||
| �@������ | �����O�@�˖{�@�_�� | ������@����֎��Y | |||
| �������� | �������@���c�@�����@�i32�j | ||||
�@���F����͌����B�e�ۂɂ����Ẳے��͖���F�Ŏ����Ă���B�i�@�j�͗��R�m���w�Z�̊��������B
�w�����ꗗ�\�i���a12�N12���j
| �R | �t�@�c | �Ґ��n | �t�c���E�Q�d�� | ���c | �Ґ��n | ���@�c�@�� | �A�� | �Ґ��n | �A���� |
| ��C�h���R | 3 | ���É� | ���c�@�i�����i16�j �@�c�K�@���Y�卲�i23�j |
5 | ���É� | �ЎR����Y�����i19�j | 6 | ���É� | ����@���卲�i24�j |
| 68 | ��@�� | ��X�@�F�卲�i20�j | |||||||
| 29 | �Á@�� | ��슨��Y�����i21�j | 18 | �L�@�� | �Έ�@�Õ�卲�i24�j | ||||
| 34 | �Á@�� | �c��@���Y�卲�i25�j | |||||||
| 9 | ���@�� | �g�Z�@�Ǖ㒆���i17�j �@����@�@�L�卲�i22�j |
6 | ���@�� | �H�R�@���[�����i20�j | 7 | ���@�� | �ɍ��@��j�卲�i23�j | |
| 35 | �x�@�R | �x�m�䖖�g�卲�i19�j | |||||||
| 18 | �ց@�� | ��o�@�鎞�����i21�j | 19 | �ց@�� | �l���@�G�O�卲�i23�j | ||||
| 35 | �I�@�] | �e��@���Y�卲�i19�j | |||||||
| 11 | �P�ʎ� | �R���@�@�������i14�j �@�Б��@�l���卲�i23�j |
10 | �P�ʎ� | �V�J�����Y�����i21�j | 12 | �ہ@�T | ���B��\�O�卲�i22�j | |
| 22 | ���@�R | �i�Í���d�卲�i23�j | |||||||
| 22 | ���@�� | ����@�`�������i18�j | 43 | ���@�� | ��ԁ@�`�Y�卲�i12�j | ||||
| 44 | ���@�m | �a�m�@���卲�i26�j | |||||||
| 13 | ��@�� | ���F�@���������i17�j �@���@�E�O�Y�卲�i23�j |
26 | ���@�c | ���c�@���d�����i19�j | 58 | ���@�c | �q�с@���C�卲�i22�j | |
| 116 | �V���c | �Y�c�@�@�t�卲�i20�j | |||||||
| 103 | ��@�� | �R�c�@����i18�j | 65 | ��Îᏼ | ���p�@�ƍ�卲�i22�j | ||||
| 104 | ��@�� | �c��@���r�卲�i24�j | |||||||
| 16 | ���@�s | ���������ᒆ���i15�j �@����@�O�v�卲�i24�j |
19 | ���@�s | ����@�C�������i20�j | 9 | ���@�s | �Ћˁ@��Y�卲�i20�j | |
| 20 | ���m�R | ���@�閾�卲�i23�j | |||||||
| 30 | �� | ���X�ؓ��ꏭ���i18�j | 33 | �� | ��c�@����卲�i24�j | ||||
| 38 | �ށ@�� | ����@�Ó�卲�i19�j | |||||||
| 101 | ���@�� | �ɓ��@���쒆���i14�j �@���R�����Y�卲(24) |
101 | ���@�� | �������O�Y�����i19�j | 101 | ���@�� | �ђˍ��ܘY�卲�i22�j | |
| 149 | �b�@�{ | �Óc�@�C�Q�卲�i19�j | |||||||
| 102 | ���@�� | �H���@�`�Y�����i17�j | 103 | ���@�� | �J��@�K���卲�i21�j | ||||
| 157 | ���@�q | ����_���Y�卲�i20�j | |||||||
| ��10�R | 6 | �F�@�{ | �J�@���v�����i15�j �@����@��跑卲�i23�j |
11 | �F�@�{ | ��䓿���Y�����i17�j | 13 | �F�@�{ | ���{�@�۔V�卲�i21�j |
| 47 | ��@�� | ���J�쐳���卲�i24�j | |||||||
| 36 | ������ | �����@�@�������i20�j | 23 | �s�@�� | ���{�@���b�卲�i22�j | ||||
| 45 | ������ | �|���@�`���卲�i23�j | |||||||
| 18 | �v���� | �����@��Y�����i12�j �@�����@�@�b�卲(20)�@ |
23 | �v���� | ���@�T�Ꮽ���i18�j | 55 | ��@�� | �앛�@�����卲�i22�j | |
| 56 | �v���� | ���R�@�O�Y�����i22�j | |||||||
| 35 | ���@�� | ��ˁ@�ȎO�����i19�j | 114 | ���@�q | �Љ��@�p�������i23�j | ||||
| 124 | ���@�� | ����@�F�������i23�j | |||||||
| 114 | �F�s�{ | �����@�Ύ������i14�j �@��c�@�O�Y�卲�i25�j |
127 | �F�s�{ | �H�R�@�[�O�Y�i18�j | 66 | �F�s�{ | �R�c�@�푾�����i24�j | |
| 102 | ���@�� | ��t�����Y�卲�i21�j | |||||||
| 128 | ���@�� | ���@�@�ەv�����i17�j | 115 | ���@�� | ���ߎO�����i27�j | ||||
| 150 | ���@�{ | �R�{�@�d�{�����i23�j | |||||||
| 5 | 9 | �L�@�� | ����@�@�o�����i19�j | 41 | ���@�R | �R�c�S��Y�卲�i20�j | |||
���F�i�@�j�͗��R�m���w�Z�̊��������B
�@����ɑ��싞�h�q�R�̕��͔z�����퓬����͎��̒ʂ�ł���i�����I�A鰓����Ғ��w�R����j�x���ؖ������h�����@�o�łɂ��j�B
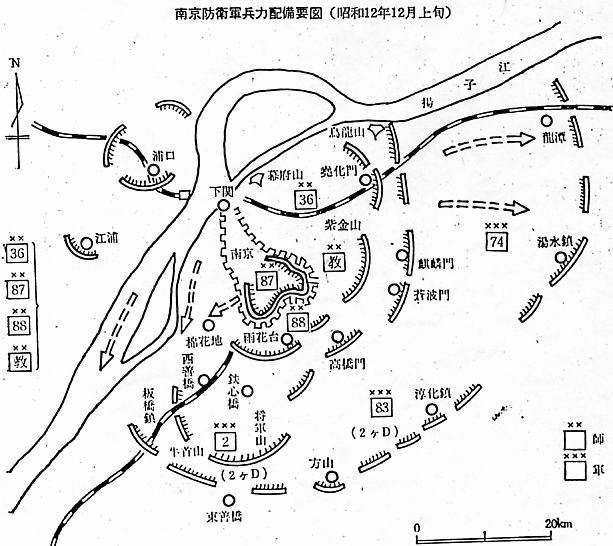
|
||||||||||||||
|
���͔z���͏�}�̒ʂ�ł���B�i�u�R����j�v54�y�[�W�j�B
�@�������{�R�͒����̎�s�h�q�R��10���ƌ��Ă����B
�@����͑O�L�̐퓬����ɖ���A�˂����c�ԍ��ɂ�邪�A�싞�ח����̏���̕��͂͂��̔����ȉ��Ƃ݂�̂��Ó��̂悤�ł���B
�@�j���[���[�N�E�^�C���Y�̃_�[�f�B���L�҂́A���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@
�@�u�싞��͂̓��{�R�ɑR�����̂́A�L���R���t�c�A�]���R2�A3�t�c�A��̌Γ�R�A����ɏ���ł͑�36�t�A��88�t����т�����싞�t�c�ł������B�L���R�����́A��C�t�߂�����{�R�̑O�ʂ�ދp����ԁA���T�Ԃ����{�R�̖C���ɂ��炳��Ă����B
�@���ďӉ�Α����̐��s�R�ł�������36�t�Ƒ�88�t�́A��C�t�߂ő呹�Q��ւ��Ă����B
�@�����̎t�c�͓싞�ɑދp���ĐV�����[�����B
�@�h�B�Ƌ�e�̊Ԃœ��{�R�̐i�U�ɑ����ɗ����Ē�R���Ă����l��R�̑啔���͕�����͗g�q�]��n�͂��Ă��܂��A�싞�̐퓬�ɂ͉����Ȃ������B
�@�싞�s���O�̒����R�̐�͂��ǂ�قǂł����������m�ɂ�����͓̂���B
�@����ώ@�҂����̐���ł́A�싞�U�h��ɂ�16�t�c���Q�������Ƃ����B���̐����͐��m�ƌ��Ȃ����B
�@�����R�̎t�c�͕����ɂ����Ă������A���ς��Ă킸��5000���Ґ��ɂ��������Ȃ��B�싞��h�q���ĒɌ���ւ�����t�c�́A���Ȃ��Ƃ��ꍇ�ɂ���Ă͂��ꂼ��2000�`3000���Ґ��ł��������Ƃ����蓾��B
�@��T���l�̌R���싞�h�q��ɎQ�����A�܂̃l�Y�~�ƂȂ����Ƃ����Ă��ԈႢ�Ȃ��B�v�i�`�h�h286�`7�y�[�W�j
�@���̂ق��A�ݓ싞�đ�g�كA���\���O�����L������݊����W�����\����g���Ăɑ��t�����싞�ĕ��̎��W�F�[���X�E�G�X�s�[�̕��ɂ́u���i�싞�j��5�����z�����镺���ɂ�����邱�ƂƂȂ苏���B���ۋ͂����B�̂T���ɉ߂�����Ȃ��v�Ƃ���i�u���L�^�v58��21�E8�E29�j�B
�@�܂��A�����ٔ��̔������̒��ɂ��u�����R�͂��̎s��h�q���邽�߂ɁA��T���̕����c���ēP�ނ����v�u�c���R�T���̑啔���́E�E�E�E�v�Ƃ���A�����̓싞�������5���Ɣ��肵�ċc�_��i�߂Ă���B
�@�܂��u�싞���S�捑�ۈψ���v�̓��{��g�قւ̌������̒��ɂ��u�싞�q���R�ܖ��v�ƋL�ڂ���Ă���A���a12�N12��13���̓싞�ח����ɂ����铂���q�����i�����j�̕��͂͂����ނ�5���Ƃ݂��Ă����B
�@�������A������19���c�i�ߕ��̒ʐM�ǒ������`��Y���́A�����R�Ő퓬�����̌��ƁA���̒������̎������̑����琄�����āu�ח������̏���̕��͂́A�u��������3���Ă��ǁv�Ƃ������������Ă���B
�@����𗠕t����悤�ɁA�ŋߐ`��F����p�Ŏ�ނ����Ƃ���ɂ��ƁA���ؖ����̊W�҂́A�������3.5���ƌv�Z���Ă���B�v�����3.5�����瑽�����ς����Ă�5���ł���B
�@�Ȃ������q��11��28���A�O�l�L�҉�ŁA�����R�͌P�������肸�A�K�����ǂ��Ȃ��̂ŁA�s�ˎ����N���邩������Ȃ��A���p�̊O�l�͑ދ����ꂽ���ƌx�����Ă���B
�@�������������ł������킩���A�ӔC�͎��ĂȂ�����ދ�����Ƃ����̂ł���B
�@���̂��߁A�O�q�́u���S�捑�ۈψ���v�̈ψ�15���A�V���L��5���A��̌��و���20�������c�����́A12��7���̏Ӊ�ΒE�o�ƑO�サ�ē싞��ދ����Ă���B
���邷����{�R�ɔ���i����1�j
���a12�i1937�j�N12��13���B�e
�B�e�ҁ@�A�[�T�[�E�����P��
�i��p���}�E���g�E�j���[�X�f��J�����}���j

�i���{�R�����ڂ̑O�ɂ��Ȃ���j����ق�ƋQ���������l����������Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�j�Z����ʐ^�Łg�싞��s�E�h�˂�
 |
| �u�����V���v���a59�N8��4���t�[���Ɍf�ڂ��ꂽ�g�싞�s�E�h�̋L���Ǝʐ^�i��ʐ^�A�_���ň͂܂�Ă���̂�����ʐ^�j |
�@�u�L���̍Ē������������ʁA�����ŕ�3���̎ʐ^�Ƃ͖��W�̃��m�������B
�@�߂��A�u�S���Łv�ŁA�ʐ^����юʐ^�Ɋւ���L�q�ɂ��Ă���т��A�������v
�@��ɉ����������V�������{�Ђ̍L��S�������A�R���j���́A�{���L�҂̎���ɁB�Ă��ς��Ƃ����ԓx�ʼn��������A���t�̒[�X�ɁA���ЋL���̔��F�߂���Ȃ����₵�����ɂ���ł����B
�@���a61�i1986�j�N1��17���A�����{�Ж������ł̂��Ƃł���B
�@���ƂȂ����u�����v�L���\�g�싞��s�E�h���ؖ�������L�Ǝʐ^���������ꂽ�\�����a59(1984)�N8��4���ɕ��Ă��A����1�N5�����Ԃ�ɖ{���̒Nj��ɂ���Ă悤�₭�����̓j�Z�ʐ^�́u����ыL���v�f�ڂ����肵���̂ł���B
�@�u�����v����ޔǂɁA��ǎ҂���u�싞��s�E�v����u�����v�L���̋^��_���w�E�����������X������Ă����̂́A�u���X�E�����V���́u�ƍ߁v�v�̘A�ڂ��Ō�̒ǂ����݂ɓ��������a60�N12��14���̂��Ƃł������B
�@���̓��e�́A���a59�N8���싞�ɓ��邵�����m���c�������L�Ǝʐ^����������A�u�����ʑ�ʎE�l�����j�I�����v�Ƒ�X�I�Ɂu�����v�������A���̌�̊W�҂̒����Łu������ɊY������l�������Ȃ��v�Ƃ������̂ł���B����Ȃ��Ƃ��͂����Ă���̂��H
�@�����A���u�싞��s�E�v�͂������Ǝ��X�ɕ������Ă��钩���V���̂��Ƃ��B
�@���������L�����̋L�҂������Ȃ��Ƃ�����Ȃ��B
�@�������Ē����̓싞�s�E�L���̐^�������Ɏ��g��ł������B
�@���ہA���Ɋւ��Ē����ɂ́A�������́g�O�ȁh������B�ŋ߂̗�ł́A���a59�i1984�j�N6��23���t�[���A�S���łŁu�싞��s�E�ڌ��̒��R�V�^�u��蕔�v�L�^�f��Ɂ^�����ł̍u���ȂNjL�^�v�Ƃ̌������ŕ�ꂽ�L������������B
�@���̋L���ɂ��ƁA�����E�]�ː�ɏZ�ޒ��R�d�v���i72�j�����R��ԑ��̐������Ƃ��āA�싞�����2���O�ɁA�싞�x�O�̉J�ԑ�ŁA�������f���Ă��钆���l����{�����e���Ŏ��X�Ǝh���E���Ă������i��4���Ԃ��܂�Î������Ƃ����B
�@�����A�]�_�ƁA�c���������̒��ׂ�
�@(1)���R���̏�����������ԑ��i�⒇��ԑ��j�͉J�ԑ�ɓ˓����Ă��Ȃ�
�@(2)�܂��Ē��R���͊⒇�����̒i��i�A�����Ō���Ζ��j�ł���A�J�ԑ�ɂ͍s���Ă��Ȃ��͂�
�@(3) �u�싞����2���O�v�̉J�ԑ�̐퓬�́A�匃�킪�W�J����Ă���Œ��ł���A�ƂĂ��������f���Ă̑�ʍ~����4���ԗ]�ɂ킽��E�Q��ʂȂǑz������ł��Ȃ�
�@�\�Ǝw�E�����B
�@�������A�����V���͉��̉����Ȃ������̂ł���B
�@���R���͂��łɑS���S�\�����ōu�����s���Ă���A���̗l�q�͋L�^�f��Ƃ��Ďc����Ă����Ƃ����B
�@���̉e���͌����ď������Ȃ��B
�@�u�싞��s�E�v�������ɏؖ����悤�Ƃ��邠�܂�A���U�́g�،��h��g�؋��h���j���[�X�L���Ƃ��ė����߂����A�u�����v�̋L�҂͂܂��Ƃ����̂ł��낤���B
�@���n�Ŋm�F���邽�߁A�L�ҁi����j�͋{��ɔ��ŊW�҂̎�ނɓ������\�\�B
�@���̋L���́A���{�Дł̏��a59�i1984�j�N�N8��4���t�[���ōł��ڍׂɕ��A�����{�ЁA�����{�Дłł��f�ڂ��ꂽ�B
�@���łł́A���Љ�ʃg�b�v�Łu���L�Ǝʐ^���������\�싞��s�E�^�ߎS���ʂ����O���^�{��̌����m�^����̔O���Â�v�̌������Ŏʐ^�����đ傫�����A���������̑S���łł������Z�����Ă̂���ꂽ�B�L�����������̂͒�����ʁE�{��x�ǒ��i���a61�i1986�j�N1��10���t�ŁA�����{�Њ�敔�����Ɉٓ��j�B
�@�L���́A�{�茧���P�n�S�k�����i�Ђ������������������ނ�j�o�g�ŁA�싞�ɓ��邵���s��i�݂₱�̂��傤�j23�A���̌��㓙���i����23�j�����a49�N�i1974�j�N�ɐt���a�Ŏ������̈�i����A�s�E�ɒ��ڂ��������A�ꂵ�ސS����Â������L�ƁA�S�E���ꂽ�����l�ƌ�����j���⏗���̐��]�����Ă���ʐ^�Ȃǂ����������A�Ƃ������́B
�@���a12�N�i1937�j�̌��U���炨���݂����܂Ŗ����y���ŏڍׂɋL�^����Ă���Ƃ������̓��L����A�����x�ǒ��͎��̂���������p���Ă���B
�@�\�\�ܓ��u�E�E�E�E�߂���k�R�Ȃ�܂܂ɍ߂������x�߁i�����ׂ̂��́j�l��߂܂��ė��Ă͐������܂ܓy���ɂ�����A�̒��ɓ˂�����A�ؕЂł������E������A�S���x�ߕ����畉������悤�ȎS�E�����ւĊ��ł���̂����s���������l�q�B
�@����\����u�������܂��߂̖����j�[���i�����l�̂��Ƃ��j��˂��|������ł����肵�Ĕ��E���ɂ����̂����̒��ɓ���ē���������ĂȂԂ�E���ɂ���B�E�E�E�܂�Ō���L���E�����炢�̂��̂��v
�@�����x�ǒ��́A����ɑ����āu���������������Ƃ�F�߂�ƂƂ��Ɍ���̔O���݂��Ă���B����ɋs�E�����퉻���Ă��邱�Ƃ��킩��v�Ɓg����h�����Ă���B���p���̍Ō�ɂ́A�i����������炩�Ȍ뎚�ȊO�͌����̂܂܁j�Ƃ������߂܂ŕt�������Ă���B
�@�܂��u�ʐ^�̓A���o���ɎO���c���Ă����v�u�B�e�ꏊ�͓싞������ǂ����L����Ă��Ȃ����A���O�Ƒ��Ɂw�싞�s�E�̍ۂ̎ʐ^�x�ƂЂ����Ɍ���Ă����Ƃ����v�u�Ƒ��̘b�ł́A���O�ʐ^�����Ă͎v���Y��ł��������������Ƃ����B�Ƒ��́u���s�Ŏ蒠�����������̂��V���̕Œm����ɗ��ĂƎv�����B
�@��x�Ɛ푈�͋N�����Ăق����Ȃ��v�Ƙb���Ă���v�Ƃ��āA�Ō�Ɂu�싞��s�E�̌����Ƃ�1�l�A���s��̍L����G�������i���{����j�j�́u���s�Ō������������ɔ�ׂāA�ߎS��������������ĕ\������Ă���悤���B�ʐ^�ɂ��Ă�����܂ŏo���͂قƂ�ǒ���������̂��̂ŁA���{�R�̕��m�������Ă������Ƃ͑�ϋM�d�Ȏ����ƕ]���ł���x�Ƙb���Ă���v�Ƃ̃R�����g�Ō���ł���B
�@�܂����[�h���Œ����x�ǒ��́u�i�u�싞��s�E�v�́j�L���A����̌�����A�E�V���r�b�c�ƕ��Ԗ����ʑ�ʎE�l�ƌ����Ȃ���A���{������̏،��A�؋����ɒ[�ɏ��Ȃ����������A�����ʎ��������j�I�����ɂȂ�Ƃ݂���v�ƁA�g��^�h�����B
�@20���A30���Ƃ����u�싞��s�E�v�́A�����̏���ǂ����Ă��s�\�ł���Ƃ������������ؓI�ɁA���l���̊w�ҁA�W���[�i���X�g���w�E���Ă���ɂ�������炸�A�u�L���A����̌�����A�E�V���r�b�c�ƕ��Ԗ����ʑ�ʎE�l�ƌ����Ȃ���v�Ƃ����\����p���Ă���Ƃ���ɁA�u�싞��s�E�v���������������悤�Ƃ��钆���x�ǒ��̈Ӑ}���ǂݎ���B�@
�L�����������Ɉ��l�������ꂽ�����{��
�@�����A���L�̕M�҂��s��23�A���̕��m�ƕ�ꂽ���ƂŁA���A���̐����҂ō\������A����i���y�G�Y��j�́A�u�A���̖��_��������L���v�Əd���A�V������2�T�Ԍ�ɑ��c���J�����B
�@�ȏ�A
�@(1)�u�싞�s�E�v�Ȃǐ펞���͂������A�I���ɂ����Ă����킳�b���畷���Ȃ�����
�@(2)�싞�U����ɏ]�R�������\�A�ؑ��B�A���s�ꎁ�ȂLjꗬ���M�Ƃ��ٌ������Ɂu�������Ƃ��A���킳�b���Ȃ��v�ƌ���Ă���
�@(3)�u�싞��s�E�v�͒������̈���I�������ł���
�@�\�\���Ƃ��m�F���A�����W�̒������s�����Ƃ����肵���̂ł������B
�@����c�ł́A�싞��s�E�����ꌩ�悪����u�����v�̋L�����ǂꂾ���̔g����ĂсA�A����̉���Ɍ������V���b�N��^���������A�ЂƂ̘b���A����Q���҂ɂ���Ĕ�I���ꂽ�B
�@�ނ͗V�тɗ������w���̑�����u�ꂿ����͈����l����ˁ[�v�ƌ���ꂽ�̂ŁA�u�����������ꂿ����́A�ݍ�����邽�߂ɐ����𓊂��o���Đ�������h�Ȏ҂��肾�B
�@�������ƂȂǂ��Ă����v�Ɣ��_�����B
�@����ƁA���̑��͂��������āC�g�t�P�h�����Ƃ����̂ł���B
�@�u�V���̓E�\����v
�@����ł͎Ⴍ���ĎU�����p�삪������Ȃ��\�\���������v�������ɁA�A����̒��R�L�ǎ����ǒ��ƍ⌳�ጳ23�A��������������̂��߂Ɍ��n�A�k������K�₵���̂ł������B
�@�@�W�܂���4�l�̐�F�ɁA�싞�s�E�ɂ��āA�܂��u�����v�ŕ�ꂽ���L��ʐ^�̌��ɂ��Ď��₵�����A�ٌ������Ɂu�������Ƃ����������Ƃ��Ȃ��v�ƌ����B
�@�����Œ��R�����ǒ���́A���̑��ɂ���3�̎��̉ߋ������������āA�u�����v�������a49(1974)�N�̎��S�҂ƕ��̂�����F�Ƃ��Ƃ炵���킹���Ƃɓ������B
�@�Ō�ɖK�ꂽ�b�����i�r�؍F���Z�E�j�ŁA��23�A�������̕��m�̖����������ꂽ�B
�@�͖���D���B
�@�����������́A�t���a�Ŏ��������Ƃ����B
�@�N��������B
�@�u��͂�u�����v�����l���͎��݂����̂��E�E�E�v���R����͈�u�ْ������B
�@�����͖쎁�̖��S�l�A�g�]�����K�ˁA���L�Ǝʐ^�̗L����₢���킹�Ă݂āA���R����͋������B
�@�u��l�͏�����납����L�͏��������A�J�����Ȃǂ͂�������Ă��炸�A�ʐ^������܂���v�Ƃ����̂��B
�@12��19���A�L�҂͖k�����ɍ���g�]�����K�ˁA�C���^�r���[�����B
�@
�@�\�\���l�̔��D�����O�A���L�����Ă���p���������Ƃ͂���܂������B
�@
�@�u����A�S������܂���v
�@
�@�\�\�펞���A���L�����Ă����Ƃ������Ƃ������Ƃ́H
�@
�@�u����܂���v
�@
�@�\�\�J�����͎����Ă��܂������B
�@
�@�u�������A����悩�����̂ł����E�E�E�E�v
�@
�@�\�\�u�싞��s�E�v�ɂ��ĕ��������Ƃ́H
�@
�@�u����܂���v
�@
�@�\�\���D���A�g�]����ȊO�̉Ƒ��̐l�ɁA�싞�����Ɋւ���ʐ^���A�����������Ă����Ƃ��A�b���Ă����Ƃ������Ƃ́H
�@
�@�u�Ȃ��ł��ˁv
�@
�@�\�\�u�����v�̒����{��x�ǒ�����A��ނ������Ƃ́H
�@
�@�u�Ȃ��v
�@
�@�g�]����́A�����V�����w�ǂ��Ă��Ȃ��B
�@�����l�ÂĂɁA�S���Ȃ�����l�̏������Ǝv������L�A�������싞��s�E�Ɋւ�����e���u�����v�Ɍf�ڂ���Ă���ƕ����Ĕ��ɃV���b�N�����B
�@�����A�L���̐M�҂傤����q�˂�l�����Ȃ��g�]����́A�킴�킴�����s�ɂ���F���t��K�˂āA�L���̐^�������B
�@����ƋF���t�́A�u���̋L���̓E�\���v�Ƃ����B
�@�u����ŏ��߂āA���S���܂����v�ƁA�g�]����́A���̎��̓��h�����l�q��������B
�@���ĘA�����\������24�����̑�\�Җ����̏،������23�A���Ɋւ������u�싞��s�E�v�͂Ȃ������A�Ƃ̌��_�ɒB�����A��������́A59�N�i1984�j9��22���A�����V���Ћ{��x�ǂɒ����x�ǒ���K�ˍR�c��\�����ꂽ�B
�@���̂悤�Ȃ��Ƃ肪���҂̊ԂŁA�s��ꂽ�B
�@
�@�A�����u23�A���͋s�E�͂���Ă��Ȃ��Ɗe���̑�\�҂��،����Ă��邪�M�Ђ��s�E���������Ɣ��f���������́A���L���ƌ�����B�e�����Ǝv����ʐ^���炩�v
�@
�@�x�ǒ��u���̒ʂ肾�v
�@
�@�A�����u�V���L���ɂ��ƁA���̓��p���L��1��1�����疈�����������A12��31���܂ŋL������Ă���Ƃ��邪�{�����v
�@
�@�x�ǒ��u���̂Ƃ��肾�B�\���̓{���{���ƂȂ��Ă���A���������͊��F�ɕς��A�C���N�̐F���ϐF���āA���a12�N�ɋL�ڂ��ꂽ���̂ɈႢ�Ȃ��Ɣ��f�����v
�@
�@�A�����u�x�ǒ��I�I����͂��������łȂ����I�I�푈�����Ă��镺���������A���L��������Ǝv���܂����B���M�����Ȃ�Ƃ������C���N�ŏ����Ă���Ƃ͋��ꂢ��B����Ȃ炢���m�炸�A�����̓y����������ɂ̓X�|�C�g�ŃC���N�r����C���N���[���˂Ȃ�Ȃ����ゾ���A���փC���N�r���g�s����Ƃ͍l�����Ȃ����Ƃ����A�܂��J�������g�s���ċs�E������B�e�����Ƃ��邪�A�_���̈ꕺ�m�������J�������w�����邱�ƂȂǎv�������Ȃ�����ŁA�܂��Ă�ꕺ�m�����փJ���������Q����ȂǂƂ�ł��Ȃ��b���B���Z�ł��J�������g�s�����҂͈�l�����Ȃ��B�x�ǒ��̃|�X�g�ɏA�C����邾���̊w������x�ǒ����A���L���L�����Ă���A���y�������Ƃ��邾���ŁA����͂����������Ǝv���A�J�����g�s�Ƃ��邾���ł�����͏L���Ƃ��l���ɂȂ�Ȃ������x�ǒ������g�̕�����قǂ��������Ǝ������͎v���̂ł����I�I�v�i�x�ǒ��@���������j
�@�����̂܂ܐȂ𗧂��A���炭���Ĉꖇ�̎ʐ^�������ĐȂɖ߂�
�@
�@�x�ǒ��u��������Ă��������v
��������Ȃ��Ƃ̑O�̘H�ʂɐ���12�]�����Ă���ʐ^�ł���B
�@
�@�A�����u���ꂪ�s�E������B�e�����Ǝv����ʐ^�ł����v
�@
�@�x�ǒ��u���̂Ƃ���ł��B�����l�̐���ł��v
�@
�@�A�����u��������Ďx�ǒ��͑����ɋs�E�ʐ^�Ǝv��ꂽ�̂ł����v
�@
�@�x�ǒ��u���̂Ƃ���ł��v
�@
�@�A�����u���������ł��ˁ[�B���]�����Ă��邾���ł́A���m�Ȃ̂���ʐl�Ȃ̂���������Ȃ��B
�@�X�p�C��߂炦�Ď���͂˂��̂�������Ȃ��B
�@����Ȃ�s�E�ł͂���܂���ˁ[�B����������Ȃ�A�����̕������ّ��������s�����ۂɑł���ɂȂ����ّ��̎�����܂���B
�@���͌����B���̐V���ɂ������Ƃ�����܂��B
�@���̐܂ɖ��B���R���ّ��������s���A�ّ���ł���ɂ����ʐ^��������ꂽ���Ƃ�����܂����A���̎��̎ʐ^�ɂ��̎ʐ^�͎��ɂ悭���Ă��܂��B
�@�x�ǒ��͂������ڌ��������ŁA�悭�܂����{�R�������l���s�E�����ʐ^���Ɣ��f����܂����ł��ˁB���̍����́I�I�v
�@�x�ǒ��u���̎ʐ^�������Ă����l���A���̎ʐ^�����Ȃ��������Ă����Ƃ������Ƃ��Ă��܂�������A�e�b�L���s�E�̌���ʐ^���Ɓv
�@
�@�A�����u���������̐l��10�N�O�Ɋ��Ɏ���ł����ł��傤�v
�@
�@�x�ǒ��u�����ł��v
�@
�@�A�����u����ł͒��ږ{�l���畷���ꂽ�킯�łȂ��A���̉Ƒ��̕��̘b�ł͂���܂��I�I�M�p�ł��܂����v
�A����A�S���łŕ���23�A���͓싞��s�E�ɖ��W�Ƃ̋L�����o���Ăق����A�Ɨv�������̂ɑ��A�����x�ǒ��́u���炭�҂��Ăق����v�Ɠ������B
�@�����āA���N��60�i1985�j�N2��4���A�Ăщ�k�������ꂽ�̂ł������B
�@
�@�A�����u�����͐���Ƃ���������23�A���͓싞��s�E�Ƃ͖��W�Ƃ̋L�����f�ڂ��Ă������������Ǝv���Q�サ�܂����v
�@
�@�x�ǒ��u��ʗ�������L���{���̃|�C���g���Ƃ��w�E�ɂȂ��Ă����邩�獡���͂��̓��L�����ڂɂ����܂��v
�����x�ǒ��́A����̒I����i�C�����̑܂ɂ��ꂽ���L���炵�����̂���Ɏ��A����̑�\�҂̂���e�[�u������5�`6���[�g�����ꂽ�Ƃ���ɗ������܂܃i�C�����̑܂��炻�̓��L���炵�����̂���������o���āA�����̋��̍����̂Ƃ���ŁA���L���ʂ̐^���炢���L���Č������B�A����̖�����1�l�A�㓡�c���������A�������獘�����ė����オ��A�߂Â����Ƃ����
�@
�@�x�ǒ��u�ߊ���Ă͂����܂���B���̂�������Ƃ��ꂪ��������������܂�����v
�@
�@�A�����u���̓��L���������Ă������m��10�N�O�ɐt���a�Ŏ��S�����Ƃ̂��ƂŁA�����̌��ʂ͉͖���D���Ɣ������܂����B�������S�l�͖̉�g�]����ɐq�˂܂����Ƃ���A����Ȃ��̎����Ă��܂���Ƃ̉܂�������x�ǂƉ͖삳��ƑΌ����Ă��������܂��v
�@
�@�x�ǒ��u����A���̐l�łȂ��A���L�͕ʂ̐l����͂���ꂽ���̂ł��v
�@�R�c����20�����2��24���t�A�����V���{��łɁA�����ȃx�^�L�����̂����B�u�w�싞��s�E�Ɩ��W�x�^���s��23�A���̊W�҂��\���v�Ƃ����L���ł���B
�@�����A�ŋ߂ɂȂ��Č��O�̘A��������������L�����S���łɂ̂��Ă��Ȃ����Ƃ�m�������R�����ǒ����A�����x�ǒ��ɒ����L���f�ڂ�\�����ꂽ�Ƃ���A���x�ǒ��́u2��24���t�̋L���͒����ł͂Ȃ��B�L���͑S���������v�Ɣ��_�������ƂŁA���҂̑Η��͈ꋓ�ɃG�X�J���[�g�����B
�@�L�҂́A60�i1985�j�N12��20���A�{��x�ǂŒ����x�ǒ��ɉ�A�C���^�r���[���s�����B
�@
�@�\�\�u�����v�ŕ������L�̕M�҂́A�͖̉쎁�ȊO�ɊY���҂͂��Ȃ��Ǝv���邪�ǂ����B�{���ɂ��̐l���͓s��23�A���̌����m���B
�@
�@�u���L�̎�����͂܂�����Ȃ���23�A���̕��̂��̂��B���̕��͖k�����ŏ��a49�i1974�j�N�ɐt���a�Ŏ������Ă���B�͖쎁�ȊO�ɊY���҂�����B�����Ƃ�����̎������Ⴄ�̂��낤�B�A����̒����s���łȂ����v
�@
�@�\�\�ł́A���a59�i1984�j�N8��4���[���̋L���ɂ͈�̃t�B�N�V�����A�f�b�`�����͂Ȃ��Ƃ����킯���B
�@
�@�u�S���Ȃ��B���̋L���͂��ׂĐ������B���a60�i1985�j�N2��24���̋{��łɂ̂����L���́A�����L���ł͂Ȃ��B�A����̕�����R�c���������������f�ڂ����܂ł��v
�@
�@�\�\��ނ̑����A�菇�͏\���ɂӂ̂��B�L���������܂łɁA�Г��ł��\���Ɍ��������̂��B
�@
�@�u�싞�s�E�ɂ��ẮA�����{�ЁA�܂������{�ЂȂǂł����̖�����ɂ��Ă���L�҂��A�{�����ꎁ���͂��߂��Ȃ肢��B�L���f�ڂɂ������ẮA�����������L�҂Ƃ����k���A�\���Ɏ����������킹�ď������B�t�B�N�V������f�b�`����������Ƃ����̂ł���A�_���I�ɏ��ȂŎw�E���Ă���������A�����̂��������邱�Ƃɂ�Ԃ����ł͂Ȃ��v
�@
�@�\�\���L�̐M�҂傤���ɂ��ẮA�R�����g�����Ă�����s��̍L�쏕�����̑��ɁA���ڌ����Ċm�F���������B
�@
�@�u�{�B�ɏZ�ނ��鋳���Ɍ����Ă�������B���̐l�̖��́A����̗�������Γ����Ă��悢�v
�@
�@�\�\���L�͌��݁A�ǂ��Ȃ��Ă���̂��B
�@
�@�u���L�͈⑰�ɕԂ����B�����ɂ̓R�s�[������B�⑰�����O�̌��\�����ۂ���Ă���ȏ�A���J�͂ł��Ȃ��B���Ƃ��Ă��̂��ăj���[�X�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v
�@
�@�����̃x�e�����L�҂ł��钆���x�ǒ����A�L���̐^�������������A�t�Ɂu�A����̕��̒����s���v�Ƃ܂Ō����������Ƃɂ́A���������������o�����B
�@�ނ������悤�ɁA�͖쎁�ȊO�ɏ��a49�i1974�j�N�ɐt���a�Ŏ������������m���k�����ɂ���̂��B�A����̒����͏\���ł��������B
�@������S���������R�����ǒ���́A�k������3�̎��ɂ������ߋ����ɂ������āA�͖쎁�ȊO�ɊY���҂͂��Ȃ������Ɣ��f�����B���A�ߋ����ɂ̂�Ȃ������l������̂ł͂Ȃ����B
�@�͖쎁�̖��O�����������b�����̍r�؏Z�E�́A�u�������A�@�����Ⴆ�Ήߋ����ɖ��O�͂̂�܂����v�Ƃ����B
�@�Ȃ�ΘA����̒����͊����Ƃ͌����Ȃ��B
�@�A����̋��͂āA�{�茧�����s����23�A���̕�������ɍڂ��Ă����k�����o�g��23���̓�����ǂ����B
�@���̌��ʁA23���̂������S�����������̂�10�l�B����͐펀��2�l�B�c��8�l�͏��a27�i1952�j�N�A34�i1959�j�N�A48�i1973�j�N�A49�i1974�j�N�A54�i1979�j�N�A58�i1983�j�N�A59�i1984�j�N�A60�i1958�j�N�Ɉ�l���������Ă���B
�@��͂菺�a49�i1974�j�N�ɐt���a�ŖS���Ȃ����A�Ɓu�����v�����l���́A���N9��25���Ɏ��������͖���D���̑��ɂ͑��݂��Ȃ��B
�@�������A���̌�̘A����̒��ׂʼn͖쎁���싞���������͂܂����W�i���傤���イ�j���ꂸ�ɓ��n�ɂ����Ƃ����̂ł���B
�@�u�����v�̋L���͌���I�ɖ������Ă���B
�@���U�̓��e���`�����Ă���B�����I�ɔ��f���ď����ꂽ�̂��A���a60�i1985�j�N12��27���t�A�{����ʃg�b�v�L���ł���B
�@�u�싞�����̓��L�����^�����x�ǒ����g���쎩���h�^���M�ґ��݂����^��F������������v�Ƃ̌��o���ŁA���̂悤�ȃ��[�h�ŕ��̂ł���B
�@�����푈���̏��a12�N���A���{�R���싞���̂����ۂɁA�u�싞��s�E�v���s��ꂽ�Ɛ��A�������Ă��钩���V���́A���a59�N8�����߂ɂ��A�싞�ɓ��邵�����m���c�������L�Ǝʐ^��������A�u�����ʑ�ʎE�l�����j�I�����v�Ƒ�X�I�ɕ����A���̌�̊W�҂̒����ŁA���ꂪ�S���̃f�^�����Łu�����v�L�҂ɂ��˂��ł��邱�Ƃ����������B
�@���L�҂́A�L���̐M�҂傤�������߂邽�߂ɁA�s�E�̗l�q���畺�m�̋�Y�A�Ɛl�̒k�b�܂ł����ɂ�����炵���`�ʂ��A�ǎ҂̃R�����g�܂ł̂���ȂNjɂ߂čI���ň����Ȃ��������Ă����B
�@�����V�������Ӎ߁A�����L���̌f�ڂ����ۂ������Ă��邱�Ƃɑ��āA�W�҂͍��i���܂߂āA�Ή����������Ă���B
�@�u�����v�L�҂͍ŋ߂ł��A�c�����̂ĂĖ������ŒE�o�������u�o�҂���v�Ƃ킢�Ȃ�����A���q���������u���O�Ȃǔ���̂͊ȒP�v�ȂǂƂǂ�������Ȃǂ��ĎЉ��艻�������A����́u�˂��v���A�W���[�i���X�g�̘_�����犮�S�Ɉ�E�����g�ƍߓI�s�ׁh�Ƃ��āA�g����Ăڂ��B
�^���͖��B�ŏ��Y���ꂽ�n���̎ʐ^
 �@���́A�����܂ő�_�ɕ邱�Ƃ��ł����w�i�ɂ́A���̎�ނ̓r���Łu�����v�ɍڂ��Ă���ʐ^�̈ꖇ���������o�ŕ��̈ꖇ�Ɠ���ł���A����͓싞�Ƃ͑S���ʂ̒n��̎ʐ^�ł���A�Ƃ������Ă�������ł���B
�@���́A�����܂ő�_�ɕ邱�Ƃ��ł����w�i�ɂ́A���̎�ނ̓r���Łu�����v�ɍڂ��Ă���ʐ^�̈ꖇ���������o�ŕ��̈ꖇ�Ɠ���ł���A����͓싞�Ƃ͑S���ʂ̒n��̎ʐ^�ł���A�Ƃ������Ă�������ł���B
�@�����28���t�{���͓�������ʃg�b�v�ŁA�u�����A���x�͎ʐ^���p�^�싞�s�E�������˂��^�����̏o�ŕ��ɍ����^��w�u�t���w�E�v�ƕ��B
�@�L���̖{��͎��̒ʂ�ł���B
�@���̎ʐ^�́A�����V�����{�Дł̏��a59�i1984�j�N8��4���t�[���A��2�Љ�ʃg�b�v�ŁA�g�ߎS���ʂ���3���h�Ƃ��āA���L�̉��ɕ��ׂ�ꂽ3���̂����̈ꖇ�B
�@���L���������������x�ǒ��́u���h�������ŁA�ꖇ�͐l�ƂƎv���錚���̒��ŁA12�l�̐��]�����Ă���A���̒����ɂ͏����炵�����������v�u�B�e�ꏊ�͓싞������ǂ����L����Ă��Ȃ����A���O�Ƒ��Ɂw�싞�s�E�̍ۂ̎ʐ^�x�ƂЂ����Ɍ���Ă����Ƃ����v�ƋL���̒��Ő������Ă���B
�@���̓��L�Ǝʐ^�̎����傪���݂��Ȃ����ƂŁA���̏o�ǂ��낪�^�⎋����Ă������A�u�g�싞�s�E�h�̋��\�v�̒��҂ő�B��w�u�t�A�c���������͒����̐V�؏o�ŎД��s�́u���{�N�ؐ}�Ўj���W�v90�y�[�W�̎ʐ^�̂�����1���A�Ǝw�E����B
�@�c�����́A�u�����V���L���̎ʐ^���g�僌���Y�Ō���ƁA���������Ă���l�q�△�O�����ȕ\��A��ЂƂ̎�̒u����Ă���ʒu�W�܂ŋɂ߂ėގ����Ă���A����100�p�[�Z���g�ԈႢ�Ȃ��Ɗm�M����B�ƌ���Ă���B
�@�u���{�N�ؐ}�Ўj���W�v��90�y�[�W�̎ʐ^�ɂ́u���������큛�j�����E�V�S��B�\�\�ю���C���ؔ��ؐ}�����v�Ƃ���A�܂�ɔJ�ȗɌ��ŎE���ꂽ�j�����E�̎S��A�Ƃ̎ʐ^�����������Ă���B
�@�ɔJ�Ȃ͋����B�̔M�͏Ȃɑ�������n��œ싞�Ƃ͖��炩�ɈႤ�B
�@�܂����l���A���A����ɂ���ĎE���ꂽ���͑S��������Ȃ��B
�@���L�Ǝʐ^�̎����傪�{��̌��s��23�A���̕��m�ƁA�����V���͕����A���A���̐����҂Ō�������s��23�A����̎����ǒ��A���R�L�ǎ��́u�ʐ^�͓���̂��̂Ɗm�M����B
�@�����V���́g�싞�s�E�h�����������Ƃ����o�ɑi���Ċm��I�ɂ��悤�Ƃ����Ӑ}�I�Ȉ������s�������̂ƍl���Ă���v�ƁA�����V���̕��������ᔻ���Ă���B
�@���̖��ɂ��āA�����x�ǒ��́A�u�����_�ł́A�����������Ȃ��v�ƌ��t��������B
�@�����V���͏��a60�N6��23���t�[���ł��A���a12�i1937�j�N12��11���A��ԕ��Ƃ��āA�싞�x�O�̉J�ԑ�Ŕ������f���ė��钆���l�����X�ɋs�E���Ă����ʂ�4���Ԃɂ킽���ċÎ������A�Ƃ��������E�]�ː��̒��R�d�v���́g�s�E�،��h���Љ�Ă��邪�A���̌�̓싞��Q���҂̒����ŁA���R���̏��������⒇��ԑ��͉J�ԑ�ɂ͓˓����Ă͂��炸�A���R���̏،����S���̋��\�ł��������Ƃ��������Ă���B
�@�����V�����A���̂悤�ɃE�\�̏،���؋��܂ŏW�߂āg�싞��s�E�h�����������Ƃ����Ƃ���ɋ������闝�R�ɂ��āA�c���������́A�u�����V��������قǂ܂łɂ��ċ����{�R���g�s�E�h��g�ƍ߁h���s���Ă����ƈ�ۂÂ��悤�Ƃ���_���́A�����̓��{�R�����Ă����Ƃ���̓V�c�É��̐푈�ӔC����������A�����������͋C������Ƃ���ɂ���̂ł͂Ȃ����v�Ǝw�E���Ă���B
�@�{���̕����������ɁA�u�T���V���v�̋L�҂��A�{��ɔ��ōs�����B�����x�ǒ��́A�j�Z�ʐ^�̌��ɂ��Đq�˂���ƁA�u�����̎ʐ^�W�̕��������̋L������Ɋ��s���ꂽ�B���������Ԉ���Ă���̂�������Ȃ��v�Ɣ��_�A�����܂Ŏ��Ȃ͐̕������Ƃ̎p�����т����̂ł������B
�@�����A���U�͉i���͑����Ȃ������B
�@���̎ʐ^�Ɠ���̂��̂����a6�i1931�j�N�A�����̒��N�Ŕ����Ă������Ƃ������푈�ɎQ�킵�������m�̏،��Ŗ��炩�ɂȂ����̂ł���B
�@�{�����a61�i1986�j�N1��13���t����ʃg�b�v�́A�u�����̓싞�s�E�j�Z�ʐ^�^�����ȑO����s�́^�����{�����w���E�ۊǁ^�������Ɂw�S��ŏe�E�x�^�����̏o�ŕ�����p�v�Ƃ̌��o���ŁA���̂悤�ɕ��B
 |
| ���݂̖k���N�A��J�Ŕ������u�n���̎�v�̎ʐ^����ɂ��鍲���i�������a61�i1986�j�N1��12���ߌ�A����s�̎���Łi��ʐ^�j |
�@���̎ʐ^�̎�����́A�_�ސ쌧����s�V�_���ɏZ�ތ��z�ƁA�����i���i74�j�B
�@�������͏��a6�i1931�j�N10���A�����̒��N�ƒ����̍����Ɉʒu�����J�̍H��19����ɓ������A����75�A���ƂƂ��ɍ����x���ɂ��������B
�@�������ɂ��A���N�����痂�N�ɂ����āA���̉�J�ɂ��镶�[��ʐ^���ŁA��10���������ʐ^��1�����A�u�����V���v���a59�i1984�j�N8��4���t�[���́g�싞��s�E�h�ɗp����ꂽ�ʐ^�̈ꖇ�Ɠ������̂Ƃ����B�����Ń^�e9.7�Z���`�A���R13.5�Z���`�̑傫���ł���B
�@�������́u�ʐ^�͂�������1��5�K�������B������ƕς���Ă���ʐ^�������̂Ŕ������B
�@���N�z�̕������ԂȂ炱�̎ʐ^�������Ă���l������ł��傤�v�ƌ��B�ʐ^�̏㕔�ɂ́A�u�S��j�e�e�E�Z���n���m��v�Ƃ̕��������荞�܂�Ă���B
�@�S��Ƃ́A�ɔJ�ȓ����c�z�ׂ̗̓s�s�B
�@�������́A�u�ʐ^�̎B�e�͏��a4�A5�i1929-30�j�N�̍����Ǝv���邪�A�����̒������k�n���͒��w�ǂ��������Ă����B�ނ�̔z���̎҂������l�ّ̔��i�Ђ����j����ʐl�ւ̌������߂Ƃ��Đ������̂ƍl������B
�@���藎�Ƃ���̂͒����l�̎����Ă��������ł���A���{�̕����̎����Ă���e���ł͖����ł��v�Ƃ����B
�@�܂��������͓��x���ς̂ڂ����ŁA���W����A�H��13�A���̕��m�Ƃ��Ē����̍]���A�싞�A�֏�A���B�A�����A�鏹�Ȃǂ���������A�u���鎞�ɂ͂��łɓG���͓����Ă��Ȃ��B�Z�����킸���ɘV�l�������c���Ă���̂݁B
�@�ߗ����ʂɋs�E���邱�ƂȂł��Ȃ��B
�@�����V���͌���������Ă������������v�Ɨv�]����B
�@�����V���̒����x�ǒ��i�����j�͂��̎ʐ^�ɂ��āu���h���v�̑傫���ƋL���ŏ����Ă��邱�Ƃ���A�k�������ʐ^����肵�����̂Ǝv����B
�@���������x�ǒ��͏\���ȋᖡ���s�킸�ɁA�g�싞��s�E�̏؋��ʐ^�h�ƌ��߂��Ĉ��p�A�u�B�e�ꏊ�͓싞������ǂ����L����Ă��Ȃ����A���O�Ƒ��Ɂu�싞�s�E�̍ۂ̎ʐ^�v�ƂЂ����Ɍ���Ă����Ƃ����v�ƁA����߂čI���ȕ\����p���ēǎ҂��\�i�����ށj���Ă���B
�@����ɂ��̎ʐ^�͒����̐V�؏o�ŎЂ��u���{�N�ؐ}�Ўj���W�v��90�y�[�W�Ɍf�ځA�u�ɔJ�ȗ����ŎE���ꂽ�j�����E�̎S��v�Ƃ̎ʐ^���������A����ėp���Ă���B
�@�����ɂ͍���������J�Ŕ������A�n���̎�̎ʐ^���f�ڂ���Ă��邪�A������܂��u���{�N���R�͂킪���̐l�����E�������ƁA���̎��d���ɂԂ牺�����v�ʐ^�Ƃ��ėp����ȂǑS���m��i������j�ȕҏW���e�ł��邱�Ƃ����������B
 |
| �ʐ^���ɂ���u�n���̎�v�ʐ^���g�債�����́B�u�S��j�e�e�E�Z���n���m��v�Ə�����Ă���B |
�@�����x�ǒ��́A���L�Ǝʐ^�̎����傪���s��23�A���̕��m�ƕ����A���A���̐����҂ō\������s��23�A���̎����ǒ��A���R�L�ǎ��́u���̎ʐ^�͏��a16�i1941�j�N�A�����̐V���i���݂̒��t�j�œ������̎O�D�G�g�����̕��ɂŌ������̂Ɠ����ł���A���Ȃ�L�͈͂ɏo����Ă����Ǝv����B�L���̃f�^�����Ԃ肪����Ɉ�w���炩�ɂȂ����ȏ�A�����V���ɑ��Ă͂ǂ����Ă��Ӎ߂ƋL���̎����������߂�l���ł���v�ƁA�Ό��p�������߂Ă���B
�@���łɁu�싞�s�E�v�L���̓f�^�����ƕāA���̎��_��2�T�Ԃ��߂��Ă����B
�@�����V���Ђ���A�킪�Ђɑ���R�c�͈�x���Ȃ��A�u����̋s�E��F�߂����̂ƍl������v�Ƃ��������B
�@�������A���ʉ��ł́A�����V���Ђ͐ϋɓI�ɓ����Ă����̂ł���B
�@�����V�������{�Ђ̋{�{���́E�ʐM���������ĎO�ɂ킽���āA�A����̒��R�����ǒ��ɐڐG���͂��낤�Ɩʉ�̐\�����݂��s���Ă����B
�@��̓���s�ɏZ�ލ����i����ɂ��A�{���̋L�����ڂ���13����2�x���A�����V���Љ�̏����L�҂��A�u�ʐ^�������ė~�����v�Ɠd�b�����Ă��Ă���B
�@����́A�Ƃ��ɒf���Ă���̂ł��邪�B
�@�����V���{�Ђ͂͂����āA����̋s�E�ɂ��āA�{���̕�َE����ԓx�Ȃ̂ł��낤���B
�@���_�ł��Ȃ��̂��B�Ԉ���Ă���Ȃ�A���̔��F�߂�ׂ��ł͂Ȃ����B
��p�F�ߑS���łŁu����ыL���v
�@���̂�������ǂ����Ă������Ă݂����ƁA1��16���ߌ�A�����V�������{�Ђ̍L��S���A�R���j���ɕ����Ă݂��B���̎��A�R���͕s�݂ŁA������͖���`����݂̂ŁA�p���܂ł͌��Ȃ������B
�@�������A�[���A�鏑����d�b������A�u�����A�ߌ�2���ɖ{�Ђł���������Ƃ̂��Ƃł��v�Ƃ̕Ԏ����������B
�@�R���͂��łɁA������̗p�����@�m���Ă����̂ł��낤�B
�@��17���ߌ�A�����V���������ɐR����K�˂�ƁA�ނ͂����ނ�ɁA�u�����炪���₷�邱�ƂɁA��������������`�Ői�߂܂��傤�v�Ɛ�o�����B���łɁA�����V���̑ԓx�͌ł܂��Ă���ȁA�Ɗ������B�p�ӂ���������A���Ԃɍs�����B
�@�\�\�{��O�x�ǒ��̒������́A�u���E����v�̋L������Ȃ�����A�̐S�̓��L�A�ʐ^�̐M�҂傤���ɂ��Ă͉��������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@�����u�����̍L��ɕ����Ă���v�ƌ����Ă���B
�@���łɔ����������A�������Ȃ��ꂽ�Ǝv���̂Ō��ʂ������B
�@�u�L���̍Ē������s�����B��i���a59�i1984�j�N8��4���t�L���j�̎�ނɃ^�b�`���Ă��Ȃ��킪�Ђ̎҂��S�����A���L�̕M�҂̊W�ҁA�⑰�ɂ��������B
�@�ڍׂ��T�d�ɒ��������B
�@�ʐ^�ɂ��ẮA�����V���k���x�ǂɒ����˗��������B
�@���̌��ʂ͂܂��A���L�ɂ��Ă͊ԈႢ�����������Ă���B
�@����͂킪�Ђŕۊǂ��Ă���B
�@�������A�ʐ^�ɂ��Ă͓싞�̂��̂ł͂Ȃ��B
�@16���A�k���x�ǂ��Ԏ����������B
�@�{���ŕ���3���̎ʐ^����������A���A��C�Ŕ��s���ꂽ�w���k���ό������j�x�Ɏ��^����Ă����B
�@�B�e�̌����A�B�e�҂͂킩��Ȃ��������A�ꏊ�͓��k�n���̗����ƂȂ��Ă���B
�@���̂��ߋ߂��A�w�S���Łx�ŁA�ʐ^����юʐ^�Ɋւ���L�q�ɂ��Ă͂���т��A�������v
�@
�@�\�\�Ȃ��A���̂悤�ȊԈႢ���N�����̂��B
�@
�@�u�S���L�ҁi�������j���A�ʐ^�҂��A�����w�ʐ^�͓����̂��́x�Ƃ����킩��Ȃ��̂ɁA�싞�s�E�̂��̂ƌ��ߕt�����悤���B��ނ̃��L���Â������v
�@
�@�\�\���̂悤�Ȗ��̎ʐ^�ƈꏏ�ɂ��������L���ԈႢ�����A�������ƌ�����̂��B
�@
�@�u���L�Ɋւ���L�q�͑S�Đ������v
�@���������āA�R���́u�����V���v�ŕ��S�E�̂�����̕������R�s�[�ŋL�҂Ɏ������B
�@���L�ɂ͌l�̖��O���L����Ă���A���ꂪ�킩��Ɠ��L�̕M�҂��킩���Ă��܂��A��ތ���铽�ł��Ȃ��Ȃ�A�Ƃ����B
�@�R���Ƃ̃C���^�r���[��1���ԂقǂŏI������B
�@18���t�{���́A���̓��e���u�����A��p�F�߂�^�싞�s�E�j�Z�ʐ^�^�S���łŋ߂������v�Ƃ̌��o���ŕ��B
�@���̋L���ł͐[���ӂ�Ȃ��������A�j�Z�ʐ^�������ł͂��邪�A����ȏ�ɍI���Ń^�`�������̂��A�ʐ^�Ɋւ��邭����ł���B
�@�u�B�e�ꏊ�͓싞������ǂ����L����Ă��Ȃ����A���O�Ƒ��Ɂw�싞�s�E�̍ۂ̎ʐ^�x�ƂЂ����Ɍ���Ă����Ƃ����v
�@�u�Ƒ��̘b�ł́A���O�ʐ^�����Ă͎v���Y��ł��鎞���������Ƃ����B
�@�Ƒ��́w���s�Ŏ蒠�����������̂��V���̕Œm��𗧂ĂƎv�����B
�@��x�Ɛ푈�͋N�����Ăق����Ȃ��x�Ƙb���Ă���v
�@���ǁA���̕����͑S���́g���쎩���h�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����B
�@���L�Ǝʐ^�̒҂����݂��Ă��Ă��A���̐l���͎ʐ^���A�싞�U���̂��̂ł���Ƃ͎v���Ă��Ȃ������B
�@���̂悤�Ȑl���A�u�싞��s�E�v�����̖͗l�������ɋL�^�������{���m�̎蒠�����s�Ō��������A�Ƃ����j���[�X��7��28���t�u�����V���v�Ɍf�ڂ�����A�������Ă�ꂽ���̂悤�ɁA�u���ɗ��Ăv�ƁA�����x�ǒ��Ɏ����Ă����Ƃ����̂��B
�@�蒠�����̕�7��28���t�ŁA�����x�ǒ��̋L����8��4���[���B���̊ԁA7���Ԃ����Ȃ��B
�@�킸��1�T�ԂŁA���L���܂�����Ȃ����a12�N�����ɁA�싞�U����ɎQ�킵�����m�̂��̂ɊԈႢ�Ȃ��Ɣ��f�A���ƂɌ��Ă��炢�A�R�����g���Ƃ����Ƃ����킯�ɂȂ邪�A�ǂ����A�b�����u���܂�����v�C�����ĂȂ�Ȃ��B
�@���āA�u�����v�A��p�F�߂�v�Ƃ̖{���̋L�����f�ڂ��ꂽ18���ߌ�2��������A�{��s���̒��ؗ������u�l�C�O�v�ł́A�s��23�A����̑�c�����J����Ă���B
�@�`���A�������ɗ��������y��́u�����V���v�́g�싞�s�E�h�ɂӂ�āA�u�O��I�ɋ������Ă��������v�ƌ��ӂ��q�ׂ��B
�@���R�L�ǎ����ǒ��̌o�ߕ��s��ꂽ��A�����V���Ђɑ���Ӎ߁A�L���������v���̌��ɂ��ċ��c�B���̌��ʁA�u�g�싞�s�E�h�̓��L�Ǝʐ^�͌��ł���܂����̂ŁA23�A���̖��_�����������Ƃ�[������т��A�L���������s���A23�A���́g�싞�s�E�h�ɖ��W�Ȃ��Ƃ����m�点���܂��v�Ƃ̓��e�̎ӍߋL�����A1�����ɁA�����V���́u�S���Łv�u�n���Łv�ɂ��̂��̕����̂Ɠ����傫���Ōf�ڂ��邱�Ƃ��v�Ō��c�����B
�@�����Ă����A�����V���Б������̗v��������Ȃ����
�@(1)�{�茧���ł̒����V���s���^�����N����
�@(2)������@�ւɂ��̖��ɂ��ăA�s�[�����Ă���
�@(3)���i�ɓ��ݐ�\��3�_�����߂��̂ł������B
�@���̓��̌��c���āA���a61�i1986�j�N1��21���t�œs��23�A�����A���y�G�Y���Ǝ����ǒ��A���R�L�ǎ��̘A���ŁA���e�ؖ��A�z�B�ؖ��Œ����V���Г����{�Ђ̈������Y�В��ɂ��Ă�ꂽ�u�L������ƎӍ߂Ɋւ��錏�v�̓��e�͎��̂悤�Ȃ��̂ł������i�����̂܂܁j�B
| �@�q�[�@�ҁi�̂Ԃ�j���a�\��N�����l���A�ܓ��M���n���ŁE�S���łɂČ��������\�O�A�����싞�ɉ����ċs�E���s��������Ԃ������L�ƛ��^�����t����e�p�i�Ƃ����j���̗L�����_�c����Ă���싞��s�E�͐��i�܂��j�������݂����������j�I�����ł���Ƃ��߂���ꂽ�B �@���������\�O�A���̐����Җ��疼�Ō������ꂽ�s���\�O�A����ɂƂ��Ă͑S���g�Ɋo���̂Ȃ��G��߂ł��葁���A������\�������\�l�̕����ɖȖ��Ȃ钲���𖽂����Ƃ���E�͑S�����������̋��U�̕ł��邱�Ƃ����������B �@�ˁi����āj�����a�Z�\�N���������������čR�c�A�E�R�c�͎�����ē��N��\�l���̋M���n���łɌ��������\�O�A���͓싞��s�E�Ƃ͖��W�̎|����{���͂���ɂďI���������Ɍ������B �@�R�鏈�A���O�ݏZ�̐�F���S���ł̉��������Ɍf�ڂ��ꂽ���̖⍇��������A�ׂɓ��N�\��\���A�M�Ћ{��x�ǂɏo�����Đq�˂����A�ӊO�ɂ��S���łɌf�ڂ̖Ȃ��Ɣ������ꂽ�w�M�s�ׂɓ��{���\����ꗬ�V���ЂȂ邪�̂ɓ{�����X�Ɋo�����i�����j�ɉ��߂č��L�Ɉ˂�L������ƎӍ߂�v�����鎟��ł���B�@�@�h�� �@ �@�@�@�L �@��A�L������ƎӍ߂͏��a�Z�\��N�ꌎ�����܂łɋM���S���ŁA�n���łɌf�ڂ��邱�� �@��A�싞��s�E�ƌ��������\�O�A���Ƃ͖��W�̎|��\�����邱�� �@��A����̌��Ɉ˂�{�茧�����тɌ��������\�O�A�������Ē����V���Ђɖ��f���������S���L�҂̐ӔC��Njy���ꂽ������ �@��A�O���ɂ����ۂ��ꂽ��ꍇ�͋{�茧����ۂƂȂ肱�̋M���s���^����W�J����Ƌ��ɌY�@230���Ɋ�Â����i�����鎖��O�ׂ̈ɐ\���Y���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȏ�@�i���r�́A���E����Ђ��L���j |
�@���̘A����̍R�c�����t�Ɉ���x��āA�����V���Ђ�22���t�����̑S���łŁu����ыL���v���o�����B��\�O���t�{���́A�u�w�����x�Ӎߔ[���ł��ʁ^�g�싞�s�E�h�^��F��L���������v���^�w���L�̌���������x�v�Ƃ̌������ŁA���̂悤�ɕ��B
�@�u����ыL���́A�����x�ǒ��́g�싞�s�E�h�L�����Ē����������ʁA�u���L�͌������܂����A�L���ŐG��Ă���ʐ^3���ɂ��Ă͓싞���������̂��̂ł͂Ȃ����Ƃ��킩��܂����B�L���̂����A�ʐ^�Ɋւ���L�q�́A����т��Ď������܂��v�Ƃ������e�B
�@���Ɏʐ^3���Ɠ��L�̎ʐ^���f�ڂ����u���Łv�ł́A����ɉ����āA�u�ʐ^�̂����ɏ��a9�N1���A��C���v���p�}�����i���甭�s���ꂽ�w���k���ό������j�x�Ɏ��^���ꂽ���̂�����A�B�e�ꏊ�͒������k�n���̗����Ƃ��Ă���v�Ƃ�����������������Ƃ����A�ٗ�̈����ŏo�����B
�^��c��u�ʐ^�̓E�\�������L�̓z���g�v�̕�
�@�����A���L�̎�����̏������Ă����s��23�A���̐����҂ō\������A����i���y�G�Y��j�͒����V���Ђɑ��āA
�@(1)�싞��s�E�ƁA23�A���Ƃ͖��W�Ƃ̕\��
�@(2)23�A������ы{�茧���̖��_�������ꂽ���Ƃւ̎Ӎ�
�@(3)�S���L�҂̐ӔC�Njy
�@�\�\����v���A���������Ȃ��ꍇ�́A�{�茧���ł̒����V���s���^���ƍ��i�ɑi����A�Ƃ��Ă���B
�@�A����̈��y��́A����ыL���ɂ��āu����ł͎q�����܂��ł͂Ȃ����B�g����сh�Ƃ͍l���Ă��Ȃ��B�������́A�ʐ^�������L�ɂ��ĎӍ߂����Ăق����B�������̍R�c�ɂ������x�ǒ��͐����[�g������Ă��������Ă���Ȃ������B����ȓ��L���{���ƌ����Ă��ƂĂ��[���ł��Ȃ��v�ƌ����B
�@�����ǒ��̒��R�L�ǎ����܂��u���L�̌��{���V�����ۊǂ��Ă��邩��ɂ́A��������Ȃ��ȏ�A�[�����Ȃ��v�Ƃ����܂Ő^������������p��������Ă��Ȃ��B
�@���R�����ǒ��̘b�ɂ��A�����V�������{�Ђ̋{�{�ʐM����������A21���[�A22�����2�x�A�u����ыL���v�̓��e�ɂ��Ē��R���ɓd�b�Ő������A�u����ł���ׂĂق����v�Ɠ`���Ă������A���R���́u���m�ł��Ȃ��v�Ɠ˂��ς˂��Ƃ����B
�@�����{�Ђ̍L��S���A�R���j���́A���L�̌��{�������{�Ђɕۊǂ���Ă���Əq�ׂĂ���A�A����ł͂�������Ĕ[���̂����Ȃ�����A�����V���ւ̍R�c�́A���������Ȃ��A�Ƃ��Ă���B
�@1��25���ߌ�A�s��23�A���������͒����V���{��x�ǂŒ����V�������{�ВʐM���������4���ԋ߂���k�����B
�@��k�ɂ́A�A������璆�R�L�ǁE�����ǒ����͂��ߖ���5�l���o�ȁA�������͐����{�Ђ̋{�{���́A��_�����ʐM�������Ƌ��ې��E�{��x�ǒ����o�Ȃ����B
�@�ȏ�A�{�{�����͘A���21���ɓ��e�ؖ��ő��t�����������Y�����{�ЎВ����Ă̍R�c���ɂ��ĐG��A�u�����̌��ʁA�����́w����ыL���x�ȏ�̗v���ɂ͒����Ƃ��Ă͉����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�u���L�Ɋւ��Ď��������̋��U�ł���ƍR�c����Ă��邪�A���ǂ��Ɍ��킹��Ƌt�Ɏ��������̍R�c�ł���v�Ɠ˂��ς˂��B
�@����ɑ��ĘA����́A�����{�Дł́u����ыL���v�ɂ������A�u���̓��L�́A�싞�ɓ��邵���{�茧�o�g�̕��m�i�����㓙���E�̐l�j�̐�L�ŁA�Ȃ��ɋs�E�̗l�q��S����Â��Ă��܂��v�Ƃ���������Ɍ��y�A�u����сv�ɖ�������ċt�ɓ싞�s�E���`����L���ɂȂ��Ă��Ĕ[���ł��Ȃ��A�Ɣ��_�����B
�@�����āA�A����͎ʐ^�̌��ȏ�ɁA�u�싞�s�E��23�A���͖��W�ł��邱�Ƃ�S���łŕ\�����Ăق����v�Ɨv�������B
�@�������́A�u����23�A���̕��m�̓��L�ɋs�E�̋L�q������ƋL�ڂ��������ŁA23�A�����싞�s�E��������Ƃ��s�E�Ɏ���������Ƃ͈ꌾ�������Ă��Ȃ��v�Ǝߖ��������A�A����͉������̍R�c�������ǂ��Ăɑ����������Ƃ������A�u�ǎ҂�23�A�����s�E�������Ɣ��f����v�Əd�˂Ĕ��_�����B
�@�������́A���̏�ł͖��̓��L�ɂ��Ă͌����邱�Ƃ����ۂ������A�A����w���������t�̕�����ǂ݂����Ă���B�������A���L�ɑ��̎t�c�ɂ��Ă̓����������Ă���ȂǁA�A����o�Ȏ҂͓��L�̐M�҂傤���ɂ��Ĕ[�������A�u����ŁA�����̕����������A�����̎咣�����������A�������悤�v�Ɣ������B
�@�A�����26���ߌ�A�{��s���Ŗ�������J�ÁA18���Ɍ��c������c����̍R�c�����d���A�����܂Œ����V���ɑ��ĎӍ߂�v�����邱�Ƃ��m�F�����̂ł������B
�@�A����́A���̗v���͂Ƃ������u�싞�s�E��23�A���͖��W�ł���v�Ƃ̕\�����A�����V���Ђɋ��߂Ă���B
�@�ٗ�́u����ыL���v���o�����B�u�����v��1�̋L���ŁA2�x�A�u����ыL���v���o���Ƃ������ƂȂǁA�펯�I�ɂ͍l�����Ȃ��B�����܂ŁA�˂��ς˂Ă����p�����\�z�����B�A����ɂ́A����A���C�����킢���������悤�B����̂Ȃ�䂫�������ƌ������Ă��������B
�@�����V���́A�e���r�����̂�点�����`�����A�L�c������h�E�����A���X�g�^�f�h�ȂǂŃ}�X�R�~�ϗ������������ꂽ���a60�i1985�j�N�̐V���T�Ԃ̏����ɂ�����10��14���t�̈�ʂɕx�X�ҏW�ǒ��́u�V���T�Ԃɂ������āv�Ƒ肷��L���������Ă���B�����V���̋L�҂͂��̌��_���v���o���Ă������������B�����ŕx�X���͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@���f�B�A���A�̎��R�𗐗p���Ď�̑��̒m�肽���S�ɂ������邱�Ƃ����ɕ��S���Ă���ƁA����挊���@�邱�ƂɂȂ�B�V�����e���r���L����ԑg�̐R���@�\������Ɏ����Ă���̂�����A�Ƃ肠�����͂��̋@�\���������āA�ᔻ�ɑΉ����邱�Ƃ��K�v�ł��낤�B���ł��V���́A�ǎ҂Ƃ̑����M���W�������āA�͂��߂Ė���Љ�ł̖������ʂ������Ƃ��o����B���̓_�ň�w�̓w�͂��K�v�ƍl����B�i���E����u�����v����ޔǁw�����V���́u�ƍ߁v�N�����߂ɏ��͑��삳���x���j
�@���̘b�͍�����\�N�O�̂��Ƃł���B
�싞�U���Ɠ����ɓ��邵�Ď�ނɂ������������V���̑����a�Y�L�҂ɁA�]�_�Ƃ̈������ꎁ���d�b�Ŗʐڂ�\�����B����ƁA�������͂����������Ƃ����B
�@�u�싞��s�E�Ƃ���������Ă��܂����A���͑�s�E�Ȃ��Ă��܂���B���Ȃ����ǂ̗l�ȗ���̐l���m��܂��A��s�E�̏،��͂ł��܂���v�ƍŏ��f��ꂽ�����ł���B�����A�悤�₭�����āA����Ɏf�����������́u�������A�����������������������V���ł͖{������L�҂��싞��s�E���������Ǝ咣���Ă��邵�A�Љ�ʂł��悭�Ƃ肠���Ă��܂����E�E�E�E�E�B�v�Ɛ�o�����B����Ƒ������́A�u���Ɏc�O���B����������V���Ђ̖����ɉ���Ƃ��������̂ł��̂��Ƃ����������A��s�E�ȂǂȂ��������Ƃ��ˁB�v����ɑ������͌���p���ŁA�u�����V���ɂ͐e�����i�������Y�}�j�E����p�A�e�k���E���؍��Ƃ�������������B�{���N��l��������Ȃ��A�Љ�ɂ��������C�^������B�����炠���������ʂɂȂ�B�v�i�������꒘�w�������싞�����x�P�Q�V�v�j����͉��������V����������Ȃ��āA�Y�o�V�����������{�̃e���r�ǂ��܂ރ}�X�R�~�S�ʂ̕����ł���B�@�������ɂ��A�W�V�N�̒i�K�ŁA�R�̎Q�d�A�t�c�̎Q�d�ȂnjR�W�҂����łP�T�O�l�A�W�҂R�O�O�l�A�O���W�҂Q�O�l�ȂǁA�����i��̒���j�싞�ɂ�����T�O�O�l�̐l��������A���ړ싞�̗l�q��
���A�����̖{���̓싞�̗l�q��������ł���̂ł͂Ȃ��낤���|�|�|�Ƃ����̂ŁA���͂��̒��̂U�V�l�ƘA�������A���A����ɂR�T�l�ɂ͂P�l�R��Âʐڂ����Ď�ނ��A�{�l�̍Z�{�������ďo�ł����̂����́w�������싞�����x�ł���B
�@�����ł͑����L�҂̑��ɁA�����̓싞�x�ǒ��߂����{�o���O�Y���ɖʐڂ��ăC���^�r���[���Ă���B���{���͒����V���Ђ���h�����ꂽ�T�O�l�߂��L�҂�A���������ē싞�ɓ��邵�A�x�ǂ��J�݂����x�ǒ��ł���B�������́A�|�|�|�|�|�u�싞�ł͑�s�E���������Ƃ����Ă��܂����A�싞�̗l�q�͂ǂ��ł������H�v�̖₢�ɁA���{���͂��������Ă���B
�u�싞�ł̎����˂��B���͑S�R�����Ă��Ȃ��B��������L�҂̊ԂŘb�ɏo�Ă���͂����B�L�҂͏����ł��b��ɂȂ肻���Ȃ��Ƃ�b�����邵�A���ꂪ�d��������ˁB�\�Ƃ��Ă����������Ƃ��Ȃ��B�����V���ł͌��n�ō��k�������Ă������A�������̂Ȃ�A�I���łȂ��ɂ��Ă��A��R���������Ƃ��A����Șb���ł�͂����B�싞�����͂Ȃ������낤�v�i�O�f�����P�R�Q�`�R�v�j
�@���{�o���O�Y�Ƃ����A�������t�Ŋ��[�����A�c�����t�Ŏ����}�̊��������Ƃ߂����͎҂ŁA�����ăE�\�����悤�Ȑm�ł͂Ȃ��B�N�����͖Y�ꂽ���A�א엲���������l�������Ƃ̃e���r�Βk�ł����q�ׂĂ������Ƃ��v���o���B
�@�u�킵�������V���̕ҏW���̂Ƃ��A�싞�U����ɎQ�������L�҂�J�����}���S�����W�߂āA��s�E�̂��Ƃ������Ƃ�����B�����A�N��l�Ƃ��āA�������Ƃ����������Ƃ�����܂���ƁA�͂����蓚���������B��s�E�Ȃǂ���Ⴕ�Ȃ���A�f�}����B�v�Ƒ�����Ă����B
�@���̏؋��́A�����R�N�O�ɏ㈲�����w�����V�����g���a�S��싞�h�̎ʐ^���W�x�ł���B�싞�ɐ�̂Ɠ����ɓ��邵����Q�O���̒����̋L�ҁE�J�����}���́A����̂P�Q���P�R������P�Q���R�O���܂ŁA�R�T�Ԃ��炸�̊ԂɁA�S�ʂɂ킽���āw���a�S��싞�x�̏��A���y�[�W��̃X�y�[�X�ɑg�ʐ^�ɂ��Đ�̂ł̓싞���Љ�Ă���B
���̑�P�ʂ́A��̂T���ڂ̎ʐ^���W�ŁA�肵�āw���a�S��싞�s�c�R���}���Ċ��앦���t�x�ł���B���̒��ɂ́A��������X���o��(1)�u��������̔������v�p���łĂ���A(2)�u�c�R����Ɉ��g���ď�O�̔����k���_�������v�̎p���ʂ���Ă���B����ɑ�������O�ɂ���(3)�u���̌Q�����X�ƋA���ė��镗�i�v�B�����(4)�u�a�₩�ȊX���������i�v�B���ʂ�������Ă���B�i�͑����h���B�e�j
�@
�@��Q�̎ʐ^���W�́A��̂W���ڂɎB�����w���̂ӂ̓G�ɉ���s�싞����̐e�P���i�t�x�Ƃ����^�C�g���ł���B�ʐ^������(1)�́u���Â��Ă���x�ߕ������v�ŁA�ߗ��s�E�ǂ��납�A���{�̌R�オ�ނ��f�Â��Ă���ʐ^���B(2)�́u�c�R�����̗l�ɐH�~�������~���v�ł���B���{�����H�Ƃ�z�����Ă���ʐ^���B(3)�́u�����Ǝs���Ƃ̐e�P���i�v�A(4)�u�萻�̓��̊ۂ̘r�͂������s���v�����̎p�ł���B�i�͑����h���B�e�j
�@�ʐ^���W���̂R�́A�肵�āw�싞�͔��ށs����_�`�t�x�ł���B(1)�́u�ߋ�̐�ԂŎq���B�ƗV�ԕ�������v�ł���A(2)�́u��ꂽ�n�ԂŗV��ł���q�������v(3)�́u�q��������f�Â��Ă�����{�R�̉q�����v�A(4)�́u�x�ߐl����̒납��k���^���́v�Ƒ肷���50�l�قǂ̂���Ⴂ�����������I���K���̑O�ʼn̂��Ă���ʐ^�ł���B�i�ѓ��h���B�e�j
�@�ʐ^���W���̂S�́A�肵�āw������荇���ĉz�N�s���ɐ[�ޓ싞�̓��x�e�P�t�x�ł���B�i���a�P�Q�N�P�Q���R�O���̐V���f�ځj�ʐ^������(1)�́u�����������ɌC�̏C�U�������܂����v�Ǝx�ߐl�̌C������ɐ����Ă��镗�i�A(2)�́u�T�@�����ς�������Ȃ���~���N�����オ��v�ƃq�Q�̑����������w�l�Ƀ~���N�������o���Ă���B(3)�́u�V�����K�[�[���Ƃ肩���Ă������������}���܂����v�Ɠ��{�R�̌R��B���x�ߕ��ߗ��̕�т��Ƃ�ς��Ă��镗�i���B�i�ѓ��h���B�e�j�@�����V���ʐ^���W��
�@�������������V���̂����̎ʐ^������镗�i�̂Ȃ��ɁA�ǂ����ĂR�O���̑�s�E�A�����Q�����A�U�T�Ԃɂ킽����E���D�E�\�s�̒n���}�ȂǑz���ł��悤���B�܂������O�q�̒����̑����L�҂�A���{�싞�x�ǒ���A�א엲���ҏW���̌������Ƃ��A�u��s�E�Ȃnj������Ƃ����������Ƃ��Ȃ��A�g�ł��������̃f�}��`�h���B�v�Ƃ����̂����b�Ȃ̂ł���B���Ƃɐ�̂��Ă��傤�ǂR�T�Ԗڂ̂P���R���ɁA�����R���ψ����Ƃ���u�싞���@���ψ��v���a�������Ƃ����̂ŁA�R��̎s�������͊��ƂT�F����U�肩�������s������Ă���ʐ^�܂ł���B�s�E�̊X�ł͐�ɍl�����Ȃ����Ƃ��B
�@
�@�܂��ƂɊ�Ȃ��ƂɁA���̒������A��s�E�͂������A�������ƁA�}�X�R�~�̐擪�ɗ����Ă͂₵���Ă͂��߂��̂ł���B�G���u���_�v�Ɂw�����V���̐��ӔC�x��A�ڂ��Ă���]�_�Ƃ̕Љ��������ɂ��ƁA���a�S�T�N�̂R������S���ɂ����āA���Ђ̊��呍����ق����炩���āA�L���m�j�В��́A�����ɔ�B�����Ė�P�����ԁA�������{�̔M�}���������B���̎����璩���̕ҏW���j�͈�ς����̂ł���B�u�������𑣐i�v���И_�ɂ������āA���������������Y�}���{�̈ӌ��⌾�����𐳘_�Ƃ��āA���{�����ɓ`�B���邱�Ƃ��g���Ƃ���u������ӓ|�̐V���ɕϐg�v�����̂ł���B�И_�����ł͂Ȃ��B�����̎��ƕ��́A�����싅�e�P�����̊J�ÁA�����o�y�����W�̎�ÁA��C�����c�̌����ȂǁA��p�����ɒ����������Љ���B����ɓ����{�ЕҏW�ǒ��㓡��Y��K�������߂āA�����̕ҏW�⎆�ʍ\���ɂ��Ă܂ł��k�������Ƃ����B�܂�Ђ������Ē����̐���ɂ̂߂荞�̂ł���B�{������L�҂������ɓn��A���_�������т������Y�}�́g��蕔�h�i��`�}���j�Ƃ݂���l�Ԃ����f�^�����̍��b������A��������ʑ�s�E��A���l�R�̐��S����܂�Ȃ��A���{�R�R�����Ƃ����c�s
����ᔻ�ɁA���������A�E�����Ƃ炸�A���̂܂ܒԂ����̂��w�����̗��x�ł���B�@�j���Ƃ��ƍ������A���{���̈ӌ����������A���ӔC�ɂ܂�w�����̗��x���������ꂽ�̂͏��a�S�U�N�ł��邪�A���ꂪ����ɁA�����V���ɂ����L���ŁA�j���Ƃ��đ�X�I�ɘA�ڂ��ꂽ���߁A���{�����ɗ^�����e���͐r��Ȃ��̂��������B�@�@�u�싞��s�E�����v�Ȃ���̂́A�����ٔ��ŏ��߂Ēm�炳�ꂽ�����ł���B����܂ł͓��{�����́g�\�h�ɂ��畷���Ă����Ȃ������B�싞��̖ʐς͓����s���c�J������⏬�ł���B�i��S�O�����L���j�����֊O���l�L�҂T�l���܂ނP�R�O�l�قǂ̋L�ҁE�J�����}�������邵�Ď�ނɂ��������B���̂������\�A����S���A���s��A��ˏG�s�A�ΐ�B�O�A�ѕ����q�Ƃ����������Ȏ��l�E�]�_�ƁE��Ɠ������邵�A���@���Ă���B���̂����̒N�ЂƂ�Ƃ��āA��s�E�Ȃnj��Ă��Ȃ����A�����Ă����Ȃ��̂ł���B�]���Ď��̂̎R�����̉͂��A��퓬�����E�Q���Ă����ʂ̎ʐ^�Ȃǂ��ꖇ���Ȃ��B����叫�͏�C�ɋA���ĂQ��A�O�l�L�Ғc�Ɖ���Ă��邪�A���̐Ȃł����A�s�E�Ɋւ��鎿��ȂǎĂ��Ȃ��̂ł���B�@�����ٔ��͏��҂��s�҂ɑ������I�ȕ��Q�ٔ����B
���{�����͏��߂ĕ����싞�s�E�̌��ɋ����������̂́A�����ƂƂ��ɂ��̈�ۂ����ꂩ���Ă����B�������A���߂āw�����̗��x�������ɘA�ڂ����ɋy��ŁA�����͜��R�Ƃ����B�Ȃ��Ȃ炻��́A���{�̐V���L�҂ɂ�錻�n������ł���B�@�싞��s�E���������߂Ē��w�̗��j���ȏ��ɓo�ꂵ���̂́A���a�T�O�N�̏t����g�p���鋳�ȏ��ł���B����́A�����炭�A�����������Ă��̋s�E�L�����y�[���̉e���Ǝv����B�����Ȃ̌��芯�́A�����A�u�헐�ɂ܂���āE�E�E�v�������N�����ƏC���ӌ���t�����B�@�@���ꂪ�T�V�N�́u�N���v���u�i�o�v�ɒ��������Ƃ��������A���̋{�[�������A���ɂ�������炸�����ɎӍ߂��ĈȌ�A�ǂ̋��ȏ��ɂ��u�Q�O���A�R�O���v�Ƃ����֑�ȋs�E�����L����悤�ɂȂ�A�u�헐�ɂ܂���āE�E�E�v�������Ă��܂������Ƃ͂������̒ʂ�ł���B�����͖{���L�҂𒆐S�ɎГ��Ɂu�싞���������������v��݂��A��s�E�h�̓��x�Y�����勳�����ږ�ɁA�������A�}���\��i�A�g�c�T�Ƃ����������E�s�E�h�̊w�҂��W�߁A�����ς�싞�ɑ�s�E���������Ƃ���o�ł��e���d�ˁA����ɋs�E�̎����̔��\��،��̎��W�ɂƂ߂��B�@�@�������Ē������g�b�v�ɁA���{
�̃}�X�R�~�S�̂��A�싞�ɑ�s�E���������Ƃ��镗�����x�z�I�ƂȂ����B�i�������Y�o�V�������͐��_���Ȃ��Ȃ����߁A���܂��ɖk�����݂���O����Ă���A��O�ł���j�����͓x���߂��āA�{��̕�����Q�R�A����F���i����ꂽ�B����̓E�\�̐w�������▞�B�n���̐���̎ʐ^�܂ł������āA��s�E�̏؋����Ƒ傫���������߂ł���B�����͑i�ׂɔs��A�Ӎߒ�����]�V�Ȃ�����Ă���B�܂��ŃK�X�̃j�Z�ʐ^�Ȃǂ��o���ĎӍ߂��Ă���B�@�@���a�U�O�N�W���A�����͍R���푈�����S�O���N���L�O���ē싞�Ɂu�N�����R�싞��s�E����E�L�O�فv�����݂��Ă������A���Ƃ��̊����������͓̂��{�Љ�}�i���݂̎Ж��}�j�^���͎҂ł���A���̎����͑��]�i���݂̘A���j���܂��Ȃ����Ƃ����Ă���B�@�@�O�q�̒����́u�싞���������������v�̃����o�[���A�L�O�ٌ��݂̑O��ɓ싞��K�₵�ĔM�}���Ă���B�{���A���A��������P�Q�l�ɂ��w�싞��s�E�̌���ցx�̒�������������o�ł���Ă���B�ٓ��ɏ���ꂽ�ʐ^���̑��̎����͓��{���玝���o���ꂽ�Ƃ݂��āA�ٓ��Ŕ̔�����鎑���W�́A�Ȃ��������A���{�l�ɂ͔���Ȃ����ƂɂȂ��Ă����Ƃ����B
�@�싞��s�E�̍ő�̃v���p�K���_�Ƃ��ēo�ꂵ���{���L�҂́w�����̗��x�̈�p�����S�ɕ�����������B�@�@�w�����̗��x�̒��ɂ͕����Y�z�ł̋s�E�������o�Ă���B���B�ő�̒Y�B�ł����������Y�z�ɂ͖��l�R���R�O����������B�P�����P���l�Â��߂��Ƃ��āA���{�l�͒����J���҂��R�O���l���s�E�����Ƃ����̂ł���B��͂�w�����̗��x�̉e���ł��̂��Ƃ͍��Z�̋��ȏ��ɂ��o�Ă���B�@�ȉ��́u���_�v�Q�����̓c�ӕq�Y���w�u�����R�����v�u���l�R�v�ɂ݂鋳�ȏ��ƕ̕s�����x������p�����Ă����������B�@�@�@�s�u�����̒����l�J���҂��e���ȏh�ɂƐH�������������č��g����A���{�l�o�c�҂̈ꕔ�̍z�R�Ȃǂł́A�������l�J���҂̈�̂����Ă�w���l�R�x������ꂽ�v�i�O�ȓ��w���Z���{�j�x�j�@�@�u�w���̃|�C���g�v�ɂ́A�قڂP�y�[�W�ɂ킽���āw�����̗��x�̈��p������B���̈ꕔ���o���ƁA�u�i�ʂ肩����������̓��{���Q�A�R�l���j�Ԃ�V����������������ƁA��������o���āA���̏�ŋ������悤�Ƃ����B��͐Ԏq��������߂Ē�R�����B�{�������{���́A�Ԃ�V���̎肩��ނ���Ƃ�ƁA���̏�Œn�ʂ����ς��ɂ����������B�Ԏq�͐����o���ɑ�
�������B�������ɂȂ�����e���A�䂪�q��n�ʂ�������グ�悤�ƍ��������߂��u�ԁA���{���͕�������납�猂�����B�E�E�E�v�@�@�����āA�������̒��ɂ́u�����ł̓��{�R�̎c�s�s�ׂ͖{�����꒘�w�����̗��x�w�����̓��{�R�x���K�Ǖ����B���ƂɌ�҂̎ʐ^�͗ǂ����ނɂȂ�A�v�Ə�����Ă���B�@�@�w�����̓��{�R�x�́w�����̗��x�̓��{�łł���B���l�R�Ɋւ�����̂����ł��A�����������l���̎ʐ^�Ȃǂ��R�O�y�[�W�ȏ�ɂ킽���Ă���B���l�R�L�q�����ȏ��ɂȂ��Ă��A�u�K�Ǖ����v�Ƃ����ȏ�A���t�͂�����ǂ݁A���k�ɋ����邱�ƂɂȂ�B�@�@�c�ӕq�Y���͏��a�T�P�N������w�����̗��x�Ȃǒ����ɂ����鋌���{�R�E���̎c�s�����ɋ^��������A�����Y�z�▞�B�z�Ƃ̌��Ј���Q�O�O����ΏۂɎ�ނ����B�������т����k��⌤������J���A���邢�͎Y�o�L�҂Ƌ��Ɍ��n�̓����ɂ��s�����B���̌��ʁA�����Y�z�ɖ��l�R�ȂǂƂ������̂͂P���Ȃ��A�������Ƃ����������Ƃ��Ȃ��A�ƊW�҂����ٌ͈������Ɍ����B�܂��ĕa�l�⓭���Ȃ��Ȃ��������l�z�v���Ȃ��猊���߂ɂ���悤�Ȏc���ȍs�ׂȂǁA�f���Ă��蓾�Ȃ��ƒN����������B�@�c�ӎ��͂��ꂩ��̕���������A���k��ł̋L
�^��A���n�����̕����G�����_��Y�o�V���ɓ��e�����B�����Ē����V���ɂ��R�c�����B�����V���́u���߂Ē��������܂��v�Ƃ܂Ŗ����Ƃ����B�����A�����������Ղ͊F���ł���B�@���҂̖{���L�҂ɑ��āA�u�����Y�z�̖��l�R�L�q�Ȃǂ́A�S���̋��ς��B�������ė~�����v�ƍR�c����ƁA�Ȃ�Ǝ��͂������������B�@�@�u���͒����l�̌����̂����̂܂ܑ�ق��������ł�����A�R�c������̂ł���A�������ɒ��ڂ���ė~�����v�ƁB�@���Ƃ������ӔC����܂��Y����Ԃ肩�B�����V���Ƃ����낤�S�������A�u�����O��䎮�v�֑̌�ό����Ȃ�т��Ă钆���̐�`���̃v���p�K���_���A���̂܂܂P�����ȏ���A�ڂ��āA��������ʑ�s�E�����Ƃ͉������B�c�ӕq�Y���́w�������Ȃ߂�ꂽ����j�x�Ƃ����������㈲���Ă��̂��Ƃ����킵���ׂ̂Ă���B
�@�����͒����̌����u�R�O����s�E�v��M�Ă����B�{���L�҂��Ƃ��́A�u�싞��s�E�Ƃ����̂́A�����싞�ɂ�����s�E�������w���̂ł͂Ȃ��A���{�R�͍Y�B�p�㗤������s�E������Ă���A�ꏊ�Ǝ������L���čl����ׂ����v�Ȃǂ��k�ق�M���Ă܂ŁA�R�O����s�E��i�삵�Ă����B���ĐΌ��T���Y�����Ď��v���C�{�[�C�i�����Q�N�P�P�����j�Ɂu�싞��s�E�͒����l�̍��b���v�Ɣ����������e�̘_�����̂����B���̉e���͑傫���A����ɕ��S�����ݕĉ؋����A�j���[���[�N�^�C���Y�ɂP�v��̈ӌ��L�����o���āu�R�O����s�E�v�����������B�Ƃ��낪�����́A���ꂩ��P�T�Ԍ�̕����R�N�P���R���t���̎А��ŁA�u�Ό����̔����́A���j�������\�_�ł��邱�Ƃ͖��炩���v�Ɖ؋��̈ӌ��L�����x�������B�܂蒩���V���Ў��̂����߂ē싞�����ɑ��錩�����А��Ŗ��炩�ɂ����̂ł���B�@�@�����œ싞�����ɊS���������̎��҂���A�����͒����̂����u�R�O����s�E�̏؋��������v�Ƃ�����������ꂽ�B���̂P�l�A�쑺��N���i�x�R�̕�����R�T�A���̑���{���t���L�E�R���j�ɑ��A�O�q�̎А��̕M�ҁi�_���ψ��j������������B�Q���Q���t���ŁA�v��ƁA�u�R�O���Ƃ�
���������������Ƃ͎v���܂���B�w���x�ŏЉ�������V���w�싞�����x�̌������A�����_�ł͑Ó��ł͂Ȃ����ƍl���܂��v�Ƃ����̂ł���B�@���̒��҂Ƃ����̂͐`��F���ŁA�`���́u�s�E�͂S���Ă��ǁv�Əq�ׂĂ���B�M�҂͂��̒����ǂ������A������˂��������A�}�X�R�~�̋s�E�����ɛZ�т����͂ł���B�@�@�����́A�Ό������u�_�d�v�ɓ��e�������Ɛ\�����ꂽ�ہA�������ɂ������f���Ă���B�����̓ǎ҂̎���ɂ��u�싞�ɂR�O���̑�s�E�����������ۂ��ɕt���Ă̌䎿��ɂ͓����闧��ɂȂ��v�Ɠ˂��ς˂Ă����B�����������u�`���̂S�����v���x���������Ƃ́A���ʓI�ɂ͐Ό����̌����u�싞�̂R�O���s�E�͒����̍��b�ł���v��F�߂����ƂɂȂ�B�����͌��_�̎��R�����Ȃ��}���N�X�E���[�j����`�̘_���Ɖ��l�ς����\�A�E�����ɂ̂߂荞��ŁA���̂����Ȃ�ɂȂ�A���Ȃ������̉ߋ���N�����������Ƃ���j�ςŁA������`���ӂ�܂��Đ��`�Ԃ�B�ߐ[���ߋ��̔��ȂȂǒ܂̍C�قǂ��Ȃ��B���낵���V���ł���B
�@�ŋ߂́u�����V���v�͋C�ł��������̂ł͂Ȃ����Ǝv����قǁA�����嗤�ɂ����鋌���{�R�́g�߈��h�o�N���ɐɂ������Ȃ����ʂ������Č֑�ȃL�����y�[����W�J���Ă���B�����̎茳�ɂ���X�N���b�v�E�u�b�N����˂��������ł��A���́g�����L�����y�[���h�������ɋC�������݂����̂ł��邩���킩��B�@
�@�����̋L�����\���Ȓ����������ˁA�E�����Ƃ��Ď����܂������Ȃ����̂Ƃ��Ĕ��\�����Ȃ�܂������A���ׂ�����킩��悤�ȋ��U�̏،��܂ł��A���X�Ɛ��I�匩�o�������Ĕ��\���Ă���B
�@�������A���Ƃ���q�ׂ�悤�ɁA���炩�ɂ����̋L�����ԈႢ�ł͂Ȃ����Ƃ����؋��𑵂��Ă̔��_�ɑ��āA�u�����V���v�͂����َE���Ď��グ�悤�Ƃ��Ȃ��B�v����ɁA��̕����\�\���{�R�͓싞�łR�O�����̒����l���s�E�����\�\�Ƃ������_�ɏ��߂��猋�т��悤�Ƃ���ԓx�ł���B���ܒ����V���Г��Łu�싞��s�E�h�v���\���Ă�����ƂȂ��ĕM���ӂ���Ă���{������Ƃ����L�҂��A���ăx�g�i���푈�ŁA�����ɔ��Đe�\�I�Ȗ������ʂ���������z�N���Ă݂Ă������������B���̌�A�S�����z�����≽�\�����̃{�[�g�E�s�[�v�����o�Ă��A�u�����V���v���{���L�҂��A�݂�����̖k�x�g�i���ςɂ��č����ɂ���������Ȃ̌�����S�������Ȃ��B���������V���y�ыL�҂��A���܂܂��V���ɂ�������Ȃ������u�싞��s�E�v�Ƃ������ς������ɉ������A���{�́u�����I�p�J�v���i�v�ɗ��j�ɍ��ݍ��ލH��ɐ�O����w�߂Ă���̂ł���B
�@���́u�����V���v�Ɍf�ڂ����g�싞��s�E�h�Ɋւ���L����]�_�̎��グ�������܂�ɂ��ł���߂������̂ŁA�ǎҗ��ɂT��ɂ킽���ē��e�����B����������������ۂ���A���Ɉ�x�����̔��_�͌f�ڂ���邱�Ƃ��Ȃ������B
�@�ŏ��Ɏ������e�����̂́A�S���Q���́u�����v�́u���v���ɁA���𖼎w���Ŕ�掂��鎟�̂悤�ȓ����������̂����������ł���B
�@�s�ʐ^�W������s�E�̎��ԁB�@�@�@�@�@�@�{�錧�@�@�@�@���{�l�Y�i���E�T�U�j
�@���͐푈�̔ߎS�����q���⑷�ɒm�点�邽�߂ɂ����̐}����ʐ^�����߂Ă��܂��B���{�R�l�炪�����ȂǃA�W�A�̊e�n�ōs�����c���Ȑl�E���͐�����Ȃ��A�싞��s�E�́A�i�����N�������i���@�j���R�l�������悤�ɋ��U�̕����ł͌����Ă���܂���B�a�藎�Ƃ�����������Ă̋L�O�ʐ^�A�W�c�Ő������߂ɂ���钆���l�A���ꂪ�s�E�łȂ��ĂȂ�ł��傤�B
�@�����ٔ��̋L�^�ɂ́u�Q�O���l�̒����l���E�Q�v�Ƃ��邪�A���U�̕������ƌ����i���A�j�̓c���������炪�M���Ă���Ȃ�A�Ȃ��ؐl�Ƃ��Ĉӌ����q�ׂȂ������̂��낤���B�푈�ɂ��Ă̎����B����i�߂鎩���}���{�A�����Ȃ̊�т����ȓc������̔��Ȃ̂Ȃ��s�ׂɓ{��������܂��t
�i���j�����A�u�i�����N�������v�Ƃ��A�u�����v�Ƃ��������t���o�Ă��邪�A����́A���Ö��A����L���Y�A���{�����A���⒆�A�m����A�ɐ����Ǝ��̂V�l���A���i�����ȁj��ɁA���N�Ă̋��ȏ������ŁA���E�ؗ������{�̍R�c�ɗ�ؓ��t���������ĈȌ�A���̕Ό��Ԃ肪��w�r�������Ȃ������E���Z�̕Ό����j���ȏ��̐��������߂�i�ׂ��A����R���P�T���A�����n�قɋN���������Ƃ��w�����̂ł���B���Ȃ݂ɁA��R������͂P�O���P���J��\��B�i���̌��Ɋւ���₢���킹�͓����s���c��O�_�c�T�|�U�|�R�@���ȏ������i�����ǂց@�d�b�O�R�|�W�R�Q�|�U�W�O�T�j�@���{���̕����Ɂu�����ٔ��v��u��v�̌�������A�����ٔ���������邽�߂ɂ́A�ܕS���́u���v�̗��ł͏\���łȂ��Ǝv��ꂽ�̂ŁA���͓������e���́u�_�d�v�i�O�����j�ɓ��e�����B�S���R���A���e�͎��̒ʂ�ł���B
�@�s�싞�Ɂg��s�E�h�͂��������B�{���R���R�O���ɂ͖{������L�҂́u�싞��s�E�S�U�N�v�̃��|�[�g�Ɓu�싞��������������v�̔����L�����̂�A�S���Q���ɂ́A���̖��O�܂ŏo���u�싞�s�E�v�Ɋւ���^�ۗ��_�̂Q�̓��e���f�ڂ��ꂽ�̂ŁA���ɂ����킹�Ē����B�@�{�����ɂ��ƌ���n�ɂȂ��������e�n�̒n�����{���ǂ́u�����Ԃ̗��j�I�����𐳂����m������ł̗F�D�����z�����m�̗F�D�v�Ƃ̈ӌ��ɂ͎����^���ł���B�����Ƃ������̐ӔC�ґ�������Ă���ԂɁA�ꋉ��������b�ɂ��Č����Ȃ钲�������{����Ƃ���]����B��N���ҋL�^�f��w�����ٔ��x����f����b����Ă��A���̎����ѐ����ḗA�X�X���܂Ńh�L�������^���̂��̉f��ɁA�P���������w�����̓{��x�Ƃ�����`���f���}�����āA�싞�Łu��s�E�v���������Ɖ�������B���ъḗu�v���W�f���g�v�i�T�W�N�X�����j�Ɂu�f��g�����ٔ��h�ɉ�����v�Ƒ肵�āA���̉f��̐���Ӑ}�ɂ��Ă��Ȃ�ڂ����������Ă���B����ɂ��Ə��ю��́u�m���ɂ���͍������{���싞�������������邽�߂ɂ�������������点�f��ł��邱�Ƃ͍ŏ�����킩���Ă����v�Əq�ׂĂ� ��B��点�Ƃ͂킴�Ƃ��̂悤�ȏ�ʂ����炦�A�킴�Ɖ��Z���āA�^���̂��Ƃ�������f��Z�@�ł���B���������̃t�B��������ɓ���邽�߁A�W�҂͑�p�ւX��������^��ł悤�₭��ɓ��ꂽ�̂��Ƃ����i�]�c�a�Y���k�j�B����قǂ܂ł��āu�싞��s�E�v�𗧏��Ȃ���Ȃ�Ȃ����R�͂ǂ��ɂ���̂��A���ɂ͂킩��Ȃ��B�@���̉f��ɂ́A�^�~�Ƃ����ɔ����A���Y�{���̕������o�Ă�����A�싞�ɏ㗤���Ă��Ȃ�������̕�������������������ʐ^���o�Ă���̂ł���B�����̋��{�l�Y���̎ʐ^�W�̎ʐ^�������炭���̂������ł��낤�B�@���{���́A�����ٔ��ł����̔����ŁA�u�Q�O���l�̒����l���E�Q�����v�Ƃ���ł͂Ȃ����ƌ����邪�A����叫�ɑ���l�����ł́u�P�O���l�̎E�Q�v�Ƃ��̐��͔������Ă���̂ł���B���̍ٔ��͓��{�R�̖\�s�ɂ��ẮA�u�U�؍߁v�Ȃ��̌�����������������A���{���̒�o�؋��͂��Ƃ��Ƃ��p������Ƃ����s�����ȍٔ��ł������B��N�T���T���V���C���r���ŊJ�Â��ꂽ�u�����ٔ����ۃV���|�W���[���v�ŁA�A�����P�P�����̔����������P�l�̐����҂ł���I�����_�̃��[�����O���m���o�Ȃ��āA���̕s������
��F�߁A���܂��o�Ȓ��̉Ɖi�O�Y���������A�����ٔ��͌����Ȃ�ٔ��Ƃ͌�����|�̔����������قǂł���B�u�싞��s�E�v�͂��̓����ٔ����f�b�`�������g�n��h�Ȃ̂ł���B�@�@�싞�͍x�O�܂Ŋ܂߂Ă���S�O�����L���A�������c�J��̂T���̂S�̖ʐςŁA�����ɂP�O�O�l�ȏ�̓��O�L�Ғc����ނɂ��������̂ł���B�����̎s���͂Q�O���l�Ƃ����A��������S���u���S��v�̒��ɏW�߂��Ă����B�i�싞���S�捑�ۈψ���\�j�B�����ɂ͈ꔭ�̔������C�����Ȃ��A�Ђ���ꌏ���Ȃ��ی삳��Ă����̂ł���B���̂��߂R�T�Ԍ�ɂ͂��̐l���͂Q�T���ɑ����Ă���B�����̒����V���́u���a�S��싞�v�Ƒ肷��ʐ^���W��g�A���{�R��̂S���ڂ̂P�Q���P�V���A�c�R�ɕی삳�����̌Q���A�A�҂����_������O�̔����k���Ă���ʐ^���f�ڂ��Ă���B�@������������������q�R��T���́A�퓬�ɂ���œI�Ō����Ă���B�Ӊ�Ύ��́u�싞�ɂ�����䂪�R�̑��Q�U��v�Ɣ��\���Ă���i�w�Ӊ�Δ�^��P�Q���x�j�B���������Q�O�����̂R�O�����̂Ƃ����s�E�����͂ǂ�����o�Ă���̂��B�L���̌����]���҂ł������̐��͂P�S���ł��邱�Ƃ�z�N���Ăق����t�@
�@���̓��e�́u�����v�̕ҏW�ǘ_�d�W����A�u�c�O�Ȃ���f�ڂ������点�Ē����܂��v�Ƃ�������n�K�L�������āA�v�ɂȂ��Ă��܂����B�����ō��x�͂�����U�O�O���Ɉ��k���āA�u���v���ɓ��e�����B�S���P�O���̂��Ƃł���B
�@�s�g�싞��s�E�h�͐����̈�l�����B�@�@�{���R���R�O���Ɂu�싞��s�E�S�U�N�E���������͂��܁v�Ƃ����{�����ꎁ�̃��|�[�g���f�ڂ���A�܂��S���Q���́u���v���ɂ́A���𖼎w�����Ă̎��������̂ł��������܂��B�@�V�N�x����̒��w���ȏ��A�����w�Z�̗��j���ȏ��̒��ɂ́A�싞��s�E�Q�O���A�R�O���Ƃ��������܂Ō���܂����i�������Ёj�B�������̂悤�ɓ싞�����͓����ٔ��ő傫����肠�����A�Ȍ�^�������̂Ȃ��܂܂ɁA������������l�������Ă���̂�����ł��B�����́u�z�����m�̗F�D�̂��߂ɂ��A������
�̗��j�I�����𐳂����m��v���Ƃ��̗v���Ƃ̒ɂ͑o��������Ď^�����܂��B���̂��߂ɂ́A������`�I�Ȑ�����A����I�ȁA���邢�͕����ɂ�鐔���͕ʂƂ��āA�����o���Ƃ������̊W�҂��܂���������Ă���A�����Ȃ��O�җ�����̂��ƂɁA���ؓI���������{�����悤������]���܂��B���ݎ��̎���ƂɑS������A�����̏]�R�L�҂��܂ߎQ�폫����W�O���̕�����A�u�Q�O���A�R�O���Ȃǘ_�O���v�u��s�E�Ȃǐ�ɂȂ��v�Ƌ����ے肵�A�u�����̂���߂����ȏ��ɂ܂ŏ������Ă��A����ł����ɂ���Ȃ��v�Ƃ��������莆�₨�d�b���Ă��܂��B
�@�����ٔ��̔������i���������j�ɂ͂Q�O���Ƃ���ł͂Ȃ����Ƃ����܂����A������퍐�ɑ���l�������͂P�O���Ɣ������Ă��܂��B���{�R�̔c�s�͌�����������Ƃ����g�U�؍߁h�̂Ȃ����̍ٔ��͑S���s�����Ȃ��肩�A���̐��l���ł���߂ł��邱�Ƃ�t�����ĉƒv���܂��t�@
�@���̓��e�ɑ��āu�����V���v�́u���v���S���҂���d�b���������B
�u�������f�ڂ����Ē����܂��B���ẮA���j���ȏ��̒��ɁA�Q�O���A�R�O���Ƃ��������܂ŋL�q����Ă���Ƃ����܂����A���̋��ȏ����������ł��傤���B�v�Ƃ�������ł���B�����Ŏ��́A����Ƃɂ������u�������Ёv�̒��w�Z�Љ�ȁi���j�I����j�̎��̈�߂�ǂB�@�u���{�R�́A�ؖk���̂��A����Ƀi���L���i�싞�j�N�U���āA�e�n�ő����̒������O�̐�����D���A���̐�����j�đ傫�ȑ��Q��^�����B���@�s�r���t���@�i���L�����̂������{�R�́A���T�Ԃ̂������ɁA�s�X�n�̓��O�ő����̒����l���E�Q�����B���̎��҂̐��͕w���q�A�q�����ӂ��ވ�ʎs�������łV�`�W���A��������Ă����m���܂߂�ƂQ�O���ȏ�Ƃ�������B�܂��A�����ł́A���̎E�Q�ɂ��]���҂��A�펀�҂��ӂ��߁A�R�O���ȏ�Ƃ��݂Ă���B���̎����́A�i���L����s�E�Ƃ��āA���O������������т����A���{�̈�ʎs���́A���̎�����m�炳����Ȃ������v�i�Q�V�V�v�j
�@�u���v���̒S���҂́u���肪�Ƃ��������܂����v�ƒ��d�ɗ�������ēd�b������B�@���ꂩ���T�Ԃ܂��A�\���҂���������Ɍf�ڂ���Ȃ��B���т��炵�ē�������u���v���W��Ɂu�ǂ��Ȃ��Ă���̂��A�̂���Ɩ��Ȃ���A����ɂ̂�Ȃ����\�\�v�Ɩ₢���킹���B�u���v���S���҂��u������Ƃ��҂��������v�Ƃ����Ă��炭�҂��������A���������l���̐��ŁA�u���ʂ̂����ōڂ�Ȃ��Ȃ����A�������炸�v�Ɩŕ@�����������悤�Ȃ������œd�b�͐ꂽ�B�@�������Ď��̂Q��ɂ킽��u���_�v�́A���ɓ��̖ڂ����邱�ƂȂ����苎��ꂽ�B�u�����v�̗[���Ɂu�[�C���v�Ƃ����R������������B�T���P�S���A�{������ҏW�ψ����ŁA�u�s�E�������Ƃ��ꂽ���v�Ƃ����ꕶ���f�ڂ��ꂽ�B���̒ʂ�ł���B
�@�s�E�E�E�E�ŋ߂��̖��ő����Ă���ЂƂɁA���N�̋��ȏ���肩��ĔR�����싞�����i�P�X�R�V�N�j�ł̋]���Ґ�������B�挎�Q�S���ɓ����n�قő���@�삪�J���ꂽ��O�����ȏ��i�ׂł́A���ȏ����苭���̎���̒�����A�ے��I�Ȑ���ɑ��_�����ڂ��Ă��邪�A���̈���u�싞��s�E�v�ł���B�����Ȃ��u�C���v��������ЂƂ͎E���ꂽ�l�̐������A���̒������̈ӌ���ǂނƁA�Ȃ�Ɓu�P�|�Q���v�Ƃ����������������Ă���B���Q�ґ��̐��{�̌��芯�Ƃ��Ă̒����ł́u�R�O�����l�v�Ƃ��u�R�O���l�v�Ƃ������\�����蒅���Ă���B�i�����j
�@�s�s�ł̑�ʋs�E�̏�Ƃ��āA�����Ȓ�����m�Ȑ����͉i�v�ɕs�\�����A�������炠����x�̑傴���ςȐ����͂ł��悤�B���̓~�A���{�R�㗤�_�̍Y�B�p����A���̐i�����[�g��싞�܂ł��ǂ��Ē������Ă������A���̖��ɂ��Ẵq���g�����̂��ړI�̂P�ł������B�S���\�l�̐����҂����Ɍʂɖʐڂ������ʁA���悻���̂悤�Ȃ��Ƃ�������Ǝv���B
�@�싞�����ɂ��Ă͂��́u���v�Ɓu�ꏊ�v�̂Ƃ炦���Ő������傫������Ă���B�u���v�ɂ��ẮA���{�R���싞������S��̂����Ƃ����P�Q���P�R��������ꎮ�̂P�V���܂ł́u�T���ԁv�Ƃ�����肪�����ŒZ���B�܂��u�ꏊ�v�ɂ��ẮA�싞�s�́u�s�X�n�v�����Ɍ��肷��������ŏ��͈͂ł���B���������̍ŒZ�E�ŏ��̏ꍇ�ł��A�u����v�Ƃ��u���S�v�̒P�ʂ̏W�c�s�E���e���ōs��ꂽ���Ɓi���̊�ՓI���Ҏ҂����������Ă���j��A�����̋L�^�f��i���{�����J�j�E�ʐ^�Ȃǂ���l����Ƃ��A�u�P�|�Q���v�Ƃ��������͂ǂ��ɂ����Ȃ����͂��ʂ��B
�@�����A���̂悤�ɂ��Ƃ��班�Ȃ����Əꏊ�Ɍ��肷�邱�Ǝ��̂ɂނ���{���I��肪����B�P�R���̂P���O�̂P�Q���ɍs��ꂽ�s�E�������ʂ��Ƃ̓i���Z���X�����A�s�X�n���������ꂽ��݂������ʂ̂���Ȃ��Ƃ��B�ƂȂ�ƁA�ǂ����ɋ��E���������Ǝ��̂ɖ������łĂ���B�@�܂Ƃ܂����S�̂Ƃ��Ė����̂Ȃ����߂́A�싞�U���̊J�n�i�P�P����{�j���獬���̂قڏI������Q���͂��߂܂ł̖�R�����Ԃł��낤�B�����Ȃ�Ƃ܂����\���������������˂邱�ƂɂȂ邪�A�u�싞�U����v�Ƃ����s�בS�̂���싞�s��_�ł̌ܓ��Ԃ����藣���i���Z���X����܂���������Ȃ��B�W�c�s�E�͍Y�B�p�㗤���ォ��싞�܂ł̓r��e�n�ōs��ꂽ�̂�����t�@
�@�܂��ƂɊ�L�e���c�Ș_���ł���B��́A�{�����͉������������̂��H�܂�肭�ǂ��A�u���v���ǂ����Ƃ��u�ꏊ�v���ǂ��Ƃ������Ă��邪�A�v����ɒ������̌����u�싞�s�E�R�O���l�v�����m���Ƃ������Ƃ����������̂��낤�B�������̂R�O�����l�Ƃ����l�Ԃ��싞�ɂ͂��Ȃ������\�\�\�Ƃ������Ƃ�{�����͒m���Ă���B�����łR�O�����l�̋]���҂���邽�߂ɂ́A�u���v���̂��A�u�ꏊ�v���Ђ낰��ق��Ȃ��B�����Ŗ{�����͂���������ȁA�����ٔ��ł������łȂ������_�����u�`�������̂ł���B���͌����B�u������싞��s�E�͓��{�R�̓싞��̒���ɓˑR�������������ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�s�E�E�\�s�́A�Y�B�p�㗤���ォ��n�߂��Ă���A�i�����j�s�E�E�\�s�͓싞�ւ̓r��Łg�P���h���݂Ȃ���i�݁A���͂�K����������R�ƂȂ��āA�싞�ւȂ��ꂱ�ς�����v�����u�싞��т͑�l��������A���������đ��ΓI�ɋ]���҂̐����傫���Ƃ������������āA�{���I�ɂ͂��̎����́A�싞�U���J�n�̏\�ꌎ��{����A�ח�����߂��Â����g�������h���Ԃ��܂ޖ�O�����Ԃ̏o�����A�ƂƂ炦��̂�����ɂ������Ă��邾�낤�v�i�u�����v�R���R�O���t�u�싞��s�E
�S�U�N�v���j
�@�܂�A�u�ꏊ�v�Ɓu���ԁv���Ђ낰�Ȃ����Ƃɂ́u�R�O�����l�v�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ��������ł���B�Ƃ������Ƃ́A���Ԃ��Č����A�싞�ł͂R�O�����l���̑�ʎE�C�͂Ȃ������Ƃ������Ƃ�F�߂����Ƃł���B
�@�w����œ싞��s�E�x�̒��҂ł��铴�x�Y���ɂ��Ă��{�����ɂ��Ă��A���悻�u��s�E�h�v�̗��_�́A�퓬�ɂ�鎀�̂ł��������̎��̂͂��ׂċs�E�Ƃ��Đ�����B�ߗ������炢���Ƃ����،�������A���������ɋs�E�ɂ���B���̑��������̂̐��A��悩��E�o���ꂽ�ֈߕ��i�Q�����j�̐��E�E�E�E�E����炷�ׂĂ���s�E�҂̐��Ƃ��Čv�Z�����̂ł���B�@�Ⴆ�ΑO�f���Ŗ{�����́u�\�O���̈���O�i�싞�ח��̑O���j���\����ɍs��ꂽ�s�E�������ʂ��Ƃ̓i���Z���X���v�Ƃ����Ă��邪�A����͈�̂ǂ������Ӗ��Ȃ̂��B�\����͓싞��ɓ����������{�R���A�싞��̎�肪�ӊO�Ɍł��A��F�̂����˂����z���A��ԏ���ڎw���āA�E�҉ʊ��Ɉ���ꓬ���d�ˁA�����̋]����������ꂽ����ł���B����Ȏ��ɁA�ǂ������u�s�E�v���������Ƃ����̂��낤���B�{�����̂����u�s�E�v�Ƃ͂����������Ȃ̂��H�퓬�s�ׂœG���E�����A���ł��邱�Ƃ��u�s�E�v�Ƃ����̂��낤���B
�@�����A�싞�s���̐l���͂ǂ̂��炢���B��̏\���ڂ̏\��\�O���ɂ́A�싞�Ɏ����ψ���������A�ψ����ɂ͍]�J�l�̓����R������ꂽ�B���{�R�͂��̓����璆���l������̂��ƂɁu�ǖ��v�����t�����B����͗ǖ��̒��ɕ��ꍞ��ł���s�c�����������邽�߂ł���B���̂Ƃ����{�R�ɓo�^���ꂽ�s���͂P�U���ɒB�����Ƃ�����B���������̒��ɂ͂P�O�Έȉ��̎q����N�V�����w�l�͂ӂ��܂�Ă��Ȃ������B�����S���܂߂āu�Q�O���l�v�Ɛ��肵���u�싞���S�捑�ۈψ���v�̋L�^�́A����قǑ傫�Ȃ���܂�łȂ��Ƃ݂Ă悩�낤�B���x�Y��w�����푈�j�����W�x�ɂ��ƁA�u���S��i���j�ɂ͌����@�ւ̌����𗘗p���ď\�������̔����e�����݂����Ă����B�����̌����������ɂ͏\�\�������݂Ŗ�T���l�����e����Ă������A�\���{����ꌎ���̍Ő����ɂ͂��ꂪ�Z������l�Ȃ��������l�ɂ��B�����v�B���̂ق��Ɂu���e���ւ����炸���S����ɏZ��ł������̂��Z������l�����Ƃ����B�v���̑����S����̎��@�i�Ɓj��e���g�����ҁA���ӂ̏Z���������킹�āA���\���ƈψ���͐��肵�Ă����B�@���S��i���j��
�����̂́A�������̈�p�ŁA��͊����H�A�����瓌�k�͒��R�k�H�i���݂̐l���k�H�j�A�k�͎R���H�A���͐��N�H�Ɏ��͂܂ꂽ�l�D���L���̖ʐςŁA������ʐς̔����̈�ɂ����Ȃ��B�����������ɂ́A���ˑ�w�A���ˏ��q�w�@�A�����@�@�A���{�̎��فA�ۘO�a�@�Ȃǂ̌��������������A�����R�l�⊯���̊��@��O�l�E�x�T�K���̓@��������B���̒n����Ǘ������̂��O�l�������ŁA�Đl�����A�p���l�l���A�h�C�c�l�O���A�f���}�[�N�l�ꖼ�A�v�\�ܖ�����Ȃ�u���ۈψ���v�ł���B�@�싞�s���n���r�́A�\����A�S�s���ɑ��āA�s���͂��ׂĈ��S��ɈڏZ����悤�Ɍ������A��ʎs���͎O���S�̃����P�����A����я\���h���̏����������ۈψ���Ɉϑ����āA����͑D�ŒE�o�����B�Ӊ�A�v����A�����ԁA�����U�獑�����{��]���싞��E�o�����̂͏\�����ł���B��������������K���́A���Ă����̎����������Ԃ�g���b�N��D�ɐς�œ싞����ɂ����B�������͓d���������A�d�b���r�₦���B�@���̂��납��͓싞�͊��S�Ȗ����{��Ԃɂ�����A��������s���ɂ�闩�D�A�\�s���s��ꂽ�B����ɂ͏���R�i�ߊ��́u�~���������v����s�@�ŎT�z���ꂽ���싞�h�q�i�ߊ������q���R
�͂�������ۂ����B���͐����O����u������v���������Ă����B������Ƃ͏Ă��������̂��Ƃł���B�j���[���[�N�E�^�C���Y�̃_�[�f�B���L�҂́A���̎S����Ԃ��ɕ��Ă���B�ނ͂�����u�Ă������̋����v�Ƃ����Ă��邪�A��O�̂��������������|��Ԃ܂ŏĂ������A���C�̂��Ƃ������⎖�����Ԃ��j�A���D�����B���̑��Q�́A����܂œ��{�R�̋�P��C���̗^�������Q�̏\�{�ɂ�����ƕ��Ă���B�i�����ٔ��ł͂���炪�S���A���{�R�ɂ��ƍs�ɂ��肩����ꂽ�j
| �� �� |
�@���@�@�@�� | ���a �N�E���E�� |
�l�� �i���l�j |
���l | |
| �� �� �� �� �� �� �� �� �� |
T�@6�� T�@9�� T14�� T19�� T22�� T24�� T26�� |
J20�� J26�� J41�� J43�� J46�� J47�� J49�� J54�� J68�� |
12.12.17 12.12.21 12.12.27 13. 1.14 13. 1.17 13. 1.18 13. 1.19 13. 1.22 13. 1.28 13. 2.10 |
20 20 20 25�`30 25 25 25 25 25 25 |
T�@�F �e�B���p�[���[�u�푈�Ƃ͉����v�E�i�O���l�̌������{�R�̖\�s�j J�@�F ���@�i��u�싞���S�����āv |
| �� �v |
���ۋ~�ψψ���� �싞�n��ɂ�����푈��Q |
12.12.�`13.3. | 221150�l | �X�~�X���m�Ə���ɂ�鐄�v | |
| �� �� |
�A�����J��g�ٕ� �h�C�c��g�ٕ� |
13. 1. 13. 1. |
20�`25 20 |
�G�X�s�[�� ���[�x�� |
|
| �� �� |
���`�� M�ES�E�x�C�c |
21. 7.26 21. 7.29 |
20�`30 221000�l |
�ɓ����یR���� �����@���،� |
|
| �Q �l |
R�EO�E�E�C���\�� | 21. 7.25 | ��100 12������50 |
���� �ۘO�a�@��t |
|
�@�@���̂悤�Ȉ��@�����̒����A�s���͈��S�����߂āA�قƂ�Lj�l�c�炸�A���S����ɐg���悹���B���̐��������ނ˓�\���Ƃ�����̂ł���B
�@�E�̕\�́A���{�R��̒���̏\�O�����痂�N�\���܂ŁA���ۈψ���A���S����O�̎�������{�R�̖\�s�A���邢�͐H�ƕ�[���Ɋւ���Z�\��ʁi���j�̓��E�āE�Ƒ�g�قɂ��Ă����͂̒�����A�l���ɂӂ�Ă���ӏ��𒊏o�������̂ł���B�E�̕\�����Ă������������B�\�\�O���̓싞��̒���̐l����\������킸���O�T�Ԍ�̈ꌎ�ɂ͂���ƁA�l���͓�\�ܖ��ɑ����Ă���B�܂����A���ǂ�ǂA���Ă���̂��B���̑�O���l����݂��l���̐��ڂ��炨���͂����Ă݂Ă��A�싞�Ɂu�O�\�����v�͂��납���Ƃ����P�^�̋s�E���������ȂǂƁA�ǂ����Đ����ł��悤���B�{�����������悤�Ɂu���v��܂ʼn������悤�ƁA�l���͑��������Ȃ̂ł���B����R�i�ߊ��̓����̐w�������ɂ́A�u�ډ��싞��������Z�Җ�O�\���̐l�����\���]�͏���ɕ��A���ĊT�ˉ�R�ɐe���݂���v�Ƃ���B�{�����͓싞�Łu�g����h�Ƃ��g���S�h�̒P�ʂ̏W�c�s�E���e���ōs��ꂽ�v�Ƃ������A����ȂԂ������ȁg�s�E�̊X�h�ɂǂ����Čܖ����\�����̎s�����������X�ƕ��A���Ă���ł��낤���B
�����Ŏ��́A���̖{�����́u�s�E�������Ƃ��ꂽ���v����ǂ��Ă����y�����Ƃ��āu��O�҂̌����g�싞�s�E�h�̐��v�Ƃ����ꕶ�𑐂��āu�����v�́u���v���ɓ��e�����B�܌��\�ܓ��̂��Ƃł���B
�@�s��O�҂̌����g�싞�s�E�h�̐��B
�{���\�l���t���[���ɖ{�����ꎁ���u�s�E�������Ƃ��ꂽ���v�Ƒ肵�āu�싞��s�E�v�Ɍ��y���A��Ș_��W�J���Ă���B
�@���{�R����̂������̓싞�̐l���͖��\���i�싞���S�捑�ۈψ���\�j�ł���A�싞��������������R�͖�ܖ��Ƃ����Ă���B��l�c�炸�s�E�����Ƃ��Ă���\�ܖ��ł���B�Ƃ��낪���{�R��̂���킸���O�T�Ԍ�̏��a�\�O�N�̐����ɂ́A�싞�̐l���͓�\�ܖ��ɑ����Ă���̂ł���B�i�O�f���ۈψ���\�j�]���Ăǂ��v�Z���Ă��O�\�����̋s�E�͐����̏�łȂ肽���Ȃ��\�\�Ƃ������Ƃ�{�����͏�
| ���@�@�@�t (1937 - 1938) |
�� �S �� �� | �� �� �� �� | �f�v�� �ꂽ�� ��** |
������ ���@�v |
���m�̖\ �s�ɂ�� �����҂� �䗦(���j |
||||
| �R�� �s��* |
���m�� �\�s |
�s�� | �R�� �s��* |
���m�� �\�s |
�s�� | ||||
| 12��12���ȑO 12��12�A13�� 12��14���`1��13�� 1��14���`3��15�� ���t�s���̂��� |
600 50 �\ �\ 200 |
�\ �\ 150 �\ �\ |
�\ �\ 150 �\ �\ |
50 �\ �\ �\ �\ |
�\ 250 2200 �\ 600 |
�\ �\ 200 �\ 50 |
�\ 200 3700 250 50 |
650 550 4550 �\ 1000 |
�\ 91 92 �\ 75 |
| �v | 850 | 2400 | 150 | 50 | 3050 | 250 | 4200 | 6750 | 81 |
| 12��13���ȍ~�̖\�s�����̔䗦�i���j |
89 | 90 | |||||||
�m���Ă���B�����Ŏ��́A�u���̂悤�ɂ��Ƃ��班�Ȃ����Əꏊ�Ɍ��肷�˂��Ǝ��̂ɂނ���{���I��肪����B�Ə̂��āA�u�싞��s�E�v�Ƃ����̂́u�싞�U���̊J�n�i�\�ꌎ��{�j����͂��܂��ė��N�͂��߂̖�O�����ԁv�Ɗ������������A�ꏊ���Y�B�p�㗤����싞�܂ł͒����������\���Ă���悤�ȋs�E�͂Ȃ������Ƃ������Ƃ𗠕Ԃ��ĕٖ����Ă���̂ł���B�풆�싞�ɒ��݂����m�x�^�C���Y�̃^�[�f�B���L�҂́u���悻�l�̒����������{���ɂ���ď��Y���ꂽ���Ƃ͂��肤���B�i��(1)�j�v�Ƃ����\���œ싞���������|�[�g���Ă���B�܂����{�R��̎O������A�����̊w
�������Đ푈��Q���T�O�˂ɂP�˂̒��o���@�Œ��������X�~�X���m�́A���{�R�ɂ�钆���l�E�Q�Q�P�R�U�l�Ɣ��\���Ă���B�����̐��l�́u��O�҂̌����i��(2)�j�g�싞�s�E�h���ł��邱�Ƃ����m���ꂽ���t
���@�_�[�f�B���L�҂̓��ɂ킽��ڍׂȃ��|�[�g�̒��ŁA�ނ͓��{�R�ɂ��w���E�q���ȂǃV�r���A���̎E�Q�Ȃǂɂ͑S���G��Ă��Ȃ��_�͒��ڂ��ׂ��ł��낤�B�ȓ��L�҂́A�s������������ɂ��đ��������S�����Ӊ�͂��ߒ�����]�̖��ӔC�ȍs������A���ꂪ�u�S�ʓI�j�łւ̍��}�ƂȂ����v�Əq�ׂĂ���B
�@���A�X�~�X���m�͋��ˑ�w�̊w�����������āA��l��g�ƂȂ�A�\�˂Ɉ�˂̊����ʼnƑ��̔�Q�̕�����蒲�����s���Ă��邻�̌��ʂ͕\�Q�̒ʂ�ł���B�X�~�X���m�́u���m�v�̖\�s�ɂ���ĎE�Q���ꂽ���l�S�̂����ɂ́A�������ɂ��E�Q������A���{�R�ɂ����̂��̂W�X���̓��S�O�\�Z�l�ƌv�Z���Ă���B�푈����̂��̉Ȋw�I�ȋM�d�ȏ؋��𓌋��ٔ��͋p�������B���̗��R�͎��S�Ґ������܂�ɂ����Ȃ���������ł���B�Ȍ�u�s�E�h�v�͂��̑�ꋉ�����ł��钲���f�[�^��p���邱�Ƃ����Ȃ��B
�@
| �E�l | ���Q | �A�s | ���� | ���D���̑� | ���@�l | |
| 12��13�`20�� 21�`31�� |
28 |
14 2 |
337A 20B |
134AB,AB,AB 120 |
48 11 |
No.114�`136 No.155�`164�i���j |
| 1��1�`10�� 11�`20�� 21�`31�� |
4 6 5 |
4 1 11 |
2 3B 26 |
13 3BB 68B |
1 5 66 |
No.204�`209�� |
| 2��1�`7�� | 6 | 12 | 2 | 21 | 48 | |
| ���@�@�v | 49 |
44 |
390 �@A �@BB |
359 �@�@�@AAA BBBBBB |
179 |
No.1�`No.444 �����@405�� |
�@�����̓싞�s���̑S�l����\���Ȃ�����\�ܖ��̂����A���{�R�ɂ���ĎE�Q����A�A�s����A�������ꂽ�҂����l���邩�A���ۈψ���͂����莦�����L�^������B
�\�ܐl�̍��ۈψ��͂����ނ˔����I�ȓG�����l�ł��邪�A���̏\�ܐl�ƍg�����x�l�b�`�̐E���Ȃǐ��\�����A���{�R��̉��̓싞��������܂Ȃ��l�Z�����T�����A������L�^���āA���{��g�قɒ�o���Ă���A����Γ��{�R�ɑ�����\���̂悤�Ȃ��̂ł���B�\�\�l�����痂�N�̓\����܂Ŗ�Z�\���Ԃ̂������ɒ�o���ꂽ�����́A��ꍆ���������Z�\�㍆�����܂ŘZ�\��ʁA�����ɂ��Ďl�S��\�܌�����B���̒��ɂ̓f�}����A�����A�����i�����Ԃ�j�A�֒�����ŁA�M�p������̂��������A�����S���u���v�Ƃ��ē��v����Ǝ��̕\�R�̂��Ƃ��Ȃ�B
�@���̘Z�\�㍆�����́A��N���i��́w�싞���S���c�āx�ƃe���p�[���[�́w�O���l�̌������{�R�̖\�s�x�i���@�j�̗����ɋL�ڂ���Ă���B�����͂�����_�[�f�B���L�҂͂��ߓ��O�L�҂̃��|�[�g�A�O�o�̃X�~�X���m�̒������A�e�����̐퓬�ڕ�A����叫�̐w���������̑����������ނ�L�^�Ƌ��ɑ�ꋉ�j���i�����j�ƌĂԁB���̑�ꋉ���������邩����A�싞�Ɂg��s�E�h�͐�Ȃ��B
���̕\�͔q�R�������O�L�̑�Z�\�㍆�����l�S��\�܌��̓��{�R�ɑ������ʂɓ��v�������̂ł���B����ɂ��ƎE�l�͎l�\�㌏�ł���B���Q�l�\�l���A�A�s�O�S��\�v���X�E�A���t�@�A�����͑����ƋL�ڂ��Ă�����̎O�A�����Ƃ���ƋL�ڂ�������̘Z�A�͂����萔���Ŏ����ꂽ�v�͎O�S�\�㌏�ł���B�O�������ƍs�������ɂ��A��̒���̓싞�̎�ނɓ������������ʐM�̑O�c�Y��L�ҁi���E���{�v���X�Z���^�[�ꖱ�����j�͕M�҂ɂ������B
�@�u�s�E�Ƃ͐푈�ɊW�Ȃ��Z����w���q���ނ��ɎE�Q���邱�Ƃ��낤�B�Ƃ��낪�E����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Z���w���q�́i���j���ɂ����āA���{�̌x���i�ߕ��ɂ���ĕی삳��Ă����B���̏������Ă��������ʐM�̋��x�ǂ͂��̒��ɂ������B����l���ڂɂ͎������͑S�����̎x�ǂɋ����ڂ��A�����ɐQ���܂肵�Ď�ފ��������Ă����B�܂�������������̐��������ŁA���łɏ��X���X���J���A�I�V����哹�|�l�܂ŏo�āA���퐶�������Ă����B���̒n��̏��͂��������������̎��ڂɓ����Ă����̂��B�����������ŁA���͂��납�A��A�S�A���邢�͏\�������Đ�����قǂ̋s�E�ȂǍs���悤�͂����Ȃ��B��������A���������������͂����Ȃ��v�ƌ�����̂ł���B
�@����叫�̐w�������⍖���L�ɂ��ƁA�叫�͓싞������ς܂��ď�C�œ��ɂ킽��O�l�L�҂��W�ߋL�҉���s���Ă���B���̉�Łg�s�E�h�Ɋւ��鎿��͂ȂɈ���Ă��Ȃ��B������肩�j���[���[�N�E�^�C���Y�̃A�x���g�L�҂���������āA�싞��̂Ɋւ��鍑�ە]���⍑�ې��_�̓�����u�˂Ă���B�����ł��叫�͂��̂��Ƃ��Ă��Ȃ��B�����̒����V�����ӂ��ߊO���V���̂ǂ��ɂ����̂悤�ȋL���͂̂��Ă��Ȃ��B�싞�ɓ��邵���S��\�l���̓��{�̃J�����}������h�L�҂̂����N��l�Ƃ��āg��s�E�h�̑��݂�m��Ȃ������̂ł���B�Ɠ��l�A�\���l�̊O�l�L�҂��A�싞�ɋ��c������l�\���̊O�l���A�g�q�]��̌ܐǂ̕ĉp�̊͑D������g��s�E�h�͌��Ă��Ȃ��̂ł���B�������ł͂Ȃ��A���̗��N�\���A��C���݂̊O�l�L�Ғc�\�������A�Ԃ��ɓ싞�̐�Ղ����@���Ă��邪�A���̎����g�s�E�h�̎���͂Ȃ������ƁA���������ʐM�싞���h���̏��R���v�����i���E�����h���S���Y�В��j�͏،����Ă���B
�@�������g�ɂ������u�싞�s�E�v���L�^���������͂ȂɈ�Ȃ��B�u�e�B���p�[���[�̕ҏ��i���@�j�Ɋ��s����̏����͗�O�I�Ȃ��̂̂悤�Ɍ�����v�Ɓw�،��E�싞��s�E�x�̉���ҕP�c���`���͎��̂��Ƃ��q�ׂĂ���B�u�싞��s�E����O�A�l�N�����Ĕ��s���ꂽ�����̒��ɂ��A���̎����̂��Ƃ͂�����Ƃ��ĐG����Ă��Ȃ��v�i������ꔪ�v�j
�@���{�̒��w�E���Z�̗��j���ȏ��ɂ́A�u�������{�͍��ۓI�������т��v�Ƃ��邪�S�R�E�\�ł���B���Ȃ��Ƃ��O�L�̈ꋉ�����̒��ɂ́u��s�E�v�̕З��猩������Ȃ��B
�@�����̐V�����̑��̋L�^�͂��̋t�ł���B
�@�싞�s���ł��ۘO�a�@�⒆���a�@�\�\�����ɂ͒����̔s�c���������a�炵�Ă������A���{�̉q�����́A���{�R�̏��a���Ɠ��l�ɁA�������A�H�Ƃ��^�сA��т̂܂�������{������āA���ӏ�܂ŎĂ���̂ł���B
�@���ɋ~��������A���c���ɂ͕��~���N��z�����A�q�������ɂ̓L������������^���Ă���B
�@�u�����V���v�͂����������i���u�ʐ^���W�v�ɑg��ŁA�ǂ̐V�����������ɁA�M�S�ɕ��Ă���B�������x���x�ł͂Ȃ��B�\��\���t���̒����́u���a�S��싞�v�Ƒ肵�āA���y�[�W���l���̎ʐ^�Ŗ��߂Ă���i�\�����A�͑����h���B�e�j�B�����ɂ͑������u�c�R����Ɉ��g���Ĕ����k���_�������̎p�v��u�c�R�ɕی삳�����̌Q�v�����낼��A���Ă���ʐ^���̂��Ă���B
�@����ɗ���\����ɂ́A�O�ʃg�b�v�ܒi�k�L�ŁA�u�R���̂���ږY�ꂽ�싞�s��/��������e����/�g�ޗǂ̎��h�Â���z�����i/�G��s�ɔ���Ȗ��N�v�Ƒ肵�āA��R���h���̏\������d���A�~���N�ʔz���̕��i�ʐ^�Ƌ��Ɍf�ڂ��Ă���B
�@���̗����̓�\����A�܂������y�[�W���Ԃ��āu���̂ӂ̓G�ɉ���/�싞����̐e�P���i�v�Ƒ肵�āA�ʐ^���W���s���Ă���i��\���A�͑����h���B�e�j�B�����ɂ͓��{�̌R���Ō앺�Ɏ��Â��Ă���x�ߕ��̎p��A�u�c�R�����̏�ɐH�~�������~���v�Ƒ肵�ē�l�̓��{�����U���ɓ��ꂽ���т�z�����Ă���ʐ^������ʂ��ɂ���Ă���B
�@����ɓ�\�ܓ��ɂ��u�싞�͔��ށA����_�`�v�Ƒ肵�āA�܂������y�[�W�߂��ʐ^���W������Ă���i�ѓ��h���A��\�O���B�e�j�B�����ł͓��{�̕�������ƗV�Ԏq���B�̖��邢���V�Y�̖͗l�𑽖ʓI�ɂƂ炦�Ă���B�ѓ��h���́u�x�ߐl�̎q���̖��S�ɗV�ԗl�߂āA��������͍��ɑ҂킪���Ƃ��q���Â�ł���̂��B�g�V���L�҂ǂ́A���x�莆�����݂̂܂��h�Ǝv���o�����悤�ɍ��ւ̕ւ���肤�̂ł���B�v�ƃR�����g���Ă���B����̒�ŃI���K���ɍ��킹�Ď^���̂��̂��Ă���S���߂������k�̎ʐ^������B�����͂���ɁA�u������荇���ĉz�N/���ɐ[�ޓ싞�̓��x�e�P�v�Ƒ肵�Č܉�ڂ̎ʐ^���W��g��ł���B
�@�Ȃ��������̂悤�ɂ��ǂ��ǂ����u�����V���v�����p���A���{�R�̓싞��̌�̎s�X�̏�������邩�Ƃ����ƁA�����ٔ��ɂ����钆�����̏،���{�����ꎁ�ɂ��ƁA���{�R�ɂ��w���E�q�����ӂ��ގO�\�����̋s�E���s��ꂽ�v�Ƃ��A���邢�͑g�D�I�A�W�c�I�ȕ��A���D�A�\�s���̕s�@�s�ׂ���̒��ォ����߂܂ŘA���̂悤�ɑ������Ƃ����Ă��邪�A�������ꂪ�u�����v�Ȃ炱�̌܉�ɂ킽��ʐ^���W�̉�ʂɉf���ꂽ�u�����v���A�{������u�����v�̕ҏW�X�^�b�t�͓ǎ҂ɂǂ���������̂��A���͂���������̂��B�{�����ɂ��Ă��A���́u�����v�̕ҏW�X�^�b�t�ɂ��Ă��A�l�\���N�O�A���Ŗ������Ŏ�ނ��A�����ɕ������N��̐�y�̂����̎ʐ^�݂͂���点�ʐ^���Ƃ����̂��H�R�Ɍ}�����邽�߂̃f�^�����̃C���`�L�ʐ^�ł���A�E�\�̋L���ł���Ƃ����̂��H�����ɐ킢�ɔs�ꂽ�Ƃ͂����A���Ȃ������Ԃ��悤�ɁA����܂ł̐�y�̎ʐ^��L���͂��ׂăE�\�ł����A�C���`�L�ł����A�f�^�����ł����Ƃ����āA�킴�킴���{�R�̋����ɏo�����A�G���̓��������̎q���������l�X�ɁA�܂�ŋ��������S���̌�p�����̂悤
�ɁA���̔�Q�����f�����āA��������̂܂܋L����ʐ^�ɂ��A���ꂱ�����싞�����̐^�����Ɣ��\����\�\����ȑԓx��������Ă������̂��ǂ����A�ǎ҂ɑ���u�̐ӔC�v�Ƃ������̂��A���������u�����v�͂ǂ��l���Ă���̂��₢�����B
�@���@�}���`�F�X�^�[�E�K�[�f�B�A���̃e���p�[���[�L�҂̒����́A���L�҂��싞�̗F�l�����ꂽ��������b�Ɉ��O���N�O���㈲�����{�ŁA�p�E���E���̎O������ɖ|��L���ƂȂ������A���͂��̒��́A�������{���ΊO��`�̂��߂ɏo�ł������̂ŁA��̊s���Ⴊ�����������A�Ӑ������Ŕ�����`��S�����Ă����ؘa�v�A���n�j�̗������|��E�����ɐs�͂��Ă���B
�@�u�����V���v�Z����\�O���t�[���̎Љ�ʂɁA���o���ܒi�k�L�ŁA�u�싞��s�E�ڌ��̒��R�V/�w��蕔�x�L�^�f���/�����ł̍u���Ȃǎ��^�v�\�\�Ƃ����L�������̖ڂ��Ђ����B�����ɂ̓A�S�E�Ɋዾ�̎��\��̒��R�d�v���̊�ʐ^������A�g�b�v�L���ł͂Ȃ����A���o���n�����̔h��Ȉ����ł���B�L�����e�͎��̒ʂ�B
�@�u�ꕺ�m�Ƃ��Ėڌ������싞��s�E����葱���Ă��铌���s�]�ː�敽��̒��R�d�v����i72�j�̋L�^�f�悪�߂���������B���̌܌��A�����̍����]��w�ōu�������͗l�𒆐S�ɁA���{�ł̊����Ȃǂ��O�\���A�P�U�~���J���[��i�ɂ܂Ƃ߂��B�푈�̎������،�����S������s�r���n�߂Ă��łɕS�\�����B�w���ʂ܂Ō�葱����x�Ƃ����g�푈�̌�蕔�h�ɂӂ��킵���A�薼�́w���R�V�̏،��x�ƌ��܂����v�����܂ł���������ŁA�{���́A�u���a�\��N�\�B�싞���ח��������A���R����͗��R��ԑ��̏㓙���Ƃ��āA���̏��Ԃ��Ɍ����B�w���͐������������B��Ԃ��C�����Ȃ���i�ޓ�������A�݁X�Əd�Ȃ鎀�̂̒��ɂƂĂ��퓬���ɂȂꂻ�����Ȃ�������V�l�������������Ă���̂����ĕs�v�c�Ɏv�����x�Y����Ȃ��͓̂싞����̓���O�A�x�O�̉J�ԑ�Ō������i�B�������f���Ă��钆���l�����i�����j�̏�ɍ��点�ẮA���{�������X�Əe���Ŏh���E���Ă����B��˂��ł͎��ɂ��ꂸ�A�ꂵ��ł���l���R�C�ō��ɂ����Ƃ��Ă͓y��������B�N���ł��낤���A�����Ȃ��ɎE�C���������B�w�l���ԗ]����Î����Ă����ł��傤���B����܂ł͍��̂��߁A�V�c�̂��߂ɂ͎d�����Ȃ��ƍl��
�Ă����̂��A���̓�����͂����푈�͂��₾�A�Ǝv���悤�ɂȂ����x
�@����т��Ă��̑̌�����葱���Ă����B�\���N�Ăɂ͐É��s�̒��w���@�X���F����̂W�~���f��w�N���x�Əo�������B�싞��s�E��O���������������̍�i�Ɂw�������t�Ō���Ă������Ƃ��f���ŏؖ����Ă��ꂽ�x�Ɗ����B����Ŕ������߂Ă�����g���u�����ĉ�����B�i�����j�g�푈�̌�蕔�h�Ƃ��Ă̊������A�����̌�������ɏЉ�ꂽ�B�{�N�O���ɂ͒����̃e���r�ǁA�����]�ȓd����K���c�����R������K��B���ꂪ���ƂȂ��Č܌��\��������\�l���܂œ�T�Ԃ̖K�������������B
�@�f��w���R�V�̏،��x�́A�\��������]��w�̓��{���U�w����S��\�l�ɑ���u���𒆐S�ɁA�n���s�����ӂ̐Έ䎵�O�ꕔ���ՂⓌ�k���j�L�O�ق�K�˂钆�R������Љ�B���{�ł̊������X�`�[���ʐ^�ő}�����Ă����B����̓����f�����ɂ��ƁA���ݕҏW�̎d�グ�i�K�ŁA�Z�����ɂ͊������������A�Ƃ��Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�~�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�~�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�~�@
�@�f��ɂ��Ă̖₢���킹�́A�����s������V��P�m�Q�Q�m�P�Q�A�j�b�e�C�r���X�O�Q�����f�����i�d�O�R�|�T�T�Q�|�Q�S�U�W�j�ցv
�@���R���̂��Ƃ́A���āu�����v�ɂ��ڂ������Ƃ�����A���͕ԐM�t���ŁA���Ђ��ڂɂ����肽�����A���s����낵�������E�ꏊ�����w�艺�����Ƃ����莆���o�����B
�@�Ԏ��̓i�V�̃c�u�e�ł������B���x�́u�����v�̋L���ɑ��A���̗F�l�x�́A�����f�����ɓd�b���āA���R����ƒ��ڂ��b�����������ǂ������炢���������B
�@���J��Ɩ����j���Ј����A���낢�닺�����Ă���̂ŁA���ژb�͂ł��Ȃ��A�v���̌����͎�莟���܂��傤�A�Ƃ������Ƃł������B
�@�����łx�́A���J�쎁�C�t�ŁA�u�N���v�Ƃ����f��������Ē�������A�u�����������������A���̂��߂ɂ́A�ǂ̂悤�Ȏ葱���������炢�����Ǝ莆�����B
�@���̕Ԏ������Ȃ��B
�@�����ł܂��A���߂Ē��R����̏��������������ė~�����ƍāX�d�b�����B����Ɓu���������͖Y�ꂽ�v�Ƃ����Ԏ����A���Ă����B
�@�����A������ԑ��̏㓙���ŁA�싞�U����������j�Ƃ��������ɏZ�ތ��݉�Ђ̎В������āA���̕������R����Ɩʐڂ����B���̎В�����̂������Ŏ��̂悤�Ȃ��Ƃ��킩�����B
�@���R�d�v���͑吳��N�ꌎ��\�ܓ��A�������O��S���쒬�厚�g�Ő��܂�A���a�\��N���������A���Z���͍]�ː�敽�䁛�����̓s�c�Z������������A��l��炵�ŁA�����E��Õی���Ă���Ƃ����B
�@�싞��ł̏����������͐�ԑ��A���i�⒇��ԑ��j�ŁA�K���͏㓙���A�i�ł���B�i��Ƃ́A��ԑ��̒e��E���a���̉^������яC�����ɔC�������C���̕����̂��Ƃł���B
�@���˂ē싞�������E�������Ă���L���s��쒬�ݏZ�̐��{�������i�����Ɨ��y���b�ԑ���������j�Ɋ⒇��ԑ��ɂ��Ē��ׂĂ�������B���̌��ʊ⒇��ԑ��́A�J�ԑ�̐퓬�ɂ͎Q�����Ă��炸�A�i�ٖ傩�璆�R��Ɍ������싞�X����i�����Ă��邱�Ƃ��킩�����B�J�ԑ�͋N�������A�J����͂���Œn�`���G�̂��ߐ�ԑ��͓˓��ł����A�����œ��{�R�͌y���b�Ԃ�����W�߁A�i���т�������w�����Đ���Ă���B�⒇��ԑ��Ƃ͑S�R�����ł���B����ȏꏊ�Ɋ⒇��ԑ��̒i����͂����Ȃ��B
�@�������O�Ƃ����Ώ\�\����̂��Ƃł���B�\���A�\����̗����͂��ƂɓG�̔��U���̂������A�g�[�`�J�ƓS��Ԃƒn���Ōł߂����̗v�ǂɗ������������F�s�{�̑�S�\��t�c�ƌF�{�̑�\�Z�t�c�̈ꕔ�́A�����̋]���҂�������ꂽ�B��j�ɂ��Ɠ싞��O�ɂ�����킪�R�̑��Q�͐펀��S�Z�A�����Z�S���\��A�폝���Z�A�G�̈�����̖�ܐ�Ƃ���B���̑啔���͂��̉J�ԑ�ł̎����ł���B�i��̕������l���Ԃɂ��킽���āA�ߗ�����l��l�˂��h�����܂������Ɓu�Î��v����Ƃ��������ł͂Ȃ��̂ł���B�����Ŏ��̓y�����Ƃ��Ď��̂悤�ɋ^�╄�𓊂��������B�Z����\�Z���̂��Ƃł���B
�@�s�������O�͉J�ԑ�匃��B
�@�{���Z����\�O���t�[���Ɂu�싞��s�E�ڌ��̒��R�V/�w��蕔�x�L�^�f��Ɂv�ƌܒi�k�L�œ����s�]�ː��̒��R�d�v���̒k�b���f�ڂ���܂����B����ɂ��ƒ��R����͓싞�u����̓���O�v�x�O�̉J�ԑ�ŁA�������f���ė��钆���l���s�E���Ă����ʂ��l���Ԃɂ킽���āu�Î����Ă����v�Ə،����Ă��܂��B���͋^��Ɏv���đ����W�҂ɂ������Ē��ׂĂ݂܂����B
�@�@���R����̏�����������ԑ��i�⒇��ԑ��j�͉J�ԑ�ɂ͓˓����Ă��܂���B�A�܂��ĎR������͊⒇�����̒i��i�A�����Ō���Ζ��j�ł�����J�ԑ�ɂ͍s���Ă��Ȃ��͂��ł��B�B�u�싞�������O�v�Ƃ����Ώ\�\����̂��ƂƎv���܂����A�J�ԑ�̐퓬�́A�������\����ɂ����đ匃�킪�W�J���A���{�R������ꓬ�̖������̋]���҂��o���Ă��܂��B�ƂĂ��������f���Ă̑�ʍ~���Ƃ��A�l���ԗ]�ɂ��킽��E�Q��ʂȂǑz������ł��Ȃ�����̏C����ł������Ƃ����̂��A�����Ő����������l�\���A�������̏،��ł���A��j�ɂ������L�^����Ă��܂��B���R����͉������Ⴂ����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���A��x���ڂɂ����肽���ȑO���莆���܂������A���Ԏ��͒����Ȃ��܂܂ł����B��V���ł���u�����v�Ƃ����낤���̂����̂悤�ȋL�����������߂Ē��������A���ꂪ�̐ӔC���Ƒ����܂��B�������̒��������ł����炲�����������t
�@����ɑ��āu�����V���v�́A���̓�������������łȂ��A���̒����ɑ�����Ȃ������B
�@�u�����V���v�͎�����\�����A�u�싞��s�E������/�]�R���m�̎蒠����/���s�̐푈�W�v�Ƒ肵�đ傫�������B���̎蒠�ɂ͂��������Ă���Ƃ����B
�@�u�\�\�l�����V�@�͂��c�����i���j���傫�Ȉ�Ƃɐ疼�قǂ̓�ƈꏏ�ɂȂ��Ă����̂Łi���j��͂��c���炵�����̌ܕS��������o�����i���j�ꃖ�����������Ă͂ƂĂ��E�������ł��Ȃ��̂ŁA���@�֏e�i�����j�@�֏e�������̂݁A�Ȃ������̋@�֏e�Z�e�ŁA���e���S���W�܂�A�����̏�ւ��R����ɁA�͂��c���S�����W�߂āA�y�@�A�d�@�̈ꐺ�ˌ��ɂ��S�������E�����A����������Ȍ��i�������v�i�����̂܂܁j
�u�����v�͂��̋L�����S�̎�ł���������̂悤�ɂ�낱�сu�g��s�E�h���������킹��ӏ��������ɂ���v�Ƃ��A�Ⴆ�u���A���̔s�c���̑|���ŁA��O�Ɏl��l����W�߂Ă����v�i�����\�Z���j�ƋL���Ă���ƌ����A���s��̍L����G�������́u�R���g�D�I�ɋs�E���s�����������A�����Ҏ��g�̃����Ƃ��Č��������Ӌ`�͑傫���v�Ƃ����k�b�܂ł̂��Ă���B���Ȃ݂ɁA���̎蒠�́A�ǂ��������̂��A���s�̐푈�W�ɓW������邱�ƂȂ��A�u�����v�u�����v�u�Ԋ��v�̎O�Ђ������݂̂ŁA�p�������Ȍ����J��錾�A�g�܂ڂ낵�̎蒠�h�ƂȂ��Ă���B
�@�{�����ꎁ�͂��̋L���������āA�����O�\���u�����V���v�[���́u���|�f84�v�ɖ�l���̈�̎��ʂ�h��Ԃ���������̋L�����������B�ʔŔ��k�L�����o���ŁA�u�싞��s�E�E���ȏ��ٔ��Ɉ�v����Ƀ^�e�ɓʔłŁu�ꕺ���̐w�������ƌޒ����،��v�Ƃ��A�����Ɂu�s�c���c�炸�ˎE�q�w�������r/�q�ޏ،��r�|�ˁ��N�V�h�����Ă��v�Ƃ������ǂ����匩�o���ł���B
�@�{�����ɂ��ƁA���x�������ꂽ���s�̈ꕺ�m�̓����Ǝ������싞�ŕ�����肵���ޒ����،��Ƃ͕��߂������Ă���A���̓�،��͖ډ������n�قɒ�i���Ă���Ɖi�O�Y���̎咣����u�싞�ɑ�s�E���������v�Ƃ��铮���ʏ؋����Ƃ����̂ł���B
�@�{�������������ޒ������̘b�Ƃ����̂́A���̒ʂ�ł���B�\�\�ܓ��̔�������A�ގ��̂����������i�@�@�ɓ��{�����\�����ˑR�����Ă��Đs�N�j�q���O�֒ǂ����Ă��B���̌���������ǂ����Ă�ꂽ�s�N�ƍ��킹�Ă��悻���l�]��̈�c�������o�����̂��ߑO�\�ꎞ����B�r���u��s�f��فv�O�ɂ���炳��A����̃g���b�N�����āA��������͐w�ɉ�������B�ߌ�ꎞ���늿����ɒ������B���]���͖�̓����ł���点��ꂽ�B��\���قǂ̂��A��l�̓��{�����i���̗��[�������A�S�]�l���i���ŏ��O���[�v�ɕ������B���̃O���[�v�̂܂��������͂�Ŗ�̊O�ɏo���B��\���قǂ���Ɩ�̊O����@�֏e�̍������N�������B����܂ŕs���������Q�O�́A����Ō���I�ɋs�E�Ƃ��Ƃ����B
�@���̂悤�ɂ��Ĉ�O���[�v�����i���ŕ������Ă͖�O�ɘA��o����ċs�E���ꂽ�B�ނ���̑g�̔ԂɂȂ����̂��ߌ�����낾�����B�l��̋@�֏e����䂸������ĕ��сA���̊Ԃ���ނ����͓y��̎Ζʂɒǂ����낳�ꂽ�B��O�Ɏ��̂��w���Ȃ��Ă���̂������u�ԁA�ނ���͑O�ɂ�̂߂�悤�ɓ|�ꂽ�B�Ɠ����Ɉ�Ďˌ��ƂȂ�A���̂��܂�d�Ȃ��Ă����B�u���ꂿ���I�v�Ɛe���ĂԔߖ����������B
�@�@�e�̂��Ə��e�̑_�������̉��������B���ꂪ����ƁA�l�̂̑w�̏������C�z������A�Ƃ����Ȃ�w���Ɍ��ɂ��o�����B�����҂��������ďe���Ŏh���Ă����������A��ɓ|��Ă���l�̂��т��Čނ�����N�V�h���ɂ����̂��B�����Ɖ䖝���Ă���ƁA���x�͖؍ނȂǂ����̂̏�ɓ����A����ɃK�\�����������ĉ������B�ނ���͉̂���������E���̂āA���̂̊Ԃ��͂��Ȃ����ւƂт��B�j���̓��ӂ������ނ���́A��݂ɒ����Ɠ�S�\���[�g�����炢�͂��Đi�Ƃ���ŏ��M���݂��A���ɂ������{�����𒅂��B����ɂ͂��Đ쉈���ɓ쉺���A������̈ꌬ�̏Ă��c��̋Ƃɂ��낪�肱�B
�@���ꂪ�ޒ������̕���ł���B�{�����͂��̕�����Ȃ��Ȃ��Ə�i�`�ʂ������Ȃ���Ԃ������ƁA�ގ��̌��^�ɂ͂܂��������܂�u���͍K���ł��v�Ƃ����ё�^�ł̒��������߂������Ă���B
�@���̕���ɂ͊���̋^��_������B�@���̈��́A�\��N�\�ܓ��ɂ́A���{�R�͎i�@�@�̌����͂��Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ��A���ۈψ���̑掵�������ɋL�ڂ���Ă���B�]���Čގ��̑ߕ߁A�A�s�̓E�\�ł���B
�@���̓��́A�i�@�@���o�āA�������[�^���[�����։�钆�R�H�E�����H�͓����Ō�������ʂ�A���{���ʂ�ɕC�G����B�ߑO�\�ꎞ����ߌ�ꎞ�܂ŁA���]�l�������������{�R�ɘA�s����čs���̂��A�V���L�҂��������A�N��l�����Ƃ����҂����Ȃ��B���ۈψ���̎҂����̑厖����m���Ă��Ȃ��B
�@���̎O�́A�d�@�֏e�ˌ����͒ʏ�S�L������U�L���܂Ŗ苿���B���������傩���P�D�T�L��������̎��P�J�ɂ͑�l�\�ܘA���i�������j�{��������A����P�D�T�L���̐�����ɂ͎l�\�ܘA���̈ꕔ���A��Q�L�������̊ØI���ɂ͓Ɨ��R�C���A���̈ꕔ���A���̂���Ɉ�L����̍]����ɂ͑�l�\�ܘA����O��������Ԃ��Ă���B�����̏������̂����l���Ԃɂ��킽��d�@�l��̎ˌ��������Ƃ��������͈�l�����Ȃ��B
�@���̎l�́A�����H�̍�����т͓��ŁA���ۈ��S�ψ���̎������̂���C�J�H���������ς�������ˏ��q�w�@����ː_�w�Z�͂�������P�D�T�L������Q�L���̋����ł���B�d�@���ˉ��l���Ԃɋy�ԂƂȂ�A��\���̓�͖ق��Ă��Ȃ��͂����B���������ۈψ���̋L�^�ɂ͂��̂��Ƃ͑S���L�q����Ă��Ȃ��B
�@���̌��́A�g����̖�����ɂ��A���P���̖�����ɂ��A������O�̓��]�̎��̂������Ƃ����L�ڂ͂Ȃ��B�v����Ɍޒ������̈�l�̕���ł����āA����𗠂Â���T�͉����Ȃ��̂ł���B����ȕ��ꂪ�܂���ʂ��Ă������̂��ǂ����H�����Ŏ��́u�����V���v�Ɏ��̂悤�Ȕ��_�𓊍e�����B���������̂��Ƃł���B
�@�s�u�싞��s�E�v�̋\�ԁB
�@�{�������O�\���t�[���ɖ{������ҏW�ψ��́u�싞�s�E�E���ȏ��ٔ��Ɉ��/�s�c���c�炸�|��/�q�w�������r/�q�ޏ،��r�|�ˁ��N�V�h�����Ă��v�Ƃ����V���b�L���O�ȋL���ɑ��Ĉꌾ�������B
�@���̃��|�́A�싞�U����ɏ]�R�������s�o�g�̈ꕺ�m�̎蒠�i�w�������j����������u�����v�u�����v�Ƃ��w�u�싞��s�E�v�����Ɂx�Ƒ肵�Ă��̓��e�̈ꕔ�\�������A�{�����͂�����āA�����ٔ��ŏ،���ɗ������ޒ������̕������ƕ��߂���v����Ə̂��A�u�l��l��菭�Ȃ��炵�����A�Ƃ�������̃P�^�̋s�E�v���������Ƃ��āA���̖ڂɂ��܂�c�s�U��X�������l�����L���ł���B�Ƃ��낪���̋L���ɂ͍I���ȃJ���N���Ƃ������A�g���b�N�Ƌ\�Ԃ�����B
�@���̈��́A�ꕺ�m�̓����͏\���\�l���A�s�c���炵�����̌ܕS���̓�̒�������o���ďe�E�����Ƃ���B�{�����͂�������s�E�ƌ��߂��āA�S�̎�ł�������悤�Ɂu���ړ����҂ɂ�铖���̋L�^���v�Ƃ����ď���肵�Ă��邪�A�\�l���͓싞�ח��̗����A�|����̍Œ��ŁA�e���Ŏs�X�킪�s���Ă����B������B�����āA��̒��ɂ܂��ꍞ�݁A�ֈ߂łЂ���ł��邢����g�ֈߑ��h�Ȃ���̂́A�펞���ۖ@�̈ᔽ�ł���A�ߗ��Ƃ������Ă��̏�ŏ��Y����Ă�����͌����Ȃ����ƂɂȂ��Ă���B
�@���̓��́A�ޒ��������\���\�ܓ��i�@�@�ŕֈߑ��ƈꏏ�ɕ߂炦���A����l�Ƌ��Ɉ������Ă��āA������O�ŎˎE�����Ƃ����Ƃ��ꂽ�Ƃ����L�q�ł��邪�A����̓E�\�ł���B�\�ܐl�̕ĉp�Ɠ���O���l���Ȃ�u�싞���S�捑�ۈψ���v���싞�̓��{��g�قɂ��Ă��\�\�����t�掵�������ɂ��ƁA�\�\�l���A���{�R���Z���i�@�@�ɗ��ē�ƕֈߑ��Ƃ����蕪���Č���������ߕ߁E�A�s�������A�u�\�ܓ��ɂ͂��蕪���Ɉ�l�̏��Z�����Ȃ������v�Ɩ��L���A�u���\�Z���ɂȂ��Ă��̓�O���[�v�i��Ɏ�蒲�ׂ��Ȃ������������܂߂āj���琔�l�̒��������v���ĘA�s�����Ə����Ă���B�i���x�Y��E�g�E�i�e���p�[���[�ҁw�푈�Ƃ͉����\�\�\�����ɂ�������{�R�̖\�s�x�S�O�\��v�j����ƌޒ������̏\�ܓ��i�@�@������疼�Ƌ��ɘA�s���ꂽ�Ƃ����̂́A���U�̏،��Ƃ������ƂɂȂ�B
�@���̎O�́A���m�̐w�������̏\�\�Z���ɂ́u���A���̂͂��c���̂����Ƃ��ŁA��O�Ɏl��l�����W�߂Ă����v�Ƃ���B�����{�����́u���t�c�̕ʂ̘A�����l��l�����o�����̂�ڌ��A������s�E���ꂽ�炵���v�Ə���ɉ������A�����o���Ɂu�l��l���o���s�E���v�ƋL�q���āA�O�L�ޒ������́u�|�ˁ��N�V�h�����Ă��v�Ƃ����A���q�����܂߂Ă̎c�E�ɂ܂�s�E���i�ւƕ��͂��Ȃ��ł���̂ł���B�܂�u�l��l�����W�߂Ă����v���u�l��l���s�E�����v�ɘb���X���������Ă���̂ł���B���Ƃ�����ȋȕM�ł���B�@�{����������قǂ܂ł��ē��{�R�̍߉ȍ����ɂ�����ƂȂ�͉̂��Ȃ̂��B���ɂ͉���Ȃ��t�@
�@���̓��e���܂��A���̖ڂ����邱�ƂȂ��A�َE����Ă��܂����B
�@�{�����͌��_�������ɂ��鋤�Y�������֏o�����čs���A���̍�����悤�ɂ��ăJ�M�܂��A�����Ō���锽�����R�̉����̐��X�����̂܂܋L�q���Ĕ��\����Ƃ�����Ȑ��Ȃ̃��|�[�^�[�ł���B���ꂪ�^�����ۂ����^�����Ƃ�m��Ȃ��B�ᔻ�����Ȃ��A�܂��ē��{���̏،��⎑���Əƍ����邱�Ƃ����Ȃ��B�������������������̌������͕S�p�[�Z���g���������m�Ƃ��A���ꂪ�u�싞��s�E�v�̐^�����Ǝ����ԓx�ł���B�u���l�R�v��u���̋��v�̕�������̃f���ł���B�i�O���O�\���t�u�����V���v�j�B
�@�{�����̐����ɂ��ƁA��N�̏\�\�O���A�싞�s�͓싞��s�E�i������Łu�싞��j�E�v�j�l�\�Z���N�������ċL�O��̒�b�����s�����B���̏ꏊ�͓싞�鐅����̐��x�O�]�����̑�ʂ�ɖʂ�����p�ŁA���Ȃ���ʂ̐l�����w���Ȃ��Ė��܂��Ă���Ƃ���B���̋L�O�Ɍ��Ă�ꂽ�Δ�̎ʐ^�ƁA�u�ŋߎ��@���ꂽ�싞�����]���҂̖��l�R�̈ꕔ�v�Ƃ��Ĕ����͐ς̎ʐ^���傫���f�ڂ���Ă���B�{�����ɂ��ƁA���̖��l�R�͋߂������ɐ����ɔ��@����āA��ʂɎQ�ςł���悤�L�O�قƂ��Đ�������\��Ƃ̂��Ƃł���B���@���ꂽ���̔����̑͐ς��A���{�R�̋s�E�ɂ����̂ł���ȂǂƐ�`����邱�Ƃ͐r�����f�ł���A�����Ƃ����Ⴗ��B�����F�D�̏����̂��߂ɂ��A���̂��Ƃ��͂����肳�������Ǝ咣����l������B��Z�t�c�ʐM�Ǐ������̉L���q�菭�сi�����B�����s������ݏZ�j�͓싞�U���̏\�\������炱�̒n��̐퓬�ɎQ�����A�\��\��������{�Ɉړ�����܂ō]����t�߂ɒ��Ԃ��Ă���A�����ĕ�����l�\�ܘA����j�̕Ҏ[�҂ł�����B�L�����ɂ��ƁA�l�\�ܘA��������͏\�\�����㎞�A�]������̂����B����������F�����̉�z�L�ɂ��ƁA�G�����ł�
�ގU���A�X�ɐl�e�����A�d�����Ώ�̓��ɐ��ꉺ�����āA�s�C���ȐÎ₪�X����ł����Ƃ����B������͍]����ɏh�c���A���\�O�������A�Z�������ďo���A�O���͂ɂ����ēG�Ƒ��������킷��B���̑�����o���̂��ƁA��O�������͒�����]����ɓ����Ă����B����Ƃ�������ّ������Ǝv�����G���N�����Ă��Ă����܂��s�X��ƂȂ����B���̐퓬�ł킪���́A�����������d���A��ԏ������펀�A�ق��ɉ��m�����\�����펀�����B�G��������̖�S���c���đދp�����B�����̑͐ς͂��̐펀�҂̈⍜�ł���A���E�q���͈�l�����Ȃ��B���ׂĐ퓬���ł���B�Ȃ��]���吼���̐V�͒��ł́A�剒��тƂ��������\�ꒆ���ƍ����`�F���т̎w������R�C����эH���A�R���e�ꏬ����S�\�́A�\�O�����ŁA�������s�����Ă����G��ꖜ�ܐ�Ƒ����A��������l���Ԃɂ킽��匃���W�J�A���̐��œG�͓��O�S�̎��̂�������ē������Ă���i�킪���̎����ҎO�\�Z���j�B
�@���̂�������@��A�����͂܂��܂�������ł��o�ė��悤�B�����������͂��ׂĐ펀�҂̈⍜�ł����āA�f���ēj�E�i�s�E�j���̂ɂ��炴�邱�Ƃ���L���ׂ��ł���B
�@���ɖ{�����́u���̋��v�ɂ��Đ�������B
�@�u�Δ�̋߂��ɂ��镝�S�A�T���[�g���̉^�͂̋��́A���{�R�̓싞��̒���ɍ����}�R�i�Ӊ�ΌR�j�����j�������A��̌ケ�̂��Ƃ���ʂ̋s�E���̂Ŗ��߂��āg���̋��h�ƂȂ�A���̏����{�̃g���b�N���������Ă����Ƃ����B
�@�����̖ڌ��҂̈�l�E���a���i59�j���ƁA���́g���̋��h�̂����Ƃɑ�����̉Ƃ͂������B�ق�̏\���[�g���قǗ��ꂽ���H���킾�����̂ŁA���{�R�������Βʉ߂��Ċ댯�������A��S���[�g�����ꂽ�ƂɈ����z�����B�g���̋��h�͒f�ʂ���`��ɐς܂ꂽ���̂̏�ɁA�j�ꂽ�Ƃ̔���E���E�y�Ȃǂ��~����Ă������A���Ȃ�ł��ڂ�������A�����Ԃ�Ԃ�Ɠ��������������B�܂����N�̑�����́A�E���ꂽ��Ƀg���b�N�̋��ɂ���Ă��܂�����ʂ̐l�����āA���낵���Ɠ���Ō��t���o�Ȃ������Ƃ����v
�@�����ɂ������Ƃ��炵�����b�ł���B
�@�O�o�̉L���q�莁���A�V�͒��Ő���������`�F���сi�����B�v���Ďs�ݏZ�j��͌��𑵂��Č����B
�@�u���̋��i�]�����j�͔��j����ĂȂǂ��܂��B�����͂�������イ���̋���ʂ��Ă��܂����B��C���͂������l�B���������^�͂̕��͎l�A�\���[�g���Ȃ�ĂȂ��B����������A�O�\���[�g�����B�����̕����ɂ̓g���b�N�͂Ȃ������B�g���b�N�͕�⋂ŁA�\�l���ȍ~�̏�C�\�\�싞�Ԃ̕⋋�͗g�q�]�̑D���A���Ɉˑ������B�������n�d�͔n�̔w���B�]����Ƀg���b�N�͈����ʂ��Ă��Ȃ��v�ƌ�����̂ł���B
�@���������g���̋��h�ȂǂƂ������̂������I�ɂ��蓾�邾�낤���A�펯�ł��킩��͂����B���l�A�\���[�g���̃h���[���^�͂ɁA�l�Ԃ̎��̂�ςݏd�˂ċ����ł���ƁA�{�����͖{�C�ł����v���Ă���̂��낤���H���̂͐��ɕ������܂Ȃ��B�Ƃ��ɓ����̒������́A�~���͖ȓ���̌R���Œ��Ԃ���Ă����B���͓̂~�ł���A��T�Ԑ��ɂ���ƃK�X���̓��ɂ��܂�A�y���q��ƂȂ��Đ��ɕ����Ă���B���b�������܂ł���ƒ��Ԃł���B
�@�{�����́A������Ə펯���͂��炩���Ȃ�킩��悤�ȃE�\��ł���߂ł��A���ꂪ�������̌������Ȃ爢���݂����Ɉ�̍�������Ȋw�I���f�����ĂāA�����Ƃ��炵�����������Ƃ�������̂܂ܒԂ�A�����ɂ����ꂪ�^���ł��邩�̂��Ƃ��\������B
�@�����́w�O���u�x�̉����̂���A��`�d�������ӂł���B�C�����������֒����V���G�ꂽ�����ƌ����Ă��ǂ��B���̌����������̂܂ܒ����Ɏ�莟�����{�̖{������Ƃ������|�[�^�[�́A�����ɂƂ��ċM�d�ȑ��݂ƌ���˂Ȃ�܂��B
�@�i�Ȃ��싞�����̏ڍׂɂ��Ăْ͐��u�싞�����̑����@�s�E�ے�̏\�܂̘_���v�������Д��s�����Q�Ƃ��ꂽ���j
�c���������w�싞�����̑��� �s�E�ے�15�̘_���x�����Ђ��Ƃ������
�@���a�U�O�N�P�P���Q�S�A�T�̂Q���Ԃɂ킽���āA�����V���͎��̕Ғ������w������叫�̐w�������x�q���u���[���s�r�ɂ��āA�u�w�싞�s�E�x�j���ɉ�����/900���������ƃY���v�Ƒ肵�āA�����͂܂��u�w�싞�s�E�x�Ђ�����B��/�c�����̏���叫�̓���������v�Ƒ肵�āA�����Ƃ���i�A���k�L���o���Ƃ����h��Ȉ����ő�X�I�Ɏ��グ�Ď����掂��܂����B
�@�O���ّ�Ɂu�����v�̋L�҂����K���A�R�����g�����߂����A���́u������̊o���͂Ȃ��A�ǂ����ǂ��Y���Ă���̂��A���ׂ�܂Ŕ��\��҂��ė~�����v�ƌ����܂������A���������̗����O�q�̋L���ƂȂ�A�������������������Ȃ��u�\����Ȃ��v�Ƃ����l�т��Ƃ܂ł˂����āA�����ɂ������Ӑ}�I�ȉ������F�߂����̂悤�ȋL���ɂȂ��Ă���A�L�������킹�ʐ�̂Č�Ƃ̒e�N�L���ƂȂ�������B���_���A�ى���������Ȃ��A����I�Ȓf�߂ł��B���́u�����v�ɂ��������ߖ��̈ꕶ�𓊍e���܂������A��������ڂ��ɂ��ꂸ�v���ƂȂ�܂����B
�@�u�����v�͖{���ł��Љ�Ă���悤�ɁA�I�n��т��ē싞�ɋs�E���������Ƃ��ăL�����y�[�����Ă���V���ł���܂��B���̍R�c�┽�_�Ȃǎ��グ�悤�͂�������܂���B
�@���S�����s�����V�����A����Ԃɂ킽���Ď�����A���ٖ̕��̗]�n�����^�����Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�����������̐l���͂ǂ��������ƂɂȂ�̂��H�V���͑�l�̌��͂ƌ����Ă��܂����A�ЂƂ��у}�X�R�~�̃^�[�Q�b�g�ɂ��ꂽ�҂��炷��ƁA����قǖ��c�ȁA���_���������ł��Ȃ��A�قǂ����p���Ȃ�����I�Ȗ\�͂͂���܂���B���̒��ɂ́A�}�X�R�~�̖\�͂̈ꌂ��������āA���_���ى��������ꂸ�A�����ɑ����̐l�������݂ɂ���ꂽ�܂܋����Q���肳�����Ă���P�[�X���������Ƃ��A���X�Ȃ���v�킸�ɂ͂����܂���ł����B���E�������Z�̐搶�A���Ԃ��ꂽ�a�@�A���_�ʑ���l���̂��߁A�����̑i�������}�X�R�~����ɋN���Ă��܂����A�������A�����͂ق�̕X�R�̈�p�ɂ����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�����������Ə̂����w����叫�̐w�������x�Ǝ��̋L�q�Ƃ̃Y���́A�q�R�����������o�ł́u���j�Ɛl���v�i�U�O�N�~�����j�ł��킵���w�E���Ă��邪�A���̐���ӏ��ȊO�͂قڂ܂���������܂���B���Ƃ��������āA����叫�̓��L�Ǝ��̕��͂�Δ䂵���ƌ����܂����A�����������Ă����킩��̒ʂ�A�u�싞�����v���B�����߂ɁA�Ӑ}�I�ɉ��������̂ł͖ѓ�����܂���B���������叫�̓����ɂ́A�싞�Ɂg�s�E�h�������������A�Ȃ������A�ȂǂƂ������ƂƂ͂܂��������W�Ȃ̂ł��B
�B���Ȃ���Ȃ�ʂ��Ƃ͉����Ȃ��̂ł��B���̂قƂ�ǂ́A���̕M�k�̌�A�A�E���A���邢�͒��L���ׂ��Ƃ�������Ȃ��������̕s���ӂɂ����̂ł���܂��B������u�w�싞�s�E�x�Ђ�����B���v�Ƃ����ɂ��������݂����g�s�E�����h��铽�������̂��Ƃ���掂����̂ł��B
�@�ȂɂԂ�ɂ����n���������̊Ԃɑ��菑�����ꂽ���L�ŁA�������叫�Ɠ��̓���ȑ����̂œǂ݂Ƃ邱�Ƃ̂ł��Ȃ��s���̉ӏ��������A���̒��̈ꎚ�ǂ���̂ɁA�O���Ԃ��l���Ԃ��v���A����ł��Ȃ��ǂ݂Ƃ邱�Ƃ��ł��Ȃ������Ⴊ�����ӏ�������܂����B
�@���̂ق��ɁA�s�N�i�����Ȃ��炸�j�A�@���i�����̂��Ƃ��j�A�s�ځi���킵���炸�j�A���i�Ȃ�тɁj�A���i�܂��Ɂj�A�s�R�i�܂т炩�Ȃ炸�j�A�����i����āj�A���i�͂Ȃ͂��j�A���i������j�A篁i�ɂ킩�j�E�E�E�E�E�E�E���X����������ی�����܂��A�����̊������̕������A����̓ǎ҂ɓǂ݂₷������z������A���Ȃ܂��蕶�ɂȂ����A���邢�͐V���ȂÂ����ɂ����āA�����肪�Ȃ�t������A��Ǔ_��t���ȂǁA���̈����ɔz�����������_�͔F�߂܂����A����������ɏ��������āA�s�E�������B�����Ƃ��A�叫�̕s���������Ƃ��������悤�Ȃ��Ƃ͖ѓ�������܂���B���̑����ߍׂ����q���r��t���āA���L�ȊO�ɑ叫���ٌ�l�ɗ^���������̑}���i���j����L�{���Əs�ʂ��Ȃ��������A�Â���ȓ_�̂��������Ƃ͔F�߂܂��B
�@�����ł͂�����\���グ�������Ƃ́A���͑叫�̓��L�q�����ړI�́A��ꋉ�����ł���R�i�ߊ��̓��L��ʂ��āA���̐퓬���Ԓ��̏���叫�̍s�ׁE�S���E�^�ӂ��Ђ낭�]�ɓ`���邱�Ƃł���܂����A����ɑ����̃Y���͂����Ă��A����叫�̐^�ӂ��Ȃ��邱�ƂȂ��A���̖ړI�͊��S�ɉʂ��������ƌ������Ƃł���܂��B�����V�����͂��ߓ��x�Y����s�E�h�̐l�X�́A�j�Z�ʐ^��E�\�̋L�q�܂łȂ�т��ĂāA��������ʂQ�O���A�R�O���́g��s�E�h���������������̂��Ƃ���`�����q���Ă��܂��B
�@���ꂱ�����j�̉������łȂ��ĂȂ�ł��傤���B
�@��������叫�̓��L���������Ə̂��Ē����V���Œ@�����{�����ꎁ���A���x�͔q�R��������A�{������������싞�����́u������̏�K�ҁv�ł͂Ȃ����ƒ@����Ă���̂͂��̈��Ɛ\���܂��傤�B�i�����]�_���O�l���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@
�@�����V���Ђ͎����Q���Ԃɂ킽���Ĕ�掂����̂��A��s�E�h�̃��[�_�[�i�̓��x�Y���́w�싞��s�E�̏ؖ��x���o�ł��܂����B���̖{�͎����͂��ߋs�E�ے�_�Ҏ����i�q�R���A���{�����A�n�ӏ���A�R�{�����A�����G�v�A��������j�̖��������A���̏��_�����A�ᔻ�������̂ŁA�Ƃ��ɂ��̖{�̂V�O�`�W�O�p�[�Z���g�ْ͐��ɑ���ᔻ�ł���܂��B�Q�O���A�R�O���̑�s�E���������Ƃ��铴���̂��̒����ƑO�サ�āA�ꋴ��̓�����������g�u�b�N���b�g����w�싞��s�E�x���o�ł��A���̒�q�̋g�c�T�����w�V�c�̌R���Ɠ싞�����x��؏��X����o�ł��܂����B�����܂ł��Ȃ����̓��������l�A�����̐�����`�ʂ�A�싞�ɑ�s�E�����������Ƃ��ꐶ�����ɏ����A�˂Ă���{�ł���܂��B����ɑ����đ��̐`��F�����������_�Ђ���w�싞�������u�s�E�v�̍\���x�Ƃ����{���o���܂����B�`�������Ԕh�Ǝ��̂��A�s�E�����l���Ɛ������Ă��܂����A�������l�A�����ٔ��j�ς�W�J���āA����叫�ɑ��邢���Ȃ���掂Ɠ��{�R�̎c�E�����Ђ�����Ԃ��Ă��܂��B
�@���͖{���ŁA�ȏ�l���ɑ���ᔻ�┽�_�𐏏��ɉ����A�܂���N�o�ł��ꂽ�������̌��I���\�Ə̂���싞�s���j����������҂́w�،��E�싞��s�E�x�̔����O��䎮�̑�f�^�����̔�Q�҂̏،����O��I�ɔᔻ���A�e�����̐퓬�ڕ��A�����̈ꋉ�������ӂ܂��āA�������V�������@����������،�����g���āA�싞�����̐^���ɔ���������ł���܂��B
�@���͂����ɓ��{�����Ђ���w�g�싞�s�E�h�̋��\�x���㈲���܂����B���̒��͍����ő����̔������Ă���łȂ��A�����ł́u�싞��j�E�L�O�فv���݂ɂ������āA���̖{����قǖڂ����Ƃ݂��āu�l���܂��̖{�v���ƈ���`�ɂƂ߁A�\�A�̐Ԃ��d�g���A���҂̎��𖼎w���Ŕ��܂����B�܂肻�ꂾ���C�O�ł��������傫��������ł��B�{���͎�O���ƃ_�u���_������܂����A�����ʂ�u�����v�̖��ɂӂ��킵���A�s�E�̒�`����͂��܂��āA�����ٔ��⋳�ȏ��Ƃ̊W�A�{���Ƌs�E�_�A�ے�_��ԗ����A���Ẵ}�X�R�~��āE�p�E�����{�ɂ��̎����ɑ��锽����Ή��ɂ܂Ŏ��L���A�u�싞�����T�O�N�̐ߖځv�������āA���̑S�e�Ɛ^���ɔ���������ł̂���ł���܂��B
�@������ɂ���A�J�ԓ`�����邪���Ƃ��싞�ɂQ�O���A�R�O�����̑�s�E���������Ƃ��鑭�_�́A���j�̐^�����䂪�߂���j�̉�����ł���A���ςł���܂��B���Ƃɂ��̋��ς����ȏ��ɂ܂ŋL�q���A�����S���������ɂ����鎩�s�I�ȁA�c�����f�̂����̋�����{������Ƃ������Ƃ́A��������c�̗��j�ւ̖`���ł���A�����̒p�J�ł���A��������܂邱�Ƃ���ȏ�͂Ȃ͂������͂���܂���B���͍���Ƃ����̗��j�I���\�\�\���{�߈��j�ρ\�\��|�̂��߁A�s�ޓ]�̌��ӂł��������̓w�͂��d�˂ĎQ�肽���Ǝv���Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�@�z�[���y�[�W��ŁA�u���ꂪ�싞��s�E���v�Ȃ�ĕ��ɔ��\���Ă���l�Ȃ̂�����܂����ǁA���ۂɂ��싞��s�E�̏؋��ʐ^�͂P��������܂����B
�@�ǂ�����A�����Ă����̂�����Ȃ����ǁA�����̓싞�ɔ����̉Ă̐퓬���𒅂����{�������̂̑��ɗ����Ă���ςȎʐ^�Ƃ��A�\�A������{�����Ɖ�����Ă���A������v���]���҂̑�ʂ̍��̎ʐ^�ⓖ���̒�����A�����J�̍R���A�����f��̂P�V�[�����E�\�̉�������čł��炵�������Ă��邾���ł��B
�@�ʐ^�G�������Ĉ��������ɂ͒P���ȃ����Z�ʐ^�ƌ����̂͊ȒP�Ɍ����������ł��B
�@�싞��s�E���`���Ă���N��͑��40�㒆���`60���̐l�炵���A���R�]�R�o���A�R���m���͊F���B
�@������ȒP�ȃ����Z�ʐ^�ɂЂ�������A�Ƃ������Ӑ}�I�Ȃ�ł����ǂˁB
�@�^����100�N�����Ă�200�N�o���Ă��ς��鎖�͕s�\�ł��B���̑c���B���ǂ��ɂ����Ĉ��҂ɂ����Ă����Ƃ����C�����͑S������s�\�����ǁA���������e�����Ĉ�����q���B�͌����Ă��������e�h���܂���B
�@�����K���A�����ؕԂ������炤�̂͂��ł�10�N��A���̎����������ǂ��]�������̂����Ă������Ƃł��B
�n���i�ّ��j�̎ʐ^
�@�n���i�ّ��j�Ƃ͒����Ő��̖�����̖��B�ɂ͂т����āA�n�ɏ���čr�炵������W�c�I�ȓ����ŁA�吳���珺�a�����ɂ����āA�����̖k���͌Q�Y��������n���̎��ゾ�����B
�@�֓��R�ɔ��E���ꂽ�������̂悤�ɑ召�n���Q�ɂɂ�݂𗘂����A����匳���Ɩ���������͎҂������B�����ɂ͏��n���������B
�@�����̎x�߁i�����j�ł͔_���͍앨���s��̎��ɂ͔n���ɕϐg���ċߗׂ̑��X���P����������Ă������������������ł��B�����n���͋ߗׂ̊X���Ȗ�ȏP���ċ��i�����D���A�E�l�Ȃǂ��s���Ă����B�i�����̒����̒��͈��S�̂��ߏ�ǂň͂�ł����̂͂����ɗ��R������B�j�@�@���B�S�����x�X�P���Ă����B
�@�����A�ނ�͕߂܂�ƂقƂ�nj��n�̌x�@�Ȃǂɂ���ď��Y����a�ꂽ�肵����i�ʐ^1-4�j�������߂̂��ߎ��肳�炵��ɂ��Ă����i�ʐ^1-3�j�B���������{�l�Ƃ͕������Ⴄ����\���|�C���g�ł���B�i���F���{�ł͎a��A���炵��͍]�ˎ���ɔp�~���Ă���B
�@�܂��Ă⏺�a�����ɂ��̗l�Ȗ�ȍs�ׂ͈�؍s���Ă͂��Ȃ��j�u�싞�v�̎s���Ȃ�č����̂Ȃ��E�\�ł���B���Ȃ��Ƃ��u�s�E�h�v�͒����̕����ɂ��đS���m�����Ȃ��悤���B�ȉ��͑S�Ă��̎ʐ^�ł���B
| �ʐ^1-1 | �ʐ^1-2 |
 |
 |
| �ʐ^1-3 | �ʐ^1-4 |
 |
 |
�@��i2���̎ʐ^�͔n���ւ݂̂����߁i�ʐ^1-1�j�������́A�����̔n���̎a������W�߂ĎB�e�����i�ʐ^1-2�j�����̉���싞�Ƃ͊W�̂Ȃ��ʐ^�����i�ʐ^1-2�j���͂��̎ʐ^�ɂ͔�ʑ͈̂ꏏ�����w�i���f���Ă���ʎʐ^�����݂��Ă���A���ɏ�ǂ̈ꕔ�炵�����̂������A���̏�ǂ͖��炩�ɓ싞�Ƃ͈Ⴄ�B�܂�E�\�ʐ^�ł���B
�@���i���̎ʐ^1-3�́A���a59�N8��4���̒����V���Ɂu���L�Ǝʐ^�����������싞��s�E�v�Ƒ肵�{��̌����m�����L�Ƌ��Ɍ��������ƌf�ڂ����i����ɂ��Ă͕ʃy�[�W���Q�Ƃ��ĉ������B�j�B����������͍����i���i�_�ސ쌧����s�ݏZ�j�����a�U�N10���A���N�ƒ����̍����Ɉʒu�����J�ɂĕ��[��i���ʐ^���ɂĂ݂₰�Ƃ��āA��P�O���������ʐ^�̒��ɓ����Ă���u�S��j�e�e�E�Z���n���m��v�Ƃ̕��������荞�܂�Ă����B
�@�S��͖��B�ł���B�����̓j�Z���m�ł��邱�Ƃ�F�ߎӍ߂����B���̌�u�����v�͓��L�����J�������A�Â��Ĕj��₷������Ƃ̗��R�ŏ\�����[�g�������点�Č��������B
�@�����A���w�҂̘b�ł͓��L�ɂ͓������ɂ͌g�s����Ă���͂��������������N�M�ŏ�����Ă����i��̂̕��m�͉��M�������قƂ�ǂł���j�B
�싞��ɂ�����펀�҂̎��́i���R�A�푈�Ȃ̂��j
�@�悭���܂��A�ƌ��������Ȃ邭�炢�Ɂu�s�E���L�����B�Ƃ������h�v�͐퓬�Ŏ��������̎��̂����ꂪ�u�싞��s�E���I�v�ȂǂƉ��ʂ��Ȃ����\���邱�Ƃ��낤���B
�@�싞��ɂ��Ă͕ʃy�[�W�ɂďq�ׂ��ʂ肾���A�퓬�ɂ����Ă̐펀�̂��ǂ����āA���������L���v�V�����ɂȂ�̂������������������قǂł���B
�@�ȉ��̎ʐ^�͐퓬��̎x�߁i�����}�j���̎��̂ł���A���{�R���ɂ�����Ȃ�펀�ҁA������������P�Ȃ�퓬���ł̐펀�҂ɂ����Ȃ��B����͑S�Ďx�߁i�����}�j�R�Ɠ��{�R�ɂ�鐳�K��ɂ����鎀�̂ł���A�����s�E�Ƃ͊W���Ȃ��B
�@���Ȃ݂Ɏʐ^���ٔ��ł��؋��Ƃ��č̗p�����ۂɂ́u�N���H�ǂ��ŁH���H�B�e�����̂��H�v�Ƃ��������͍Œ���ł���B���ꂪ�������Ȃ��ꍇ�͏؋��Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B�펯�ł���B�ł��ʐ^���炻��炪���������ꍇ�͕ʂł����B
| �ʐ^2-1 | �ʐ^2-2 | �ʐ^2-3 |
 |
![������ہE�B�e�B�g�q�]��j���œn�낤�Ƃ������m���nj���ł̎��́i�펀�̊܂ށj](murase1.gif) |
 |
| �ʐ^2-4 |
 |
�@�Ƃ܂��A�����������ʐ^���S�قǗ�ɐ������܂��傤�B
�@�܂��A�����́A�S�Ē����R���m��̒P�Ȃ�펀�̂ł��B
�@�B�e�҂������Ă���A�ʐ^2-1�A2-2�A2-4�̎ʐ^�B�e�҂͑�����ێ��i��ʌ���z�s�ݏZ�j�ł���B
�@�����̎ʐ^�́u�����V���v���u�싞�����v�̋]���҂̂��Ƃ����������ۂ͑��̓싞��ł̐펀�҂ł��������Ƃ���45�A���A�����`�F�����т��̑��̐l�B�̏،��ʼn����Ă���B
�@���Ȃ݂ɂ���玀�̂ɂ͑S�Đ퓬���𒅂Ă���̂ňꌩ���ĕ��m�ƕ�����B
�@��́A�u�s�E���������v���Ɣ������������m�B�͍s�������������̎҂ɑi����ꂽ��E�\�����j��ꂽ�肵�Ă���̂ł��B
�@�ʐ^2-1�A2-2�A2-4�͐V�͒��ɂ�����G�̈�����́i�펀�́j�B
�@���Ȃ݂Ɏʐ^2-3�͒P�ɓ싞��O�E���ł̐펀�҂̎��̂��W�߂��ꏊ�ŎB�e�B
�@�͂����茾���āA�u�싞��s�E�v�Ƃ͉���W�Ȃ��B�i�����ƁA�ڂ����m�肽���l�́u�싞�����̑����v�@�����Ё@�c�������������ĉ������B�j�@