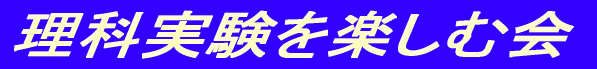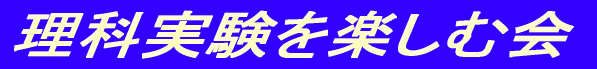物理読み物33 電子の速さ E-118 No240
2010年11月25日(木)
発泡スチロールをウールの布で摩擦してマイナスに帯電させておいて、これに絶縁体の柄をつけた金属板を置きます。(このようなセットを電気盆といいます)金属板は静電誘導で、その裏側がプラス、表側がマイナスに帯電します。
金属板に指を触れると、金属板のマイナスの電荷は地球へ逃げて行ってしまいます。(この操作をアースするといいます)金属板のプラスの電荷は発泡スチロールのマイナス電荷に束縛されているので移動できません。続いて、柄を持って金属板を持ち上げると、金属板はプラスの電荷をもったまま、発泡スチロールから引き離されます。ここで、これをアースすると、金属板のプラスの電荷は地球へ逃げます。金属板からは、初めにマイナスの電荷が逃げ、後にプラスの電荷が逃げるのだから、この実験を何度も続けていくと、金属板には電荷がなくなってしまうのではないか、という疑問がでてきます。実際はそうではありません。
マイナスの電荷は自由電子が担っているので、マイナスの電荷が地球に逃げる時には、自由電子が地球へ移動します。プラスの電荷は電子を失った原子
― つまりイオン ―
が担っていて、これが物質を構成しているので、これが移動することはありません。
プラスの電荷をアースして逃がすということ、つまり、電気的に中性にするということは、地球からマイナスの電荷を金属板に呼び込んで、そこのプラスの電荷と中和させるということです。もっといえば、先刻、地球へ移動していった電子を呼び戻したということです。俗っぽくいえば“逃げた女房が帰ってきた”のです(?)。
指でアースする代わりに、指に持ったネオン球でアースしてみましょう。ネオン球は電子が跳び出す方が発光します。初めのアースでは、金属側が発光し、後のアースでは、指側が発光します。このことから、初めは金属の電子が地球へ、後には地球の電子が金属へ移動したことがわかります。
初め地球へ逃げたマイナスの電気は、その反発力で、遠くへ分布したと考えてもよいでしょうし、相手のプラスの金属に引かれて、(未練がましく)それの近いところに存在するとも考えられます。
いま、ここの電力が長野の発電所から供給されていたものとしましょう。スイッチを入れた瞬間に白熱電灯は点灯します。電気はとても速いのです。
計算し易いように、直径1mmの導線に1アンペアの電流を流したものとしましょう。電荷の移動速度をv[m/s]とすると、この導線のv[cm]の中の自由電子の電気量が1クーロンになります。1クーロンとは1アンペアの電流が1秒間に運ぶ電気量です。導線の体積は
(0.1/2)^2・πv[cm^3]、銅の密度は8.9[g/cm^3]だからその質量は、(0.1/2)^2・v×8.9[g]、銅の原子量を64とすると、このモル数は(0.1/2)^2・πv×8.9÷64、一つの原子に1個の自由電子があるものとすると 1モルの電気量は96500クーロンだから、その電気量は(0.1/2)^2・πv×8.9÷64×96500=1 を計算すると v=0.095[cm/s]およそ、秒速1mmといったところです。これは導線の中を電子たちが一斉にゾロゾロ移動する速さです。ここでスイッチを入れると、すぐに長野の発電所では、電子を押し出す仕事を始めますが、その信号の伝わる速さはほぼ光速です。アースして地球に分散する電子の速さも、電算機の対応の速さもこの速さです。
さて、こうは言ったものの、事情はもう少し複雑です。発泡スチロールを摩擦してこれをマイナスに帯電させた相手のウールの布は、当然プラスに帯電した筈です。しかも、それがその辺に放置されていたとすると、プラスの電荷はアースされて地球に分散したのでしょうから、ここでアースされた金属板の金属板のマイナスの電荷はこれと中和したに違いありません。また、もし、この布が地球から絶縁されたまま、その近くに置かれていたとすると、アースされた金属板のマイナスの電荷は、布の近くの地球上(布が置かれた机)に分布して、布のプラス電荷と引き合うことになります。“アメリカ行きは止めにした”ことになります。このようにプラスとマイナスの電荷が離れて引きあっている状況をコンデンサーが形成されたといいます。
電荷の行動原理は極めて単純です。異種の電荷はできるだけ接近してコンデンサーを形成し、事情が許せば一緒になって中和します。同種の電荷はトータルとして、お互いにできるだけ離れて分布します。
中空の金属の容器に電荷を与えると、電荷は外側の表面に分布し、内側の表面には分布しません。もちろん、金属の中にも分布しません。この分布が、電荷がト−タルとしてお互いに最も離れた分布なのです。円筒状の金属容器に電荷を与えておき、絶縁体の柄をつけた金属球で、その内部から電荷を汲み出そうとしてもできません。内部には電荷は分布していないからです。逆に言えば、内側から電荷を与えれば、いくらでも与えられるということになります。ヴァン・ド・グラーフ起電機は、その内側から電気を供給しているので、あのように高圧にできるのです。
コンデンサーにおけるプラスとマイナスの電気の分布からわかるように、プラスとマイナスの電荷は1対1で相対していて、ちょうど、一本の線で繋がっているように考えると、“見え易い”のです。これを電気力線(電束線という場合もあります)と呼びます。電気力線はプラスの電荷から出てマイナスの電荷に入る(これは単なる約束)、あるいは、プラスの電荷から出て、どこかにいるであろう無限遠のかなたのマイナスの電荷に到達する、あるいは、全体としてその逆、のいずれかです。考えようによっては、“電気力線の切り口を電荷という”ともいえます。プラスとマイナスの電気が引きあうのを、“電気力線は縮まろうとする”とみなすこともあります。このモデルを使うと、金属球の内面には電荷は存在できません。金属ですから、当然、同種の電荷が分布しています。仮にこれがプラスの電荷だったとすると、外側表面のプラスの電荷から出た電気力線は無限遠に到達しますが、内側表面には、電気力線の分布のしようがありません! だから、電荷は分布していないのです。電気力線の考え方はファラデーに由来します。見えない電気を見えるようにするためには、優れた方法です。電気力線(電力線とはいいません)は、磁力線(磁気力線とはいいません)と対になっています。一緒にして、力線と呼びますが、その形を実験でみることもできます。しかし、この力線を実体と見るかどうかにについては、議論の分かれるところです