 RVW (1920)  ヒコックス盤・ジャケット  レーベル面 (いわゆるピクチャー・レーベル) |
Richard Hickox , London Symphony Orchestra Rec.2000 Dec.18&19 [CHANDOS : CHAN9902] 《ロンドン交響曲》はRVWの9曲の交響曲のうち、第2番目の作品にあたります。 しかし最初の交響曲である《海の交響曲》が事実上カンタータであることから、この《ロンドン交響曲》こそがRVWにとっての最初の交響曲にあたると見ることもできるようです。 この交響曲はバターワースの勧めによって1912年に作曲が開始され、翌1913年に初稿が完成しました。 さらに翌1914年3月27日、ロンドンのクィーンズ・ホールにおいて、ジェフリー・トーイによって初演されました。 しかしその年、ドレスデンのフリッツ・ブッシュの元に送られた唯一のスコアは第一次世界大戦勃発の混乱の最中で所在不明となってしまいました。 そこでRVWはバターワースやトーイの協力の下、残されたパート譜を利用してスコアの再構築を行い、1915年2月11日、ダン・ゴッドフリィによって蘇演がなされました。 その後RVWはこのスコアに1918年・1920年・1933−4年と改定を加え、1954年の改訂第四版が現行の版(Stainer & Bell)です。 さてひとたび失われた1913年版ですが、遺族の指名によりリチャード・ヒコックスにより録音され、シャンドス・レーベルからリリースされました。 もちろん1913年版ということだけでも十分に興味深いのですが、このCD、泣かせることにカップリングがバターワースの《青柳の堤》なのです。 バターワースは《ロンドン交響曲》の誕生・蘇演に深くかかわり、さらに彼の早過ぎる死の後は追悼に捧げられるという、エンもゆかりも盛りだくさんの関係なのですが、これらの事情に殆ど触れていないCD解説もあるというのが現状でした。 それはさておき、現行版より20分ほど長いこの1913年版、くっきりとしたオーケストレーションと盛りだくさんの民謡風旋律によって、とても親しみやすい顔をしています。 交響曲としての求心力という点では、いささか構成の弱さを感じさせないでもありませんが、《海の交響曲》あたりと併せて、初期のRVWの交響曲という形式へのスタンスを読み取ることもできるのではないでしょうか。 またこれも同じ時期に作曲されたグスタフ・ホルストの組曲《惑星》との親近感も感じられます(ホルストもまたRVWのよき理解者であり、交友も深かったそうです)。 ともに表題を持ちつつも、その表題にとらわれることのない自然な感性によって受容されることのできる、よくこなれた、聞き飽きのこない曲です。 ご遺族のご指名を受けてこの1913年版の復活の任に当たったヒコックスは、実に彼らしい衒いのない演奏です。 こういう演奏を「誠実な」という形容詞だけで片付けるのは申し訳ないように思います。 ヒコックスはこの版からRVWのオーケストレーション構造を浮かび上がらせながら、少々もさっとした印象のあるRVWのイメージよりも、むしろ彼の知的な側面へのアプローチに軸足を置いているように感じました。 バターワースも同様に、例えばバルビローリの慈しむような演奏からではなかなか見出しにくい、RVWとバターワースの新たな魅力に気づかされました。 RVWが苦手な人のほうがすんなりと受け入れられるのではないでしょうか。 |



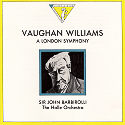


 他のCD雑感へ
他のCD雑感へ